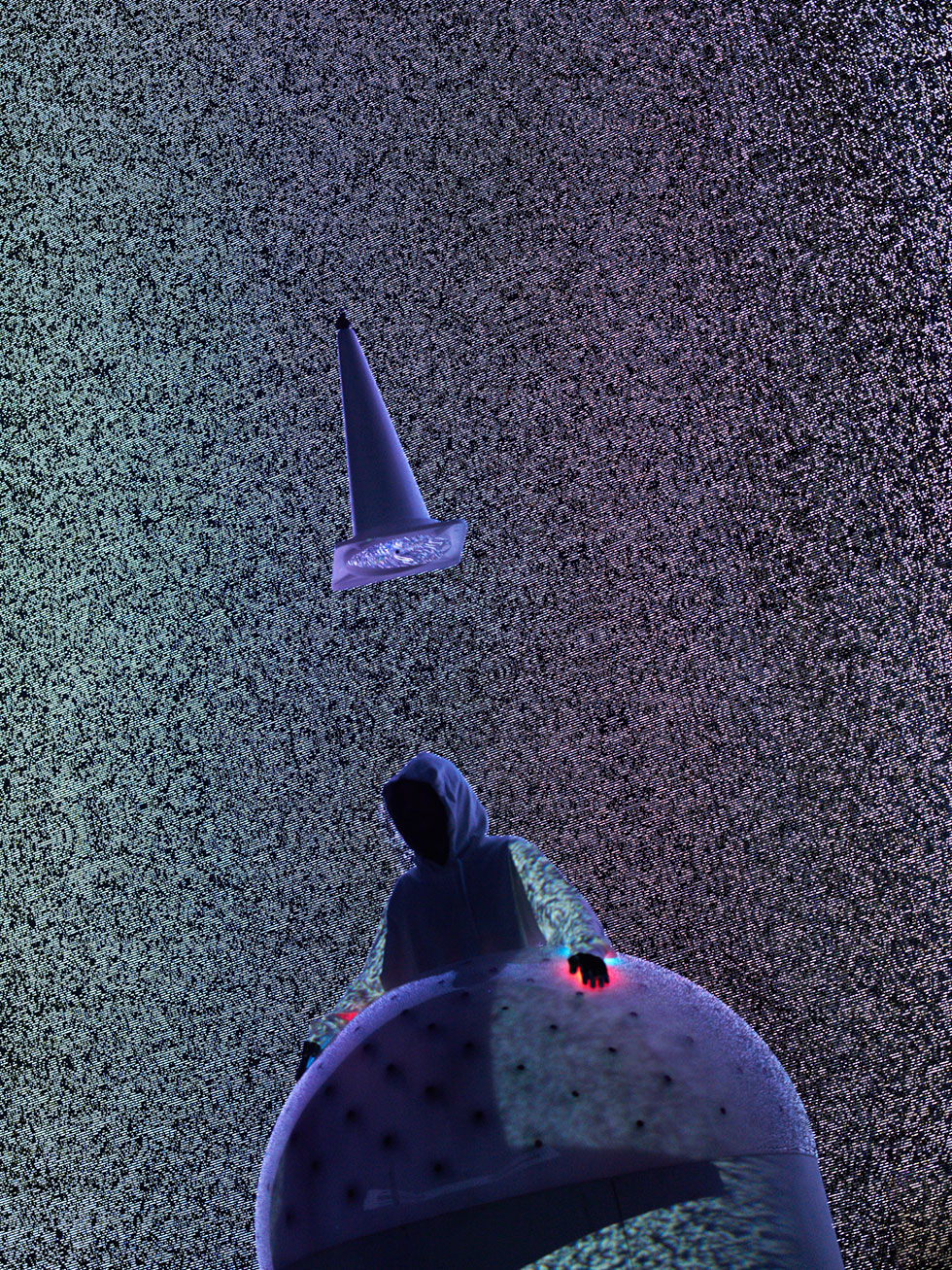2024年のフジロック・フェスティヴァルでオーディエンスをおおいに湧かせたサックス/フルート奏者のチップ・ウィッカムが3度目の来日を果たした。筆者は渋谷クアトロでのライヴを観たが、ファラオ・サンダースなどのスピリチュアル・ジャズをクラブ・ミュージック以降の感覚でアップデートしたような演奏は、ジャズとしてはもちろん、ダンス・ミュージックとしても秀でたものがあった。実際、オーディエンスのなかには踊っている者も多く、チップらの紡ぐグルーヴが身体に直に訴えかけてくるものだと証明する形となった。スタンディングのハコでライヴをおこなったのは大正解だったというべきだろう。特に目を惹いたのが、シネマティック・オーケストラにも参加しているルーク・フラワーズのドラムである。アンサンブルを立体的に見せるの長けた彼のプレイは、視覚的にもみどころたっぷりで、ドラム・ソロに目が釘付けになってしまったのは、筆者だけではあるまい。
そんなチップ・ウィッカムのニュー・アルバム『The Eternal Now』は、現在のUKジャズ隆盛の一翼を担っている〈ゴンドワナ・レコーズ〉からのリリース。〈ゴンドワナ〉はマンチェスターに拠点を置き、ゴーゴー・ペンギン、ママル・ハンズ、ポルティコ・カルテットらの名作を発売しているレーベルである。新作では同レーベルの責任者であり、チップの親友のマシュー・ハルソールが共同プロデューサーを担当。ベテランとは思えない鮮度の高いアルバムに仕上げている。特に注目すべきは、ヴォーカリストが参加していることと、ストリングスが導入されていることだろう。チップがこれまでとは違う試みに挑戦したかったと言うように、風雪に耐えうる強度を備えた、普遍的な作風が特徴だ。おそらくチップは今回、ライヴと音源は別ものとして考えて制作に打ち込んだのではないだろうか。ライヴで再現不可能なことも音源に封じ込めることで、表現の幅が広がり、音源ならではのトライアルが多数可能になっている。そう言えるのではないだろうか。クアトロのライヴでの翌々日、チップに話を訊いた。
最近はストリーミングで次々に音楽を配信していかなきゃいけないというプレッシャーが音楽家にもあると思うけれど、それとは真逆の考え方で、自分たちで好きなだけ時間を取って創作に集中したんです。
■一昨日(11月16日)の渋谷クアトロでのライヴ、とても良かったです。若いお客さんが多くて、皆、身体を揺らしたり踊りながら聴いている光景が印象的でした。ジャズ・ミュージシャンが来日すると、BLUE NOTE TOKYOやCOTTON CLUBなど、座って食事を楽しみながらライヴを観るクラブで演奏することが多いですが、あなたたちのライヴにはスタンディングが合っていたと思います。クアトロを選んだのはあなたの選択ですか?
チップ・ウィッカム(以下、チップ):そう、私がスタンディングのハコでやろうと決めました。若い人はライヴ・ハウスで踊りながら聴くのが好きですよね。イギリスでも若いジャズ・ファンが比較的多いので、クアトロみたいなハコでやることが多いです。ただ、ヨーロッパだと、もう少し大きくてフォーマルなコンサート会場でやることもありますし、そこは柔軟に対応してますけどね。BLUE NOTEのようなクラブでも、クアトロのようなライヴ・ハウスでも、分け隔てなく演奏できるとは思っています。
■今年の9月5日に新作『ジ・エターナル・ナウ』がリリースされました。このアルバムのコンセプトやテーマについて教えてもらえますか?
チップ:冒険してみたかったというか、サウンド的にこれまでの作品からより拡張したものをつくりたいと思いました。なかでも大きかったのは、長年の友だちで〈ゴンドワナ〉のヘッドでもあるマシュー・ハルソールに共同プロデューサーで入ってもらったこと。今回は、彼と一緒にちょっと新しいことをやってみようという話になったんです。前作の『Cloud 10』も反響が良くて成功した実感があったんですけれども、そこからさらに可能性を拡げて、新たな領域、新たなサウンドを求めたいなと思いながら、マシューと親密に作業しました。
■マシューとの付き合いは長いんですよね?
チップ:はい。彼が〈ゴンドワナ・レコーズ〉に入るずっと前からの知り合いなんです。〈ゴンドワナ〉の人気が上昇している頃、私はUKのシーンから離れてスペインにいたんですけれども、彼がスペインに遊びに来たら一緒に演奏したり、密な付き合いを続けてきました。だから、ずっと交流はあったんです。 私が〈Lovemonk〉というレーベルにいたときも、マシューがゴンドワナ・オーケストラという自身のプロジェクトを始めて、私もそこで演奏するようになりました。元々お互いの音楽に対するセンスとか、好きなものが同じなので、ずっと仲がいい。私が〈ゴンドワナ〉に入ることになったときも、「レーベルの一員になることで、君との友情関係を壊したくない」って言われたほどで。要するに、「ビジネス・パートナーという関係になってしまうのはどうなの? 友だちと仕事をするのって難しいじゃない?」っていうことだったんです。
■そうなると、〈ゴンドワナ〉からリリースすることでのプレッシャーはなかったですか?
チップ:正直、結構ありましたね。それで、2022年に入門編じゃないけど、「Astral Travelling」っていうロニー・リストン・スミスの曲をカヴァーしたEPを出して、それに対する反応が良くて安心したんです。「これならイケるんじゃない?」って思ったというか。ちなみに驚くべきことに、ロニー本人から私に電話がかかってきたことがあったんです。共通の友だちがいるからなんですけど、すごくびっくりして緊張しました。ロニーが低い声で「最高だったよ、君のヴァージョン。でもコードがひとつ間違っているよ」みたいな指摘を受けて。ロニーが電話越しでピアノを弾きながら指摘してくれたんです。それ以降も2~3度、電話をする機会があって、音楽や人生の話をたくさんしましたね。本当に素晴らしい人であり、尊敬すべきミュージシャンだと思います。
■〈ゴンドワナ〉からはゴーゴー・ペンギンもリリースしていますね。彼らはあなたにとってどんな存在ですか。音楽的なスタイルは違うけれど、同じレーベルに所属している。逆に言えば、それだけ〈ゴンドワナ〉というレーベルには、同じジャズ系アクトでも振れ幅があると言えるのでは?
チップ:その通りだと思いますね。ゴーゴー・ペンギンはクラシック的な要素や、エレクトロニック・ベースな部分がある。私はもう少しスピリチュアル・ジャズの領域にいるので、違うといえば違うと思います。でも、同じレーベルにいるのがおもしろい。〈ゴンドワナ〉に入ってからは、レーベルの中で自分たちの居場所とか位置づけを探していくのが大事だな、ということを意識するようになりました。
■たしかに、スピリチュアル・ジャズの要素は感じますね。ジョン・コルトレーンやアリス・コレトレーン、ファラオ・サンダースなどもフェイヴァリットでしょうか?
チップ:もちろんです。私にとって重要なルーツのひとつだと思います。
■今回、ミックスをこれまでと違う人に託していますよね?
チップ:グレッグ・フリーマンという〈ゴンドワナ〉の他のアーティストのミックスも手がけている人なんです。今回、アートワークもレーベルのヴィジュアル面を担当しているダニエル・ハールサブという人が担当してくれましたし。その意味で、今回のアルバムはレーベル・カラーに合わせてプロデュースされたアルバムになったと思いますね。ヴィジュアルもサウンドも一貫性のあるものになっているというか。自分がどう〈ゴンドワナ〉にフィットできるかを考えるようになったし、その結果、レーベル・カラーに沿いつつ、自分たちらしさも出せるような改良の仕方ができたと思っています。

根無し草だからこそ、どんなジャンルや地域の音楽にも気軽にアクセスできるんだと思います。
■さきほど、これまでと違うことをやってみたかったとおっしゃいましたが、具体的にはヴォーカルやストリングスの導入が目立ちますね。
チップ:たしかにヴォーカルとストリングスは今回新しい要素として取り入れたものです。“Nana Black” っていう曲には Peach さんという素敵な女性ヴォーカリストを迎えているんですけど、7曲目の “Falling Deep” っていう曲にもラララ~というヴォーカルが入っていて、これは自分の娘が歌っている。彼女自身がアーティストであり、シンガー・ソングライターでもあるので。私が制作中の音源を「聴いてみる? 」と聴かせたら、その2日後にこの曲に合ったヴォーカル・テイクを何個も作ってくれて。アドリブも入っていたんですよ(笑)。親として誇りに思います。
■ストリングスの導入に際してはどのような配慮をされましたか?
チップ:ストリングスのアレンジメントで気を付けたのは、レトロな感じではなく、フレッシュでモダンで洗練された響きにしようということ。私は弦楽器の音が大好きで、デヴィッド・アクセルロッドとかジョン・ハリソンなんかもよく聴くんですけど、今回は弦楽器の音が過剰にならないようにしました。余計な音を削ぎ落として本当にいいものだけを吟味して入れていったんです。
■これまでと制作の仕方で変わったところはありますか?
チップ:今回、あまり時間に左右されずに制作に臨むことを心がけたんです。アルバムの制作においてクリエイティヴィティを優先するという観点から、どれだけ時間をかけても構わないからいいアルバムを作ろうと。もちろん予算はかなりかかったけれど、ビジネスとしての音楽よりもいいものを作ることを重視したんです。最近はストリーミングで次々に音楽を配信していかなきゃいけないというプレッシャーが音楽家にもあると思うけれど、それとは真逆の考え方で、自分たちで好きなだけ時間を取って創作に集中したんです。リズム隊は実力あるふたりだけれど、ベースもドラムもたくさんテイクを重ねて、そのなかから最良だと思えるものを選び抜きました。皆センスが良く、スキルのあるミュージシャンばかりだから、最高のクオリティの作品になったと自負しています。あとは永遠に残る作品をつくりたかったですね。
■ああ、もしかしてそれがアルバム・タイトルの『The Eternal Now』と関係しているんでしょうか?
チップ:まさにそういうことです。たとえ未来に聴かれたとしても、「now」と感じられるようなもの。『The Eternal Now』というのは直訳すると「永遠のいま」という意味で、永遠に聴き続けてもらえるもの、というのが念頭にありました。
■ドラマーがシネマティック・オーケストラにも参加しているルーク・フラワーズですね。彼はじつに巧みなプレイで、ライヴでもアンサンブルの軸となっているのが印象的でした。
チップ:そう、ライヴで観ると「手が何本あるんだ? タコなんじゃないの?」と思いますよね(笑)。彼の参加もマシューのおかげで実現したんです。マシュー自身もシネマティック・オーケストラのファンであるので。ライヴでは激しい演奏する方なんですけれども、レコーディング・スタジオではすごく集中をして、熟考の上でああいう演奏をするんです。スタジオとライヴの雰囲気がかなり違うというか。

■今回のアルバム、スピリチュアル・ジャズもそうなんですが、モード・ジャズの伝統を継いでいるとも思いました。
チップ:その通りです。というのも、もともとジャズが好きじゃないけれどダンス・ミュージックとかエレクトロニック・ミュージックを愛聴するリスナーも、モーダルなジャズは入りやすいし、魅力的に感じる部分があると思うんですよね。僕自身、マイルス・デイヴィスやジョン・ヘンダーソンなどのモーダルなプレイが特徴のアルバムが大好きなので、自然とそういうものを採り入れることになったと思います。
■チップさんはUKやスペインや中東など複数の拠点を持っていて、音楽的にも多ジャンルを股にかけていますよね。いまはジャズをやっているけれど、ザ・ファーサイドやザ・ニュー・マスター・サウンズ、ナイトメアズ・オン・ワックスなど、ヒップホップからファンク、トリップ・ホップまでに関わっている。根無し草(=rootless)みたいな感覚があるのかなと思ったんですけど。
チップ:そうだと思います。というか、根無し草だからこそ、どんなジャンルや地域の音楽にも気軽にアクセスできるんだと思います。最近の若い人の音楽の聴き方もそうですよね。ストリーミングの発達も手伝って、いろいろなジャンルにアクセスする回路があって、実際にいろいろなタイプの音楽を聴いている。それと同じことを私もミュージシャンとしてやっているんだと思います。もちろん、なんでもかんでも採り入れればいいとは思わない。腕のいいシェフのように、いい素材だけを集めておいしい料理をつくるのが理想だし、大事だと思いますね。
■なるほど。それに加えて、あなたの音楽はUKのアシッド・ジャズの系譜にもあるようにも聴こえるんですよね。
チップ:アシッド・ジャズね、すごく聴いてましたよ。United Future Organizationとか、Kyoto Jazz Massiveも大好きだったし。若く多感な頃に聴いたので、とても素敵だなと思いました。日本とUKのミュージシャンのファンクとかソウルへのアプローチやそのセンスってけっこう近いと思うんですよね。ジャズを中心にいろいろな音楽の要素がブレンドされているところとか、DJ的なセンスが根柢にあるところとか。そうそう、アシッド・ジャズといえば、その黎明期からシーンの中心で活躍してきたラテン・ジャズの重鎮であるスノウボーイが、今作にはコンガとパーカッションで参加しています。
■彼はある意味、時代の生き証人ですよね。その他に、ジャイルス・ピーターソンのようなDJが昨今のUKジャズの立役者のひとりでもありますね。彼は昨今また存在感が増してきているように感じます。
チップ:そうそう。彼は素晴らしいDJですし、プレイのなかでいろいろな音楽の要素を採り入れて、自分のものとしてDJで表現している。音楽に対する愛情や造詣も深さも含め、自分と共通性があるんじゃないかなと思いますね。
■よくわかりますね、それは。ルートレスであるがゆえの自由さや奔放さが、あなたにもありますものね。
チップ:私もそれなりに人生経験が豊富といいますか、世界中でいろいろな演奏をしてきたので、それも役に立っているのかなと思います。あと、セッション・ミュージシャンですごく腕のいい人を見てきたので、そういう人たちに影響されてきたというのもありますし。サルサもファンクもブラジル音楽も、シンガー・ソングライターもアコースティック・ジャズもUKのポップスも全部好きなので、今回のアルバムにもそうした要素は入っていると思いますね。

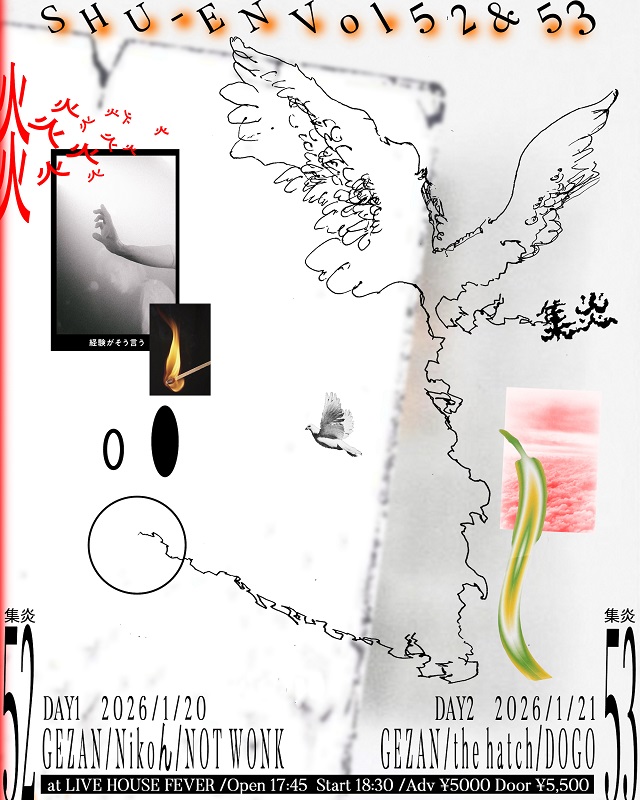





 FINALBY( ) LIVE in 歌舞伎町EXPANDED Photo : Masayuki Shioda
FINALBY( ) LIVE in 歌舞伎町EXPANDED Photo : Masayuki Shioda