MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > 6月のジャズ- Jazz in June 2023
これまで不定期に単発のレヴューを掲載してきたが、この度月一で4枚分のディスク・レヴューをまとめたコラムをおこなうことになった。私が取り上げるものは主にジャズ系の作品だが、いわゆる王道のそれではなく、他ジャンルの音楽がミックスされたものが多い。そもそもジャズを聴く前からロックやクラブ・ミュージック全般を聴いていたし、DJカルチャーに触れることによって折衷的な音楽の聴き方をするようになったから、ジャズにしてもソウルやファンク、民族音楽など自然といろいろな要素が融合したものを好むようになった。従って、ジャズを中心としつつも、それにとらわれることなく幅広い音楽を取り上げたいと思う。そして、DJをやっていると人が知らないレコードをプレイする楽しさを感じることがあるが、レヴューにおいてもそれは同じである。いろいろなところで取り上げられる著名アーティストではなく、どちらかと言えばあまり日の当たらないマイナーなアーティスト、まだあまり知られていな新人の方に目が向くことが多い。このレヴューでもそうした作品を積極的に取り上げられればと思う。
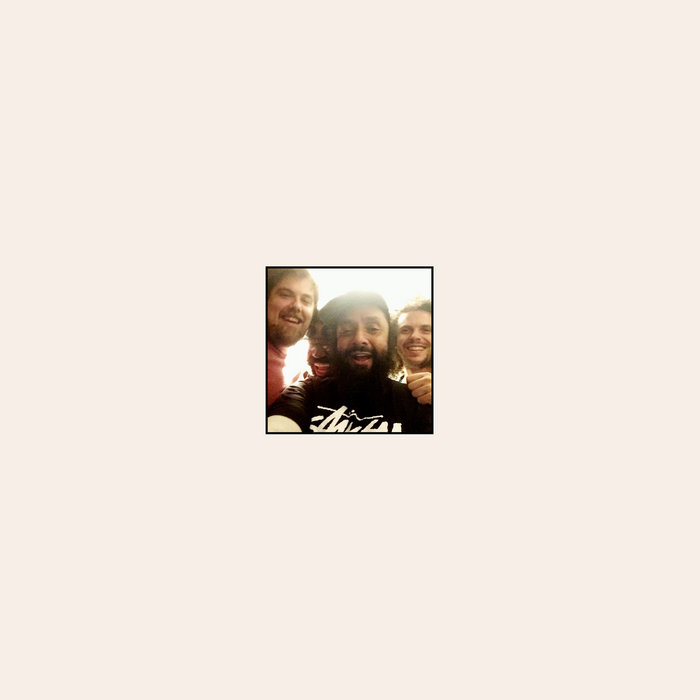
Speakers Corner Quartet
Further Out Than The Edge
OTIH / ビート
サウス・ロンドンのジャズ・シーンでは、既にシャバカ・ハッチングスやモーゼス・ボイドなど評価を確立したミュージシャンも多いが、一方で次々と新しい才能が芽吹いて新陳代謝がおこなわれている。スピーカーズ・コーナーズ・カルテットもそんな新しい集団で、もともとブリクストンでおこなわれていたスポークン・ワードやヒップホップのイベントのバック・バンドから発展している。メンバーはビスケット(フルート)、クウェイク・ベース(ドラムス、パーカッション)、レイヴン・ブッシュ(ヴァイオリン)、ピーター・ベニー(ベース)で、なかでもクウェイク・ベースはシャバカ・ハッチングスと1000キングスというユニットを組んでいたことでも知られ、レイヴン・ブッシュはマルコム・カット率いるファンク・バンドのヘリオセントリックスのメンバーだ。これまでにMFドゥーム、ディーン・ブラント、サンファ、ケイト・テンペスト、リアン・ラ・ハヴァスなどいろいろなアーティストと共演し、今回ファースト・アルバムの『ファーザー・アウト・ザン・ジ・エッジ』を完成させた。
サンファ、ケイト・テンペスト、ティルザなどこれまでの共演者のほか、シャバカ・ハッチングスやジョー・アーモン・ジョーンズらも参加しており、サウス・ロンドンにおけるジャズとその隣接する多種の音楽の融合を見せるアルバムとなっている。サンファが歌う “キャン・ウィ・ドゥー・ディス?” やコビー・セイが歌う “オン・グラウンズ” などのエレクトリック・ソウル、レイラーが歌う“ソープボックス・ソリロクワイ”のようなフォーキー・グルーヴ、ケイト・テンペストのポエトリー・リーディングをフィーチャーした “ゲロニモ・ブルース”、タウィアのダークなスポークン・ワード調のヴォーカルが光る “ラウンド・アゲイン” などのトリップ・ホップ系まで、だいたいの曲がシンガーやラッパー、詩人たちとのセッションとなっており、スピーカーズ・コーナーズ・カルテットの生まれてきたバックグラウンドを物語る。
また、ヴァイオリンを交えた編成というのが特徴で、全編における繊細なストリングス使いが奥行きのある空気を生み出している。カーク・ディジョージオ(アズ・ワン)を彷彿させるエレクトロニック・ジャズの “アキュート・トゥルース” にしても、変拍子のビートに絡むヴァイオリンの響きが他にない個性を生み出していく。そして、“ドレッディッド!” はレア・センが歌っているのだが、彼女も参加した昨年のウー・ルーの『ロガーヘッド』に共通するオルタナティヴな部分もある。クウェイク・ベースとレイヴン・ブッシュは『ロガーヘッド』の録音にも参加していて、ウー・ルーとは同じブリクストン出身ということもあってか、似た空気感を持つのかもしれない。

Aja Monet
When The Poems Do What They Do
Drink Sum Wtr
ジャズとポエトリー・リーディング/スポークン・ワードの融合では、アジャ・モネの『ホエン・ザ・ポエムズ・ドゥ・ワット・ゼイ・ドゥ』というアルバムが見事だ。ジャズはヒップホップが誕生する以前は詩の朗読のバックで演奏してきた歴史があり、ラスト・ポエッツやギル・スコット・ヘロンといったアーティストが生まれてきた。アジャ・モネはニューヨークのブルックリン出身の詩人/パフォーマーで、ニューヨリカンのポエトリー・カフェの「グランド・スラム」を拠点に詩の朗読のパフォーマンスをおこなってきて、詩集や著書もいくつか出版している。ブラック・ライヴズ・マターはじめ、有色人種や先住民族への差別やジェンダー問題に関する事柄など、社会問題を詩にしてきた活動家で、パレスチナのレジスタンス活動に関する書籍も出している。ハリー・ベラフォンテのドキュメンタリー映画『フォローイング・ハリー』にも登場する彼女にとって、『ホエン・ザ・ポエムズ・ドゥ・ワット・ゼイ・ドゥ』は初めて音楽をバックにしたファースト・アルバムで、そもそもは『ザ・デヴィル・ユー・ノウ』という短編映画の音楽から発展したものである。バック・ミュージシャンはアトゥンデ・アジュアーことクリスチャン・スコット(トランペット)、マーカス・ギルモア(ドラムス)、エレナ・ピンダーヒューズ(フルート)、サモラ・ピンダーヒューズ(ピアノ)など、アメリカの現代ジャズを代表する面々が務める。
“ブラック・ジョイ”、“ウェザーリング” など、これまで彼女が出版してきた詩集に音楽をつけた作品が並び、“イエマヤ” のようにラテン色豊かな作品もあり、非常にルーツ色豊かなアルバムだ。“アイ・アム” は自身の存在やアメリカの黒人のルーツに向き合うような作品で、アジャの声に対してパーカッションのみで綴る非常にシンプルな構成だが、詩の内容やアジャの声のトーンに対してまるで生き物のようにパーカッションが変化していくという、ジャズとポエトリー・リーディングの醍醐味が味わえる。“ホワイ・マイ・ラヴ?” のように優美なナンバーの一方で、“ブラック・ジョイ” のようなディープなスピリチュアル・ジャズ調のナンバー、ゴスペル的な “ザ・デヴィル・ユー・ノウ”、アフリカ色豊かな “フォー・ザ・キッズ・フー・リヴ” など、音楽的にも非常に優れたものが並んでいる。アメリカの女性詩人のアルバムでは、サラ・ウェブスター・ファビオの『ジュジュズ/アルケミー・オブ・ザ・ブルース』(1976年)がカルト的な傑作として知られるが、詩と音楽を両立させた『ホエン・ザ・ポエムズ・ドゥ・ワット・ゼイ・ドゥ』も、極めて重要なアルバムとなっていくだろう。

The Gaslamp Killer And The Heliocentrics
Legna
Cuss
スピーカーズ・コーナーズ・カルテットのレイヴン・ブッシュが属するヘリオセントリックスと、LAシーンの立役者のひとりであるDJのガスランプ・キラーが共演した『レンガ』。近年はプライヴェートのトラブルで活動も休止していたガスランプ・キラーだが、2020年に久々のアルバム『ハート・マス』をリリースし、それに続くのが『レンガ』となる。リーダー格のマルコム・カットがマッドリブ、DJシャドウ、イーゴンらと交流があり、LAシーンとも結びつきのあったヘリオセントリックス。ガスランプ・キラーも自身のミックス・テープにマルコム・カットのソロ作品を入れるなどしてきて、2013年にはヘリオセントリックスとのカップリング12インチをリリースしたこともあった。ガスランプ・キラーのツアーではヘリオセントリックスがバック・バンドにつくこともあり、両者の結びつきは深まっていく。そして、ガスランプ・キラーのアルバム『インストゥルメンタレパシー』(2016年)や『ハート・マス』にヘリオセントリックスはスポット的に参加していたが、『レンガ』は初めて一緒に録音したアルバムとなる。
この両者の共演作となると、内容は大体サイケデリックなジャズ・ファンクではないかと想像がつく。そうした予想にたがわず、ロウで荒々しい演奏とスペイシーなエフェクトがブレンドされ、ディープで幻惑的な世界が展開される。そうしたなかで、これまでヘリオセントリックスのアルバムでも度々歌ってきたスロヴァキア出身のシンガー、バルボラ・パトコヴァをフィーチャーした “シーズ・カミング” が出色の出来栄えだ。彼女のポエトリー・リーディングのような歌がまるで魔女の呪文のようで、カリフォルニアの伝説的なサイケ~電子ロック・バンドのフィフティ・フット・ホースから、ホークウィンドやゴングなどヨーロッパのスペース・ロックやプログレを連想させる。レイヴン・ブッシュはストリングス、エフェクト、キーボード、モーグ・シンセなどマルチに演奏しているのだが、パーカッシヴなトラックとスペイシーなSEで不穏な空気を作り出す “ウィッチズ・ウィスパー” などは、彼の手腕が大いに生かされたナンバーで、トリップ・ホップ的なアプローチが光っている。

Islandman feat. Okay Temiz and Muhlis Berberoğlu
Direct-To-Disc Sessions
Night Dreamer
トルコのイスタンブール出身のDJ/プロデューサーであるアイランドマンことトルガ・ベユクは、地元のトルコはもちろん、世界中の民族音楽を研究し、バレアリックなスタイルで自身の作品に取り入れてきたアーティストとして知られる。そんな彼がトルコ出身で、オリエンタル・ウィンドを結成して北欧などでも活動した伝説的なジャズ・ドラマー/パーカッショニストのオケイ・テミズと共演した『ダイレクト・トゥ・ディスク・セッションズ』。これまでこのシリーズは、シェウン・クティとエジプト80、サラティー・コールワールとウパジ・コレクティヴ、セウ・ジョルジとホジェー、ゲイリー・バーツとマイシャと、ジャズ、アフリカ音楽、ブラジル音楽、インド音楽など、新旧のいろいろなミュージシャンたちのセッションを実現してきたが、そのなかでも非常にユニークな顔合わせが実現した。また、トルコの民族楽器であるバグラマという弦楽器奏者のムーリス・ベルベロールも参加している。
オケイ・テミズといえば、DJからはトリッキーなパーカッション・トラックの “Denizaltı Rüzgarları” あたりが知られるが、今回のセッションでも当然取り上げていて、原曲の何とも言えないエキゾティックで摩訶不思議な感じを増幅させている。“Papatyalara” はアフリカ音楽やジプシー音楽のようなパーカッシヴな舞踏曲で、中近東と近いトルコならではのアラビックな旋律を持つ。アイランドマンのダンス・ミュージック的なセンスがうまく生かされた楽曲だ。アイランドマンのオケイ・テミズに対する敬意や研究がよく伝わってくる共演で、ガスランプ・キラーとヘリオセントリックスの共演同様に両者の個性や特徴を理解し、組み合わせた好企画と言えるだろう。
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE


