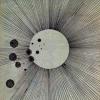MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Flying Lotus- Until the Quiet Comes
チル・ウェイヴが16ビートを取り入れるようになった→ダフト・パンクがブラック・ミュージックに近づく→ジェイ・ポールがソウル・ミュージックの文脈でそれをやったとき、「ジャスミン(デモ)」は2012年のベスト・シングルになることは決まっていた......のではないだろうか。
「ジャスミン(デモ)」はデビュー前から期待されていたシングルだった。昨年、プロモーションで撒かれた「BTSTU」をドレイクがさっさとサンプリングし、タナソーのように『テイク・ケア』を評価したリスナーには彼の名前は早くから浸透していたはずである。僕のようにドレイクはウェットでもうひとつだな......と、オッド・フューチャーやビッグ・クリットを好んだリスナーにもそれは伝わってきた。もうひとついえば、そんなことは何ひとつ知らなくても、どこからか「ジャスミン(デモ)」が耳に飛び込んできたリスナーにももちろんダイレクトにアピールしたに違いない。プリンスのファンであれば、それはもう、間違いなく。
ドレイクの名前は意外なところでも目にした。ドミューンでもすっかりお馴染みになったオンラのレーベル、〈キャットブロック〉から「プレイグラウンド」でデビューしたフランスのビート・メイカー、アゼルのデビュー・アルバム『ザ・ロスト・テープス』でも彼はラップを披露している。
アゼルのビートはどちらかというとデリック・メイを思わせる情熱的なもので、泣きのメロディに沈みたがるドレイクの趣味ではないと思えるものの、すけべの波長でも合ったのだろうか、2曲でさらっとしたフローをキめ、大物気取りのような嫌味は感じさせない(ドレイク以外にはイブラヒムが"ディス・イズ・ドープ"でふわふわと歌うのみ。ストリングスを厚く走らせたり、様々なメロディを細かく絡ませたがるアゼルもドレイク以外にMCを起用する気はさらさらないといった風情である)。
基本的には淡々とビートが刻まれるだけ。ほかに特記できることはない。"アイズ・イン"でも"シチュエイション"でもデリック・メイを遅くして聴いているようなもので、スローモーションでスウィングしていく感じは古典的なメロウネスにも直結するものがある。それが夏のダレきったムードに合ってしまうことこの上なく、この夏はけっこう重宝した。フランスのヒップホップというと、基本的にはユニオンのような(二木好みの)古くさいファンク趣味や、デラのようなラウンジ系がほとんどで、アゼルのようなタイプは珍しい。そう、フランス文化にはそぐわないストイックな作風は、おそらくフライング・ロータスの影響によるもので、ハウスではシカゴ発のディスコ・リコンストラクションからダフト・パンクがブレイクするまでに4年ぐらいはかかった計算だとすると、ここでもフライング・ロータスがセカンド・アルバム『ロス・アンゼルス』で注目を集めてからも同じく4年が経過し、フランス人が手を出すにはちょうどいい頃合ともいえる。続くフースキーやスクラッチ・バンディッツ・クルーといった変り種も控えているけれど......(フランス人のヒップホップに興味が湧いた方はぜひ、ドッグ・ブレス・ユー『ゴースツ&フレンズ』のジャケット・デザインもチェック→)。
世界中のビート・フリークが注目するフライング・ロータスことスティーヴン・エリスンの4作目は、しかし、かなり方向性を修正してきた。『ロス・アンゼルス』から『コスモグランマ』への発展を歓迎した人は腰が引けるかもしれないし、『ロス・アンゼルス』では過剰に封印されていたジャズを前作で解き放ったことの意味が明快になったと感じる人もいるだろう。「静けさが戻るまで」というタイトルから察するに、自分の身に起こったことがいかにも騒々しいことで、自分のペースを取り戻したいという願いから導き出された音楽性なのかもしれないし、「騒々しいこと」を正確に映し出したものとも考えられる。そのときにつくられたものが一大トリップ絵巻のようなストーリーテリングのそれであったことは、やはりレイヴ・カルチャーの渦に呑み込まれた90年代初頭のフランクフルトからスフェン・フェイトが『アクシデント・イン・パラダイス』でチル・アウトを希求したことを思い出させ、ほんの数ヶ月前にシャックルトンがやはり似たような組曲形式のものに『ミュージック・フォー・ザ・クワイエット・アワー』というタイトルを与えていたことを連想させる。いずれにしろ尋常ではないスピードで動いているものがなければ、それとは反対の概念に価値が求められることはない。きっと......嵐の中心は静かだということなのである。
僕が『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』を聴きながら頻繁に思い出したのは90年代にラウンジ・リヴァイヴァルの先頭に立ったジェントル・ピープルである。オープニングから数曲はそれこそイージー・リスニングじみたフュージョンを思わせるテイストにまみれ、あまりに素直なバリアリック・モードにはしばらく不可知の未来に置き去りにされてしまう。すっかり陽気になり、ときにボトムが弱く、ティンバランドのようにハイハットで手繰り寄せていくビートはオフ・ビートが効きまくったエレクトロニカにも聴こえるし、『コスモグランマ』からの脈絡を重視していると、マジで時間軸を見失いかねない。『パターン+グリッド・ワールド』のスリーヴ・デザインで全開になっていた世界最強のドラッグとされるDMTを扱ったらしき曲はまさにジェントル・ピープルそのままに聴こえてしまうし......(DMTに関してはサイエンティック・アメリカンの副編集長だったジョン・ホーガン著『続・科学の終焉-未知なる心』を読むしかない!)。なぜかトム・ヨークがドラッグのディーラーについて示唆する曲もエアリアル・ピンクやコーラと同じくノスタルジックな意味合いでシクスティーズが裏側にべったりと貼り付いたようなところがあり、ロング・ロストのローラ・ダーリングトンによる艶かしいヴォーカルが聴こえてくる頃には、あたりの景色はすっかり『バーバレラ』のセットに様変わりしている(橋元さんがモバイル・スーツに着替えるタイミングですね)、エンディングはまさしく「空飛ぶ蓮」である。この陶酔感は実に純度が高い(古代ギリシャでは、想像上の植物であるロートスの実を食べると、浮世の苦しみを忘れて楽しい夢を見ると考えられていた)。
フライング・ロータスの変化のスピード感は、現在のLAの様相をそのまま反映しているのだろう。それは内容的なものと同時に消費の速さでもあり、ムーヴメントの常識として荒廃の予感が押し寄せてくるという時間感覚との闘争でもある。それを単純にどこまで先延ばしにできるか。60年代のビートルズや90年代のジ・オーブに課せられたものと同じものに追いかけられるという幸福感が『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』には漲っている。さらなる飛躍をもたらすかもしれないし、たった1作で崩壊してしまうかもしれないLAの現在。あれが「終わりのはじまりだった」といわれる可能性だってあるし、そのすべてを左右する1作になる可能性は高い。フライング・ロータスは少なくともそれぐらいの冒険はしている。ジミ・ヘンドリクスやジーザス&メリー・チェインはあの後、どうすればよかったのかということでもある。現在のLAからは次から次へと才能が出てくるし、ジェレマイア・ジェイのように〈ブレインフィーダー〉と契約したミュージシャンだけでなく、同じシカゴからアン・アッシュやメデリン・マーキーまでがカリフォルニアに移住してくるなど、全米からミュージシャンが押し寄せているような印象があるなか、そのなかの誰かがフライング・ロータスの位置に取って代わってくれるわけではない。フランクフルトのレイヴ・カルチャーはスフェン・フェイトの失速とともに一度は崩壊している。それでも彼は静けさが回復することを願って、このような作品をつくった。ジェントル・ピープル版『アクシデント・イン・パラダイス』を。そして、それはエミネムがMDMAを摂りはじめたあたりからヒップホップ・サウンドが辿り付くべきものだったのかもしれない。カレンシーもウィズ・カリファも皆、そのための通過点だったと思えてくる。
同時期のリリースとなった『マーラ・イン・キューバ』は聴くたびに印象が二転三転した。ダブステップという明確な落としどころがあり、しかもオールドスクールの実験であることに思い至れば難しいことはなかったのだけれど、そのような基本を忘れてしまう仕掛けがあのアルバムには張り巡らされていた。『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』にも同じことがいえる。ヒップホップ・ミュージックで『サージェント・ペパーズ〜』をやろうとしたプロデューサーがいなかったのだから、梯子から落ちやすいのも仕方がないけれど、何よりも重視されているものが「流れ」であり、その強さに負けて、ほかのファクターが頭や耳からは抜け落ちやすい。かつてデイジー・エイジと称揚されたデ・ラ・ソウルにしろ、かのクール・キースにしろ、効果として狙ったものはあったかもしれないけれど、ヒップホップのグラウンド・デザインに深くメスを入れて、ここまでトリップ性を優先させるものはなかった。クリシェに倣っていえば「こんなものはヒップホップじゃない!」し、そう言わせるための作品だとしか思えない。面白いというか、『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』にもっとも似ていると思うのは、LAがまだ「静か」だった時期にダブラブが同地のプレゼンテイションとしてまとめた『エコー・イクスパンション』(07)というエリア・コンピレイションで(09年に曲を増やして再発)、カルロス・ニーニョにはじまり、フライング・ロータスやラス・Gを経て、デイダラス、ディムライトと続く「流れ」はなぜかラウンジ・テイストのものが多く、クートマやテイクを経て、クライマックスはマシューデイヴィッドによる強烈なアンビエント・チューンになっている。フライング・ロータスが考えている「静けさ」がここで展開されているサウンドを想定しているのなら、彼はまさにこの時期に戻りたいと(無意識に)願っていると考えてもいいのかもしれない。
アトム・ハートに背後から膝カックン(=Using your knee to kick someone else in the back of their knee)をやられたようなフライング・ロータスに代わって、かつてのフライロー・サウンドを引き継ぎ、そこにワールド・ミュージックの要素を豊富に放り込んだのがガスランプ・キラーことウイリズム・ベンジャミン・ベンサッセンのデビュー・アルバム『ブレイクスルー』だろう。僕は発売前の音源を法律的に貸与されてレヴューを書くことはあまり好きではないのだけれど、そうはいってられない場合も増えてきて(つーか、そのような制度を採用しているのは日本だけらしいんだけど)、毎月2周目などはそういったものばかり聴かなければならないし......ということはさておき、そのようにして同時に手渡されたフライング・ロータスとガスランプ・キラーの音源がもしも入れ替わっていたら、後者を聴いて前者が『コスモグランマ』から『ロス・アンゼルス』に揺り戻す際にワールド・ミュージックやホラー・テイストを加えたものだと判断したのではないかという可能性がなかなか捨て切れない。ひとつにはフライング・ロータスにはどこか重厚なイメージがあって(多分に「テスタメント」のせい?)、それが『ブレイクスルー』にはあるけれど、『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』にはほとんどなく、どちらも華やかな印象にあふれているのは現在のLAのムードが反映されているからだとは思うけれど、それでも少しは引いた部分が『ブレイクスルー』にはあって、それもフライング・ロータスに(勝手に)投影していたイメージに近いからである。それだけ『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』が飛躍しているということでもあり、かつてのデトロイト・テクノのような通奏低音が現在のLAには流れているということでもあるだろう。
最初期からロウ・エンド・セオリーのレジデントを務めていたというベンサッセンは、ゴンジャスフィのプロデューサーとして知名度を上げたのもなるほどで、似たようなカップ・アップ・サウンドをやらせても如実に都会的なリー・バノンとは違って、どこかヒッピー的なところである。『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』と同じく、トリップ・ミュージックとして構想されていることは明らかだけど、フライング・ロータスが執拗にシクスティーズをリファレンス・ポイトにしているのとは違って、時間軸はむしろイメージを混乱させるために悪用され、それこそウイリアム・バロウズの「時間旅行で乗り物酔い」を思わせる。アトラクションは次から次へと入れ代わり、デイダラスと組んだ「インパルス」など、いまのはなんだったのだろうとトリックめいた印象を残す曲が多く、『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』のように全体で何か訴えかけるような性格は持たされていない。ディムライトとはトラン・ザム以上バトルズ未満みたいなマス・ロックもどきに仕上がっているし、カルロス・ニーニョ率いるビルド・アン・アークからミゲル・アトウッド-ファーガスンとの"フランジ・フェイス"などはイタリアのホラー映画みたいだし......。
ただし、サーラ・クリエイティヴからフサインとキースをフィーチャーしたボーナス・トラック「ウィッスル・ブロウアー(=内部告発)」は(紙エレキング6号にも書きましたけれど)国連がサラエボで傭兵のために売春婦を斡旋している組織と裏でつながっていたという史実を扱った映画『トゥルース 闇の告発』の原題と同じだったりするので(主演がレイチェル・ワイスだったにもかかわらず日本未公開。アメリカでも国連が圧力をかけたのかほとんど公開されず)、「サラエボ」とか「内部告発」といった歌詞が断片的に聞き取れたので、それについてのものだということはすぐにわかるし、これは、現在のLAを支配している気分やトリップ・ミュージックとはかなり異質のものである(だから、日本盤のみのボーナス・トラックなのだろう。それとも、これが現在のLAと何か関係のある曲だというなら、ここまで書いてきたことはすべて崩壊するしかない)。
レイヴ・カルチャーが社会の表面に姿を現した当時、イギリスのマスコミがそれにセカンド・サマー・オブ・ラヴという呼称を与えたことを受けて、それをいうならアメリカで起きていることはセカンド・ロング・ホット・サマーと呼ぶべきではないかと書いたことがある(いまだにひとりも賛同してくれた人はいません~)。つまり、80年代後半のダンス・カルチャーはヨーロッパの白人とアメリカの黒人には正反対とまでは言わないけれど、社会的な意味はけっこう違ったということで(何度も書いたようにボム・ザ・ベースのように連想ゲームのようなことが起きた例もあるし、ア・ガイ・コールド・ジェラルドやチャプター&ザ・ヴァースのように裏目に出た例もある)、しかし、それが、現在のLAでは、白人にも黒人にも少なからず同じ意味を持つ音楽になっているのではないかということを『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』からは感じ取れるのではないかと。マーティン・スコセッシ監督『ヒューゴの不思議な発明』とともにどうしてアカデミー賞を取れなかったのか不思議でしょうがないテイト・テイラー監督『ヘルプ』のような映画を観ると(『ハート・ロッカー』に続いて『アーティスト』の受賞は本当にナゾでしかない)、60年代にもそのような事態は実際には部分的にしか存在しなかったのだろうということも想像はつくけれど、それでもモンタレー・ポップ・フェスティヴァルにはオーティス・レディングが出演し、聴衆に向かって「愛し合ってるかい?」と問いかけたことは、セパレーティスム(分離主義)を掲げていたパブリック・エナミーとは異なるヴァイブレイションの産物だったはずで、そのような融和が少しでも現在のLAには存在しているのではないかということが『アンティル・ザ・クワイエット・カムズ』と、そして、マシューデイヴィッド『アウトマインド』という2枚のトリップ・アルバムによる響き合いのなかから聴き取れるのだと僕は思いたい。そして、その青写真を与えたのはザ・ウェザーの3人だったのではないかと。デイダラス、バスドライヴァー、そして、レイディオインアクティヴの3人がはじめたことがここまで来たのではないかと。
デイヴィッド・ベニオフの原作に同時多発テロを背景に加えたスパイク・リー監督『25時』はニューヨークを舞台にしながら、最終的にはLAを目指す心性が描かれていた。ブロークン・ウインドウズ理論を振りかざしたジュニアーニによるジェントリフィケイションも少なからず影響はあっただろう。それまでは、アメリカの各州から夢を抱いた若者が出てくる都会といえば、圧倒的ニューヨークだったのに、スティーブ・アンティン監督『バーレスク』でも、デヴィッド・フィンチャー監督『ソシャル・ネットワーク』でも、目指す都会はLAであり(かの『ボラット』も!)、あっという間にエレン・ペイジを過去に押しやったクロエ・グレース・モレッツがついに初主演を演じたデリック・マルティーニ監督『HICK ルリ13歳の旅』も最終目的地はLAに設定されていた。シリコンヴァレーからはじまる物語は音楽文化だけの話ではない。フランク・ダラボン監督『マジェスティック』やガス・ヴァン・サント監督『ミルク』は過去のLAを検証し直し、F・ゲイリー・グレイ監督『ビー・クール』、リサ・チョロデンコ監督『キッズ・オールライト』、アレクサンダー・ペイン監督『サイドウェイ』、中島央監督『Lily』......と様々に夢が語られる。いまさらのように『ランナウェイズ』の伝記映画までつくられ、もちろん、マーク・クラスフェルド監督『ザ・L.A.ライオット・ショー』やジョー・ライト監督『路上のソリスト』のようにダークサイドを描いた作品も力作が多い。
そんな気運のなか(?)、信じられなかったのは2008年にLAタイムズが発表した「LAを舞台にした映画ベスト25」である。
1位「L.A.コンフィデンシャル」(カーティス・ハンソン監督)
2位「ブギーナイツ」(ポール・トーマス・アンダーソン監督)
3位「ジャッキー・ブラウン」(クエンティン・タランティーノ監督)
4位「ボーイズ'ン・ザ・フッド」(ジョン・シングルトン監督)
5位「ビバリーヒルズ・コップ」(マーティン・ブレスト監督)
6位「ザ・プレイヤー」(ロバート・アルトマン監督)
7位「クルーレス」(エイミー・ヘッカリング監督)
8位「レポマン」(アレックス・コックス監督)
9位「コラテラル」(マイケル・マン監督)
10位「ビッグ・リボウスキ」(ジョエル・コーエン監督)
11位「マルホランド・ドライブ」(デビッド・リンチ監督)
12位「ロジャー・ラビット」(ロバート・ゼメキス監督)
13位「トレーニング・デイ」(アントワーン・フークア監督)
14位「スウィンガーズ」(ダグ・リーマン監督)
15位「青いドレスの女」(カール・フランクリン監督)
16位「friday」(F・ゲイリー・グレイ監督)
17位「スピード」(ヤン・デ・ボン監督)
18位「ヴァレー・ガール」(マーサ・クーリッジ監督)
19位「L.A.大捜査線/狼たちの街」(ウィリアム・フリードキン監督)
20位「L.A.ストーリー/恋が降る街」(ミック・ジャクソン監督)
21位「To Sleep with Anger」(チャールズ・バーネット監督)
22位「レス・ザン・ゼロ」(マレク・カニエフスカ監督)
23位「フレッチ/殺人方程式」(マイケル・リッチー監督)
24位「Mi Vida Loca」(アリソン・アンダース監督)
25位「クラッシュ」(ポール・ハギス監督)
『サンセット大通り』も『チャイナタウン』も『ブレードランナー』もなければ『エリン・ブロコビッチ』もないし、『モーニング・アフター』も入っていないではないか......。『ハードコアの夜』も『奥さまは魔女』も......どういうことなんだろう......
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE