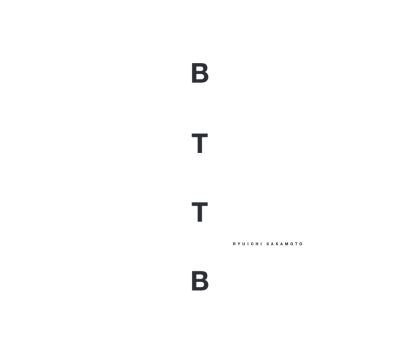MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > 坂本龍一追悼譜- 海に立つ牙
3日前の便り
3月25日の夜9時24分、パートナーの方から初めてメールが来た。
そこには、本人は送れないので「事情ご拝察のほど」とある。
「ああ、とうとうなのか」
白紙になった内心の画面にそういう文字列が浮かぶ。
私は高校時代以来の付き合いだが、彼の他界を事実として知るのはみなと同じ。4月2日のTwitterを見た時である。
その間の1週間、なにをしていたのだろうか。
8年ぶりに新しい本を出す。その準備と新宿御苑に放射能汚染土が運び込まれる問題。両方で動きまわる。言葉どおり忙殺される毎日だった。
一人の友が小舟を漕いで遠い海に去っていく。その背中を岸辺で見送るしかできない。もう声は届かないだろう。遠く夕陽が落ちていく水平線。その橙色のハレーションに吸い込まれる後ろ姿がどんどん小さくなるのである。
あるときは最後から3番目の作品、映画音楽『レヴェナント:蘇えりし者』。
あらためてその音源を聴いた。
レオナルド・デカプリオ演じる主人公が熊に体を抉られて森に横たわる場面。瀕死のまま夜の大空を見上げる。ミズーリ川沿いの大森林地帯を覆う濃紺の夜陰。無数の星々がぶちまけられている。息子を連れ去った裏切り者への怒り。さらに先住民から学んだ智慧が、彼を大地から立ち上がらせるのである。その眼が急流を見つめている。そんなシーンを思わずにはいられなかった。
だが坂本龍一が蘇ることはなかった。
結局、汚染水拡散反対を語るメッセージの公開も、私の新著『鉛の魂』も病床には間に合わなかったのである。
諫めること
諌死という古い言葉がある。
坂本龍一が去ってしばらく、そんな言葉が浮かんでいる。
彼の優美というべき「諫死」をどう受けとめたらいいのか?
しきりにそう思う。政治的にというより、『レヴェナント』や『async』、そして『12』の音響は、なにか大きな諌めを聴く者の身体に及ぼすからだ。
どういうことなのか。
ピアノが低く響くなか、大きな力に抗いつつ逝った彼の姿に、晩年のフーコーがギリシャから蘇らせた「パレーシア」を思う人もいる。「正しく生きて死を迎えること」。その姿勢を最後まで貫いた。そう言えるかもしれない。
けれども私は、彼の孤独な打弦に「畏れ」を聴いてしまうのである。最期の3作が連作のように聞こえる。その印象は絶えることなく寄せては引いていく宇宙のさざ波だ。エリック・サティのピアノ譜には簡素な部屋がふさわしい。坂本が遺した水面には長い残照が見えるのである。
諌死(かんし)ってなんだろう?
東アジアでいう諫死とは、ふつう君主の過ちを臣下が死をもって諭すことだ。「論語 徴子篇」が出典らしい。主君と家臣がいた時代の話である。
それをあえて演じた、三島由紀夫による半世紀前の惨死劇を思い浮かべればいいかもしれない。作家は駐屯地のバルコニーから「武士」になろうとしない自衛隊員を叱る。それは生き延びたスメラギを諫める声でもある。ところが下に集まる隊員たちはその説教にいら立つ。カルダンの制服を着た彼は戦地に行かなかったんじゃないの? ということはまあ措こう。
なんでこんな話を――と思うだろう。
実際私たちがまだ若い1970年11月25日、ハドソン川に浮かんだアルバート・アイラ―の訃報に心騒めく私と違って、坂本龍一は三島の首を見とどけようと市谷の坂を下るような人だった。同じ高校の3年生と2年生。前年の9月に校長室を占拠してから14か月たつ。
この日の夜、新宿通りに面したピットイン・ティールームの奥まった席で、彼はすこし興奮していた。アイラ―を悼んで『ニューグラス』を聴きたい後輩に、『天人五衰』は読んだ?なんて呟く先輩なのである。麻薬の売人に殺されたテナーマンに惹かれる私は返答に困る。新宿二丁目青線のガキは四谷の高台で育った小説家にさして興味がなかったからだ。
17歳同士でそんな会話をしたのは、私にとってつい昨日の出来事である。
時の亡霊
しかし、半世紀たった坂本龍一の去り方はまた違うと思う。
遺作『12』は「水になれ」と私には聴こえるのである。
「海ゆかば」ではない。水平な諌めの譜である。そこには君も臣もいない。夕闇が迫る海と空の境い目あたりに去っていくピアニストの後ろ姿が浮き沈みするのである。
それは、かつて彼自身が「戦場のメリークリスマス」は「海ゆかば」になってしまった――と密かに語ってくれたからだ。大島渚は先に逝った。それでも公式のステイトメントにこんな言い方は出てこないだろう。
海ゆかば 水漬(みず)く屍(かばね)/山行かば 草生(む)す屍
大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ/かえり見はせじ
――自分の死体が海に浮かび、山野で草が生えたとしても、私は天皇の傍で死のう。自分のことは決して顧みずに。詩は万葉集に採られた大友家持の長歌だ。この歌を5歳のころ聞いた1939年生まれの演出家、鈴木忠志はその思い出を書いている。
私の戦争の記憶の中では、とび抜けて忘れられない旋律である。戦争が子供心にもたらした、唯一のすばらしい記憶と言っていいかもしれない。むろん当時の私には歌詞の意味はわからなかった。後に理解した時には、茫然たる想いにさせられたことは覚えている。
(SCOT ブログ鈴木忠志「見たり・聴いたり」、2011年6月23日より)
悠久なる日輪の王。その荘厳に吸い込こまれる透明な死。その酩酊。1963年には11歳だった私の感想もたいして変わりない。なんだかわからないが、とにかく雄々しく潔い。
それでも戦後生まれの少年。赤塚不二夫「おそ松くん」が載る『少年サンデー』が待ちどおしくてたまらないガキは、同時に『少年マガジン』で始まったちばてつやの連載「紫電改のタカ」にも惹かれる。初戦の勝利を飾ったゼロ戦と壊滅へ向かう戦争末期の紫電改は違うのである。ちばてつやの絵には幼い航空兵たちが南の島で生きようと思い悩む日常がある。大戦艦の艦橋から見る将官の眼ではない。
前衛ばかりじゃないです、私たちも。坂本龍一と「紫電改のタカ」やうなぎ犬の話もするんだったなと思う。
つまり「音楽は魔術」。Yellow Magic以前に、こういう違和感は坂本にも鋭く共有されている。だから1983年に自分自身が創った「戦場のメリークリスマス」のメロディーに、中国市場に進出する企業戦士たちの新しい「海ゆかば」が聞こえてしまうのである。大陸の経済が列島のそれを凌駕する25年前だ。
これは二つの作品の比較楽曲分析ではまるでない。軍神の碑を爆破して始まる東アジア反日武装戦線の闘い。彼女/彼らが検挙されて7年という時代精神が、二つの曲に流れる音脈をつなぎ、かつ聴き分けるのである。
時代精神のドイツ語原義は「時の亡霊」である。音楽こそ亡霊。20世紀の経験は私たちにさまざまな「亡霊」たちと付き合う術を教えてくれたのである。
水になれ
私の中にも亡霊が棲んでいる。
そのゴーストが『12』の楽曲を「水になれ」と聴く。
「水になれ、Be Water」はブルース・リーの娘シャノンが書いた伝記に由来するという。その起源とされる『老子』の一篇を引こう(保立道久 現代語訳『老子』、ちくま新書』)。
上善若水:上善(じょうぜん)は水のようなものだ。水の善、水の本性(もちまえ)は万物に利をあたえ、すべてを潤して争わない。水は多くの人の嫌がるところに流れこむ。水は道に近いのである。(原著8章、現代語訳9講)
「善」と聞けば、誰でも説教臭い声を感じる。そこに異を立てる保立によれば老子の「善」
という考え方は、倫理的な「良い・悪い」と違って本性が自由自在な状態を意味するという。
言ってみればこれはanarchyなのである。そしてその「善」を主語としてこの一篇を読む。
ベースには『論語』への対置がある。とりわけ孟子が上からの「仁政(おめぐみ)」を強調したのに対して、老子にとって「仁」とは「友の善」のことだと保立はいう。紀元前4世紀の中原で交わされた哲学論争の当否を判断する知識が私にはない。それでも直観する。
最高のanarchyは水のごとし。仁なる政とは「友のanarchy」である。
これは驚くほど爽快な理解である。
ここまでくると、さらにジャンプした我流である。しかし1968年の小川環樹訳で『老子』に接した者には跳躍が必要である。もちろん坂本龍一も読んでいる。そして『12』には全編にわたって「水」が流れているのである。彼とは最期にこういう話がしたかったと切実に思う。
亡くなって25日たった4月22日の夜、神宮外苑絵画館前に6000人が集まった。彼のポートレートの傍らで樹木伐採に抗して立つ人びとの体内からは水音が聞こえる。木々には天地から水が流れ込み、そして流れ出ていく――と、私の亡霊が呟くのである。
海に立つ牙
と同時に、『async』になにか「牙」のようなものを聴きとる。
彼は息をする最後まで「癒し」の感情を拒んだと思う。
厳かな多重音が連なる。としても複雑な不協和音からさえ旋律は逃れる。三味線を弾く撥(ばち)から和を抜く。水の流れを清めつつ濁らせる。『12』でも、「戦場のメリークリスマス」ならオリエンタルな和合になじんでしまう波間に微かな白波が立つ瞬間がある。さらに2つの作品には、フレデリック・ジェフスキー「不屈の民」の欠片が飛び散っているのである。これは魂を濾過しなければ聞こえてこないだろう。
「始源のサカモト」が形を変えて帰ってきた。最期の3作はそう聴こえてくるのである。
1980年代に彼はYMOに加わり、私は山谷に流れる。バブルへ向かう時代を真逆の場所で生きたのである。それから30年近く「異論のある友情」の位置を保ってきた。これはけっこう難しい。彼がローランドのシンセサイザーを駆って世界ツアーした1年後に、寄せ場の闘いに加わった私は地面に転がる友人二人の死体を見ていた。山谷の映画を撮った二人は日の丸を背負う極道に殺されていた。それでも微かな接触はある。
とはいえお互いに「時の亡霊」の乗りこなし方を覚えたのは、この30年間だったと思う。悪性新生物が私たちをもう一度引き合わせる。近づく死霊の影は、どうしても死にきれない魂を呼び戻すからだ。
始まりの3作。1976年『ディスアポイントメント・ハテルマ』、1978年『千のナイフ』、1980年『B-2 UNIT』。ここにはよく砥がれた牙がある。そして電子音の歯牙を突き立てるのをためらう一瞬がある。この刹那が別の次元を開く。その技に知的な胆力を感じた。
例えば「Riot in Lagos」。これは黒人音楽への坂本龍一の若い応えだ。まだ朴訥な機械状ファンク。腐乱したビートをかき集めて動く心臓。その心壁に触れる0.1ミリ手前で電子メスの手を止める。これが牙だ。終わりの3作でも、遠く海の彼方に去る海獣の背にそんな牙が朧げに浮かぶのである。
ともに新生物を宿して暮らすようになってから、メールでは「龍一氏」と呼びかけるようになっていた。ベタに名を呼びながら敬意を添える。遠近を含む奇妙な言い方だが、今は水平線に向かってこう聞いてみたいのである。
―――龍一氏、奈良の暗殺者をどう思う?
ただ一人の標的だけを精密に消した者の「義と技」を、病床にいた彼はどう受け止めたのだろうか。2年前とりあえず新生物をいなした私に「おまえはいいよな」と書き送ってきたことがある。そこまで言う彼の病状は、ついにこの重い問いを許してくれなかった。
だが、痛みの中で彼はこのことを考えていただろう。
私の牙がそう言う。
坂本龍一は私にとって、いつまでもそういう「海の牙」なのである。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE