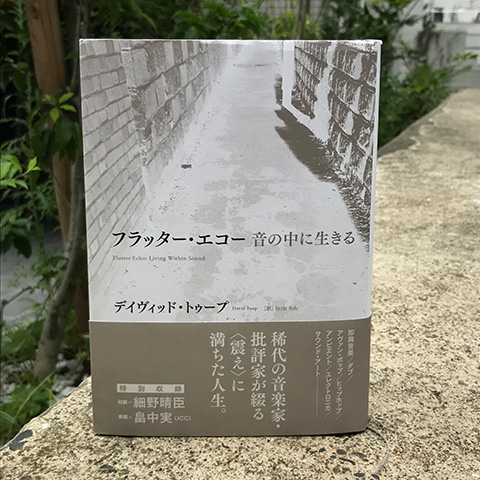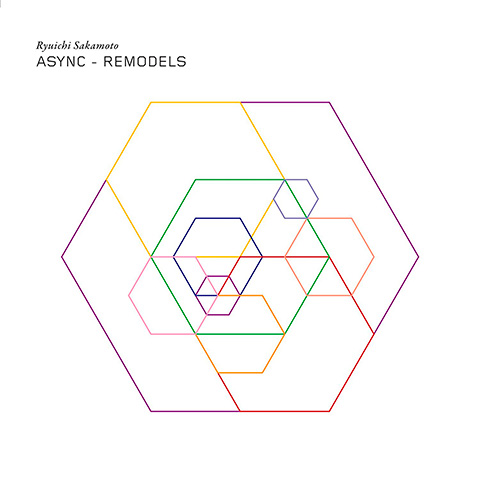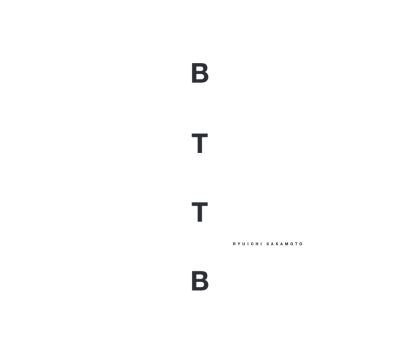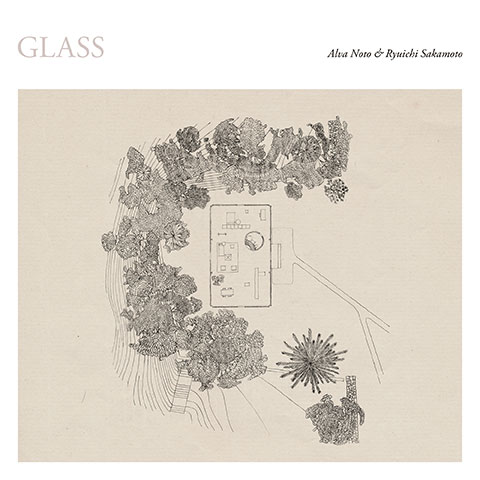MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ryuichi Sakamoto + David Toop- Garden Of Shadows And Light
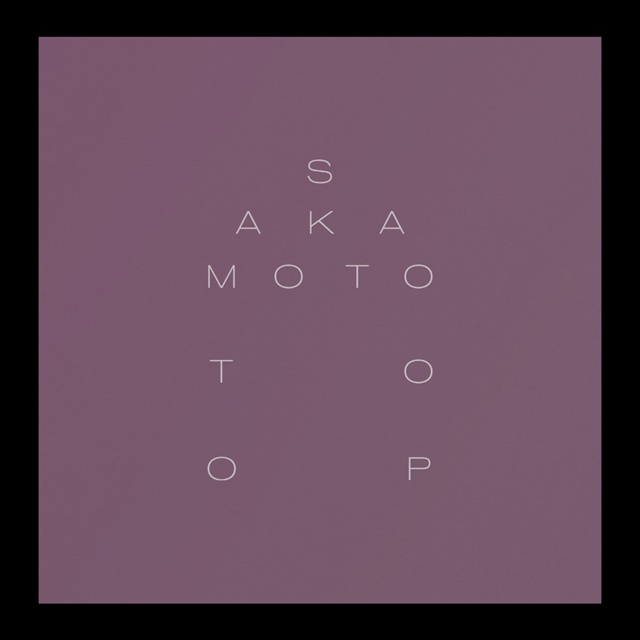
薄灯りの、仄暗い空間を、ゆっくりと行き先を探りつつ、しかし確信を持った足どりで進むかのごとき音の交錯、ざわめき。
坂本龍一とデイヴィッド・トゥープの演奏(いや音の生成とでもいうべきか)を記録した音響作品『Garden of Shadows & Light』には、まさに静謐な音の対話のようなサウンドスケープが生まれていた。
リリースはロンドンのエクスペリメンタル・レーベルの〈33-33〉からだ。カタログ数はそれほど多くないレーベルだが、灰野敬二とチャールズ・ヘイワードの共演盤などをリリースするなど、その厳選されたキュレーションが魅力的なレーベルである。
それにしてもなんて美しいアルバム・タイトルだろうか。その名のとおり本作『Garden of Shadows & Light』にはサウンドによる陰影の美学がある。坂本とトゥープが鳴らす音たちの群れは、淡く、微かにして、しかし強い。偶然の豊かさを消し去ることもない。フラジャイルな音にすらも、豊穣な気配が生まれているのだ。
坂本龍一とデイヴィッド・トゥープは音の時間のなかを思索的に、もしくは遊歩的に進む。音の気配に敏感になり、耳をそばだて、繊細な手仕事のように音のオブジェクトを組み合わせる。そうして静謐で濃厚な音響空間が生成されていく。
冒頭、何か叩くような、カーンと澄み切った音が鳴り響く。それに応えるかのように、やや小さな音がカツンと鳴る。やがて何かを擦る微細な音が鳴り、弦の音の残滓のような音も聴こえてくる。音はやがて音楽の原型のような響きへと変化するが、しかしそれはノイズのテクスチャーのなかに溶け込んでいく。そしてまた別の音がやってくる。彼らふたりは音を招き寄せている。
本作には「音が訪れる」感覚がある。「おとがおとずれる」「音が音ズレる」とでも書くべきか。非同期の音たちの群れ。しかしひとつの大きな(ミニマムな?)時間を共有もしている。そのズレと時間の交錯が、音の気配を豊かにする。
このレコードの秘めやかで、大胆な音の生成、対話、群れに耳を澄ます私たちもまた彼らが生成する音の時間に引き込まれ、音の変化、歩みを共にし、音の存在に敏感になるだろう。一音一音の存在に驚き、まるで一雫の水滴の音を聴くように静謐な時間をおくることにもなるだろう。
『Garden of Shadows & Light』は、2018年、ロンドンはシルヴァー・ビルディングでおこなわれたライヴの録音である。映像も配信されていたので、すぐに観たことを記憶している。私は「手仕事としての音響工作」を満喫した。これぞブリコラージュと感嘆したものだ。
なによりテクノ(ポップ)以降、20世紀後半における電子音楽のレジェンドである坂本龍一と、批評家、キュレイターとして、そしてサウンド・アーティストとしても長年に渡って活動を展開する才人デイヴィッド・トゥープとの饗宴には大いに興味を惹かれたのである。
それから三年の月日が流れ、いまや伝説的な演奏となった音源が本年「録音作品」としてリリースされた。いま、こうしてレコード作品となったふたりの「演奏」を改めて聴き込んでみると、配信されたライヴ映像とは異なる印象に仕上がっていたことに驚きを得た。もちろん音は同じだ。しかしサウンドがもたらすパースペクティヴや時間が新鮮なのである。視覚情報が欠如されたことによって、音に対する認識が変わったのかもしれない。
加えて坂本龍一とデイヴィッド・トゥープのこの音響ノイズ演奏には、音楽家における老境の境地が横溢していたことにも気がついた。特に本作に限らず近年の坂本の「音そのもの/音それじたい」をコンポジションするようなサウンドからは、まるで「音響のモノ派」、もしくは音の「侘び寂び」を感じた。音それ自体への感覚が横溢し、肉体性から離れ、音やモノや空気としめやかに同一化するような音響が生まれているのだ。突如として音が鳴り、それが静謐な空間性に即座に融解し、持続の只中に溶け込んでいく。音が刹那と永遠のあわいにある。
まさに「音の海」(トゥープ)と「async」(坂本龍一)の融合か。もしくは消尽の美か。自分などはこのアルバムを晩年のサミュエル・ベケットに聴いて欲しかったと思ったほどである。もしくは武満徹に聴いてほしかったとも。武満ならばこのアルバムの、演奏の、そしてサウンドスケープを大絶賛したのではないか。
西洋音楽を学んだ日本人音楽家が安直なオリエンタリズムに陥ることなく、日本、東アジアの音響・音楽を実践すること。それによって「世界」という場に立っていること。これは本当に稀有なことだ。坂本龍一は音そのものの原質に触れようとしている。
00年代以降のアンビエント/ドローンを基調とした音楽作品を生み出した坂本龍一は、まずもってここが重要なのだ。高谷史郎と坂本龍一のオペラ『TIME』の東洋と西洋、ネットフリックス配信の『ベケット』の職人的な音楽のなかに不意に満ちるドローン、『ミナマタ』の西欧的和声のむこうに交錯する無時間的な響きの交錯など、近年の坂本龍一の仕事は、どの作品も西欧と東アジアが透明な水と空気のなかで清冽に鳴り響くような音楽/音響を生み出している。
そう考えると2018年の時点で、このような音を鳴らしていた本アルバムの録音はとても重要に思えてくる。2017年の『async』から2020年代の坂本龍一の音をつなぐ音。対して西洋人であるトゥープが、これほどまでに非西欧的なノイズ・音響・時間感覚を発露できることに深い知性と卓抜な感性を感じた。
物質、空気、微かな光、闇、空間、静謐さ。時間、非同期。音。まさに「Gardens of Shadows & Light」。そう本アルバムには21世紀の「陰翳礼讃」の感性にみちている。薄暗い光と陰影の美学がここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE