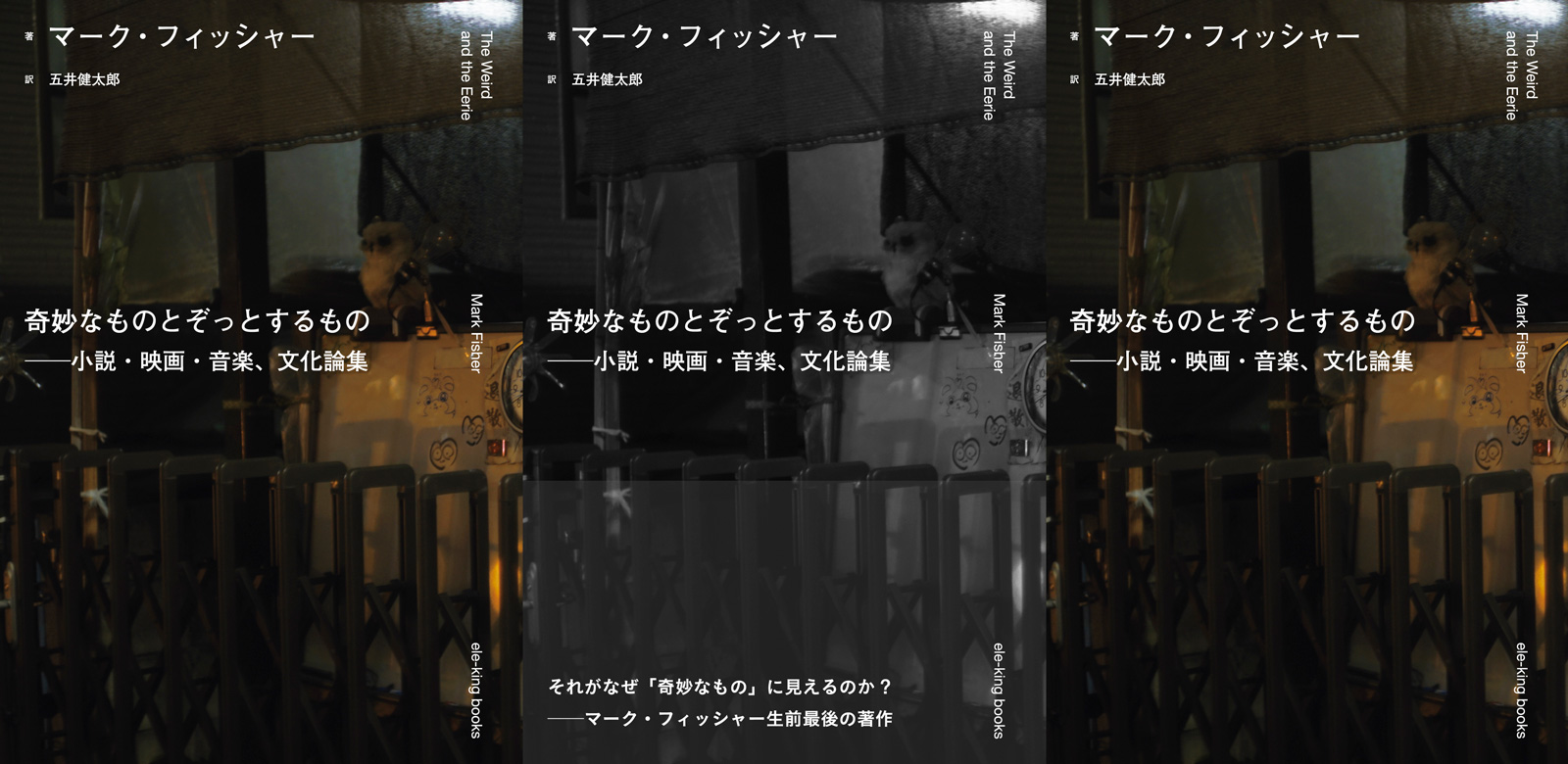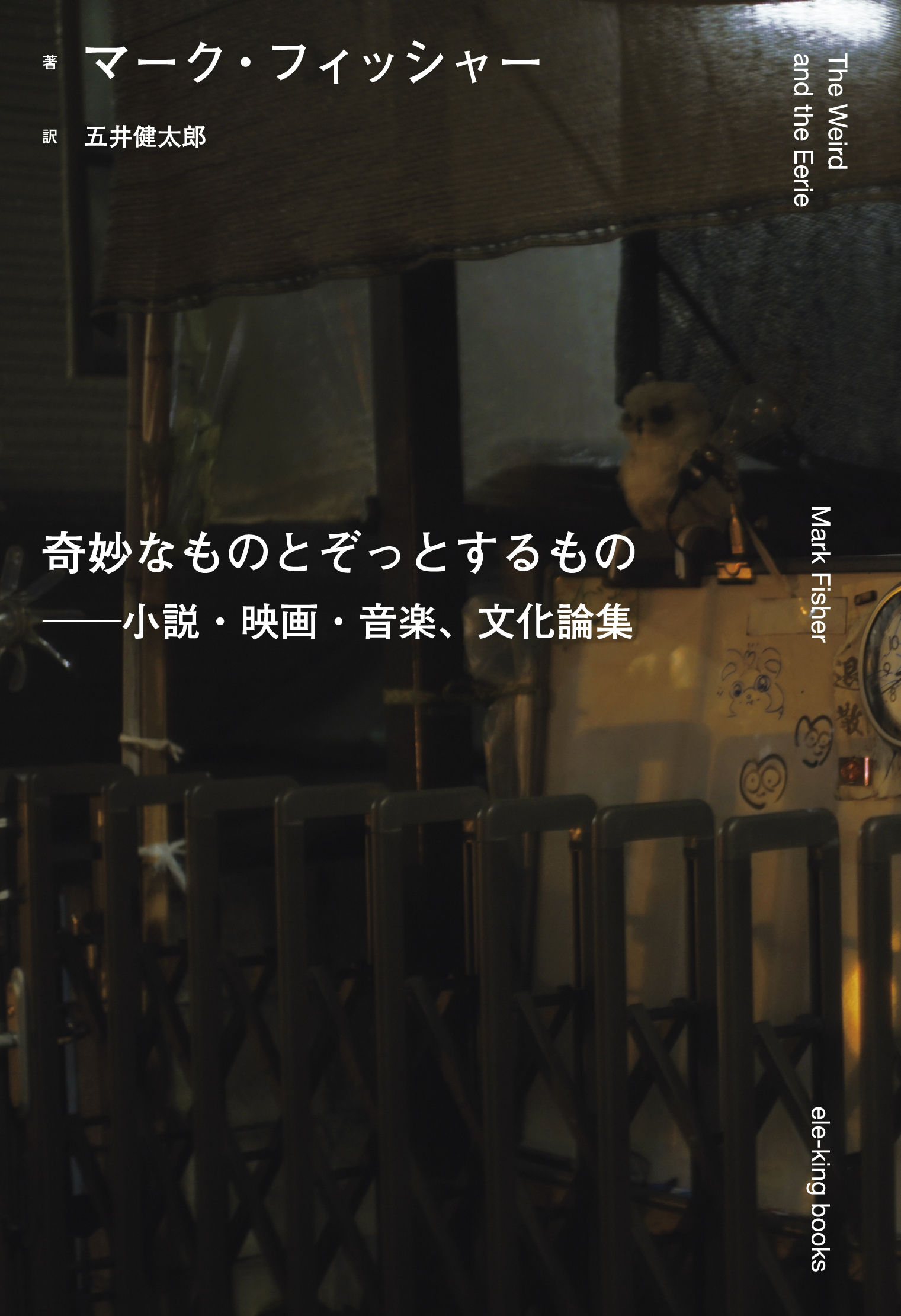MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > 不気味なものの批評を超えて- ──マーク・フィッシャー『奇妙なものとぞっとするもの』紹介
イギリスの批評家マーク・フィッシャーの『奇妙なものとぞっとするもの』の日本語訳が、先日 ele-king books の一冊として刊行された。本書は日本語に訳されたフィッシャーの著書としては『資本主義リアリズム』、『わが人生の幽霊たち』、『ポスト資本主義の欲望』に続く四冊目に当たる。これらのうちでおそらく最も有名な『資本主義リアリズム』は、ドナルド・トランプのアメリカ合衆国大統領就任と著者フィッシャーの自殺がほぼ同時期に起きたあの悪夢のごとき2017年の翌年である2018年に邦訳が出版され、資本主義とは異なる社会的組織化の原理をもった世界を想像することさえ困難になってしまった現在の私たちを取り巻く生と思考の諸条件をクリアに描き出してみせた絶望的なまでにリーダブルな書物として、日本でも大きな話題となった。それゆえ多くの人にとってマーク・フィッシャーの名は、『資本主義リアリズム』の著者として、同書における怜悧で核心を突くような政治的社会的考察の数々とともに記憶されているに違いない。彼の晩年の講義録であり最近邦訳が刊行されたばかりの『ポスト資本主義の欲望』は、2010年代に入ってからのフィッシャーがゼロ年代後半にみずから提示した暗鬱たるヴィジョンからの逃走線を、いやむしろ構築線とでも呼ぶべきものをいかにして引こうとしていたかを生々しく物語るものとなっており(ジェルジ・ルカーチの『歴史と階級意識』とヘルベルト・マルクーゼの『エロスと文明』があのような仕方で再評価されるなどといったい誰が予想できただろうか)、『資本主義リアリズム』に感銘を受けた多くの読者の期待に応えるものとなっている。「出口なし」の状況、個人主義的な快楽主義の規範のなかで見失われる集合的な享楽の可能性、「新しいもの」や実験への欲望に対して絶えず加えられる新自由主義的な抑圧──そのような条件のもとで実存的に窒息しかけながら、打開策を求めて必死で手探りし続けている人々に、翳りを帯びた表情で、しかしユーモアを忘れずに内在的な救いの手を差し伸べる。マーク・フィッシャーとはそのような人だった。現代大陸哲学の確かな知識にもとづき政治と社会を縦横無尽に論じてゆく左派のブリリアントな「理論家」としてのフィッシャーの姿が、そこには明瞭に記録されている。
他方で、『わが人生の幽霊たち』と『奇妙なものとぞっとするもの』の二冊にはフィッシャーの別の相貌が映し出されている。すなわち、「理論家」としての政治的フィッシャーに完全に統合されているとは言いがたい、「批評家」としての美学的フィッシャーである。周知のとおりフィッシャーは90年代にウォーリック大学の哲学科で学び、博士号を取得している。当時そこでは異端のドゥルーズ&ガタリ派哲学者ニック・ランドが教えており、レイ・ブラシエやイアン・ハミルトン・グラントやロビン・マッカイといった、思弁的実在論と呼ばれる大陸系哲学運動の中核をのちに担うことになる人々も学生として籍を置いていた。フィッシャーは彼らと晩年まで友人であり続ける。彼が一見すると『資本主義リアリズム』での自身の立場と正反対に見えるもの、すなわち加速主義──イギリスではランドを通じて広められた、資本がもたらす認知的かつ技術的な生産のプロセスを徹底的に加速させることで資本主義そのものを内破させることができるとする立場──に積極的にコミットする姿勢を見せたのにもそのような背景がある。しかしフィッシャーは初めからウォーリック大学にいたわけではない。ランドとともにあの伝説的な CCRU(Cybernetic Cultural Research Unit)を立ち上げたセイディー・プラントが96年に同大学に移ってくるまでは、70年代以来カルチュラル・スタディーズの牙城であったバーミンガム大学で学んでいた。つまり彼はもともと、スチュアート・ホールやポール・ギルロイの系譜に属するカルチュラル・スタディーズの研究者(の卵)だったのである。94年には雑誌『ニュー・ステイツマン』にオアシスやブラーに代表されるブリットポップの反動性を批判した記事を寄稿する傍ら、D-Generation という「パンクの幽霊に取り憑かれたテクノ」をコンセプトとしたグループで「Entropy in the UK」というEPを発表し、音楽批評家サイモン・レイノルズの目に留まったりもしている。したがってフィッシャーの活動の中心には当初から音楽が、それも文化全体への批判的視点に貫かれたものとしてのパンク(もしくはポストパンク)があったのだと言われねばならない。
以上のとおり「批評家」としてのフィッシャーは、ポピュラー文化が生み出した諸々の作品、あるいはより正確に言えば「文化的生産物」のうちに、解放的未来への政治的想像力を活気づけるようなエッジの効いた美学的ポテンシャルを探ろうとする立場をとっていた。資本主義リアリズム(サッチャー的な「この道しかない=オルタナティヴなど存在しない」)への政治的批判と、加速主義(パンク的な「未来などない=未来の幽霊の声を聴かなければならない」)への美学的コミットメントという二つのパースペクティヴの不安定な総合を試みるルート、抑鬱への傾斜をも含んださまざまな危険に満ちたルートを歩みつつあった彼の姿は、2000年代の前半から彼が自身のブログ K-Punk や『The Wire』などの雑誌に発表してきた音楽、小説、映画、テレビドラマといった多彩なジャンルの生産物を取り扱うテクストからなる『わが人生の幽霊たち』(原著は2014年に出版)においてとりわけはっきりと確認することができる。そこでフィッシャーは、ザ・ケアテイカーやブリアルといったミュージシャンたちを「アンイージー・リスニング」の実践者、失われたユートピア的未来の亡霊を絶えず回帰させるような「憑在論」(哲学者ジャック・デリダの用語)の美学の実践者として、力強く支持することになる。この「憑在論」の美学に関して強調されねばらないのは、そこで念頭に置かれている聴取のタイプが、80年代リバイバルやヴェイパーウェイヴなどに見られるような明らかに自己慰撫的な「ノスタルジー・モード」(批評家フレドリック・ジェイムソンの用語)の聴取のそれとはまったく似て非なるものであるということだ。幽霊や亡霊の形象を動員することでフィッシャーが試みているのは、私たちの眼と耳を私たちの慣れ親しんだ世界のイメージから引き剥がして、見慣れないもの、よそよそしいもの、異邦的なもの(the alien)のほうへと向けなおさせることである。フィッシャーの美学的格率が述べるのは、私たちは自身の思考をつねに「外部(the outside)」へと方向づけておかなければならない、ということだ。
『わが人生の幽霊たち』と同じく五井健太郎によって日本語へと訳されたフィッシャー生前最後の著作『奇妙なものとぞっとするもの』は、何よりもそのような「外部」の概念の具体的な練り上げを試みたものとして読むことが可能な書である。本書では、ホラー小説とSF映画と(広義の)実験音楽とが同じ概念的道具立てによって論じられるが、そこで基軸となるジャンルはホラーだ。このことは、ダルコ・スーヴィンの『SFの変容』が典型的であるように、批評的評価の観点からは伝統的にSFのほうがホラー(ファンタジー)よりも意義深いものだと見なされてきたことを踏まえるならば意外に感じられるはずである。さらにフィッシャーは、本書の序でみずから定義する「奇妙なもの」と「ぞっとするもの」という二つの概念を用いることによって、ホラーやSFをめぐる批評的言説の世界でこれまで覇権的な地位を占めてきた「不気味なもの」という精神分析的な概念を乗り越えることを企てる。「奇妙なものやぞっとするものを「ウンハイムリッヒ」なもの〔=不気味なもの〕の一部と見なすことは、外部から世俗的なものへの撤退の徴候である。広範に見られる「ウンハイムリッヒ」なものにたいする偏重は、ある種の批判〔critique〕へと向かう衝動に対応するものであり、そしてこの批判はつねに、内部の穴〔gaps〕や行き詰まりを通じて外部を処理することによって作動する。だが奇妙なものやぞっとするものはこれとは反対の動きをおこなう。すなわちそれらは、外部の視点から内部を見ることを可能にするのだ」(邦訳、14頁)。外部を内部化し、幽霊をドメスティケートしてしまう精神分析および「不気味なもの」の概念を拒絶したうえで、内部をいかなる意味でもその相関項ではないような外部の視点から掴み返し、幽霊をオイディプス的三角形から解放して猛り狂わせるような戦略をフィッシャーはとる。これは批判/批評への反逆でもあるのだ。また、ここでのフィッシャーの「不気味なもの」概念の批判(あるいはむしろ「批判の批判」)には、先述した通り彼と近しい間柄であった思弁的実在論の哲学者たちが「相関主義」──カント以来の、したがって「批判/批評哲学」以来の大陸哲学に支配的であった傾向──への批判として展開した議論とよく似た点があることも指摘されるべきだろう。ホラーの概念的ポテンシャルを展開することで、外部を内部と相関させることなく、しかもあまりに難解な表現に頼ることなく、素面で思考する方法を彼は開発しようとしたのだ、と言ってもよい。本書におけるグレアム・ハーマンやレザ・ネガレスタニやベン・ウッダードへの参照は、フィッシャーが友人たちのそうした哲学的思弁の冒険に対してある種の親近感を抱いていたことの証左を与えている。
さて、しかしそうなってくると問題は──なお、本書の訳者である五井が原語の多義性に配慮して「奇妙なもの」という包摂度の高い訳語を充てた “the weird” は、H・P・ラヴクラフトのクトゥルー神話や日本における怪談に相当するゴシックとの結びつきがはっきりと意図されている概念である以上、私個人は「怪奇なもの」あるいは「奇怪なもの」と強く訳すのが妥当ではないかとやはり思ってしまうのだが、それはともかく──「不気味なもの」の「批評/批判」を超えるための概念がなぜ二つあるのか、ということになりそうである。もっと踏み込んで言うなら、「外部」はなぜ二つ存在しなければならないのか、ということだ。それに関連することとして、フィッシャーが「奇妙なもの」と「ぞっとするもの」を恐怖(horror / terror)の情動に必ずしも結びつくものではないとしている点も注目に値する(邦訳、10頁参照)。この二つの「外部」の存在様態は、恐怖へのゲートとしても十分に機能するが、そうならないように機能することもできる──それはなぜなのか。このような問いに納得のいく答えを与えることは、この短い紹介記事ではもちろん到底なしえない。しかし、「何にも属していないもの(that which does not belong)」というフィッシャーによる「奇妙なもの」の定義が、アラン・バディウの哲学における「出来事とは状況へのその所属〔appartenance; belonging〕が決定不可能であるような多のことである」という主張を思い起こさせるという事実から、少なくとも彼がどのような狙いのもとで、「奇妙なもの」は「モダニズム的な作品や実験的な作品」にしばしば見出されるものであり、「新しいもの」の指標となるものだと述べているのかを推測することはできる(邦訳18頁)。それは「理論家」フィッシャーの関心事であるポスト資本主義的世界の実現可能性という問題に、おそらく深く関わっている。すなわち、その世界は、いまだ資本主義的世界の想像力のなかに生きる私たちにとってはたいへん「奇妙なもの」と感じられるに違いないが、にもかかわらず、私たちはそれを享楽しようとするポジティヴな感情をもつことができる──そのような含意が、「奇妙なもの」に関するフィッシャーのさまざまな記述からは浮かび上がってくるように思われるのだ。
他方で、「不在の失敗や現前の失敗によって」構成されると言われる「ぞっとするもの」が、運命論(fatalism)と行為主体性(agency)に関わるとされているのは、これもやはり『ポスト資本主義の欲望』における「資本には媒介する力(エージェンシー)があります」(邦訳174頁)という発言と関連づけて読まれるべきであろう。『奇妙なものとぞっとするもの』では資本自体がそもそもあらゆる点で「ぞっとするもの」であることが述べられている(邦訳15頁)。「ぞっとするもの」の概念は、いるはずなのにいない誰か(現前の失敗──遺跡)やいないはずなのにいる誰か(不在の失敗──幽霊)への回路を開く「ケア」的なニュアンスをもつものと解釈することもできるが、他面では、徹底的に非人称的で脱中心化された運命の車輪──私たち自身が始めたものであるはずなのにその終わりを想像することができなくなってしまったもの──としての資本主義という恐ろしいイメージに通じているものでもあるのである。「ぞっとするもの」という情動はそれゆえ、「外部」のネガティヴな存在様態としての側面をもつと言っていいだろう。むろん、ネガティヴであってもこの情動を通して私たちは、「外部」としての世界についての認知地図を拡張する機会を手に入れられることに変わりはないのだが。
必ずしも恐怖に結びつくわけではないとはいえ、それでもジャンル・フィクションとしてのホラーとの結びつきが強固な二つの「外部」概念である「奇妙なもの」と「ぞっとするもの」をどのように読み解いていくかは、読者に委ねられている。ここまでの紹介で誤解させてしまっていないことを願うばかりだが、本書『奇妙なものとぞっとするもの』は、難解な哲学書の類いではまったくない。取り上げられる作品や作家は具体的かつポップであり、フィッシャーの筆致はつねに明快でありヴィヴィッドでさえある。にもかかわらず、ここまでの紹介が示してきたとおり、フィッシャーの「理論家」的テクストと「批評家」的テクストを今後私たちが総合的に読もうとする際には、『奇妙なものとぞっとするもの』は間違いなく鍵となるような内容を含んでいると判断される書物なのである。「批評/批判」が前提とするようなジャンル間ヒエラルキーを疑いつつ、「不気味なもの」によってドメスティケートされない「外部」を思考すること、そのような普遍的(でおそらくは集合的)な理論的課題に取り組みつつも、個体的で特異的な作品や作家と向きあい、そこに表現されている幽かな行為主体性を言葉で掬いとることを、たとえその行為が淡々としすぎていてほとんど淡白に近いものになる瞬間があったとしても、本書においてフィッシャーは一切怠っていない。そこで賭けられているのは、自己の行為主体性を信じるのと同じくらい、運命の奇怪な力、あるいはむしろ運命のなさの不思議な力を感じつつ、世界そのものの行為主体性を信じることだ。それは決して簡単なことではないだろう。だからこそ、そのようなことが目論まれた書物は──ラヴクラフトが作り上げた架空の/ハイパースティショナルな書物『ネクロノミコン』がそうであるように──千年でも二千年でも、永遠に、読まれそして読みなおされることができてしまうのである。本書「も」また、そのような呪われた書物の一冊、ぞっとするほどにポップで、怪奇/奇妙なまでに希望に満ちた書物の一冊なのだということは、もちろん、言うまでもない。
Profile
 仲山ひふみ/Hifumi Nakayama
仲山ひふみ/Hifumi Nakayama 1991年生まれ。批評家。主な寄稿に「「ポスト・ケージ主義」をめぐるメタ・ポレミックス」(『ユリイカ』2012年10月号)、「聴くことの絶滅に向かって──レイ・ブラシエ論」(『現代思想』2016年1月号)、「加速主義」(『現代思想』2019年5月臨時増刊号)、「マーク・フィッシャーの思弁的リスニング」(『web版美術手帖』2019年9月5日)、「ポストモダンの非常出口、ポストトゥルースの建築──フレドリック・ジェイムソンからレザ・ネガレスタニへ」(『10+1 website』2019年10月号)、「「リング三部作」と思弁的ホラーの問い」(『文藝』2021年秋号)。また、手売り限定の批評誌『アーギュメンツ#3』(2018年6月)を黒嵜想とともに責任編集。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE