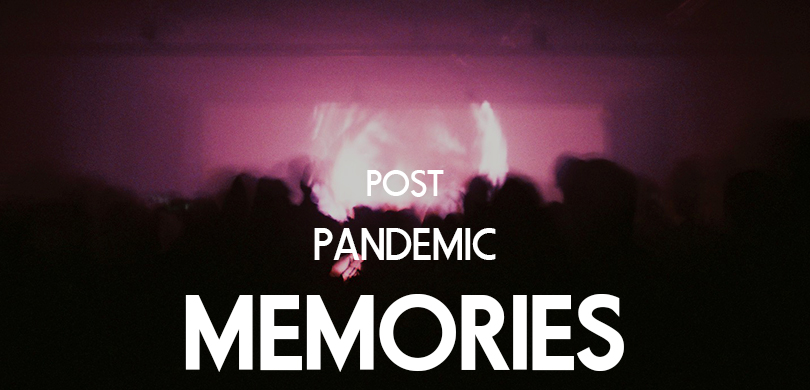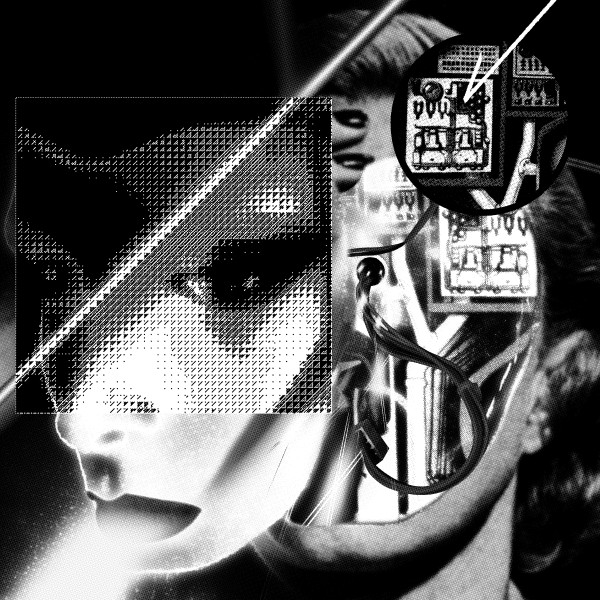MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Regulars > Post-Pandemic Memories > 第9回 増え続けるショッピングモール
ワイア入りガラスウィンドウの菱形にスライスされた、約2キロ先に聳え立つビル群と、首都高を走る車に向けられた巨大な歯科医の看板。デスクから右を向けば常にそこにある景色。ビル群の高層階は霧がかかっていて見えないが、中から届く仰々しいライトアップの光でその高さが把握できる。権威主義と資本主義の結晶の輝き。
私が育った街は、山手から見下ろす人たちに100万ドルの夜景と呼ばれていた。それが何の金額かは知らないけど、とにかくそう呼ばれていた。おそらくその金額分の電力を消費し、その金額分のカーボンを排出し、その金額分の輝きを維持していたんだろう。その100万ドルの輝きの中が私の日常だった。当たり前だけど、自分の目に映る日常に100万ドルの価値があるとは、これっぽっちも思っていなかったし、100万ドルという金額のスケールもよくわかっていなかった。薄いガイドブックに載るような観光客向けのエリアでは、電柱は埋められて、適度に清掃もされて、一通り取り繕われていたけど、私が日々を過ごしたエリアで目に入るものは少し違っていた。開かないシャッター、幾重にも塗り重ねられたグラフィティ、積層するステッカー、ひび割れたコンクリート、瓦礫、ショーウィンドウに並ぶナイフ、怪しげな漢方薬、パワーストーン、ブラックライトに照らされた何種類もの爬虫類や両生類、鈍い光沢のフックに吊るされた動物の肉、乱雑に箱に詰め込まれたレコードやカセット、染みや汚れがついたままの軍用品、動く保証のない電化製品の山だった。決して美しくはなかったけど、私はそれが好きだった。毎週のように流行を量産するタブロイド誌が説く「時代」からは取り残されているけど、そこに積み重なった愛着や歴史の厚みは、そんなものに左右されないと思っていた。しかし、消えるときはあっけない。押井守の『機動警察パトレイバー the Movie』を久しぶりに観ていたら、大規模再開発中の東京を舞台に「ここじゃ過去なんてものには一文の値打ちもないのかもしれんな」「数年後には、目の前のこの海に巨大な街が生まれる。でも、それだってあっという間に一文の値打ちもない過去になるに決まってるんだ。タチの悪い冗談に付き合ってるようなもんさ」という会話が交わされていた。昭和の時代からこの街のやり方は変わっていないらしい。そういえば、ギブスンの『モナリザオーバードライブ』では、ロンドンの露店に並ぶアンティークの小物を見た久美子が「これって “ゴミ” じゃない」と言っていたっけ。東京では、それらは埋め立て用だそうだ。「夢の島」というネーミングは案外、供養のようなものなのかもしれない。
私は10年と少し、渋谷エリアに住んでいる。この「馴染みの街」になってしばらく経つはずの街を歩いていると、私は頻繁に自分が幽霊にでもなったかのような錯覚に陥ることがある。あるはずのものがなく、何がなくなったのかも思い出せない。ただ「ない」ということだけがわかる。喪失感とも少し違った寂しさ。もしくは、マーク・フィッシャー流に言い換えるなら、ここは「集団健忘症の街」。流動的につねに塗り替えられていく街には、愛着や記憶が定着する隙は与えられないらしい。駅周辺の横丁がなくなるとき、あるいは宮下公園がいまの形になるとき、もっと派手に抵抗しておけばよかったと、いまになって思う。高円寺では再開発反対のパレードがおこなわれたらしい。渋谷ではどうだったっけ。その記憶もすでに曖昧になってる。街全体で絶えずおこなわれている終わりのない工事が、既成事実として機能し、受け入れざるを得なくしたようにも思う。今年の夏が終わると同時に、Contact と Vision という馴染みのクラブが永久にその扉を閉ざす。道玄坂エリアの再開発に伴うものだそうだ。これも人類史以前から決まっていたことかのように、諦めを伴ってコトが運ばれている。跡地には “また” 大規模商業施設やホテルができるそうだ。渋谷区の北側でも再開発は進んでいて、そこにも大規模な商業施設ができるらしい。こちらはホテルではなく、タワーマンション付き。
何年か前に、人気のカルチャー誌のいくつかが立て続けに台北特集を組んだときの出来事を思い出したので、ついでに書いておく。そのときに雑誌のカバーを飾ったものは、お世辞にも洗練されているとは言えない小さな飲食店や、それらが並ぶ街並み、あるいはナイトマーケットだったと思う。そして、それを批判する文脈で「台北は今や近代化された街であり、エキゾチズム的な消費をしてほしくない」というような意見が台北の人の声としてネットの一部で拡散された。話の流れは忘れたが、そのときにあげられたカバーにすべき近代化の象徴のひとつが台北101だった。エキゾチズム的な消費をしてほしくないという意見に対して共感できる部分もあって、台北に住む友人にこの話をしたことを覚えている。台北101に対してその友人が言ったのは「あんなところには、台北に暮らす人たちのスピリットもカルチャーもない」だった。確かに、欧米のカルチャー誌が東京の特集をしたときにヒカリエをカバーにしたとしたら、と想像すると、その可笑しさが理解できる。私が台北に行ったときに過ごすのはナイトマーケットや小さい店が並ぶエリアだし、東京に海外から友人を招いたときに連れていくのは、いつもそんな感じのエリアだ。ショッピングモールじゃない。エキゾチズム的な一方的な消費には問題もあるが、それに対する回答がショッピングモールというのは、反動的で極めて資本主義的な価値観のように感じる。ショッピングモールは、だいたい世界中のどこにでもあって、どれもが同じようなエクステリア、同じようなインテリア、同じようなサービスを備えている。だいたい街の中に突如として現れて、その街が持つ固有の匂いや色を消そうとする。そして固有の匂いを消され、あらゆるグラデーションを均一に塗り固められて規格化された街は、そこに暮らす人びとにも規格化を求める。「世界から常に人と注目を集め続ける街の実現を目指す」という文言が、渋谷区の再開発事業の案内では喧伝されている。平凡な資本主義のルールのもとでショッピングモールによって規格化された街が、どういう理屈で「世界から常に人と注目を集め続ける」ようになるのだろうか。
手垢で光沢の出た木製テーブルや、油と湿気と埃で半透明になったガラス窓、蔦植物のように有機的な成長を遂げたケーブルやダクトの類、不規則に消えるネオン、ドアの隙間から溢れ出す低音、ラッカーやマーカーの軌跡、街の匂いや色を作っていたものたちが、連続した消臭漂白によって消えていく。跡に現れるのは、シットコムのセットのような安っぽい昭和風の店や、サビ加工を施したボルトとヴィンテージ加工用塗料を塗りつけた板でできたカウンター、読めない外国の言葉で存在しないメニューが書かれた札のかかる壁、あるいは徹底的に消臭漂白された平坦な表面の連続。これがタチの悪い冗談じゃないとしたら何なのだろう。
ギブスンの有名なクオートに「ストリートは、モノに独自の使い方を見出す」というものがある。レントゲン写真にはグルーヴが掘られ、消化器はインクを吹き出し、強粘着出荷用ラベルは都市に匿名の痕跡を残す。私たちは、この街に増え続けるショッピングモール群にどんな使い方を見出すことができるのだろうか。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE