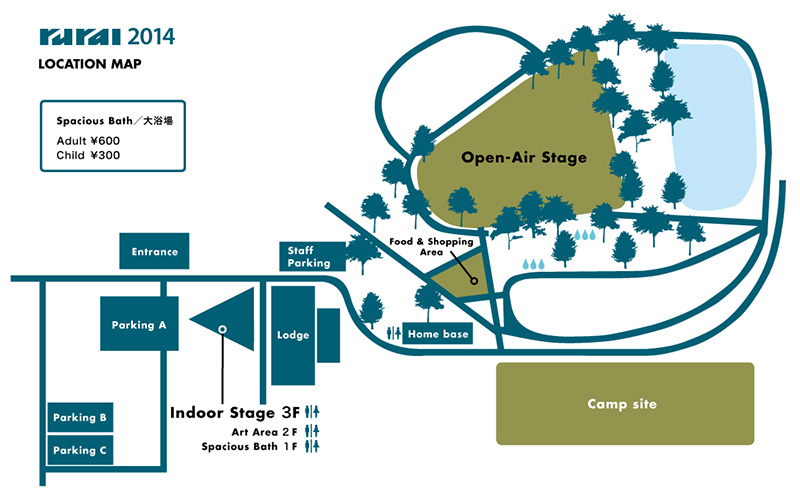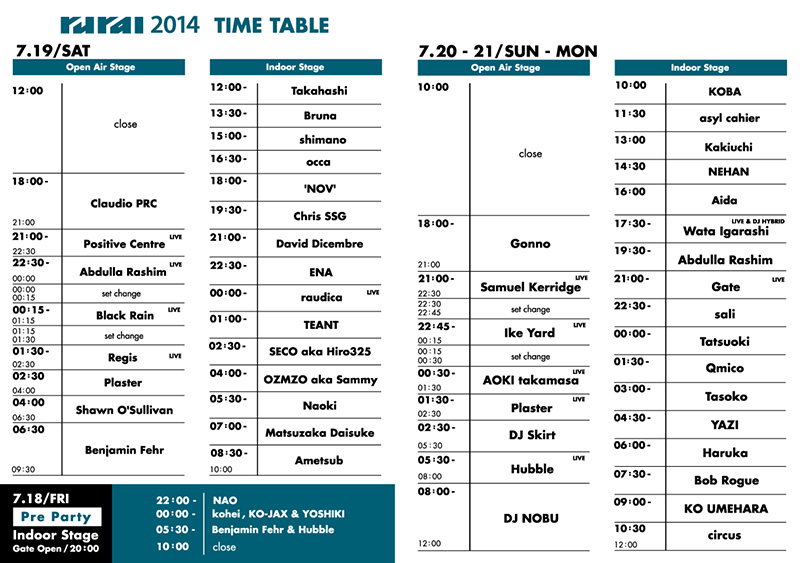昔からよく言われることだが、Jポップからは背景が見えない。見えないのが日本の風景だと言われてしまえばそれまでだが、風景らしい風景がないかわりに内面ばかりが語られる音楽を聴き続けるというのは、どこか息苦しい。セックス・ピストルズにはロンドンの下町の匂いがあったし、ザ・スミスからはマンチェスター郊外の街並みが幻視できた。レゲエからはキングストンの熱気が伝播し、シカゴ・ハウスやデトロイト・テクノは街の知られる1面をレポートした。ブリアルのダブステップからもブレア以降の寂しい郊外が一緒に聴こえた。ヒップホップやグライムにいたっては、それが見えない作品を探す方が困難だろう。(ここで言う背景/背後とは、東京や湘南や札幌など、ただ地名を言うことではない。社会や歴史的背後という言葉に置換しうるものの意味で使っている)
今日の日本の新しいヒップホップ、KOHHやBAD HOPからは背景も一緒に聴こえる。KOHHは内面的でもあるが、同時に彼が生まれ育ったところ、その背後も見えてくる(見えた気になる)のだ。KANDYTOWNのような、必ずしも経済的に厳しい出自ではない人たちも、その背後を隠さない。自分がどこからやって来たのかということに自覚的だ。要するに、本当の意味でのストリート感覚を内包した音楽ジャンルである。(しかも、言いたいことを言いたい言葉で言えるジャンルだし、そのほとんどがインディペンデントだ)
ヒップホップは10年以上前から日本の地方都市にも根付いているので、ここで紹介するのはほんのその一場面に過ぎない。しかし、注目して欲しい、たとえば表紙に写っている(キャップを被ってもいなければスポーツシューズを履いているわけでもない)青年が、いまもっとも脚光を浴びているラッパーなのだ。紙エレキングの最新号──いまヒップホップに何が起きているのか?
 ■vol.18 contents
■vol.18 contents
特集:いまヒップホップに何が起きているのか?
010 interview KOHH、ロング・インタヴュー 取材:山田文大
028 「いまヒップホップに何が起きているのか?」文:磯部涼
032 talking PUNPEE×NORIKIYO+ふたりが選ぶ日本語RAP名盤
043 columns RHYMESTERについて今一度考えてもらいたい 文:宮崎敬太
044 story 日本にラップは根付いたのか?――川崎・BAD HOPに始まる 文:磯部涼
048 interview MONJU(仙人掌、ISSUGI、Mrパグ)、ロング・インタヴュー 取材・文:二木信
062 columns いまなぜTwiGyなのか──『十六小節』刊行について 文:山田文大
064 interview WD sounds(澤田政嗣 a.k.a Lil MERCY)──ハードコア×ヒップホップ
067 interview Fumitake Tamura (Bun)──研磨されるビート/拓かれる聴覚
070 interview 荒井優作──トラップから路上の弾き語りまで
072 interview YungGucchiMane──未来の大器 取材:山田文大
074 interview Olive Oil──南の楽園設計を夢見つづける
078 story 酩酊は国境をも溶かす──「It G Ma」から見る日韓ラップ・シーン 文:磯部涼
080 columns トラップとはなにか? 文:泉智
081 talking オカモトレイジ×泉智「KANDYTWONを語る」
090 interview Moe and ghosts──新「ラップ現象」 取材:デンシノオト
097 talking 二木信×UCD「肯定する力とゆるさ──オレらが好きな日本語ラップ」
106 interview tofubeats──フロウとサウンド重視、発明がなければ面白くない
112 interview MARIA──KOHH、BAD HOPから高校生ラップまで語る
116 talking ECD×水越真紀 つまり「生きてるぜ」ってこと──ECDと考える貧困問題
126 3・11以降の日本語RAP 30枚 二木信+宮崎敬太+泉智
128 columns Beat goes on&on──あれから30年 文:高木完
129 いまUSヒップホップに何が起きているのか? 文:三田格
138 USヒップホップを知るための30枚 選・文:三田格
■連載
146 アナキズム・イン・ザ・UK外伝 第9回 わたしたちはもっと遡ったほうがいい ブレイディみかこ
148 乱暴日記 第三回 KOHHとボリス・ヴィアン ~あれもありこれもあり、あれがあるからこれがある~ 水越真紀
150 音楽と政治 第8回 磯部涼
152 ハテナ・フランセ 第5回 配達人に乾杯! 山田容子
154 初音ミクの現在・過去・未来(後編) 佐々木渉
156 ピーポー&メー 第9回 故ロリータ順子(後編) 戸川純
表紙写真:菊池良助