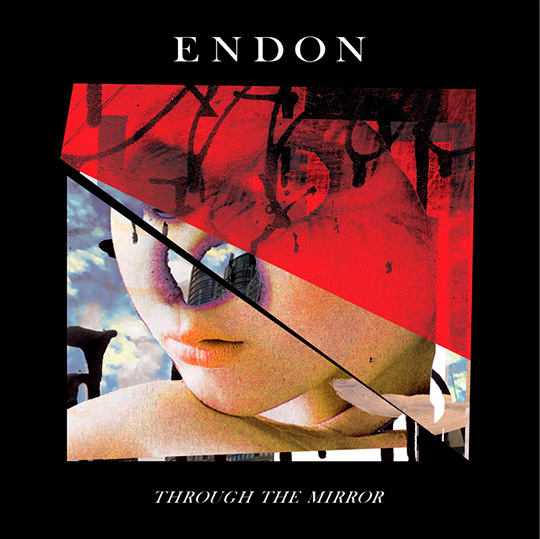難しい映画ではない。が、生やさしくもない。ハードである。見終わってからしばらく席を立つことができなかった。この苦境をどう乗り越えたらいいのだろう。もう、弱者の言うことしか信じない。それはひとつあるかもしれない。イギリスのケン・ローチ監督の最新作(33作目)『家族を想うとき』は、21世紀のいま現在の労働者の置かれた過酷な状況を、飾りっ気ナシに、そして妥協ナシに描写する。例によって、たんたんとリアルな日常を余計な演出ナシに描く。それだけといえばそれだけだが、上映時間100分のあいだ、まったく飽きさせることなく壮絶な最後まで突っ走る。
ほんのわずかだが、お茶目なところもある。ケン・ローチはそういうのが得意だ。『エリックを探して』や『天使の分け前』ように、貧しい人たちの生き生きとした姿を、ありったけの愛情を持って描いた作品はいまでも忘れがたい。新作でぼくが笑ったシーンは3つある。ひとつは、マンチェスター出身の主人公がたまたまマンUのユニを着ていたとき、ニューカッスルのユニを着た顧客と鉢会ってしまい、おたがいパチパチやりあうシーン。『エリックを探して』以来のサッカーネタだ。ふたつ目は、夫婦が知り合ったのはレイヴ・パーティだったと話すところ、で、3つ目は主人公の息子が仲間といっしょに街の広告板にタギングをするシーン……ま、最初のふたつは映画全体からすればどうでもいいちゃどうでもいいことかもしれないが、3つ目は、この映画のテーマを思えば意味深ではある。

『家族を想うとき』がどんなストリーであるかは、配給会社のホームページ(https://longride.jp/kazoku/)を見るのが手っ取り早いだろう。簡単なあらすじだ。むくわれない労働者階級の悲哀を描いていると。それはいつものケン・ローチ節だという意見もあるかもしれない。しかし、『家族を想うとき』は映画通のための映画ではないし、この映画にしかない強烈な何かは、いま苦労して働いている多くの日本人にも充分に伝わるだろう。そう言えるだけの「現代性」がしっかりと具体的に表現されている。
主人公は、ニューカッスルの宅配業者で、その妻は介護ヘルパー。じつに現代を象徴する仕事だ。前者は価格競争やサービス競争のしわ寄せが働き手に直に影響する業種で、後者に関して言えば、福祉国家たるイギリスがまだ存命しているというのなら、民営化されず、私企業が提供する仕事として拡大しなかったはずの業種である。
夫婦には子供がふたりいる。長男は高校生、妹は小学生。夫婦は少しでも良い生活をと、文字通り身を粉にして一生懸命に働いている。だが、彼らを取り巻く労働環境が、結果、家族を引き裂いていく。その黒幕は、必ずしも雇用主というわけではない。20世紀的な労使関係は縮小し、21世紀においては「雇用」は「契約」という形態で拡大している。その事例が、いまイギリスで問題になっている「ゼロ時間契約」という在宅の雇用形態と「ギグ・エコノミー」というアプリ(ネット)を介して仕事を請け負う労働形態だ。好きな時間に好きなだけ働けるという働き手にとって好都合に見えもするシステムだが、その代わり労働者にとってのもろもろの保証はない。保証どころか、感情さえも付け入る隙がない。利潤追求のための労働コスト削減がいかなる現実をもたらしているのか、その残酷な実体をケン・ローチは執拗に捉える。
企業の側に都合のいい管理体制は精密化し、労働者はただ生きるためにその悪条件を受け入れる。安部政権が失業率は下がったと言いながら非正規雇用が増加している日本でも同じようなことが起きている。NHKの「クローズアップ現代」に是枝裕和監督といっしょに出演したケン・ローチは、今日の資本主義システムがいかに労働者を弱体化させているかについて話していたが、ぼくは登場人物たちの生活におけるテクノロジーの介入(スマホ、宅配業者が手にしている装置、パソコン)も気になった。『ダニエル・ブレイク』でも主人公がパソコンに四苦八苦する場面があったように、そもそもスマホが必需品になってしまっていること自体がはなはだ疑問ではあるし、スマホから突然鳴る電子音は、場面によってはどんな効果音よりも恐怖をかき立てる。スマホから聞こえる声は雇い主だが、同時に新自由主義の声でもある。無慈悲なことを平然と言える声。従業員の家庭が崩壊しようが、不平等が常態化しようが知ったことではない。何故ならその声は、儲かるか儲からないかという基準でしか動じないからだ。トランプ、マクロン、そしてボリス・ジョンソンらがそうであるように。
マーク・フィッシャー流に言えば、ここに描かれているのは資本主義リアリズムそのものであり、作品の背後からは、「いったい誰がこんな社会にした!?」という、去る参院選で立候補した渡辺てる子の叫び声にも似た、すさまじい憤りが滲み出ている。原題の「Sorry We Missed You」とは、配達員が不在時に入れるカードの定型文で、「残念ながら不在でした」ぐらいの意味だが、映画を見終えるとより深いところでの不在を意味する「あなたがいなくて寂しい」にも読めてしまう。

グレてしまった息子がグラフィティライターをやっているところ、そして家族が楽しく過ごしている数少ないシーンでかかっている音楽がヒップホップという現代的なディテールも、イギリス映画らしく気が利いている。息子と娘が良い感じで描けているのも監督の力量だろうし、そしてどんなに窮しても暴力は決して認めないと。
物語の細部にも気が配られているし、たしかにこれはセックス・ピストルズやザ・クラッシュ(ないしはザ・スペシャルズやザ・スミス)を生んだ国の映画というか、ハリウッド的な文法がないからこそ説得力があるんだというか、人気俳優も玄人筋に受けている役者も出てこない、ほとんど無名の役者たちによる、83歳の映画監督が情熱をこめてつくったポリティカル映画である。人情ドラマではない。