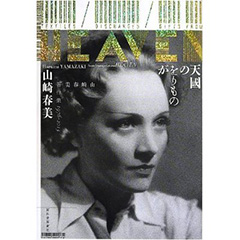MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 山崎春美- 天國のをりものが: 山崎春美著作集1976-2013
その時代を美化するつもりはない。ただ、先日の九龍ジョーとのトークショーでも話したことだが、僕が中高学生だった1970年代後半の日本には、ロック・メディア(ロック評論ないしはロック作文)文化は、手短に言って、カオスとして存在していた。ソツのないモンキリ型の社会学や便利屋ライターなんぞは出るすき間がないくらいに、好むと好まざるとに関わらず、まあいろんな人たちがろくすっぽ資料など読みもせず、が、その代わりに、深沢七郎や夢野久作や坂口安吾や、ウィリアム・S・バロウズやフィリップ・K・ディック、トマス・ピンチョンやルイ=フェルディナン・セリーヌなんかを耽読しながら、内面をどこまでも切り裂いたような、好き勝手な文章を書きまくっていたのである。山崎春美は、間章を「ファナティックな文学青年」と形容しているが、僕にしてみたら、山崎春美こそが「ファナティックな文学青年」がひしめく70年代後半の日本にあった文学的ロック批評/言語空間におけるもっとも不吉な巨星に他ならない。たとえばラモーンズを、そう、あのラモーンズを、以下のような、モリッシーも顔負けの、胸をえぐられるような切ない日本語で意訳/変換できる人は他にいないだろう。
冬が来て
もう二年も居座っている
今は、最前線の「寒さ」だ
俺の持っていた最低の威厳までもが吸いつくされるほどに
すべてが冷厳だ
でもまた、
こんな素敵な季節が外にあったか?
彼らは言う、"唇をゆるめよう、ラクにやろう"
ケッ、くだらない
それが実は嘘っぱちの固まりだってことは、
まず一番に君が知っている
これからが本物の冷時冷分だぜ
Ramoes"Swallow My Pride"(1977)
こういうのは、もうどう考えても一種の芸で、訳詞という仮面を被った何か別モノだ。当時の訳詞とは、海外取材などできない立場の人たちが、自分なりの言葉で欧米の音楽を紹介し、日本の文化(コンテキスト)に落とし込むためのメソッドのひとつでもあった。これを積極的に利用したのが『ロッキングオン』と『ロックマガジン』だった。こうした、正確さよりも解釈力や表現力を念頭においた独自の訳詞は、発想が不自由な人がやるとひとりよがりの自慰行為に終わるのだけれど、文学的なセンスを持っている人にかかるとそれ自体がひとつの作品となる。
小6で洋楽に目覚めた僕は、『ミュージック・ライフ』という白人さんが大好きなミーハーなロック雑誌を定期購読していたのだが、中1の後半に"シーナはパンク・ロッカー"や"ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン"にがつんとやられ、出てきたばかりのパンク・ロックなるものに心奪われてしまったお陰で、後にも先にも唯一雑誌のバックナンバーの取り寄せなる行為を『ZOO』というファンジンみたいな雑誌で早まってしまい、そして、同じようにまだファンジンみたいだった『ロッキングオン』から『音楽専化』、まだまだヒッピー臭かった『宝島』からプログレ雑誌時代の『フールズメイト』までをと、買ったり借りたり立ち読みしながら読みあさっていた。アメリカの西海岸文化が清潔感溢れる『ポパイ』となったように、『宝島』もぴかぴかのニューウェイヴ雑誌となり、『ロッキングオン』が商業誌として確立する、少し前の時代のことだ。
それはもう14歳~17歳あたりの子供にしてみたら、親の目を盗んで見るエロ本よりスリリングだった。僕の中学の3年間は、『ニュー・ミュージック・マガジン』以外の音楽誌ほぼすべてを読んでいたと言っていい。阿木譲の『ロックマガジン』だけは静岡に売っていなかったので読みたくても読めなかったのだが、高校時代、知り合いが『ロックマガジン』と『モルグ』を見せてくれたことがあった。僕が文筆家としての山崎春美の名前を確実に覚えたのは、そのとき初めて手にした『ロックマガジン』に載ったラモーンズの"ナウ・アイ・ウォナ・ビー・ア・グッドボーイ"の訳詞による。表紙は忘れたが、山崎春美の強烈な言葉だけはいまでも憶えている......つもりでいる。それが果たしてどんな言葉だったのか、九龍とのトークショーでは調子こいて記憶起こしで朗読までしてしまったわけだが、後から記憶違いだったらどうしようと不安になったので、ここでは止める。
先にも書いたように、1980年になるとロック/サブカル雑誌文化は経済的な自立を果たそうとする。ケオティックな言語空間と言えば聞こえはいいが、一歩間違えれば文学かぶれのアマチュアリズムとも言えるわけで、「マリファナ論争」をやっていた『宝島』が郷ひろみを表紙にツバキハウスを紹介するようになるのも、それが時代の要請でもあり、おそらく当事者の目標でもあり、サブカル・メディア業界の流れでもあったのだろうと僕は受け止めている。とはいえ、レーガノミクス、サッチャーリズム(そして中曽根)の時代だ。世のなか効率と経済が第一ですよとなれば、70年代後半の日本のロック批評/言語空間という、効率とも経済とも縁のなさそうな、カオスのなかのもっとも純度の高いカオスたる山崎春美の居場所をどこに探せばいいのだろう、世渡りを拒み、かつてラモーンズをラモーンズ以上の想像力で受け止めてしまった血まみれの若者はどこに行けば良かったのだろう。『ロックマガジン』と決別し、間章を敬愛を込めてデブメガネと呼び、『ロッキングオン』をコケにして、工作舎をしれっと離れ、そして彼は赤裸々にもこう書いている。「僕はいつでも、情況の中で沸騰する泡のように、消えたり現れたりしていたかった。けれど、オカシナ疎外者意識を軸にした共同幻想か、デッチアゲとすぐにわかるそれ以外に情況らしきものはなかった」(1980年)
本書『天國のをりものが』は山崎春美の初の著作集である。『ロックマガジン』時代の文章から最近のものまで載っているが、多くは70年代末~70年代の余韻の残る80年代初頭に書かれている。再録されているほとんどの原稿は、著者が10代から20代前半に書いたものだということを知れば、その早熟さに驚くかもしれない。数々の「訳詞」は、各章の扉にある。そして、紙エレキングに載った三田格の発言への反論もある(こんなところにまで......、さすがミタカク!)。
70年代のロック・サブカル雑誌文化および批評/言語空間は、60年代への意識的なカウンターとしてはじまっている。パンクもまた60年代への弁証法的反論だったことがいまでこそわかるが、当時の山崎春美はパンクに「分裂的、非体系的、反ヒエラルキーの思想」を見ている。彼のこうしたある種のアナキズム(ないしは虚無)は、文章だけではなく、ガセネタやタコでの音楽活動はもちろんのこと、自身も編集を務めたエロ本を扱う自販機本『Jam』、そして伝説の雑誌『HEAVEN』の編集にも垣間見ることができる。
本書の素晴らしい装丁を手がけている羽良多平吉は、『HEAVEN』のデザイナーでもあり、僕の世代にとってはネヴィル・ブロディやテリー・ジョーンズみたいな人たちとは比べようのないくらい憧れのデザイナーのひとり。当時は、海外雑誌の物真似デザインとは別次元の、実験精神旺盛のエディトリアル・デザイナー、あるいは伊藤桂司のようなイラストレーターがこの手の文化に関わっていたことも重要な事実である。ヴィジュアルも含めて、ロックについてのコンセプチュアルな解釈、活字文化が、ここまで自由なのだということの再発見にもなるだろう。
また本書は、この国の音楽メディアのターニングポイントにおけるもっとも重要な軌跡でもある。アニメ雑誌『アウト』も『Jam』やら『HEAVEN』やらの、この時代のケオティックなアングラ出版文化のなかで生まれているということは僕も初めて知った。ちなみに(笑)という表現は、山崎春美の発明で、今日のメールや書き込みのwなど、制度から離れた現代の書き言葉の先駆的な試みも著者はやったと言える。
が、そうした細かい話はさておき、あらためて何故いま山崎春美なのだろうか。80年代に経済的に自立したロック・サブカル雑誌文化は、しかし90年代に向けて70年代的な文学性を切り捨てながら、再編していく。たとえるなら、深沢七郎よりもボリス・ヴィアン、坂口安吾よりもサリンジャーという具合に。90年代後半の赤田祐一編集長時代の『クイックジャパン』が山崎春美を特集したのも、それをナキモノとする風向きへの抵抗だったのだろう。つまり、気がついたら飼い慣らされたロック・シンガーばかりの、ソツのない社会学を使った文章、便利屋ライターが500回以上も聞いたことのある言葉をさらに上塗りしているご時世だからこそ、本書『天國のをりものが』は刊行される意義がある。日本におけるポストパンクの知性がここにある、とも言える(世代的にも、著者は欧米のパンク/ポストパンクの人たちと重なる)。
僕個人が70年代後半の、山崎春美に象徴されるようなロックの言語をどのように享受して、やがていかなる考えにおいて、恐れ多くも先達の文学性とは意識的に距離を置きながら、自分自身のスタイルを自分なりに模索したかについては九龍とのトークショーで話した。それはあの場での話なので、聞いていた人はツイッターしないで下さいね。ただあのとき話したように、僕が深沢七郎を好きになったのは間違いなく山崎春美からの影響(藤枝静男と、そしてフィリップ・K・ディックもそうなんですね、きっと......)。それだけでも僕は著者に感謝しているし、山崎春美がいなかったら......と気づかされることは少なくない。だいだいこんなに長く書いてしまうなんて、やはり思い入れがあるんだなあと自分でもびっくり。
以上、敬称略でした。


 DOMMUNE
DOMMUNE