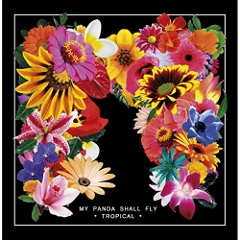MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Reviews > Album Reviews > My Panda Shall Fly- Tropical
「ハッピーバースデイ、ニーナちゃん!」という宇川直宏の掛け声でニーナ・クラヴィッツのDJがはじまる。10月だけ秋葉原の〈3331〉で開催されているDOMMUNEは、家から歩いていこうと思えば行ける距離なので、買い物のついでに足が向けられる。先日もそんな調子で軽くフロアを覗いてから家に帰ってふと思った。いつの間にか英米だけではなくロシアだとかアルゼンチンのDJを気軽に見ることができるようになっていると。90年代の初めはドイツのダンス・カルチャーだって遠くに感じられたのに。
今年に入ってからもようやくデビュー・アルバムをリリースしたモー・カラーズがモーリタニア、同じくアーカがヴェネズエラときて、ラッカー(Lakker)のリミックスに惹かれて興味を持ったスレン・セネヴィラトニ(Suren Seneviratne)もスリランカ出身だという(96年からロンドン在)。ラッカーが起用されていたEP『プッシュ』はモウ’リンとの共作だったので、どこからどこまでが彼の作風なのかは推し量ることができなかった上に、そもそも回転数がよくわからなかったので、〈サウンドウェイ〉からとなったセカンド・アルバム『トロピカル』が僕にとっては明確な導入部である。〈サウンドウェイ〉は〈オネス ト・ジョン〉をじりじりと追いかけているようなレーベルで、アンゴラのバティーダ(Batida)やコロンビアのメリディアン・ブラザーズなどクラブ・カルチャーとの境界線をなし崩しにするリリースが増えつつあり、どこか気取った〈プロジェクト・ムーンサークル〉からリリースされた『プッシュ』とはイメージが結びつかず、むしろ、そんなにもワールド寄りなのかと驚いたぐらいである。しかし、実際には、これはNYでレコーディングされたエスニック・ポップであった。同じくスリランカのMIAがクゥドロやバイレ・ファンキなど世界のリズムに目配せをしていたようなものとはまったく異なり、都会的な洗練に覆い尽くされていたのである。
と、それで価値がなくなってしまうわけではない。僕には『トロピカル』がトーキング・ヘッズ『リメイン・イン・ライト』(1980)のソフィスティケイティッドされた後日談に聴こえ、フェイクの金字塔として輝けるその地位を補強するものに思えて仕方がない。かつて、トーキング・ヘッズは都会から足が抜けなくなったルー・リードとは対照的に、都会にいながらリモート的にどこへでも移動し、トポスからはかけ離れたポップの構造を生み出すことに成功した。まさに「you may find yourself in another part of the world」(「Once In A Lifetime」)である。「ノー・ニュークス」をモジッただけとはいえ、『ノー・ニュー・ヨーク』(1978)とはよく言ったものだけれど、自分がその場にいないという感覚は故郷喪失者たちによるロックン・ロールからヴェイパーウェイヴまで、ポップには必然的に伴ってきた要素ともいえる。アフリカ・バンバータしかり、マスターズ・アット・ワークしかり。ラプチャーやLCDサウンドシステムが『イエス・ニュー・ヨーク』(2003)を掲げた時期はハテナだけれど、現在ならOPNがそのフロント・ラインに立ち返ったといえるだろうか。
途上国から出てきたミュージシャンには2タイプある。過剰に祖国やその文化圏を思い出す叙情型と、まったくのデラシネと化してしまう叙事型である。「僕のパンダが空を飛ぶ」とは上手くつけたもので、土地との結びつきをなくし、架空の世界に飛翔する契機がまずは言葉によって与えられる。それこそこの世界にパンダを私有している人間など存在しないし、それがさらに空を飛んでしまうとはファンタジーもいいところだし、それで「トロピカル」とくれば、トーキング・ヘッズを上回るフェイクが繰り広げられたところでまったくおかしくはない。そういえばアーサー・C・クラークは『スリランカから世界を眺めて』(1977)で同国を地上の楽園にたとえていたなー。
♪Letting the days go by~ (“Once In A Lifetime”)
三田格
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE