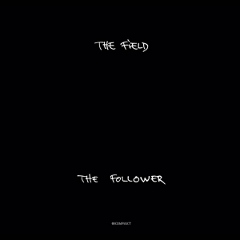MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Reviews > Album Reviews > The Field- The Follower
いまからほぼ10年前、それがシューゲイズ・テクノと呼ばれたことは時代の悪戯だったのかもしれない。シューゲイズという言葉にそれなりの重みがある時期だったし、傍らにガイ・ボラットのようなひとがいるなかで、ストックホルムから現れたアクセル・ウィルナーはインディ・ロックとの絶妙な距離感で注目を集めたからだ。シューゲイズは2013年に『mbv』が決着をつけるまである程度有効なフレーズだったように思うが、さすがにフィードバックをいつまでも響かせているわけにもいかないだろう。そんななか、わかりやすい劇的な変化を見せてこなかったウィルナーが、しかし確実に自分の音を磨き上げてきたことを体感するには、単純に新作『ザ・フォロワー』とファースト・アルバム『フロム・ヒア・ウィ・ゴー・サブライム』を聴き比べてみるといい。『フロム・ヒア〜』はいま聴いてもひたすら心地よく美しい名作だが、たとえばシングル“サン&アイス”の高揚がとても素朴に感じられる。10年かけて彼は確実に自分の「道」を掘り下げており、だからその音楽をザ・フィールドと名づけたセンスにあらためて感心する。ウィルナーにとって反復で生み出す音楽は、果ての見えない平原のようなものなのだ。
しかしながらはっきりとした転換点はやはりあって、それは突然ジャケットを黒くし、音にぐっと翳りを加えた前作『キューピッズ・ヘッド』(2013)だ。『ザ・フォロワー』は明確にその続きとしてはじまっていて、オープニングのタイトル・トラックはダークでアシッディなミニマル・テクノになっている。それは10年前とは違って簡単に快楽の出口を作っていないトラックで、上方向に螺旋を描いていた“サン&アイス”とはベクトルが逆向きだ。クラブで流されればダンスすることもできるだろうが、部屋でひとりで聴いてどこまでも潜り込むこともできる。反復自体をひとつのコンセプトとして求道的に追及していたザ・フィールドの音楽はより繊細で、より複雑なサイケデリアを展開しようとしている。ちょうど半分のところでブレイクを挟み、ビートとともに再びドライヴをはじめる構成もじつにこなれたもので、ゾクゾクするものがある。そしてアルバムは直球なタイトルの“ピンク・サン”、“モンテ・ヴェリタ”と続くが、トーンを保ったままより深いところまで聴き手を導こうとする。
〈コンパクト〉にとってもザ・フィールドのヒットは転換点だったという。ミニマルの牙城というレーベルのイメージを補強しながらも、たとえば僕がそうであるように、インディ・ロック・リスナーの耳をもたしかに魅了したからだ。その理由は『ザ・フォロワー』においてもっともチャレンジングなトラック“ソフト・ストリームス”を聴けばわかる。微妙にシャッフルするリズムが貫かれるなか、インダストリアルな質感の音がやがて丸みの帯びたエレクトロニカへと姿を変えていき、そしてそれらがゆっくりと融合していく。できるかぎりオーガニックな感触であることにこだわっているであろうその叙情的な風景は、誰をも疎外しない優美さに満ちている。もはやシューゲイズ・テクノという2要素で表される言葉では説明できないほど繊細に多くのものがそこには織り込まれており、なめらかな曲線が自在に描かれているかのようだ。
ラスト2曲、“レイズ・ザ・デッド”“リフレクティング・ライツ”は“ザ・フォロワー”とはまた違った、よりアンビエントなトラックとなっていて、アルバムの入り口と出口で景色が変わっていることに気づかされる……いつの間にか。とくに“リフレクティング・ライツ”においてギターとタブラがゆったりと酩酊感を演出していく様は、視界の色を変えそうなほどサイケデリックに気持ちいい。この感覚が次作に引き継がれるのではないかと予想するが、ザ・フィールドの音楽にはそうやってその繊細な変化こそをずっと見ていたいと思わされるようなところがある。反復というアクセル・ウィルナーのコンセプチュアル・アートは、せわしない時代を忘れそうなほどゆっくりとなめらかに、しかしたしかに途切れることなく続いている。そのマイ・ペースさのせいもあってどこか見落とされているような印象もある本作だが、招かれた人間はそう簡単には抜け出せないだろう。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE