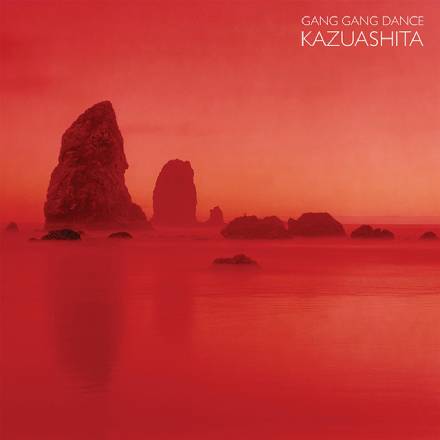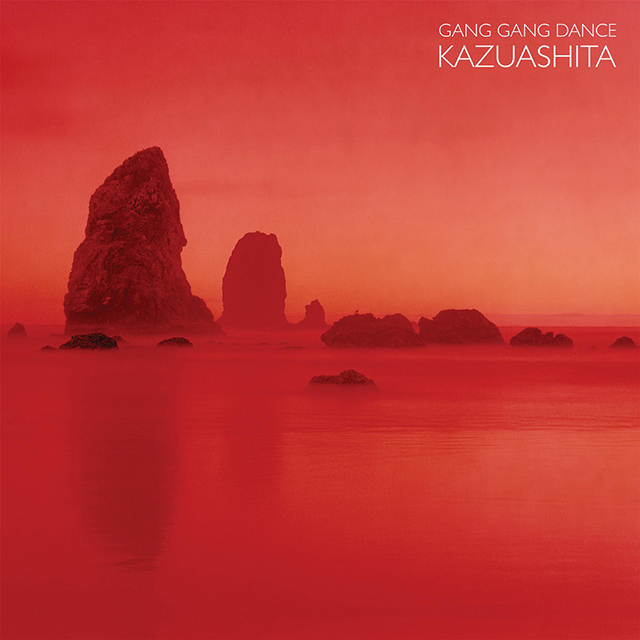MOST READ
- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス
- valknee - Ordinary | バルニー
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- 『成功したオタク』 -
- Kamasi Washington ──カマシ・ワシントン6年ぶりのニュー・アルバムにアンドレ3000、ジョージ・クリントン、サンダーキャットら
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Gang Gang Dance - ギャング・ギャング・ダンス来日直前インタヴュー
いまから振り返って、ゼロ年代に盛況を見せたブルックリン・シーンはブッシュ政権に代表されるような強くて横暴なアメリカに対する意識的/無意識的な違和感や抵抗感を放つ磁場として機能していたのではないだろうか。古きアメリカをサウンドや音響の更新でモダンに語り直そうとしたアメリカーナ勢が注目されるいっぽうで、ブルックリンのエクスペリメンタル・ポップ・アクトたちは「非アメリカ」を音にたっぷり注ぎこむというある種わかりやすくアーバンなやり方で旧来的な「アメリカ」に抗したと言える。だとすると、トライバルなリズムと異国の旋律や和声を生かしながら、それをミックスしグツグツと煮詰めてポップにしたギャング・ギャング・ダンスは、ブルックリン・シーンにおける「非アメリカ」を象徴する存在だった。ブルックリンの街の風景がそうであるように、「アメリカ以外」が当たり前に混ざっていることこそが現代の「アメリカ」なのだと。いまでこそ多様性という価値観でマルチ・カルチュラル性を標榜することは浸透したが、当時の内向きな情勢にあって、外の世界を積極的に見ようとした彼らの功績はいま振り返っても大きい。
10年代に入るとブルックリン・シーンは次第に拡散し、ニューヨークの地価と物価は上がり続けた。金のないアーティストたちはブルックリンを離れ、そして、ギャング・ギャング・ダンスも11年の充実作『アイ・コンタクト』から沈黙した。それぞれソロや別名義の活動を続けつつ、中心メンバーのブライアン・デグロウは山に住居を移して瞑想をしていたという。ニューエイジを聴きながら……。
ブルックリンという地域性はなくなったものの、当時そこで活躍したインディ・ロック・アクトが近年再び活躍を見せはじめているのは、アメリカの社会情勢の混乱と無関係だとは思わない。他国の音楽をその境界がわからなくなるまでリズムや和声に溶けこませたグリズリー・ベア。あるいは、(現在はブルックリンを離れているという)ダーティ・プロジェクターズの前向きな気持ちが詰まった新作『ランプ・リット・プローズ』も、現在を覆い尽くす恐怖や不安に対抗するものだったという。ブライアン・デグロウはニューヨークの街に戻り、そして、ギャング・ギャング・ダンスは2018年に7年ぶりの作品をついにリリースした。
そのアルバム、『カズアシタ』はGGDらしいトライバルなリズムとエキゾチックな旋律を持ついっぽうで、ニューエイジ色を非常に強めたものとなっている。近年の都市部でのマインドフルネスの流行を一瞬連想するが、サウンドはもっと深いところで、アルバムを通して瞑想的な平安を希求する。リジー・ボウガツォスの湿り気のある歌が陶酔的な響きを持つ“J-Tree”や“Lotus”、“Young Boy”などには現行のオルタナティヴなR&Bとシンクロするようなポップさがあるが、それも全体の一部として溶けこませるようにサウンドの統一感が演出されている。いくつかのアンビエント・トラックを通して内的世界に潜りこみ、『カズアシタ』は“Slave on The Sorrow”の壮大なサウンドスケープに包まれて何やらエクスタティックに終わりを迎える。
怒りと怒りがぶつかり合う時代にこそ、GGDはスピリチュアルな探求を選んだ。越境する音が混ざり合うことで得られるピースフルな精神。来る日も来る日も報じられ続ける狂ったニュースに我を失いそうになったら、テレビを消して、インターネットの画面を閉じて、『カズアシタ』の音の揺らぎに身を任せるといいだろう。
※ 以下のインタヴューは、昨年のアルバム発売時におこなわれたものです。
アーティストとか、あんまり金のないひとたちにとっては住みにくいところになったし、すごく金に動かされてる。居住空間が高くなったしね。生活が維持できなくなったんだ。これってニューヨークだけの話じゃなくて、あらゆる場所で起きてることだけど(笑)。
■前作『アイ・コンタクト』から本作の間、ブライアンさんがソロを出すなどメンバーそれぞれで活動をされていましたが、あらためてギャング・ギャング・ダンスのアイデンティティについて考えることはありましたか? だとすると、それはどのようなものですか?
ブライアン・デグロウ(Brian Degraw、以下BD):ふむ。僕らは自分たちのサウンドがどんなものか、ある程度意識してると思う。僕らが集まると何をするのか、どういうことが可能なのか。つまり、僕ららしさはつねにあるものなんだ。でも、僕らがそれに頼ってるとは言えない。音楽を作るとき、そういう思考プロセスに頼っているとは思わないからね。より自然なもので、逆にそこに頼らないようにしてるんじゃないかな。たとえば、今回のアルバムはこれまでに比べて前もって考えた部分が大きかったんだけど、とくにこういうサウンドはキープしようとか、そういうのはまったくなかった。たしかに僕ららしいサウンドというのはあるんだろうけど、意図的なものじゃない。だからこそ、それが何か説明できないしね。ギャング・ギャング・ダンスのサウンドの定義なんて絶対できないよ(笑)。
■ギャング・ギャング・ダンスとして7年ぶりのアルバムを制作するにあたって、はじめに設定したゴールのようなものはありましたか?
BD:これはきっとほかのどのレコードより、青写真的なものがあったレコードだろうな。普段はそういうものはまったくなしに、そのままスタジオに入って音を鳴らして、何が起こるか見てみようって感じだから。でも今回はそうしなかった。あらかじめどういうレコードにしたいか、よりクリアなアイデアを持っておきたかったんだ。もうちょっと空間があって拡張的なもの、ある意味、よりシンプルなレコードにしたかった。簡単な言い方になっちゃうけど、カオス的なサウンドというよりは、シンプルなレコードだね。そう……落ち着いた、平静なサウンドというか。
■本作はリズムよりもサウンド・テクスチャーやメロディに重点があったということですが、逆に言うと、ギャング・ギャング・ダンスにとってリズムのボキャブラリーはすでに身についたという自信の表れでしょうか?
BD:BD:うん、だと思う。あと、いまの音楽のほとんどがリズムをベースにしてる、っていうのとも関係してる。ラジオで流れるようなポピュラー・ミュージックでさえ、多くがリズム中心、ビート・オリエンテッドの曲だったりするよね? ビートを起点にしたエレクトロニック・ミュージックとか。で、僕らには、そのときの流行りがなんであれ、その正反対に行こうとする傾向がある。だから、それも前もって決めたことにかなり関係してると思う。
■“( infirma terrae )”や“( birth canal )”のようにインタールード的なアンビエント・トラックが入っている狙いは何でしょうか?
BD:このレコードは、全体をひとつの曲として聴くように作られてるんだ。だから、そういうトラックもレコードのほかの曲と同じくらい重要で。でも、いまの音楽やレーベルのあり方というか、音楽をどう提示するか、っていうところで、レーベルには「レコードとして出すなら、曲を分けてほしい」って言われてね。そうやって見ると、分けるのも可能ではあったし、いくつか独立した曲として出せるものもあった。ただ、君が挙げたようなアンビエントなトラックもあるし、僕にとってはそういう部分こそ、このレコードでいちばんエキサイティングなところなんだ。いつ聴いても僕自身興奮する。まあ、ある意味では曲と曲を繋ぐような役割とも言えるんだけど、僕としてはいちばん聴いてて楽しいんだよね。
■アルバム全体で流れがあるいっぽうで、“J-TREE”、“Lotus”、“Young Boy”辺りは独立したポップ・ソングとして完結した強度があるトラックだと思います。ギャング・ギャング・ダンスならいくらでも長尺のジャム・ナンバーが作れると思うのですが、完結したポップ・ソングを作るというのは本作にとって重要でしたか?
BD:僕らはああいう曲、よりポップな曲を作るのも好きなんだ。2005年からはそういうこともやってきたと思う。その頃からはじめたんだけど、それ以前はまったくそういう曲を作ろうとしたこともなかった。純粋に即興で、サウンド・ベースの音楽をやってたから。曲を構築したり、作曲しようとしたりはしてなかったんだ。だから2005年くらいから徐々にはじまって、あるレコードのある部分ではかっちりとした曲を作ろうとしたり、でもほかの部分ではそんなアイデアは捨てて、そうならなくても構わない、って感じだったんじゃないかな。うん、僕らはずっと、いわゆる「ポップ・ソング」を作ることに興味はあった。それがいまのところ、どこまで達成できてるかはわからないけど、ずっとトライはすると思うよ。
■そうしたことと関係しているかもしれませんが、“Lotus”や“Young Boy”からはこれまでよりR&Bの要素が聞きとれます。近年のR&Bから刺激を受けるようなことはありましたか?
BD:僕らはこれまでもずっとR&Bに影響されてきた。きっと……90年代あたりからかな。実際、僕ら全員に大きな影響を与えてきたんだ。多くの場合、ある音楽からの影響はメンバーの誰かにはあっても、ほかのメンバーにはなかったりするんだけど、R&Bとヒップホップは僕ら全員が影響としてシェアしてる。ずっと僕らの音楽に影響を与えてきたひとをひとり挙げるとしたら、ティンバランドかな。いっしょに音楽をはじめて以来ずっと彼について話してきたし、リファレンスになってる。ティンバランドと、J・ディラもそう。僕らの話題にずっとあがってきた、ふたりのプロデューサーだね。アリーヤの話もよくするよ。
■いっぽうで、“Snake Dub”は本作でももっともエクスペリメンタルなトラックのひとつですが、とくにエディットの緻密さと大胆さに驚かされます。本作のトラックのエディットにおいてもっとも重要なポイントはどういったものでしたか?
BD:“Snake Dub”はかなり最後のほうでできたトラックで。実際、レコード全体の順番、流れを作ってるときだった。その時点で、ほかにもいくつか、レコードに入れるかどうか迷ってるトラックがあったんだ。で、結局、より曲らしい曲を2、3、削ることにした。僕からすると、その時点でレコードとしてのバランスが、ちょっと「曲」、ソングに偏りすぎてたから。もっとルースな抽象性が足りなかった。どんなレコードを作るにせよ、やっぱりそういう部分は欲しいんだよね。だから、レコードの曲順を作ってるとき、最後の段階であのトラックをまとめたんだ。それまでにやってたいろんなインプロヴィゼーションを繋いで、コンピュータでエディットした。それもやっぱり、レコード全体のバランスを考えてやったんだよ。だからエディットの重要性というより、全部をひとつのものとして考えることが第一だった。
よりフィジカルで、ほとんど血管のなかに入って、身体のなかを循環するような感じ。僕にとっては時折、ドローンやアンビエント・ミュージックは僕の体のなかに存在するような気がするんだ。
■現在は山のなかで暮らしているということですが、山の暮らしからもっとも学んだことは何でしょう?
BD:いまはまたニューヨーク・シティに戻ってきてるんだ。どうかな、ほんとにいろんなことを学んだから。ひとつだけ挙げるのは難しいよ。僕はたくさんのことを学んだんだ(笑)。そのほとんどは……うまく言えないけど、いまの僕が生活に対してどうアプローチするようになったかに関わってる。いろんな点で前とは違うんだ。山で暮らすことで、自分の優先順位について考える余地ができたから。僕自身や自分のアートにおいて、何にフォーカスしたいのか。生き方そのものについても考え直したしね。振り返ると、そういうことを僕は一度も考えてこなかったんだよ。長く街中で暮らして、とにかく前に進むことばっかり考えて、立ち止まることがなかった。「何が自分を幸せにするのか」さえ考えてなかったんだ(笑)。ちゃんと自分のこともケアしなかったし、健康にも気をつけてなかったし。だから、音楽やアート以外のこと、それまでネグレクトしてたことを考えられる機会になった。料理やサステイナブルな家、サステイナブルな生活みたいな、ほかの興味にもゆっくり時間をかけられたし、ガーデニングにもかなり夢中になった。だから、いまの僕には音楽やアートの領域以外にも、大事なことがたくさんできたんだ。
■いっぽうで、ニューヨークの街はどうでしょう? 前作『アイ・コンタクト』の頃からとくに変わったと感じられることはありますか?
BD:実際、また街に戻って適応するのがかなり大変だったんだよね。最初は時間がかかった。いまはだいじょうぶだけど。前といちばん違うのは、いまは自分のアート・スタジオがあること。長い間住んでたのに、ずっとアート・スタジオを持ってなかったんだ。でもいまはアート・スタジオも音楽スタジオも持ってる。そういう空間があると、僕はずっとクリアにものが考えられる。でも最初に都市を離れて田舎に住もうと決めたときは、そういう場所がなかったんだ。だから、心の平安を見つけるのが難しかった。いまは自分がそこに行って、ちょっとしたものを作れるような空間があれば、街でももっといい生活が送れるんだ、っていうのを発見してるところ。以前はそういう場所がなかったからね。前の僕は小さなアパートメントで暮らして、落ち着かなくなって外に出たら、街中はもっとクレイジーだったりした。でもいまはスタジオ用の部屋があって、そこで落ち着いて考えたり、何か作ったりできる。実際、静かだしね。
通訳:街のほうも変わりましたか?
BD:うん。前とは違うタイプのひとたちが住んでる。ニューヨークはアーティストとか、あんまり金のないひとたちにとっては住みにくいところになったし、すごく金に動かされてる。居住空間が高くなったしね。もちろん、よくなったところもある。ある意味クリーンになったし……まあ、僕はときどき、30年前のクリーンじゃないニューヨークが懐かしくなるけど。でもやっぱり、一番変わったのは物価やコストだろうな。それでアーティストが押し出されて、僕を含め大勢が北部や田舎のほうに引っ越していった。生活が維持できなくなったんだ。とはいえ、これってニューヨークだけの話じゃなくて、あらゆる場所で起きてることだけど(笑)。
質問・文:木津毅(2019年1月18日)
| 12 |
Profile
 木津 毅/Tsuyoshi Kizu
木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE