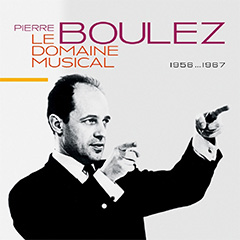MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > News > RIP > 追悼:ピエール・ブーレーズ(Pierre Boulez)
十代は懐がさびしいので湯水のごとく音楽に金を使うわけにはいかない。いきおい、ただで聴けるラジオがことのほか大切になる。彼とのつきあいは短くない。年端のいかないころにさかのぼるので、幼なじみ同然、長じて友人、ほとんど恋人。とはいえ、性交するわけではないので親友くらいで手を打ちたいが、友だちのだれよりもいっしょにすごす時間は長かった。中学にはいるころにはいくらか距離ができて、好きな番組を選んで聴くようになった。NHK FMのバラカンさんや渋谷陽一氏、同じ時間帯のヒット曲のリミックス中心の番組(DJは失念)と、日曜夜の「現代の音楽」は欠かさずエアチェックした。テーマ曲であるヴェーベルン編曲のバッハ「6声のリチェルカーレ」につづき、上浪渡さんの「現代の音楽です」のナレーションが入ると、寝床のなかで居住まいを正したものだ。60分テープに録音しつつ耳を傾けながら気づいた朝のこともしばしば、私にとってブルーマンデーの足音を告げるのは「笑点」でも「サザエさん」でもなく(そもそもテレビがなかった)、ヴェーベルンのバッハだった。
テープを聴きかえし、インデックスをつくるのは翌週の課題である。多くの作曲家の名前と曲をこの番組で知った。武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」をはじめて聴いたのもこの番組だし、諸井誠、湯浅譲二、松平頼則、伊福部昭等々、日本の作曲家が印象に残っているのは、記憶の捏造かあるいは文化振興の意図からそうなっていたのかもしれないが、ケージ、メシアン、ナイマンもこの番組で知ったし、ノーノの「ガルシア・ロルカの墓碑銘」のガルシア・ロルカが聴きとれず、二十代までそのナゾが解明しなかった面目ない経験もしたが、現代音楽ないし前衛と呼ばれた(録音物としての)20世紀音楽は私にとって、ロック、ジャズやポップ・ソングなしいそのリミックス(クラブミュージック)と同列の刺激的な響きのひとつだった。その発見はなににもかえがたい、(音の)世界の広さに戦くことであり、音楽は学校で学ぶ音楽がすべてではないとほのめかすばかりか、音に不協和の関係など存在しないと(なかばあやまった)考えに開眼するきっかけだった。そこから、自作テープの編集が高じてのテープ・コラージュやカセットデッキの倍速ダビング機能の誤用、レコード・プレイヤーの回転数の意図的なとりちがえ、ラジオ、無線といった放送の音質そのものを音楽的に聴くハンドメイドの聴覚実験まではひと跨ぎである。私をふくむ健全な男女のだれもがそんなことにかまけたのが20世紀であり、いくつもの戦争に縁どられたこの20世紀を俯瞰し、二次大戦の前後でそれを劃する象徴として、音楽史──ここでいうそれは西洋音楽のそれであるが──にあらわれるのがピエール・ブーレーズである。
1925年、仏モブリゾンに生まれたブーレーズはパリの高等音楽院でメシアンらに学ぶも中退、終戦の年、二十歳を迎えた彼は「12のノタシオン」を書きあげている。この短い断章めいたピアノ曲は名刺代わりともいえるもので、後にオーケストラ用に編曲され巨大化するこの作品をきっかけにブーレーズは20世紀音楽の重要作を江湖に問いはじめる。「婚礼の顔」「ピアノ・ソナタ第2番」「構造Ⅰ」、「ル・マルトー・サン・メートル(主のない槌)」──シェーンベルクの十二音技法を補足するとともに進化させたトータル・セリー(総音列)はものの本によく出てくるので、耳なじみの方も多いと存ずるが、平均律内の1オクターヴ内の半音をふくむ十二の音を平等かつ過不足なく用い完全な調和を目す十二音技法では満足できない、音価や強弱などのニュアンスまでパラメーター化し統治するのがトータル・セリーであり(乱暴な要約だが)、ブーレーズは自身の、というより20世紀のピアノ曲を代表する作品のひとつである「ピアノ・ソナタ第2番」(1948年)でシェーンベルクとの訣別を目した、とみずから語るように、その先に踏み出していく──のだが、私は思うのだが、「ピアノ・ソナタ第2番」にコーダにドイツ語の音名による「BACH」のアナグラムがあらわれるのとおなじく、シェーンベルクが最初の大機規模な十二音技法の作品「管弦楽のための変奏曲作品31」(1926〜28年)の基本音列の最後に「HCAB」つまりバッハの逆行形を置いたように、ブーレーズのいう訣別とは鏡像的な結びつきを意味するのではないか。ともに作曲家で指揮者であり教育者であるふたりは20世紀を前後に分かつ境界線上で対峙する(シェーンベルクが死んだのは1951年だ)だけでなく、音楽史上最大の巨人バッハを影に日向に志向し思考することで、前衛は古典との偏差のかぎりでの前衛であると彼(ら)はいいたがっている(「現代の音楽」のテーマがシェーンベルクの弟子であるヴェーベルンが編曲したバッハであるのも暗示的である)。本稿ではナイマンの著書『実験音楽』にならって、前衛と実験とを区別しているが、ブーレーズにはたとえば、ケージの偶然性を「管理する」など、完璧主義者の側面があり、その厳密さは旧作の改訂につながり、ダルムシュタットなどでの後進とのかかわりでは導きの光となり、マーラーやヴェーベルンのすべての交響曲の録音をのこした卓抜なタクト捌きにも実を結んだ(いまは指揮者のほうのファンが多いと思う)。行政官としても、IRCAM(フランス国立音響音楽研究所)の初代所長となり、リアルタイムでの音響処理できる高速コンピュータ「4X」の開発が、みなさんご存じの「Max(Max/MSP)」につながった経緯もある。「レポン」や「...explosante-fixe...」はいまや超然としたところがかえって古きよき時代を思わせ牧歌的だが、ブーレーズがいなければ、リチャード・D・ジェームスはミュージシャンになれなかったもしれないしIDMは流産したかもしれない。フロリアン・ヘッカーは「ele-king」Vol.7のインタヴューで、音楽の複雑さを例証するにあたり、ブーレーズとクセナキスを対比している。さらにポピュラー音楽とのかかわりつけくわえると、1976年に創設した現代音楽の室内オーケストラ、アンサンブル・アンテルコンタンポランを率い、フランク・ザッパの筆になる「パーフェクト・ストレンジャー」を振ったのは84年。ヴァレーズ、ストラヴィンスキーとともに「ル・マルトー・サン・メートル」をフェイヴァリットにあげるザッパの、当時の現代音楽の水準でいえば時代がかかった、しかし生粋の現代音楽の作家にないユーモアをひきだしたブーレーズの手腕には、ザッパ・ファン、ロック・ファンのみならず、タイヨンダイ・ブラクストンも目をみはるにちがいない。
ことほどさように、広範な視野と豊富な語彙、音楽史の弁証法を信じながら古典あるいは西欧の美学の風合いを失わないたたずまいは20世紀音楽の最後の巨星と呼ぶにふさわしい。そのブーレーズが歿した。今後おそらく彼のように多面的に音楽を体現する作曲家はあらわれまい。ファーニホウやラッヘンマンがそうなれるとは思わない。ミニマル、ポスト・ミニマルの方々はどうだろうか。それとも、そもそも私たちはそのようなひとの必要ない時代に生きているのか。20世紀がまた遠のいた? そうかもしれない。ところが遠のけば遠のくほど道のりを踏みしめる楽しみは増さないともかぎらない。ブーレーズはその道の向こうにかすかに見える指標のようなものだ。それはこの平坦な時代に隆起した山のように見えなくもないし、行けども行けどもたどりつけない城のようなものでないとはだれもいいきれない。(了)
松村正人
NEWS
- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる
- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿
- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開
- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日
- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回
- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース
- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売
- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ
- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定
- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選
- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定
- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演
- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場
- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場
- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ
- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース
R.I.P.
- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ
- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木
- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー
- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー
- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン
- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル
- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート
- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター
- R.I.P. 鮎川誠
- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン


 DOMMUNE
DOMMUNE