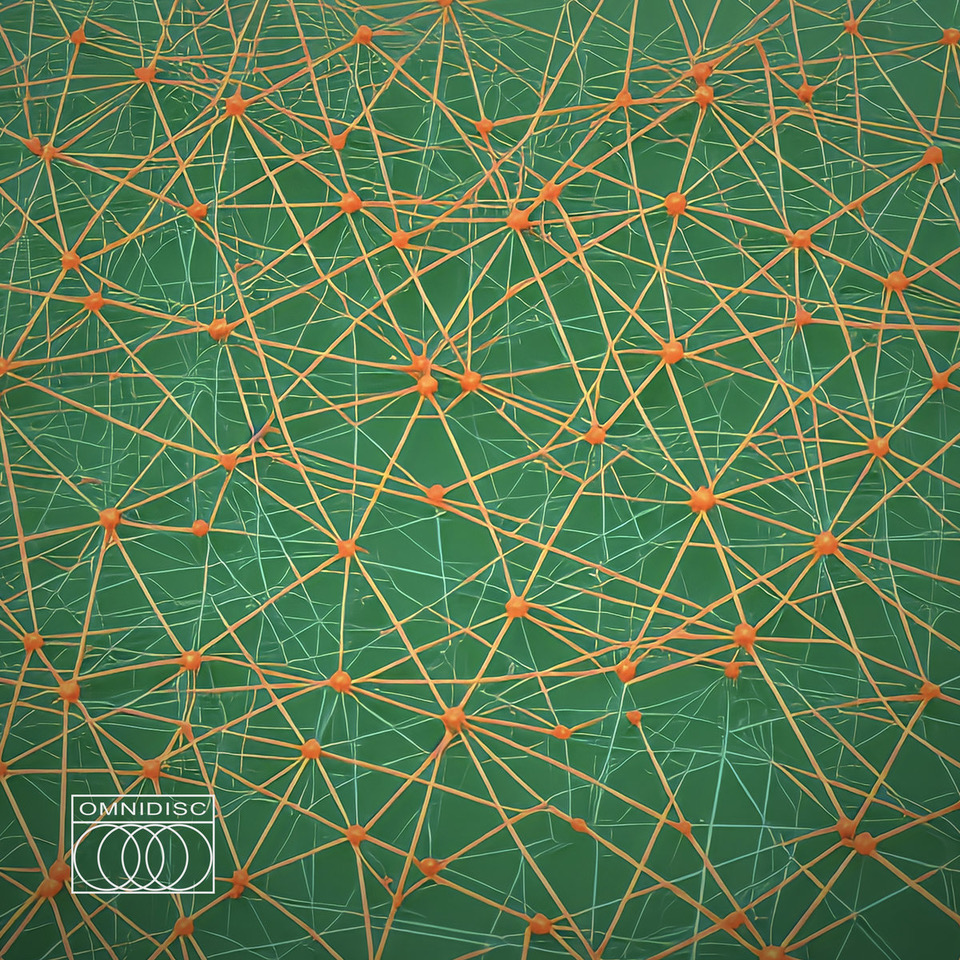MOST READ
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- KMRU - Kin | カマル
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
Home > Reviews > Album Reviews > Nick León- A Tropical Entropy
レゲトンのサブジャンルにネオペレオ(Neoperreo)がある。簡単にいえば少し陰のあるレゲトンで、10年代前半にチリのトマサ・デル・レアルとアルゼンチンのミズ・ニーナがハッシュタグに用いたことでジャンル名として定着したという。ペレオというのはレゲトンと呼ばれる以前のレゲトンのことで、レゲトン自体がいつ始まったのか定かではないために(ノリエガでよくね?)どの時期までを指すのか人によってまちまちだけれど、いずれにしろネオペレオという呼称自体はレゲトンの新たな展開を意味している(ネオ・ペレオ=ニュー・レゲトン)。ちなみに黎明期のレゲトンに回帰する動きはペレオコアなどとも呼ばれたり。勃興期のネオペレオは女性中心で、セクシュアリティに言及する歌詞が多く、すぐにもスペイン系のバッド・ギャル(Bad Gyal)やロザリオ、ホンジュラス出身のロウ・ジャックがプッシュするクララ!などヨーロッパの女性プロデューサーへと飛び火していった。10年代後半に入ってネオペレオがL.A.で隆盛を極めるとブラック・アイド・ピーズやバッド・バニーなどメジャーへと波及し、その一方で、ジャム・シティやケルマン・デュランなどアンダーグラウンドなプロデューサーたちがデコンストラクティッド・クラブとしてマイナー・チェンジを重ねたものがより音楽的な面白さにフォーカスしていった。僕が最初に興味を持ったのもコード9とベリアルによるミックスCD『Fabriclive 100』に収録されていたウルグアイのレチュガ・ザフィロ(Lechuga Zafiro)で、ぴちゃぴちゃと水の跳ねる音をビートに使った“Agua y puerta”は実にシュールで、ヴィデオも鮮烈な印象を残した。レタス・サファイアという意味のレチュガ・ザフィロが同じ年にリリースした「Aequs Nyama Remixed」では早くも700ブリスがリミックスに起用されていて、音楽的な広がりに対する期待が一気に加速したことも忘れがたい。さらにはアルカである。コロナ禍に5枚連作でリリースされた『Kick』にはシリーズの前半でレゲトンとともにネオペレオがフィーチャーされ、ストリート・ミュージックとして発展してきたネオペレオがそれはもう見事なほどグリッチと手を結んでいた。アルカはその後もシングルで“KLK”(20)、“Prada/Rakata”(21)、“Chama”(24)、“Puta”(25)、“Sola”(25)とネオペレオを連発。優雅で高貴な世界観を増幅させることに余念がない。バッド・バニーとアルカは同じ2020年のリリースであり、メジャーにもアンダーグラウンドにも広がっていたネオペレオはコロナ禍でやや減少傾向に転じたものの音楽的な勢いが衰えた印象はなく、ニコラ・クルズ&イザベル・ラヴストーリー、フロレンティノ、デング・デング・デング、シャイガールと様々な方向に触手を伸ばし、ビリー・アイリッシュやビョークともコラボレイトしたロザリア『MOTOMAMI』(22)やリズ『Extasis Silicone』(23)などメジャーでも充実作が続いている。トキシャ(Tokischa)“CANDY”やLSDXOXO(エルエスディーエックスオーエックスオー)“Freak”のヴィデオを観ていると『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の人気がどこから来たものなのかよくわかるというか。
12歳でレゲトンに人生を変えられたというニック・レオンによる9年ぶりのセカンド・ソロでもネオペレオは大々的にフィーチャーされている。 マイアミ・オールスターズによる『Homecore!』で書いた通り、「マイアミを音楽都市として再浮上させたプロデューサー」として高く評価されるニック・レオンはかねてからDJパイソンやケルマン・デュランと同じくレゲトンとアンビエントの接点を探ってきたこともあり、ここでもネオペレオから陰の部分を多く引き出すことに成功している。冒頭から初期のソフィを思わせるザンダー・アーマドのヴォーカルを起用した“Entropy”。ファヴェーラ・ファンク(バイレ・ファンキ)を基本としながら仕上がりはマイアミ流のバブルガム・ベースといった趣で、これにアトモスフェリックな浮遊感をたっぷりと混入させ、後半はパーカッションを強調。続く“Ghost Orchid”と“Metromover”はその余韻を受け継ぐかたちでネオペレオとUKガラージの接点を模索しながらゆらゆらと水の中を漂っていく。前者にはダンスホールのエラ・マイナスが起用され、カリブ海文化に対するレオンの強い執着を窺わせる(ニック・レオンはオークランド出身説もある?)。『熱帯の無秩序(A Tropical Entropy)』というタイトル通りヘンな効果音にまみれた“Millennium Freak”はアグレッシヴなチャンガ・トゥキ。中南米産とはかけ離れたシャープなプロダクションが臨場感を掻き立て、勢いを増したパーカッションはM.I.A.を彷彿させる。
“Hexxxus”、“Crush”とソリッドでクールな展開が続き、“R.I.P. Curren”で少しテンポ・ダウン。海中を疾走していくようなイメージに変わる。珍しく男性ヴォーカル(Lavurn)を起用した“Product of Attraction”は竜宮城を巡るイメージでしょうか。“Ocean Apart(海から離れて)”でも男性ヴォーカル(Casey MQ)が続き、ビートが後退してメランコリックなムードに沈んだバブルガム・ベースを展開。短くまとめた“Broward Boyy”を波打ち際の音で締めくくり、エンディングにはヴォーカルにエリカ・ドゥ・キャシエを起用した先行シングル“Bikini”を再録。全体の出発点となった曲なのか、この曲が最も無邪気なムードにあふれている。この曲だけはなぜかマスタリングがラシャド・ベッカー。
レオン自身は彼のサウンドを建築を意味するアルキテクトロニカ(Arquitectronica)と称している。マイアミの建築物を指す典型的な用語だけれども、おそらくクラブ・ミュージックを自在につなぎ合わせたデコンストラクティッド・クラブと同じ意味なのだろう(?)。『A Tropical Entropy』の元になったイメージはジョーン・ディディオンの異色ルポルタージュ『マイアミ ― 亡命ラテン・エリートのアメリカ』(87)で、ケネディ暗殺、ウォーターゲート事件、レーガン・ドクトリン、イラン・コントラ事件などを通してキューバ革命でカストロに祖国を追われたキューバ人たちが亡命先となったマイアミでアメリカの外交政策にどのような影響を与えたかを考察した本だという。ドナルド・トランプの横にいつも立っているマルコ・ルビオ国務長官がまさにそうした出自を持つキューバ系で、祖国を憎むあまり、共産主義を憎み、イランや中国に対してかなり強硬な姿勢で臨む外交政策を現在進行形で続けているところである。『A Tropical Entropy』にはさらにドラッグ体験と睡眠不足によって引き起こされたオルタード・ステーツから得たインスピレーションも反映されているそうで、社会の崩壊にともなって人生が崩壊していく様を目撃したという個人的な体験が重ね合わされているのだという。さすがにそこまでは聴き取れなかったw。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Milledenials - Youth, Romance, Shame
- KMRU - Kin
- Deadletter - Existence is Bliss
- Cardinals - Masquerade
- Jill Scott - To Whom This May Concern
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her
- xiexie - zzz
- Cindytalk - Sunset and Forever
- CoH & Wladimir Schall - COVERS
- KEIHIN - Chaos and Order
- DIIV - Boiled Alive (Live)
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations


 DOMMUNE
DOMMUNE