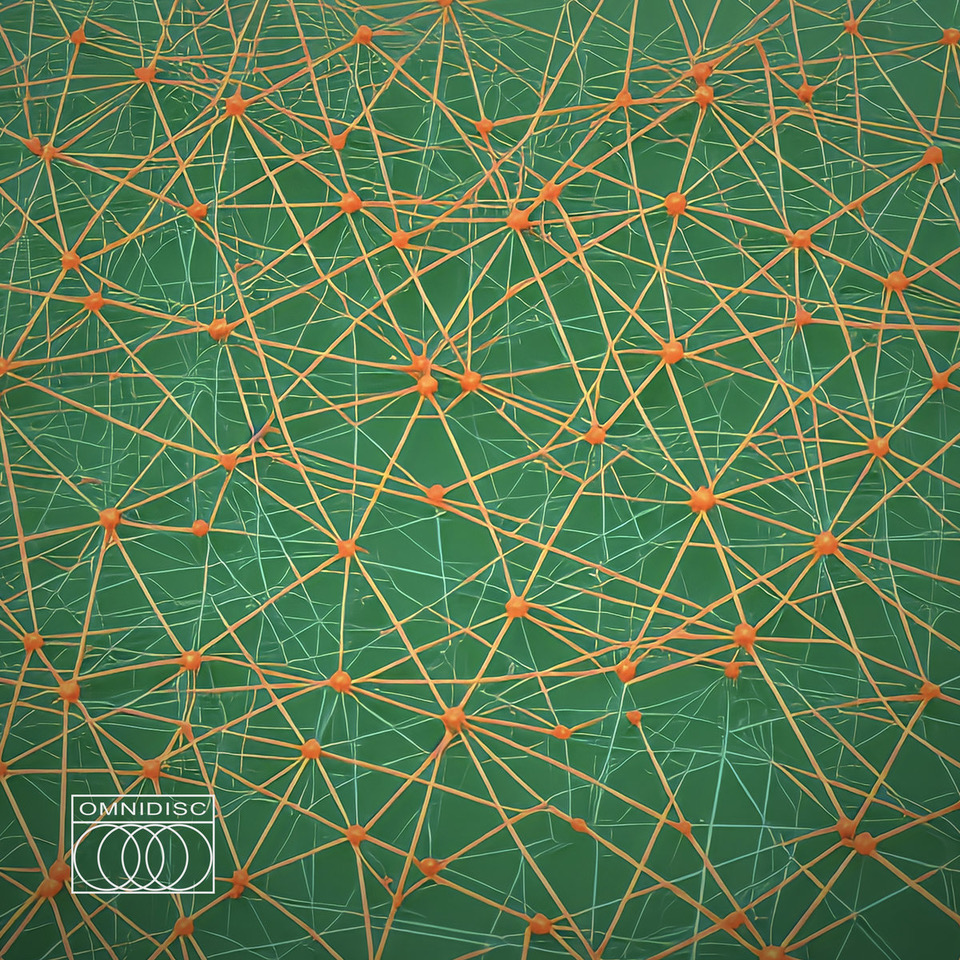MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > Various- Homecore! Miami All-Stars
『地元コア!』と題されたエリア・コンピレーションで、ここ30年間にマイアミで名を挙げたダンス・アクトがほぼ一堂に会している(テクノ、ハウス、エレクトロが中心で、ヒップホップは除外)。壮観。全44曲。すべて新録のようで、ヴェテランもニューフェイスもなかなかにしのぎを削り合っている。短い曲が多いせいか、テンションも持続し、いわば「マイアミ・ベース以降」がまとめて体感できる。マイアミ・ベースはアトランタに波及してトラップに発展したり、中南米にはファヴェーラ・ファンクやファンク・カリオカといったシーンを誘発したものの、地元マイアミではどのような変化を遂げたのかということがまとめて報告されたことはなく、それがここに見晴らしよく並べられたという感じ。猥雑でダイナミック。簡単にいえばマイアミの魅力は大胆さと低音の太さに尽きるだろう。ロンドンやベルリンは新しいことをやろうとし過ぎて、時にヒネくれた感じになりやすいけれど、マイアミにはそういったことはない。自由闊達なダンス・ミュージックの最前線である。
収録順ではなく、プロデューサーのデビュー順に聴いてみよう。まずはラルフ・ファルコンとオスカー・Gによるマーク(Murk)。彼らが名を挙げたのは92年にファンキー・グリーン・ドッグス名義のハウス・クラシック“Reach For Me”がデトロイト・テクノを広めた〈Network Records〉にライセンされ、ヨーロッパでヒットしてから。いわゆるシカゴ・アシッドとは異なるヘヴィなベースがマイアミらしさを打ち出し、本作にも2人はこの30年が何事もなかったように同じパターンの“Filth”を提供している。この不動の価値観。シカゴ・ハウスがヨーロッパに飛び火し始めた80年代後半、マイアミで最も人気だったのはエレクトロ・ヒップホップの2ライヴ・クルーで、彼らのサウンドはデトロイトのサイボトロンがマイアミでもヒットしたことから始まったとされる。2ライヴ・クルーのピークといえる『As Nasty As They Wanna Be』(98)の10年後にはそして、サイボトロンをダイレクトに継承しようとするイグザクト(Exzakt)やBFXが現れ、ここでは両者がタッグを組んで“Reach For Me”をミニマル化したエレクトロの“Let Go”を、また同時期にブルックリンで活動し、後にマイアミに移ってきたゴーサブはマッド・マイクを思わせるデトロイト・タイプのエレクトロ、“Who The Fuck Is Me?”をそれぞれに提供し、さらに少し遅れてデビューしたアルファ606は“Cacique”で、これらとはまったく違った神秘的なエレクトロをオファーしている(同作が全体のクロージング・トラック)。
最近ではチャイルディッシュ・ガンビーノ“This Is America”のリミックスで名を挙げたジェシー・ペリッツは母親が2ライヴ・クルーのダンサーだったことから音楽の現場とは距離が近く、最初は俳優として活躍していた存在。なかなかの遅咲きで、“Jesse Don't Sport No Jerri Curl”が注目を集めるまでに7年かかり、エレクトロとハウスの中間をいくサウンドを模索。ここではエレクトロに寄った“Pocket Full Of Ones”を提供。エレクトロ回帰と同時期にマイアミに大挙して現れたのがグリッチ・ホップで、元ソウル・オディティのフォーニージア主宰による〈Schematic〉を中心にディノ・フェリペやオットー・フォン・シラクが頭角を現し、本作でも後者はオープニングとなる“Miami All-Stars (Tremendo Intro)”を、前者は当時と変わらずファニーな“In Order To Ground The Listener”をそれぞれに提供。彼らのサウンドはプリフューズ73やフンクシュトルンクなどと並べて聴くよりもマイアミ・サウンドの一部として聴いた方がしっくりとくることは間違いない。さらに活動の途切れていたプッシュ・ボタン・オブジェクツを約20年ぶりにレーベル・オーナーのダニー・デイズが担ぎ出して“I.E.”を共作、ピッチを早めたオールド・エレクトロにアシッド・ハウスを絡めたなパーティ・サウンドに仕上げたことはひとつの快挙といえる。
エレクトロからクランクへと歩を進めたヒップホップとは距離を置き、マイアミ独自のテクノやハウスが増えたのが00年代。まずはマークの後継としてラザロ・カサノヴァが現れ、ゴーサブ同様、ブルックリンからマイアミに移った彼は作風も“Reach For Me”を継承。ここではレイドバックしたダウンビートの“Nieve”を聞かせる。レーベル・オーナーのダニー・デイズもこの世代に属し、彼もどちらかといえば遅咲きで、『Silicon EP』『Speicher 80』(ともに14)では“Reach For Me”やジェシー・ペリッツの試みをテクノの領域に移植。彼が主宰してきた〈Omnidisc〉ではボディ・ミュージック・リヴァイヴァルのヘレン・ハフやアンソニー・ローター、ワタ・イガラシにブラック・マーリンとオルタナティヴ志向を強くしていたものの、16年にリリースしたヘヴィ・エレクトロの「Miami EP」から本作『Homecore!』のアイディアが膨らんでいったのだろう。〈Omnidisc〉では異色といえる本作には蛆虫が地を這い回るような気持ち悪い“110 Dudes”を提供してマイアミのイメージを根底から覆す役割を演じる一方、ひと世代下のニック・レオンと組んでラ・グーニー・チョンガ“Phonkay”ではアフリカ・バンバータそのままのエレクトロ・ヒップ・ホップも聞かせる。
このところローレル・ヘイローからニコラス・クルスまであらゆるDJミックスに登場するニック・レオンは「マイアミを音楽都市として再浮上させたプロデューサー」と言われるほど評価の高いプロデューサーで、〈Alpha Pup〉からのデビュー・アルバム『Profecía』(16)ではリスニング寄りの穏やかな側面を見せ、世界中のレーベルからリリースされるシングル群ではワラチャというキューバのリズムやドラムンベース、最近はラプター・ハウスと称されるチャンガ・トゥキにデトロイト・テクノを縦横に駆使し、どれも外しがない。とはいえ、本作ではあまり本領を見せていないメカニカルなエレクトロの“Sapo”を提供していてやや残念。ヴォーカリストとしてニック・レオンと組む機会が多いビター・ベイブも本作にソロ名義で“Gimme”を提供し、レゲトン版ドレクシアなどと評されたニック・レオン「FT060 EP」(最高です!)に共作で参加していたグレッグ・ビートー(Greg Beato)はリズム感がそれほどよくないせいか、最近は実験的な作風に傾き出し、〈Schematic〉をエレクトロに戻したような作風をプッシュ。ここでは90sリヴァイヴァル風の“Hey Angel, Whatever”を提供している。
ダニー・デイズと活動を共にしているジョニー・フローム・スペースことジョナサン・トルヒーヨはニック・レオンやシスター・システムらと合わせてニュー・スクールと呼ばれる若手の代表。DJパイソンの向こうを張る形でレゲトンのリズムに由来するデンボー(dembow)の使い手とされ、これをプッシュ・ボタン・オブジェクツなどのグリッチ・ホップと接続させたと評される。しなやかで柔軟性のある『R.E.M.』(ムスリムガーゼ、池田亮司、ヤン・イエリネクらに捧げられている)や『Tide』など彼は本当に才能豊か(“Sueño Latino”みたいな曲がたまにあるところもよい)。本作にはいままでとイメージが異なるタイトなエレクトロの“Refresh”を提供。本作でデンボーを扱ったものはMJ・ネブリーダによるフィッシュマンズみたいな“Arquitecto”も。また、トルヒーヨが新設した〈Space Tapes〉から4thアルバム『Parrot Jungle』をリリースしたニコラス・G・パディヤはエレクトロとベース・ミュージックを接合させたハイブリッドで、ニューエイジ用語をちりばめているわりに曲が荒々しいのは絶滅させられた少数民族の代弁者を名乗るからだろうか。本作にはガラッと変わってポリリズミックなブリープ・エレクトロの“Zone”を提供。ジョニー・フローム・スペース周辺からはほかにシスター・システム、バニー(Bunni)などがエントリー。
ベース・ミュージックがマイアミと相性がいいのは当たり前というか、ハーフタイムとエレクトロをスムースにつなげ、珍しくUKガラージを意識したINVTも短期間にミニ・アルバムを量産しながら(この4年で『Sano』『DisruptionI』『Extrema』『Cambio De Forma』『Mundos』、ニック・レオンと組んだ『Paseo』『Media Noche』『Plaza』『Doble Carga』『Ritmo Caliente』『Gazebo』『Duro』『La Chamba』『MiradaI』『Prendida』など)クオリティは下がる気配もなく、本作では前述のワラチャを応用したらしき“Dassit”を提供。このドラムはたまらない。リトル・シムズの新作『No Thank You』に収められていた“X”もおそらくは同じリズムで、個人的にはこれがベスト・トラック。ほかにUKとダンス・ミュージックの文脈を共有しているのはFKAトゥイッグスを早回しにしているようなバブルガム・エレクトロのティドゥー(TIDUR.)、トッド・テリーが派手にジュークをやっているようなセル6(sel.6)、アレックス・リース“Pulp Fiction”を思い出すなというのが無理な90sドラムン・ベースのシノビ(Shinobi)、同じくドクター・ロキット名義のハーバート“Café De Flore”を思わせるスパニッシュ・ムードのハーフタイム、“Red Keycard”を聴かせるニア・ダークといったところ。UKはやはりどこかに冷静な感じがあるというか。
ニック・レオン、ジョニー・フローム・スペースと並んでいま、マイアミにおける台風の目となっているのが、そして、フィー-ゴー・ジット(Fwea-Go Jit)。同じフロリダ州のタンパで生まれたジューク(スペルはJookで、ジュークボックスに由来)と呼ばれるヒップ・ホップ・ダンスがマイアミに飛び火してジャージー・クラブやダンスホールと融合し、DJキャレド“To the Max”(17)によって世界的に広められたバウンス・ビートを縦横に駆使した3thアルバム『2 La Jit』はけっこうな評判を呼んだ。MCの起用も多く、どこを取ってもピットブルかよと思う激しいダンス・ミュージックの嵐で、本作では折り返し地点に置かれた“Touch It Turn It”が微かな哀愁も漂わせつつ、次章への幕開けとなっている。また、リッチー・ヘルはこれまでになかったタイプというのか、バンド編成でマンボやクンビアを演奏し、ボビー・コンダースやモーリス・フルトンに近いリラックス・タイプ。本作にはクンビア調の“Rapto Cosmico”を提供。
ここからは少し端折ろう。さすがに数が多過ぎる。ウィッチハウスとしてキャリアをスタートさせたブラック・アントことジャン・ピエール・アンソニーは少し変わり種で、初期には拷問のようなゴシック・ホップを掘り下げ、4作目から〈Schematic〉に移籍、レーベル・カラーに合わせてLAビートに転じている。5thアルバム『Hidden Packages (Islands 3 + 4)』はまさかのJ・ディラとラス・Gに捧げられ、本作にもフラッシュ音を強調したグリッチ・ホップの“Bellfast3”を提供。同じ〈Schematic〉からゾン・ジャマール(Sohn Jamal)とマックス・ブゾン(Max Buzone)、そしてロイジュー(Roiju)もエントリー。サイケデリック・ブレイクコアのジョセフ・ナッシングを思い出すゾン・ジャマールは比較的オーソドックスなグリッチ・ホップの“TQ Visa”を、哀愁に沈んだIDMのマックス・ブゾンはいままでとは比較にならない出色の“Epoch”を、そして叙情的なIDMのロイジューはパーカッシヴな“Sin Gravedad”をそれぞれに提供。珍しくミニマル・テクノのフィーフ(Feph)はまったく表情を変えずに“Resolve”をオファー。やはりマイアミには珍しく〈Warp〉風のリスニング・テクノからミニマルも射程内に置くエライアス・ガルシアも本作ではジェフ・ミルズ風の“Radiant”を。
『Homecore!』は半数がここ2年でデビューした新人か本作で初めて曲を発表したニューフェイスで占められ、オープニングに続いて2曲目と3曲目に抜擢されているのがロウ・エンズ・レコーズとジ・オウ・ファイ(Tre Oh Fie)。どちらも荒々しいエレクトロを提供し、イメージ通りのマイアミで幕を開けるという役割を全うしている。御大マークの次に置かれたコフィンテクスツ(Coffintexts)も新人ながらやはり大役を担い、これもハードなブレイクビーツ路線とは少し変わってハーフタイムの“Muy Bien”で面白い流れをつくっている。無名どころの新人ではほかに(って僕が知らないだけかもしれないけれど)、ジャン・アンソニーによるポリリズムのエレクトロ、“Trees Whispers Leave”もなかなかに良かった。
10年代の前半こそロサンゼルスにレイヴの舞台を奪われたものの、ほどなくしてその座を奪い返し、レイヴどころか『お熱いのがお好き』の昔から踊る天国であり続けているマイアミ。キューバとの関係が様々な意味でマイアミを活気づけ、介護される富裕層が共和党支持なら介護する労働者が民主党支持というスタンダードな政治風土を背景にマルコ・ルビオ上院議員や最近ではトランプの代替わりとされるロン・デサンティス州知事が吠える、吠える。ゲイ・クラブでの銃乱射事件が象徴しているように、いまや性別を気にしないノンバイナリーに対して性別をはっきりさせるバイナリーのテリトリーとしても強度を増し、マジック・マイクたち男性ストリッパーもステージ狭しとショーを続けている。最近になってマイアミに引っ越したジェフ・ミルズ夫妻によると日本並みに湿度が高く、コロナでも誰もマスクなんかつけていなかったというし(ロックダウンが解除されたと思ったら、あっという間に海岸がゴミだらけになったとも)。突拍子もない水着ショーも面白いし、できることならエルモア・レナードやカール・ハイアセンの犯罪小説を読み続けて一生を終えたいなー……と思った3時間半でした。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE