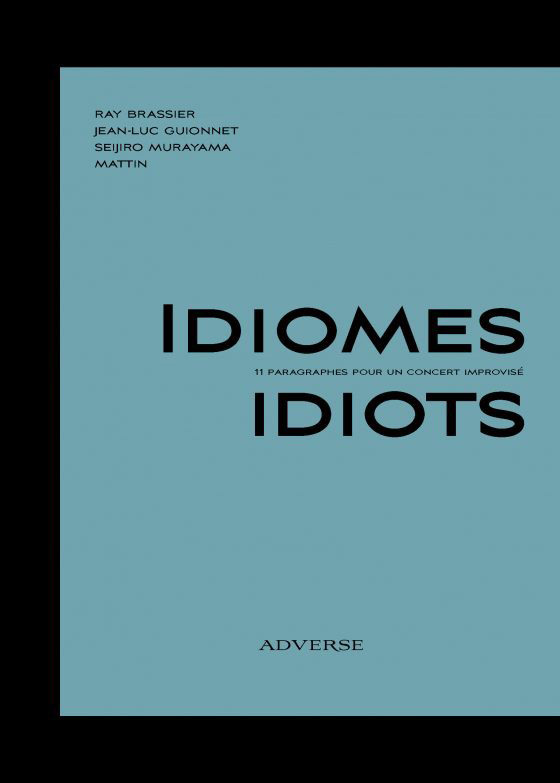MOST READ
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Ikonika - SAD | アイコニカ
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー
- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場
- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー
- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー
- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet | ジェイ・エレクトロニカ
- Geese - Getting Killed | ギース
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ
- ele-king vol. 36 紙エレキング年末号、お詫びと刊行のお知らせ
- Nouns - While Of Unsound Mind
- Columns なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009
- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
- 発見の会60+1周年公演『復興期の精神ー近代篇』 - 2025年12月18日〜21日@上野ストアハウス
Home > Columns > イディオムとイディオット(語法と愚者)- ──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ
イディオムとイディオット(語法と愚者)
──ある即興演奏のコンサートについての11のパラグラフ
文:ジャン=リュック・ギオネ、マッティン、レイ・ブラシエ、村山政二朗 訳:村山政二朗 Jun 12,2020 UP
2 頼むからインプロヴィゼーションを始めないでくれ!
我々はインプロヴィゼーションを一つの公理と見做すが、それは、人がインプロヴィゼーションをしているところなのか否かを決して本当には決められないという意味においてである(自由意志、主観性そしてイデオロギーについて、このことが提起する問題の多さを考えてみればよい。そして、そうした問題に満足な答えをもたらすのは我々には不可能に思われる)。
この公理的アプローチを取ることにより、インプロヴィゼーションは自らの考え、決定、概念により我々が寄与できる領域になる。こうしてそれは、インプロヴィゼーションの場を限定し焦点を当てる、その特異な様相の一つを特定する、その効果を検証する、そして様々なメソッドを発明する、等々を可能にする領域となる。
「インプロヴィゼーション」と言うとき、我々は単に特異な音や出来事の産出だけでなく、社会的な空間のそれについても触れているのである。我々はこれを戦略的なタームであると同時に概念的なツールとして援用する。したがって、インプロヴィゼーションは実験音楽の創造にも、平凡な日常の実践についても関係し得る。しかし、それはどんな領域に適用されても、なにがしか不安定なかたちを引き起こすはずである。インプロヴィゼーションが機能するとき、それが持つ定義し難いものは、あらゆる固定化と商品化を回避させようとするに違いない。少なくともそれが効力を持つ間は。
目指すべきは、世界とインプロとの関係について練り上げた推論を、展開しつつあるいかなる言説にも適用し、常に、そして世界の外側でさらによい良くこれを理解することだろう。そもそも「世界」はここでは適切な語ではなく、おそらく、「それがそうではないもの〔ce que cela n’est pas〕」と言った方がベターだろう。
アートの文脈において現実と非‐再現的な関係を持つことは可能だろうか? 場所・空間としてのホールの全ての特徴を考慮に入れることにより確かにそれは可能になるだろう。また、ホールを最大限に活用しようとし、以前の習慣や振る舞いを断ち切り、新しく変えなければならないだろう。
言い換えれば、人は標準化のプロセスに対抗しようと努力すべきである。
我々は即興演奏(インプロヴィゼーション)とは、ホールで起きるすべてへの考慮が要請される実践であることを期待する。それは、他の場所で、のちに使えるような、新しいなにかの創造であるのみならず、社会的関係を変化させることにより瞬間の強度を高める一つの方法である。
即興演奏は、ラディカルで、個人的かつ内在的な自己批判であるのと同様に、「その場限り〔l’in situ〕」という極端な形もとりうるが、それは、将来の状況のためにあるポジションを守ったり、作り上げる必要がないからである。このようにインプロヴィゼーションは自己解体の方を向いていると言える。
こうして、インプロヴィゼーションを外を持たない純粋な媒体〔médialité〕、あらゆる形の分離化、断片化あるいは個体性に対立する、限界も目的もない純粋な手段とみることができる。しかし、そう言うだけでは充分ではない! いつ、この空間のより良い活用は達成されるのか? それは、何か重要なことが起きようとしているという印象を与えるのに充分なほど、濃密な雰囲気を発生させることに成功したときである。この体験を記述する既定のカテゴリーや語彙は存在せず、ここでまさに賭けられていることを記述するのは常に困難である。
しかしながら、この奇妙さは、それを同化する、あるいは即座に理解することの困難さゆえ、標準化のプロセスに対立する。充分に濃密な雰囲気が生みだされると、その場に巻き込まれた人々は、自己の社会的地位と標準化された振る舞いをしばしば痛切に体験することになる。その雰囲気の密度はある閾に達すると、我々の知覚を妨げ、からだに馴染みのない感覚を生むほどの身体的なものにさえなり得る。ニュートラルな見かけの中のある混乱により、どこに自分がいるのかは本当にはわからぬまま、人は不思議な場所にいる感覚を最終的に持つ。ひとつひとつの動き、ひとつひとつの語が意味を持つようになる。そのとき生まれるのは、空間あるいは時間の統一された感覚ではなく、それぞれの位置が様々な空間及び様々な時間性を含むようなヘテロトピア〔訳註1〕である。空間について、以前のヒエラルキーと従来の区分が露呈する。伝統的な演奏時間と注意の配分(音楽家を尊重する聴衆の振る舞い、など)は置き去りにされる。さらに事態を進めれば、これらのヒエラルキーは消失することさえあり得ようが、それは誤った平等の感覚を与えるためではなく、時間と空間に対する新しい社会的関係を生み出すためである。
訳註1 ヘテロトピア:現実の枠組みの中で、日常から断絶した異他なる場所。
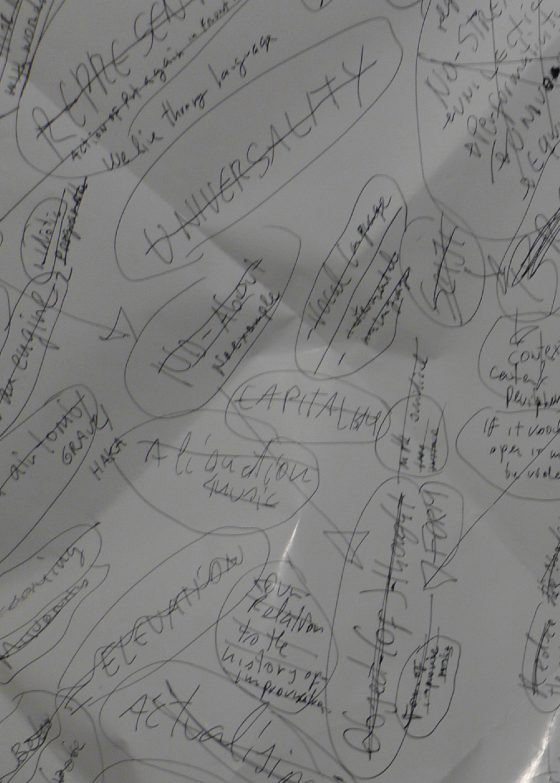
誤解のないようお願いしたい。我々が喚起しているのは「関係性の美学〔esthétique relationnelle〕」のいかなる変種でもない。関係性の美学においては、聴衆との対話性を少しでも注入すれば、胡散臭いイデオロギーを信奉している制度化されたアーティストがつくる退屈極まりない作品に、文化的余剰価値が付加される。我々はむしろ、ステージ上での演奏の限界を問い質したい。即興演奏の素材として、どの程度まで舞台芸術を定義するパラメータ(すなわち、聴衆、演奏家、ステージ、そして期待などの区分)を使うことができるのかを。このコンサートにおける期待の問題は、多くの人が一人の哲学者を見ることを待ち望んでいたゆえに重要である。即興音楽のコンサートで哲学者が何をするのだろう? スピーチを含む何かのはず……ところが、彼はその代わりにギターを弾いた、それも下手くそに! これらの期待により生まれたテンションが、どれほど我々に影響し、演奏のヴォルテージを上げたことか?
コンサートに先立つ会話中、我々が多く話したのは、出来うる限りそこにいようとすること、すなわち、パフォーマンスに没入する方法を見つけることであった。のちに判ったのだが、そうするためには、作業の枠組みをその境界あるいは限界まで押しやる必要がある。しばしば疑問なしに受け入れられるこれらの境界点には、実際、多くの問題、矛盾、そしてコンサートの状況を決定する条件が密かに含まれている。この境界点に我々がある仕方で振舞うように強いられ、どれほど影響されているかを見極めたいならば、非常に注意深くそれを扱わなければならない。我々は、コンサートホールが暑いのか寒いのかなど、だけではなく、書かれてはいないが我々を縛る惰性で従っている慣習のことも話しているのである。すなわち、異議を唱えることができるとはみなされぬルールのことである。即興演奏の実践において、まず第一に最も頻繁に見過ごされる単純な問いとは、いかにコンサートの社会的な文脈が我々の行動の範囲を枠付け限定しているか、である。
そのような限界を越えていくには何が必要か? それは、確立したルールを再現する実践の拒否、あるいは紋切り型の音楽制作を反復する実践の拒否である。そこには「実験音楽家」として認知されるためそうするのが当然とされ、不可欠なものとして受け入れられているルールの拒否も含まれる。
例えば、演奏者と観客間に適切な距離を決めるルールをとってみよう(これが演奏家と聴衆のあいだに能動的、受動的役割を割り当てることになる)。もし人が演奏中であるか、演奏の予定を入れたなら、彼には何か提案するか、提供することがあるということになる。しかし、その提案が、例えば演奏家が「聴衆になる〔être du public〕」というような内容であると、コンサートそのものを単に日々の平凡で「正常な〔normal〕」な状況に変えるというリスクが生じるだろう。とはいえ、コンサートの状況について最も興味深いことのひとつは、それが日常の空間とは際立って異なる社会空間を生む、あるいは提供する可能性を持っていることである。コンサートに行く人は影響を受けたい、感動したいと思っている。彼らは何かを受け取りたいのだ(あるいはたぶんそうでない?)。演奏家の「与える〔donner〕」、あるいは「与えない〔ne pas donner〕」という決定は、聴衆の「受け取る〔recevoir〕」、あるいは「受け取らない〔ne pas recevoir〕」という願望そして欲求不満との際限のないゲームを繰り広げる……
この聴衆の受動的役割を承認するのは非常に問題があるにせよ、このおかげで、演奏家は何か「例外的な〔extraordinaire〕」ことを行なう機会をも得られる。即ち、人々の習慣的、社会的なやりとりに対立する状況をつくることである。我々が目撃した、あるいは行なった最も興味深いコンサートは、聴衆と演奏家のポジションとそれぞれが承認されている役割(聴衆と演奏家が共にコンサートの状況のルールから受け継いだもの)が混じり合い、何か別物へと発展したものだった。これは聴衆がより責任の伴う能動的な役割を引き受けた結果であり、こうして彼らはどんなことでもなし得ると考えるようになったのである。
我々は「能動性〔activité〕」や「受動性〔passivité〕」のような用語の疑わしい性質を愛する。また、恩着せがましい態度をとるのはいかに容易であるかも我々は意識している。しかし、気がついたのは、誰もガツンとやらない、誰にも影響も及ぼさないようなコンサートは全てを現状維持のままにするだけで、人が能動的に関わることを生みだせないということなのだ。それでは何も起きなかったようなものである。他のコンサート(ニオール〔Niort〕はその一つ)は、後後まで我々の考察に糧を与えてくれるだろう。まさにそれは、コンサートの「良し〔bon〕悪し〔mauvais〕」をどんな音楽的意味においても判断するのが、どれだけ時間が経っても難しいからである。こうして、我々はこの二つの語のはざまで考えることに駆り立てられる。このコンテキストにおいて、良いコンサートとは、良い・悪い、成功・失敗という確定した二分法に従うかぎり、それについて下すどんな判断も理屈に合わないようなコンサートのことになる。こうしたケースでは、既成の判断基準は保留され、判断のもとになるパラメータの根拠の問い質しが余儀なくされる。これまでの基準と価値は崩れ去る。
これは単に判断の破棄、そして芸術的成功と失敗の区別を可能にする制約を清算するという問題に留まらない。「自由即興演奏〔l’improvisation libre〕」の理想に内在する挑戦を、コンサートの状況の性質こそ即興演奏において賭けられているという地点にまで強化するという問題でもあるのである。
音を反応的にやりとりする plink-plonk だけでは充分ではない。即興演奏におけるこの手の単純な反応のやりとりはすでに過去のものだ。我々が目指しているのは、まず、ほとんど無反応の仕方を、反応の仕方として探求することにより、「互いに反応すること〔réagir l’un à l’autre〕」が何を意味し得るかを問題とすることである。しかし、重要なのは「反応〔réaction〕」に「非‐反応〔non-réaction〕」を置き換えることではなく、いかなる種類の模倣(潜んだ、あるいは隠れた)も凌ぐような、反応あるいは非‐反応のモードを見つけ出すことである。ここで言う模倣とは、まさしく、それ自体が模倣として現われないような種類の模倣である。実際、これは音楽(作曲されていようと即興演奏されていようと)における反応〔réagir〕と呼ばれるものの本質に関係する。
我々ひとりひとりが、自分自身の手段をコンサートの状況に持ち込む。楽器、アイディア、持続、技能、知識……これら全てとの関係を忽ちにして断つことができると信じるのは、少なくとも非現実的だ。ここで、「お互いに反応すること〔réagir les uns aux autes〕」とは何を意味する? 我々が考えるところでは、それはあまりにも明白なやり方ではそうしない、ということに関わっている。また、これまで試みられなかったことを敢えて試みることにも。脆さを招く恐れがある何か、不安、他のミュージシャンに影響する緊張感。これらのものにより、誰もが最大の注意を払うようになることを期待しつつ。究極の目的は、それぞれの演奏者が個人的な時間感覚を自分のものにし得るような、相互作用の形態を達成することだろう。コンサートによっては時間の経過が極めて特異に経験されることがあるが、まさしくこのようなことがニオール〔Niort〕で起きたのだった。
COLUMNS
- heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティーについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁 - Columns
7月のジャズ- Jazz in July 2025


 DOMMUNE
DOMMUNE