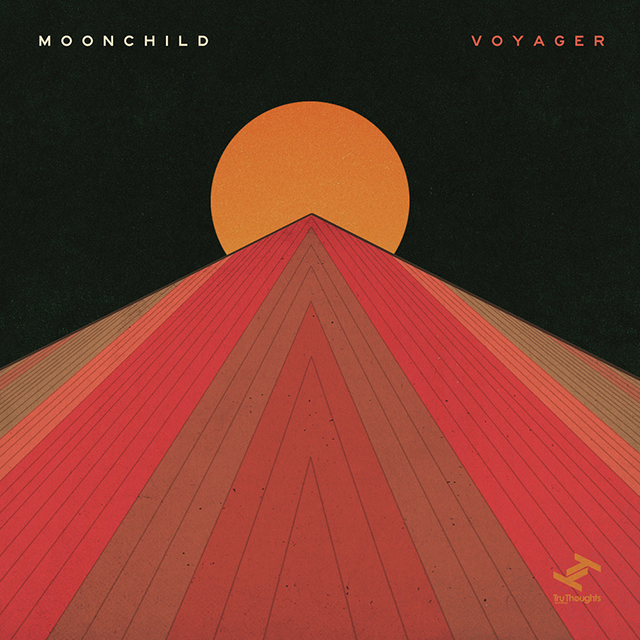MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Columns > スウィートなLAのソウル・トリオ、現代女性のリアルを描く- ──ムーンチャイルド最新作『Starfruit』の魅力
今回のコラボレーションによって世界への扉が開かれたという感じかな。一緒にやるのが夢っていうアーティストがまだたくさんいる。そういう扉が開かれた気がするね(アンドリス)〔*オフィシャル・インタヴューより。以下同〕
ムーンチャイルドの5作目となるアルバム『Starfruit』がリリースされる。
バンド結成10年目という節目に制作された今作は、〈新たな扉〉を開ける作品 であり、彼らの〈コミュニティ〉が生んだメモリアル・アルバムでもある。
南カリフォルニア大学ソーントン音楽学校のジャズ科に通っていたアンバー・ナヴラン、アンドリス・マットソン、マックス・ブリックの3人は、ホーン・セクションに属するツアーで時間を共にすることが多く、意気投合し楽曲制作をおこなうようになった。2011年にムーンチャイルドとして活動を開始し、ファースト・アルバム『Be Free』(2012年)を発表したのちに、〈Tru Thoughts〉から3枚のアルバム(『Rewind』(2015年)、『Voyager』(2017年)、『Little Ghost』(2019年))をリリース。国際的なツアーをおこないながら知名度を上げ、前作のUSツアーでは、演奏した各都市で地元のチャリティを推進する活動も展開し、バンドとしての影響力も増していたところだ。
ドラムとベース不在のこのバンドは、3人が管楽器をメインとしたマルチプレイヤーでソングライターであるのが特徴だ。各自が持ち寄ったビートを基盤に、ベースパートはシンセベースで担当し、キーボードとホーンによるハーモニーやヴォイシングは、大学のビッグバンドの授業で培ったテクニックをもとに複雑に練り込まれている。そこから感じられるのはひたすら心地良いフィーリングで、その音楽性が彼らの圧倒的な個性となっている。今作でも、曲作りのプロセスは変わっていない。
まずはそれぞれが個別に作るところから始めるから、ビートは常に選び放題の状態なのよ。各自1日1ビート、あるいは1日1曲というのを1ヶ月くらい続けて、そこから多くのアイデアが生まれた。でもその制作過程っていつもと変わらなくて、全員のアイデアを集めて、そのなかからやってみたいと思ったことをやるっていうのが私たちのやり方なの(アンバー)
前作では、アコースティック・ギターや、カリンバなどオーガニックな楽器も積極的に取り入れながら音色の領域を広げ、ミックス、プロデュースを含め、全工程を3人で完結できるまでにそれぞれがレベルアップしていた。思えばムーンチャイルドは、デビュー作を出してからは、フィーチャリングを一切おこなわないアルバム作りを続けていた。その結果ブレない3人の世界が形成されてきたわけだが、今作では一転、堰をきったように、豪華面々をゲストとして迎え入れている。
多数グラミー受賞経歴を持つベテラン、レイラ・ハサウェイや、現代のジャズ・シーンの面々と共演するアトランタ出身のヴォーカリスト、シャンテ・カン、ブッチャー・ブラウンの2021作でも大きくフィーチャーされていたシンガー、アレックス・アイズレー(アイズレー・ブラザーズのギタリスト、アーニー・アイズレーの娘)、そして、ラッパー陣も名うての面々が集う。LAの実力者、イル・カミーユ、BET(Black Entertainment Television)ヒップホップ・アワードで2020年のトップ・リリシストにも選ばれたラプソディー、さらに2020年にグラミー最優秀新人賞にノミネートされたニューオーリンズ・ベースのソウル/ヒップホップ・バンド、タンク・アンド・ザ・バンガスのヴォーカル、タリオナ “タンク” ボールや、マルチオクターヴの声域を持つボルチモア出身のラッパー/シンガー、ムームー・フレッシュといった多彩なキーウーマンが集結している。
近年フィメール・ラッパーを取り上げるメディアの動きがあり、女性の在り方を彼女たちの立場から紐解く視点がこれまでにないほど広がってきたが、その流れにも呼応するかのような圧巻の顔ぶれだ。これらのゲストを迎えた曲では、アンバーのパートと、ゲストによるリリックのパートがあり、〈もう一人の違う私〉が見えてくるようで興味深い。また言葉の中に、愛を綴りながらも確固とした自身のアイデンティティが見え隠れしていて、夢を持っている女性の心境、音楽への強い志、これまでに植えつけられた女性観など、各所に現代女性のリアルを感じさせる部分がある。
いつも私の夢を応援してくれてた 裏方みたいに でも呑まれそうになるのは慣れてる
──“Love I Need feat. Rapsody”
良い彼女になろうとはしたんだ でも知っての通り 私が愛してるのはこのマイクだけ それが人生で大事なこと
──“Don't Hurry Home feat. Mumu Fresh”
母には祈りを捧げて耐えろと言われた 女の心は神聖不可侵であり続けるべきだから
──“Need That feat. Ill Camille”
彼女たちがやっていることを聴いて、さらに自分も曲に取り組んで、この曲ではどうしようとかどう歌おうかと考えているのと同時に、他のシンガーが自分では絶対に思いつかないような、本当に素晴らしいことをするのを目の当たりにするっていう、その過程はすごく楽しかったし、自分の創造する上でのマインドが開かれたと思う(アンバー)
ゲストたちがテーブルに乗せていく多彩な表現がムーンチャイルドの新たな扉を開け、彼女たちに誘発されるように音楽的にもチャレンジングなプロセスが増えていった。
曲を各ゲストに送って、送り返してもらって、その人が曲をどういう方向に持っていったかによってさらに新たな要素やサウンドを加えたりという感じだった(アンバー)
“Get By” でタンクとアルバートがホーンのパートを歌ってるところなんかまさにそうだったよね。(中略)どの曲にも鳥肌が立つような瞬間があって、たとえば “I’ll Be Here” のブリッジのところでアンバーがやってることも好きだし、“Need That” のイル・カミーユも素晴らしくて、彼女がラップしている部分は元々の形から変化していて。変化した部分の作業はみんなが同じ空間に集まってやったもので、アルバム制作期間のなかでもレアな瞬間だった(アンドリス)
今作のコラボレーションの源となるのは、10年の間に築かれたムーンチャイルドのコミュニティだ。そしてそのベースとなったのが、DJジャジー・ジェフである。彼は音楽コミュニティ向上のために毎年100人近くのアーティストを自宅に呼ぶなど、コラボレーション促進のための活動に力を入れている。ジャジー・ジェフは、ツイッターを通じて彼らの音楽を発見し、その後ジェームス・ポイザーと共にリミックス(“Be Free”(2013年)、“The Truth”(2017年))を買って出るほど、活動初期から3人の支持者だった。
ジャジー・ジェフはコラボレーションについてすごく力強いメッセージをくれて、それは、音楽は関わる人が多ければ多いほどよくなるってこと。その言葉がすごく印象深かった。一般的に言えば、自分だけの力でやり遂げなきゃいけないプレッシャーってあると思うの。自分だけでもアルバムを作れることを証明しなきゃいけないとか、自分の芸術性を証明しなきゃいけないとか。でも実際歴史的に見ると最高の音楽は複数人で作ったものが多いっていう。それで私も、より多くのアイデアを取り入れたいと思うようになった(アンバー)
アンバーが語る通り、コラボレーションの話題は目白押しだ。現在進行中のアンバーのプロジェクトでは、〈Stones Throw〉レーベルの人気ビートメイカー/ピアニストのキーファーや、そのキーファーの公演で2019年に共に来日していたキーボード奏者、ジェイコブ・マンともアルバムを制作中のようだ。さらに今作でフィーチャーされているアルト奏者のジョシュ・ジョンソンは、ジェフ・パーカーの『Suite for Max Brown』やマカヤ・マクレイヴンの『Universal Beings』でも印象的な音色を与えるLAシーンの名脇役で、今後も彼らのコラボレーションは広がっていきそうだ。
そしてもうひとり、ムーンチャイルドの畑を耕したキーバーンが、スティーヴィー・ワンダーだ。デビュー時期に彼らの音楽を知ったスティーヴィーは、毎年恒例となっている自身のチャリティ・コンサート「House Full of Toys」のオープニング・ステージに彼らを抜擢した。2012年12月のこのステージで彼らが演奏した、エリカ・バドゥの “Time's a Wastin” は、LAシーンとR&Bシーンの両方にムーンチャイルドの音楽を発展させるための決定打となった。
コンサートの短い時間で彼が言ったことがすごく印象に残っていて、彼の言葉を要約すると、自分は音楽を色で捉えないんだと。僕らが白人のミュージシャンで黒人の音楽をやっていることについても、今やっていることをやり続けなさいって言ってすごく励ましてくれたんだよ(マックス)
このときに刻まれた志を胸に彼らはスキルアップを重ね、10年後のいま、ソウルやR&Bをルーツに持つ現代のメッセンジャーたちと共に、これからの扉を開く作品を生み出した。彼らはこの作品を、まさにコロナ禍で得た『Starfruit』と表現している。
この10年ムーンチャイルドを続けてきて、その間にバンドの周りに小さなコミュニティが築かれて、それはすごく嬉しいことだなと思っていて。それは長くバンドを続けてきてよかったと思う部分だね(マックス)
彼らが築き上げた境地を、“I'll Be Here” の歌詞から感じてみよう。その言葉は、聴く私たちの扉を開け、背中を押すものでもあるはずだから。
代わりにノックしてくれたり歩いてくれる人は誰もいない 代わりに傷ついたり働いたりしてくれる人は誰もいない 代わりに感じてくれたり癒されたりする人は誰もいない きっと自力で見つけることになる だけど私はここにいるから これまで何度も聞いてきたでしょ ここまで来たなら扉を開かなくちゃ
──“I'll Be Here”
Profile
 大塚広子/Hiroko Otsuka
大塚広子/Hiroko Otsukaアナログレコードにこだわった'60年代以降のブラックミュージックから現代ジャズまで繋ぐスタイルで、東京JAZZ、フジロック、ブルーノート・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパン他、日本中のパーティーに出演する一方、音楽ライターとして活動。老舗のジャズ喫茶やライブハウスPIT INNといった日本独自のジャズシーンや、国内外の新世代ミュージシャンとのコラボレーションを積極的に行い、インタビュー記事やライナーノーツ等の執筆、選曲監修の他、自身のレーベルKey of LIfe+を主宰。
COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE