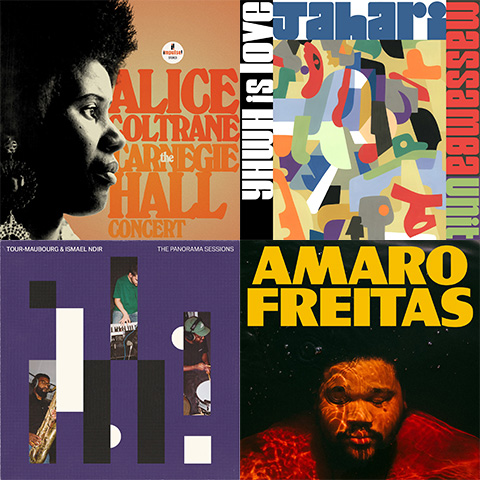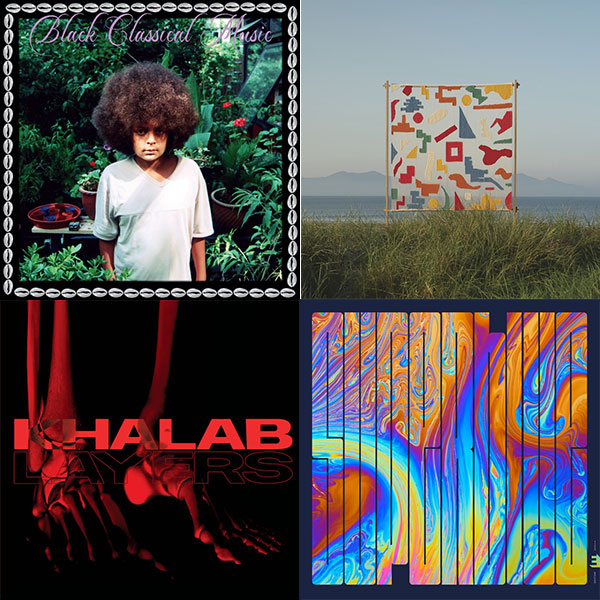MOST READ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- aus - Eau | アウス
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Columns > 1月のジャズ- Jazz in January 2025

Emile Londonien
Inwards
Naïve
本誌ムック本の2023年のジャズ・ベスト・アルバムにも挙げたエミール・ロンドニアン。フランスのストラスブールを拠点とするトリオで、マテュー・ドラゴ(ドラムス)、ミドヴァことニルス・ボイニー(ピアノ)、セオ・トリッチ(ベース)という構成。2021年頃から作品エリリースを始め、2023年のファースト・アルバム『Legacy』ではホーン・セクションやシンガーも配し、ロバート・グラスパー的なジャズとヒップホップを融合したスタイルから、よりエレクトロニックでブロークンビーツなどにも接近したスタイルを見せた。同じトリオ形式のゴーゴー・ペンギンなどに比べてさらにクラブ・ミュージック的なアプローチが強く、またヴォーカル作品などでは極めてソウルフルな要素が際立っていた。『Legacy』にも参加したサックス奏者のレオン・ファルも同系のジャズとクラブ・サウンドが融合したアルバム『Stress Killer』をリリースするなど、現在のサウス・ロンドンに呼応するかのようなシーンをフランスで形成している。
そして、この度『Legacy』に続くセカンド・アルバム『Inwards』がリリースされた。前作に続いてレオン・ファルのほか、ジョウィ・オミシル、ローラン・バルデンヌとフランス人サックス奏者がホーン・セクションを固めるほか、サウス・ロンドンからアシュリー・ヘンリーやシンガーのチェリス・アダムス・ヴァーネットもゲスト参加。アシュリーは昨年リリースしたアルバム『Who We Are』が同じレーベルなので、そうした関係もあって参加したのかもしれない。ブロークンビーツ調のダイナミックなジャズ・ファンクの “Catch The Light”、ダブの影響を感じさせる “Early Days” や “In Motion”、ドラムンベースのビートを取り入れたコズミックな “Inside”、ポエトリー・リーディングを配したディープな “Shades” など、前作以上にジャズとクラブ・ミュージックの融合が進んだ内容となっている。“Crossing Path” のようにホーン・セクションとエレピが絶妙のマッチングを見せるサウンドは、1970年代のハービー・ハンコックやロニー・リストン・スミスあたりのフュージョンを彷彿とさせるところもある。そして、アシュリー・ヘンリーが歌う “Another Galaxy” はR&B的な要素が強く、UKで比較するならジョー・アーモン・ジョーンズからブルー・ラブ・ビーツなどが思い浮かぶアルバムだ。

Ganavya
Daughter Of A Temple
Leiter
ガナーヴィヤ・ドライスワミーはニューヨーク生まれ、南インドのタミル・ナードゥ州育ちのシンガー/ダブル・ベース奏者/作曲家。祖母がインドのカナルティック音楽の大家で、幼少期から宗教儀式を通じて音楽を学び、即興演奏家、学者、ダンサー、マルチ・インストゥルメンタリストとしての教育も受けてきた。アメリカに戻って大学では演劇や心理学の学位も取得し、民族音楽からコンテンポラリー・パフォーマンスなど芸術を多角的に学んだ。キューバ人ピアニストの名手アルフレッド・ロドリゲスのアルバム『Tocororo』(2012年)に参加して名前を知られるようになり、2018年にファースト・ソロ・アルバム『Aikyam: One』をリリース。エスペランサ・スプルディングの『Songwrights Apothecary Lab』(2021年)では、南インド音楽の専門家としてヴォーカルなどに携わり、同作がグラミー賞に輝くことにも貢献した。また、演劇や映画に関わる音楽活動も多く、ピーター・セラーズ監督の映画『This Body Is So Impermanent…』(2021年)にサントラの作曲で参加している。
2023年にブラジル出身のギター/ベース奏者/作曲家のムニール・オッスンと共演作『Sister, Idea』を発表し、2024年春にはシャバカ・ハッチングスら南ロンドンのミュージシャンから、カルロス・ニーニョ、フローティング・ポインツまで参加した『Like The Sky I’ve Been To Quiet』を発表。より幅広いリスナーから注目を集めたガナーヴィヤが2024年末に発表したアルバムが『Daughter Of A Temple』である。ガナーヴィヤはヴォイス、ダブル・ベース、カリンバを担当し、エスペランサ・スポルディング、ヴィジェイ・アイヤー、シャバカ・ハッチングス、イマニュエル・ウィルキンス、ピーター・セラーズほか、音楽家やそうでない人も含め約30名の人たちが声、ダンス、写真などで参加する。なかには故人のウェイン・ショーターも含まれるが、生前の彼の声などをサンプリング素材で用いているようだ。アリス・コルトレーンの “Journey in Satchidananda”、“Ghana Nila”、“Om Supreme”、ジョン・コルトレーンの “A Love Supreme” を取り上げるなど、全編に渡ってアリス&ジョン・コルトレーンに対する敬意や愛情に包まれたアルバムである。シャバカ・ハッチングスをフィーチャーした “Prema Muditha” は、近年の彼が傾倒するアンビエントな世界が展開される。

Raffi Garabedian
The Crazy Dog
RG Music
ラフィ・ガラベディアンはアメリカ西海岸のベイアリアを拠点とするサックス奏者/作曲家。ホルヘ・ロッシー、ベン・ストリート、デイナ・スティーヴンス、ジョニー・タルボットなどと共演し、ベイアリアの集団即興演奏集団のインセクト・ライフやフリー・ジャズ・グループのスティックラーフォニックでも活動するほか、最近ではクロノス・カルテットのサン・ラー・トリビュート・アルバムにも参加していた。ラフィの祖先は1915年にオスマン帝国でおこなわれたアルメニア人虐殺の生存者の末裔で、彼の祖父母はアメリカへ難民として逃れ、苦難の生活を続けていったのだが、そうした民族の悲しい歴史はラフィの家族へも代々伝えられてきて、このたびリリースした通算3枚目のソロ・アルバム『The Crazy Dog』は祖国アルメニアや彼の家族の歴史を題材としたものとなっている。
トリオ編成のファースト・アルバム(2017年)、カルテット編成のセカンド・アルバム『Melodies In Silence』(2021年)に対し、『The Crazy Dog』はヴィブラフォン、クラリネット、トロンボーンなどを交えた7人編成の演奏で、より色彩豊かなアルバムになっている。特に重要な点は初めてヴォーカリストを加えた点で、2015年セロニアス・モンク国際ジャズ・ヴォーカル・コンペティションのセミファイナリストに選ばれたダニエル・ウェルツをフィーチャーしている。本作でのダニエルはジャズ・ヴォーカルというよりもヴォイスに近いもので、クラシックの声楽のような要素を感じさせる。ジャズにアルメニア民謡を取り入れたアーティストとしてはティグラン・ハマシアンが有名だが、音楽的に本作はことさらアルメニア的な要素を前面に出すのではなく、基本は西洋音楽としてのジャズの技法に則ったもの。ただ、変拍子のモーダルな “Escape To Erzurum” のメロディなどにはアルメニア民謡の影響も感じられ、ラフィの遺伝子のなかにあるものが顔を出す場面もある。この “Escape To Erzurum” はじめ、西洋音楽の技法である対位法をテーマとした “Contrapuntal Bewilderment”、ほとんどスキャットのみで綴る神秘的な “The American Question” など、ノーマ・ウィンストンやジェイ・クレイトンあたりを彷彿とさせるダニエル・ウェルツのヴォイス・パフォーマンスが印象的だ。

Rowan Oliver
Quickbeam
Soundweight
1990年代末から2000年代にかけて活動したゴールドフラップは、ポーティスヘッドの再来と評されたこともある男女ペアのエレクトロニック・ユニットだったが、そのゴールドフラップのサウンドを7年間に渡って支えたドラマーがローワン・オリヴァー。プロデューサーでマルチ・ミュージシャンでもある彼は、ゴールドフラップ以外にもプラッド、ポール・オーケンフォールド、スペーサー、アドゥン・トゥ・エックス、マーラ・カーライル、マリリン・マンソン、マックス・デ・ヴァルデナーらの作品に参加し、〈ソウル・ジャズ〉〈ミュート〉〈ワープ〉〈フリーレンジ〉〈プッシーフット〉といったレーベルで仕事をするなど、長年に渡ってUKの音楽シーンで活動してきている。そんなローワン・オリヴァーが初のソロ・アルバム『Quickbeam』をリリースした。
基本的にローワンが全ての楽器やプロダクションを担当しているが、一部楽器で兄弟のアーロやジェイコブが演奏し、ファンク・バンドのスピードメーターからサックス奏者のマット・マッケイも参加する。スリリングなストリングスを配した “Burning Boat” に代表されるように、1960年代から1970年代にかけてロータリー・コネクションやドロシー・アシュビーなどの作品プロデュースで活躍したリチャード・エヴァンスや、ヒップホップのサンプリング・ソースとして名高いデヴィッド・アクセルロッドなどの作品群を彷彿とさせる。基本的にはドラマーなので、“Wheeling”“Road Of Dreams” のように、ビート感覚に優れたドラムが軸となるジャズ・ファンク、ジャズ・ロック系の作品が中心となるわけだが、“Onwards & Upwards” におけるダークでミステリアスな感覚はトリップホップやダウンテンポなどを通過してきたUKのミュージシャンらしいと言える。
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
COLUMNS
- Columns
Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記
Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns
2025年のFINALBY( ) - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns
Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns
なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記
Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns
Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns
Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns
英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns
9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記
8月28日 岸部四郎 - Columns
8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち
第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁


 DOMMUNE
DOMMUNE