MOST READ
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- KEIHIN - Chaos and Order
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- Autechre - Move Of Ten
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
Home > Interviews > interview with Isao Tomita - 音に色を塗る
戦時中ですから、西洋音楽は聴くのも演奏も禁止、ラジオから聞こえてくるのは、軍歌、国民歌謡、文部省唱歌だけなんです。ジャズもシャンソンも、ラテンも、西洋音楽はすべて禁止されていたんです。
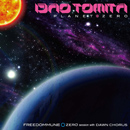 冨田勲 PLANETS ZERO ~Freedommune<zero> session with Dawn Chorus 日本コロムビア |
■冨田さんご自身がモーグ・シンセサイザーを取り寄せたのが......?
冨田:1972年です。
■それで1年4ヶ月かけて研究された。
冨田:自宅というよりも自分の工房ですよね。
■当時、おいくらしたんですか?
冨田:1千万ですね。
■うぉぉぉぉ!
冨田:いや、1千万だけれども、僕が個人で道楽で入れたわけではないんです。ひとつのプロダクションを作りまして、それで輸入したんです。だから町工場で営業用の印刷機や洗濯機に1千万円を投じると言ったら、それほどたいした金額ではないでしょ。だって、それで稼ぐつもりでいたわけですから。
■はははは。ちなみにどうやってモーグ社と連絡を取って購入したんですか?
冨田:それはもう、連絡の取りようがなかったですね。
■いまみたいにインターネットがあるわけじゃないですからね。
冨田:ですから、個人的に、モーグ・シンセサイザーを作っている工場を知っているという人を介して、その人の紹介状をもってモーグさんを訪ねていったんです。
■アメリカまで行かれたわけですね。
冨田:いまのような格安の航空券などないし、しかも1ドルが360円の時代ですから、それはもう高い渡航費ですよ。JALの普通のクラスの座席で40万円しましたから。それでバッファローの工場に尋ねて行ったんですが、田舎の野原のなかのお粗末な平屋の工場で、以前は屠殺場だったとか。とても世界の最先端を行く電子楽器をここで作っているとは思えませんでした。入り口には受け付け窓口もなく、いきなりモーグさんが奥からぬっと顔を出しました。まさに「暗闇から牛」です。
■連絡はどうやって取ったんですか?
冨田:テレックスですね。打ってくれる人がいましてね、それでやりとりしていたんです。それでね、シンセサイザーを買ったものの、税関がどうしてもこれは楽器に見えないと(笑)。
■はははは、見たことないですもんね。
冨田:それでとにかく通関が通らなくて、手こずりました。1ヶ月ぐらいかかりましたね。どうしても楽器じゃないと言うんですよ。そうこうしている羽田の倉庫が狭いというんで、千葉県のJALの倉庫に入れられちゃったんですよね。それで1ヶ月後に通関税を払うべくモーグを取りにいったら、1ヵ月の倉庫の保管料を払えって言うんですよ。
■はははは、シンセサイザー、1台を取り寄せるのがどれほど困難だったかという(笑)。
冨田:そうですね(笑)。それと、僕もその時点ではよく把握していなくて、それがどういうものなのか理解するのに苦労しましたね。電源スイッチを入れても音が出ないんですから。出るには出ても意図した音は出ないんです。オシレーターから発信音むき出しの音で、音程も合ってないんですから。ようやく意図する音色が出せるようになっても、次は音程を合わせなければならない。
■初期の、組み立て式のコンピュータみたいなものですか?
冨田:コンピュータまでいかない。たんなる音出し機ですね。
■なるほど。さきほど音を創ることに惹かれたと言いましたけど。
冨田:そこなんです!
■最初はワルター・カーロスの『スイッチト・オン・バッハ』を通してシンセサイザーと出会われたという話ですが。
冨田:そうです。大阪万博の1970年にその存在を知りました。現物はみていませんがそういうものがあるということを知ったわけです。
■それで、いまおっしゃったように、ご自身で輸入して、時間をかけていろいろ研究されたと。実際に手に取ってみて、あらたにお気づきになった魅力などありましたか?
冨田:それはもう、従来の楽器の枠におさまらない音が出るということです。組み合わせによっては従来の楽器の音に似た音も出せますが、僕が興味を持ったのは、従来のオーケストラの楽器のなかにはない音が自分の技術によって出すことができるということでした。
■エレクトロニックな音質というか、電気的な音への魅力はなかったですか?
冨田:そんなもの、何も魅力を感じてなかったでしたよ。
■ハハハハ(笑)。
冨田:電気的な音とは何を言うのか(笑)。たとえば電話の受話器を上げると「ツー」っと発信音が鳴りますけど、あれは電気の発信音ですけど、あの無機質にはぜんぜん興味はないです。そうではなくて、自分のイメージした音を出すということなんです。そもそも電気とは自然のエネルギーですからね。風が吹けば風車がまわり、水が流れれば水車がまわるように、電気の流れたがっている自然の習性をうまく利用して仕組んだのが電子楽器で、その習性を人間が捻じ曲げたら回路は働かないんですね。だいたい電気的な音とはどういう音ですか?
■我々はそれをエレクトロニックな響きとか、ブリープ音などと言ってしまうのですが、電子機材で生成される無機質な音色、電子機材を介して生まれる信号音めいた響きと言いますか。そういう音が、乱暴な言い方をすれば僕のようなリスナーにとっては使い方次第ですが、バイオリンやクラリネットの音と等価でもあるんです。
冨田:道路に並んだ照明がありますよね。昔は日本橋の照明なんかもものすごく彫刻に手の込んだ照明がありました。ところがいま高速道路を走ると、先端がひゅいともやしのように曲がっているだけの照明がずらーっと遠方まで並んでいるんですね。まるで印刷されたようにね。あれはあれでね......、つまりシンセサイザーの電気的な音はあれのことだと思うんですよ。出しやすいんです。同じ波形が続いている。オシレーターにうつしても動いていないんですね。同じ波形が続くんです。バイオリンでもフルートでも、かならず揺らぎますからね。似た波形でも、同じ波形は出てこないんです。電気的な音とはその波形が同じことなんじゃないでしょうか。
■たしかに、おっしゃる通りです。
冨田:電話の受話器の「ツー」っという音に揺らぎはないですから。同じ波形が続くだけですからね。初期の電子楽器はそういう音を出しやすいんです。簡単にコンデンサーとコイルでもって発信させればそういう音になりますからね。それは安易で、出しやすい音なんです。しかし、たしかに意図的にそれを使っている人もいますよね。
■まさにそのことなんです。クラフトワークですね。
冨田:そう、あのドイツのね。あれはあれで、僕は面白いと思うんですね。あれは、まさにシンセサイザーの無機質な音を逆手に使っているんです。
■そうですね。
冨田:それから最近では音響で、48k(Hz)よりも96k(Hz)のサンプリングとか、192k(Hz)とか、それは細かければ細かいほどいい音になるといわれています。だけども、トレヴァー・ホーンがアート・オブ・ノイズをやったときには、逆にそのクオリティを悪くした音を使って面白いアルバムを作りましたよね。
■すいません、冨田さんの口からアート・オブ・ノイズという名前が出てくるとは思いませんでした(笑)。
冨田:あれはあれで面白いですよ。たしかに自然音を録音した場合は、48kと96kでは差があると思うんです。気配も違う。自然音はハイサンプリングのほうがより自然に近く聴こえます。でも、モーグ・シンセサイザーの場合は、スピーカーやヘッドフォンによらない生音がないので比較のしようがない。モーグさんは40年前にはそのようなハイサンプリングで聴かれるとは考えていなかったので、せいぜい48kぐらいまででそれ以上の高聴波は想定していない。実はそこの部分に予期せぬノイズが潜んでいて編集機に悪さをし苦労をしました。生音とは比較することのできない、シンセサイザーでの場合は48kまでで充分だと思っています。『Planets(惑星)』は96kでやってしまいました。労力の無駄でした。
トレヴァー・ホーンは人間の声をあえて低周波数でサンプリングしましたよね。まるで初期のサンプラーみたいな使い方をしたんです。それが面白かった。サンプリング周波数の高低は音響技術者のなかでの話しで、アートはサンプリングの周波数の高低のなかには潜んでいないんですよね。
■おっしゃる通りだと思います。
冨田:礼拝堂のタイル職人が作ったタイルの絵がありますね。あれは素子が荒いですね。イエスだろうがアラーだろうが、素子が荒いんです。それが細かければありがたみが上がるわけではないんですね。シンセサイザーにも、それと似たところがあるんです。そこはたしかに現実音とは違います。それを電気的と言うのか、人工的と言うのか(笑)。そういう意味では面白いジャンルです。とくに若い人たちには面白い題材ではないでしょうか。初期のモーグ・シンセサイザーのあの面倒くさい操作にも挑戦してもらってね。
■ハハハハ。
冨田:というのも、最近のシンセサーザーは操作がすごく簡単になってますでしょ。あまりにも簡単過ぎるんですよね。したがってだんだんひとりひとりの個性がなくなってきていますね。僕の音とYMOの音では表現しているものがぜんぜん違います。僕がモーグ・シンセサイザーを使うのと松武(秀樹)君が使うのとではぜんぜん違うんです。また喜多郎さんも違う。
■音が均一化されているのはたしかにそうだと思います。それだけ広く普及したってことでもあると思うんですけど。
冨田:それが残念なんです。
取材:野田 努(2011年11月17日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE