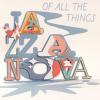MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Jazzanova - ベルリンからの温かいソウル ──ジャザノヴァ、インタヴュー
ビットとバイトからなる世界に生きている
一緒になれるのはネットの世界だけ
"アイ・ヒューマン"
ジャザノヴァとは、温かきジャズやソウル、そして最新のエレクトロニックの激突だった。たとえば、ジャズなど生楽器によるヴィンテージな音楽、ドラムンベースのような打ち込みによるクラブ・ミュージックを並行して聴いてきた僕にとって、ある時期までそうしたふたつのジャンルは別モノとして接していたが、1997年に登場したジャザノヴァは、生音を好む耳とクラブの耳との交流をうながした。
ジャザノヴァは、もともとはサンプリング主体の音楽だったけれど、たしかにそこには最初からライヴ感と臨場感があった。15年も前にリリースされたデビュー曲「Jazzanova EP」は、生とエレクトロニックの混合、ヴェンテージと最先端を組み合わせがある。ドイツらしくバウハウス調のデザインにパッケージされたそれは、クラブ・ジャズの新境地を切り開いた名盤として知られている。
彼らの初期の影響はアメリカのヒップホップ(ATCQやジャングル・ブラザース)だが──そこがベルリンのテクノ一派とは違っている──、彼らにはセンスがあり、なによりも勤勉さと緻密さとテクニックがあった。やがて、ジャザノヴァはヨーロッパのジャズとマスターズ・アット・ワークやデトロイト・テクノをミキシングした。彼らのレーベル〈コンポスト〉はジャズ・ハウスの引率者となり、他方で彼らは、そして、いわゆるnu jazzの走りともなった(そしてもうひとつの彼らのレーベル〈ソナー・コレクティヴ〉は、その後、新しいヨーロッパ・ハウスの潮流を生んでいる)。
 Jazzanova Funkhaus Studio Sessions Sonar Kollektiv/Pヴァイン |
ベルリンを拠点とするジャザノヴァは、ステファン・ライゼリング、アクセル・ライネマー、ロスコ・クレッチマンのプロデューサー・チーム、そしてユルゲン・フォン・ノブラウシュ、アレクサンダー・バーク、 クラアス・ブリーラーのDJチームからなる。ベルリンにおけるクラブ・ジャズの最重要拠点である。
2002年にリリースされたファースト・アルバム『イン・ビトゥイーン』では、うまさや熱狂だけではなく、彼ら自身の深いエモーショナルな側面も強調しているが、2008年に由緒ある〈ヴァーヴ〉からリリースされた『オブ・オール・シングス』では、アジムス、ドゥウェレ、ホセ・ジェームス、ベン・ウェストビーチなどなど豪華なゲストを招き、それまで以上に生演奏の比重を増やし、よりダイナミックで華麗なサウンドを確立している。ちなみに『オブ・オール・シングス』のクローザー・トラックが、大人に成長することを拒む少年の気持ちを歌っているモリッシーの"ダイアル・ア・クリシェ"(1988)カヴァーだったことは実に興味深い。
そして、先月リリースされた4年ぶりのサード・アルバム、『ファンクハウス・スタジオ・セッションズ』で、ジャザノヴァはまったくの生バンドとなった。デジタル化する世界とは逆行するように、彼らはビットとバイトの世界よりもアナログを選び、サンプリングよりも生演奏に徹し、ジャザノヴァ流のバンド・サウンドの完成へと向かった。アルバムにおける唯一の書き下ろし曲"アイ・ヒューマン"がそうなったことの本心を明かしている。
いずれにせよ、美しい歌、心躍る演奏、それらヒューマンな行為のなかの陶酔する甘美な時間......我々がなぜソウル・ミュージックを必要とするのか、その理由がここにはある。
ジャザノヴァをステファン・ライゼリングとともにオーガナイズしている中心人物のアクセル・ライネマーに話を訊いた。
バックステージでも空港でもemailをチェックしたり、Facebookのコメントをチェックしたりと、これも僕たちの生活の一部になっている。まあ、当たり前なことだと思う。でも隣に座っている人とSkypeで会話をするのではなく、向い合って心のこもった会話をすることは大切なことなんだ。
■まずはアルバム完成おめでとうございます。とても人間味あふれる素晴らしい内容で、いつまでも色褪せないアルバムだと感じました。まず、今回のこのバンド・プロジェクトを試みることになった経緯を教えて下さい。
アクセル:このバンド・プロジェクトのきっかけは2009年にロンドンで開かれたジャイルス・ピーターソンのワールドワイド・アワードだった。ジャザノヴァは今年で結成15年になるんだけど、前作の『オブ・オール・ザ・シングス』では、いままでのプログラミングとサンプリング主体とは違って、ミュージシャンをたくさん使って制作した。だからジャザノヴァのDJは世界中でプレイするたびに各地で「なんでバンドを連れてこないの? DJだけなの?」と質問され続けてきた。だから僕とステファンは「すべてサンプリングで制作された自分たちのエレクトロニック・ミュージックをどうやってステージ上で再現しようか」と話し合ってきた。
最初はやり方がわからなかったけど、『オブ・オール・ザ・シングス』はドラムスだけがプログラミングされたものだったから、もしかしたらいまならバンドで再現することができるかもしれないと思って、そこで以前から一緒に仕事をしてきたミュージシャンを招いた。ミカトーンのポール・クレバーはいつも僕たちの楽曲でベースを弾いてくれていたし、セバスチャン・シュトゥッドゥニツキーは音楽的なディレクターとして楽曲の別アレンジを作る際に協力してくれた。前のアルアバムではオーケストラやストリングス隊など多くのミュージシャンと制作していたから、一緒にステージで演奏するのは難しいと思っていた。でも、セバスチャンが別のアレンジを作ってくれたので9人編成で演奏することができるようになった。
■打ち込み、ダンス・ミュージックに飽きてしまったんでしょうか?
アクセル:飽きたってことはないね。ライヴだってダンス・ミュージックだろう。"フェディムズ・フライト"のようなクラシックから"アイ・ヒューマン"のような最新曲まで演奏するよ。充分にダンサブルな曲だし、パーティ用のセットでもあるからね。クララ・ヒルやラ・ルーの作品をプロデュースしたり、たくさんレコーディングしてきたんで、スタジオでの作業もどんどん良くなっていって、その制作過程を自分たちの楽曲にも活用できると思った。だからステファンはもっと作曲にフォーカスするようになってきたんだ。それでもプログラミングでの制作に飽きたわけじゃないよ。いまでもビートはクレイジーな感じにプログラムしているしね。
■これまでの制作との違いはなんでしょう? こだわりの部分や、苦労したこと、予想もできないハプニングなどがあったら教えて下さい。
アクセル:もっとも変わったことといえばフル・バンドとともにスタジオに3日間入ってレコーディングしたことだね。いままでのジャザノヴァの制作ではホーン隊で1日、次の日にストリングスをレコーディングしたりと、すべてレイヤーになっていて、録音も分けてやっていた。
だけど今回はフル・バンドで一緒にスタジオに入ってレコーディングしたんだ。これは本当に新しいことだったね。しかもかなり上手くいったよ。一緒にツアーをしてきたバンドだから楽曲も知っていたし、演奏も熟知してたからね。このスタジオ・セッション・アルバムはジャザノヴァのスタジオで制作された楽曲とライヴ・ショーとの架け橋だと思っている。ライヴについて言えば、つねにステージの上でジャザノヴァのスペシャルなサウンドが出せるわけでないけどね。ときには20分しか準備時間がないときなんかもあって、9人のバンドでみな違うセッティングだと正しい音が出せないこともある。だけどこのレコーディング・セッションではヴィンテージなマイクをたくさん持ち込んでレコーディングして、自分でミックスをした。だからサウンドがスタジオでのプロダクションとライヴ・バンドの中間なんだ。
■前作から4年間ブランクがありましたね。たとえば、その間、アレクサンダー・バークはクリスチアン・プロマーとのコンビで〈Derwin Recordings〉から積極的に作品をリリースしていましたよね。」他のアーティストは、どのような活動を続けていたのですか?
アクセル:ステファンと僕はバンドと一緒にずっとツアーに付きっきりだった。新しいアルバムはすぐリリースできると思っていたんだけど、ツアーや準備に思った以上に時間がかかってしまった。新しい体験だったからね。でもすごく楽しいことだったよ。それから他のミュージシャンのスタジオ作業やプロデュースでも忙しかった。たとえば〈P-VINE〉からリリースしたフィン・シルヴァーも僕のプロデュースだし。フィン・シルヴァーとはレコーディング、ミックス、ツアーとたくさんの仕事をしてきた。この4年間はこんな感じだったよ。
■各個人が有名なって、なかなか一緒に制作をする時間がないと思いますけど、どのようにやり取りし、制作を進めたのですか? また、衰えることのない制作意欲の源はなんでしょう?
アクセル:ジャザノヴァのメンバー全員がレコーディングに参加したわけではないんだ。オリジナルのメンバーは僕とステファンだけだった。このふたりですべてのプロジェクトをオーガナイズしている。ライヴ・バンドはジャザノヴァのオリジナルのメンバーとはまったく違ってライヴのために結成した新しいものだよ。DJたちは世界中をツアーしたり、コンピレーションを作ったり、自分たちのレーベル、〈ソナー・コレクティヴ〉のことに集中したりとみんな忙しいから、少し休んでからまた制作を再開したんだ。
取材:渡利一典(2012年6月12日)
Profile
 渡利一典/kazunori Watari
渡利一典/kazunori Watari1974年長野県出身。学生時代から現在まで、かれこれ15年程渋谷のレコード・ショップ「テクニーク」にてバイヤーを担当中。
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE