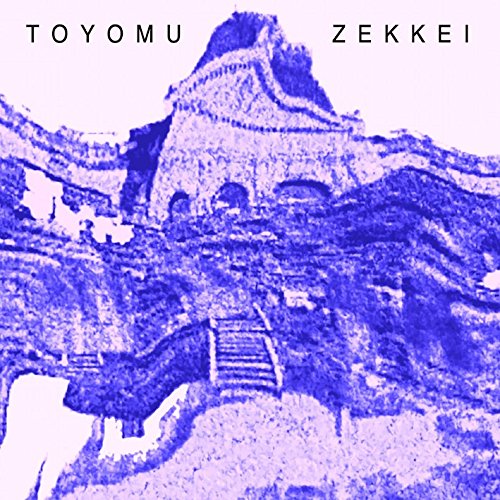MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with TOYOMU - どんなにがんばってもシリアスになれない
まいったね、トヨムは罪深いまでに楽天的だ。荒んでいくこの世界で、シリアスな作品がうまくいかない自分に葛藤していたようでもあった。しかし、人生を「面白がる」ことはとうぜん必要なこと。いや、むしろ面白がる、楽しむことが土台にあるべきだろう。ストゥージズだって「no fun(面白くねえ)」といって面白がったわけだし、泣くのはそのあとだ。
トヨムの名が知れたのは、2016年のカニエ・ウェストの一種のパロディ作品によってだった。『ザ・ライフ・オブ・パブロ』をおのれの妄想で作り上げたその作品『印象III:なんとなく、パブロ』がbandcampでリリースされると、欧米の複数の有力メディアから大きなリアクションが起きた。それまで知るひとぞ知る存在だったトヨムは、一夜にして有名人になった。
それから彼は、日本のトラフィック・レーベルからミニ・アルバム「ZEKKEI」を出したが、それはパロディ作品ではなく、牧歌的なエレクトロニック・ミュージックだった。そんな経緯もあって、いったいトヨムのアルバムはどうなるのかと思っていたら、ユーモアとエレクトロ・ポップの作品になった。〈ミュート〉レーベルの創始者、ダニエル・ミラーの初期作品を彷彿させる茶目っ気、LAビートの巨匠デイダラスゆずりのエレガンス、それらに加えてレイハラカミを彷彿させる叙情性も残しながらの、チャーミングなアルバムだ。“MABOROSHI”という曲は、トーフビーツの新作に収録された“NEWTOWN”、あるいはパソコン音楽クラブの“OLDNEWTOWN”なんかと並んで、2018年の日本のエレクトロ・ポップにおいてベストな楽曲のひとつだと思う。
取材は、10月上旬、広尾のカフェでおこなわれた。通りに面したオープンエアのテーブルには、心地良い秋風が入って来る。この時期の黄昏時は、あっという間に夜を迎えるわけだが、江戸川乱歩が幻視した都会の宵のなかに紛れる怪しいものたちの気配を感じながら、インタヴューは、ゆるふわギャングからサンダーキャットまで、節奏のない彼の好きな音楽の話からはじまって、気が付いたらお互いビールを数杯飲んでいた。
だんだんアートといってやっても自分自身がそこまで楽しくないなと思いはじめて。それだったらもうちょっと単純に明るくやろうと思いはじめました。だから自分としてはこのアルバムは明るいアルバムだなと思っています。
■今回のデビュー・アルバム『TOYOMU』は、自分ではどんなアルバムだと思いますか?
TOYOMU(以下T):ジャケに表れているように、自分ではすごくカラフルな作品になったと思っています。1曲1曲の単位が集まって、アルバムとして。ぱっと見がそういう感じではあるんですけど、いままで自分自身が、ビートと呼ばれるものをやろうと思ってやっていた時期とか、ラッパーに提供しようと思ってやっていたとか、もしくは”MABOROSHI”みたいにシングルを作ろうという感じで、作り方に対する考え方自体がだいぶシンプルな方向に、シンプルって言ったらおかしいな……、自分の感情として分かりやすい方にだんだん近づいていった。アルバムとしてできあがってみるとあんまり複雑なことや、自分ができないことはもうできないなということを割り切ってやったということもちょっとある。
■食品まつりさんのコメントとぼくのコメントは言葉は違うけど、だいたい同じような内容で、同じような印象を持ったのかなと思いました。ドリーミーで、ほっこりなアルバム。そう思われていることを自分ではどう思いますか?
T:人から見たときにドリーミーということは、きっとファンシーさが最後まで残り続けたんだろうなと思います。たぶん現実とひたすら向き合い続けたら、あのようなアルバムにはなっていなかったと思うんですよね。音楽という世界だけに関して言ったら、自分の世界のなかで考えて作ったので、その部分が要素として強いかな。それがたぶんドリーミーと言われる原因ではないかなと少し思います。
■自分自身ではそう思わない?
T:ぼくはみんなにわかりやすいように、お祭りみたいな感じ、カーニヴァルちっくな感じだと思っているんですよ。いや、サーカスとかそういうものも近いかな。渋い曲や、かっこいい曲がいちばんベストだと思って作っていたときと、どれだけ人と違うことをやるかみたいな部分で魅せようと思ってやっていたときがあって。人から見たときにそういうわけのわからないものって結構不気味にうつるとぼくは思うんですね。まったくわけのわからないものとか、あとは真剣に物事をやっている人とか。そういうのに対してはお客さんからすると、まじめな演劇を見ている感じ。大衆とか民衆の人たちが楽しみにきているというよりかは、高尚なものを見ている感じで接するような。
■アートを見ているような?
T:アートを見ているような、そっちの方を自分はかっこいいと思ってやりたいという感じでいままでは動いていたんですけど、だんだんアートといってやっても自分自身がそこまで楽しくないなと思いはじめて。それだったらもうちょっと単純に明るくやろうと思いはじめました。だから自分としてはこのアルバムは明るいアルバムだなと思っています。たぶんJ-POPとかになってくると思うんですけど、ただひたすら明るいということは、全く屈託がないというか。サーカスとかもそうですけど、ピエロとか大道芸の人とかも一応は明るくはふるまっているじゃないですか。でも、ずっとツアーじゃないですけど、各地を転々としてまわっているから疲れも出てくるし、ずっと笑顔ではいられないと思うんですね。でも、みんなに対して明るい顔をしようという気持ちで動けばある程度はみんながわーって拍手もしてくれるだろうし。いちばん近いのはサーカスのイメージという感じなんですよね。
■サーカスには影というものもあるんだけど、影や暗闇をこのアルバムには感じないです(笑)。
T:きっとぼく自身がサーカスに対してそう思っていないからということが大きいと思います。あとは、このアルバムを作るにあたって、何回か曲自体を捨てたりとかしたんですよ。作っては捨てみたいなことが繰り返しあって。だから自分のなかでは、もう作るのが嫌だなと思うくらいにまでたまになったりして。
■どういう自分のなかの葛藤があったの?
T:『ZEKKEI』を出した2年くらい前に遡るんですけど、それくらいからアルバムをいちおう作りだしてはいたんですよ。
■2年かかったんだね。
T:じっくりやっていてもそのときはアートみたいなものが頭のなかにあったので、人と違うかっこいいものを作るんだみたいな感じがすごく大きかったんですよね。
■そのときのかっこいいアートな音楽ってエレクトロニック・ミュージックで言うとたとえば何? OPNみたいな?
T:OPNとかアルカとかもそのときはよく聴いていた。あとは坂本教授の『async』。こういうのがかっこいいなみたいな感じで。いったら全部影があるじゃないですか。でも自分としてはそういうのもやるんですけど、そういうやり方でやっても、人に伝わるまでにならないんですよね。
■あるいはそれをやると、自分自身が自分に対してオネストになれていない?
T:オネストになれていないということと、それに偽っているみたいな感じも若干はあった。かっこいいだろというものを思い込みでやったけど、結果的に作り出したものを周りの人に聴かせても、とくにそれに対して何かコメントがあるということがまったくなかったんですよ。ということは、自分ではかっこいいと思って作っているけど、相手に伝わっていないみたいなことが出てきた。そこの伝わらなさみたいなものがすごく自分ではもどかしいというか、イライラするというか。自分ではかっこいいと思っているのに。そういうことが作りはじめてから長いこと続いたんですよ。
■じゃあ1枚分のアルバム以上の曲を作っては捨て、作っては捨て。
T:最近もボツ曲をもういちど聞いてみてた んですけど、ものすごい量があって。ちょっと工夫したら別の要素に使えるみたいなものがいっぱいまだあるんですけど。その状態自体が自分自体を陰鬱な気持ちにさせるというか。作れば作るほど、より悪くなっていくなみたいな。
■ぼくはOPNやアルカみたいな人たちを評価しているんだけど、これだけ音楽がタダ聴きされて、飲み放題みたいな世界になっていったときに、逆に飲み放題だと酔えないということだってありうるわけだよね。
T:ハードルが下がったのに別に聴く人が増えていないということ?
■そういう意味で言うと、トヨム君はもともと曲を無料ダウンロードで出していたわけじゃない? しかし、これはこれで作品として作りたいと思ったわけでしょ?
T:もちろん。ただ、自分の能力との差がどうしてもある。きっと誰だってそういうことはあると思うんです。自分はこうしたいけど、いくら気持ちを入れ替えようと思ってもできないとか。そのときは簡単な話、ちょっと切り替えて、自分はそれができないからできることをやろうみたいな感じでシフトすればすぐに道を切り替えられたと思うんです。いまになって思えば、自分とその周りの状況に甘えていたという感じがあるんですよ。自分にウソをついていたというか。
■OPNやアルカみたいな人はすごくシリアスじゃない? そのシリアスさを捨てたなという感じはするんだよね。
T:シリアスになりたかったけど、それをやろうと思ってもまったくできなかったんですよね。そんなフリをするということ自体がいまになって思えば間違っていた。自分に合っていなかった。そういうところのレベルで全然コントロールしきれていなかったというのが自分のなかであるんですよ。
■それでこういうジャケットにしたんだろうけど、何かきっかけがあったの?
T:結局いくらやってもできないということになったときに、音楽を辞めるかどうかくらいまで考えていたんですよ。別に音楽を作ることに辞めるとかないけど。あとはいろいろな人と会ったりして。自分はいまでも実家暮らしなんですけど、実家暮らしをしている人でもちゃんとやっている人はもちろんいますが、その生活レベルからして見直した方がいいんじゃないかと思って(笑)。京都でやっていたらどうしても周りがめちゃくちゃ競い合っているという状況では正直ないと思うんですよ。
■ゆるい?
T:もちろん京都でもしっかりやっている人はいるけど、自分と同じトラックメイカーやビートを作っている人で競い合っているような状況は東京のようにはない。京都は超田舎ではないけど、超都会でもないから。
■独特なところだからね。
T:居たら心地良いんですよね。自然もあるし、川もあるし。そこに居たら、自分では俺は他人とは違うんだと思っていても、どうしてもあらがえないだろうなというのは意識しないと。そこに気付いたのが一番大きかったですね。地方都市に住んでいてめちゃくちゃ頑張っている人もいっぱいいるし。
■自分が地方都市でやっているんだという意識はこの作品にはすごくあるの?
T:その反面インターネットがあるから、意識さえ、やる気さえチェンジできたら関係ないんだろうなというのは思うんですけど、そう口では言ってもできない方が絶対に多い。なんでこういうアルバムになったかというときも、実感として自分の人生がそう思ってきたということがけっこうある。
野田努(2018年10月22日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE