カナダでファーウェイのモン副社長が拘束された後、カナダ資本のショップが中国での開店時期を遅らせるなど両国の関係悪化が懸念されたりもしたけれど、ヴァンクーヴァーのラッパー、ベイビーノーマニー(BabyNoMoney)ことアレキサンダー・グムチアンはむしろ中国だけで大スターになっている。中国初の少年アイドル、TFボーイズのメンバーが彼の曲で踊っているヴィデオをソーシャル・メディアにアップしたらしく、一気に彼の名が知れ渡たったため、中国に行けば地元でもやったことがないような大きな会場でライヴをやるようになったのだという。流行りのサウンドクラウド・ラッパーとして知られるグムチアンの曲をTFボーイズがどうやって見つけたかは謎だけれど、おそらくはまだグムチアンがトラップをコピーしていた時期のものを材料に「ハーレム・シェイク」のマネでもしようと思っただけなのだろう。グムチアンがトラップにこだわっていた時期は2年ほどで、今年に入ってリリースされた『Recess』でも最後の1曲だけはトラップを引きずっているものの、すでに彼はそこから大きく飛躍してしまった。
音楽に出会ったのは背中を折ったことがきっかけだったというグムチアンはブローク・ボーイ・ギャングというクルーとして活動を開始し、すぐにもひとりになってしまったにもかかわらず、2016年が終わる頃にはとにかく曲を量産し、片端からサウンドクラウドにアップしまくったという。スーサイド・ボーイズやポウヤなどがインスピレーションだったというわりには明るい曲調が多く、実際、それは彼の信条でもあるらしく、『Recess(=凸)』でもリリックのほとんどは自分がいかに成功し、人々に感謝しているかということで占められている。そして、現在でも大学に在籍している彼は背中を折ったことで興味を持った運動学などを専攻しつつ、ラッパーらしくなくありたいという動機から大学の学位を持ったラッパーを目指しているという。そう、汚い言葉を多用し、典型的なマンブル・ラップにもにもかかわらずいわゆるマンブル・ラップにありがちなリリックから遠ざかることも意識的なら、そうした姿勢に導かれたのだろう、『Recess』というアルバムはサウンド的にもあまり聴いたことがない領域へと踏み込んだヒップホップ・アルバムとなった。ひと言でいえばワールド・ミュージックとヒップホップを不可分なものとして結びつけ、それはかつてネプチューンズが試みたポリリズムを飛び石的に受け継ぎ、躍動感を削ぎ落としたものといえる。USメインストリームよりもイキノックスやダブ・フィジックスといった最近のUKモードに近いビート感。実にリラックスしていて、ファティマ・アル・ケイディリとかウエイトレスの流れと結びついたら面白そうなんだけど。
ワールド・ミュージックと接点を持ったのはサウンドクラウドをたどっていくと、グレイヴス“Meta”にフィーチャーされた時が最初だったのかなあと思う。兆候などというものを探し始めると限りなく存在する参照点に振り回されるだけかもしれないけれど、次にピンときたのは昨年アップされていた“Who Dat Boi”。民族楽器に特有の高音がループされ、明らかに原型はここから始まっている。共にレントラ(Lentra)のプロデュースとなる“tony thot”や“Moves”などがこれに続き、それらとはやや趣向を変えた“Opus”がウェブ上では初のブレイクスルーになったとされている。つまり、この段階ではまだ方向性は厳密に定まっていなかったということで、“Opus”を含む「BB Steps」EPは実にヴァラエティ豊かな内容でもあった。しかし、ソー・ロキとの「Whatever」EPを挟んでリリースされた『Recess』は11曲中8曲でレントラとタッグを組み、完全にサウンド・イメージをひとつに固めている。こういう人は次でまったく違うことをやりそうなので、この先も楽しめるかは未知数だけれど、しばらくこの路線にこだわってくれないかなあと。



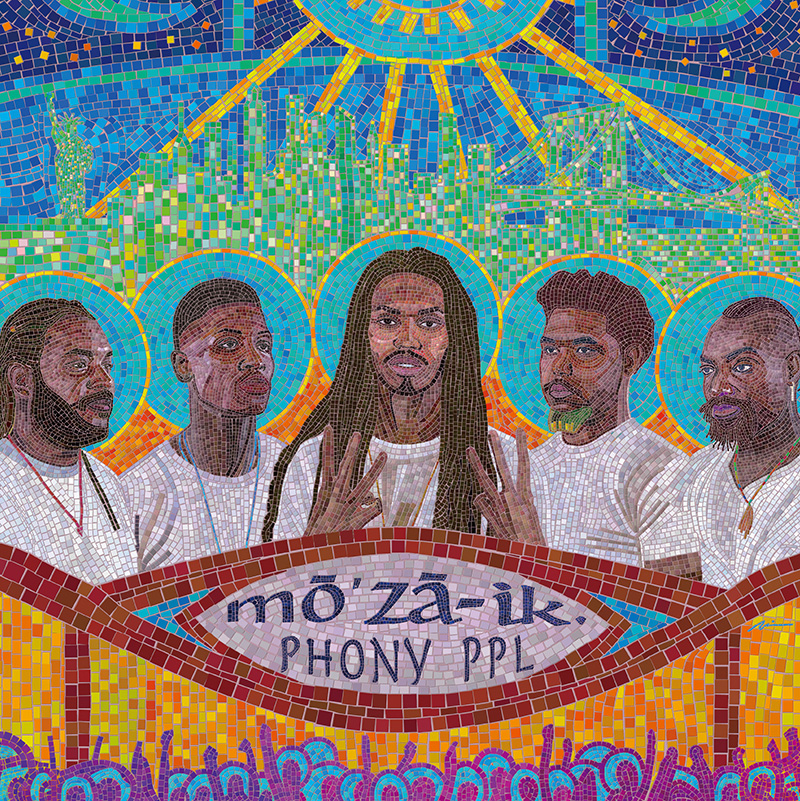
 label: On-U Sound / Beat Records
label: On-U Sound / Beat Records