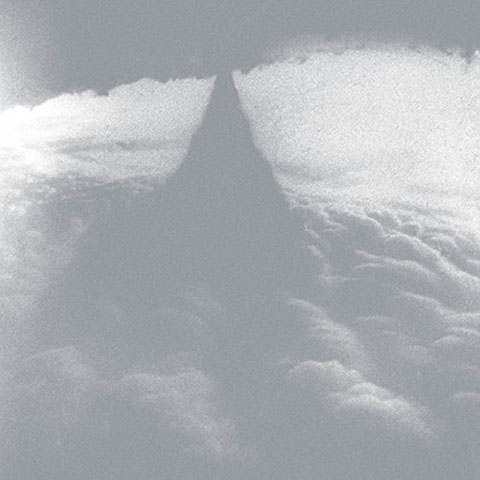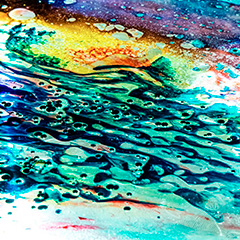MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Lawrence English - 新しい世紀のために
 Lawrence English Cruel Optimism Room40 |
昨年のニューエイジ・ブームが、その現実逃避性をもって2016年という年の混乱を象徴していたのだとすれば、それとはまた別の形で世界の歪みを映し出す音楽もある。ドローンがそれだ。シドニー、メルボルンに次ぐオーストラリア第3の都市・ブリスベンに暮らす音楽家ローレンス・イングリッシュは、ためらうことなく「音楽は政治的である」と言い切る。彼の最新作はシリアの情勢やブラック・ライヴズ・マター、あるいはブレグジットや大統領選挙などから刺戟された作品だそうで、なるほど、たしかに『Cruel Optimism』が響かせる漆黒の音の連なりは、今日の世界の不穏なムードを一身に引き受けているかのようだ。『残酷な楽観主義』というタイトルの訴求力も群を抜いている。
かつてわれわれは紙の『ele-king vol.7』で「ノイズ/ドローンのニューエイジ!」という特集を組んでいるが、ローレンス・イングリッシュが頭角を現してきたのもまさにそのような文脈においてである。ローレンス本人が自らの代表作と見做している2008年の『Kiri No Oto』はいまでも根強い人気を誇っているし、2014年にリリースされた『Wilderness Of Mirrors』はその年の『FACT』誌のベスト・アルバム50に選出されて話題となった。一昨年はデヴィッド・リンチの写真展覧会のサウンドトラックを手がけるなど、彼はすでに海の向こうにおいて大物の地位を築いていると言っていい。またそういった音楽制作と並行して彼は、自身の主宰する〈Room40〉からさまざまなアーティストの作品を世に送り出してもいる。ベン・フロスト、オーレン・アンバーチ、テイラー・デュプリー、ティム・ヘッカー、リュック・フェラーリ、グルーパー、デヴィッド・トゥープ……これらの固有名詞を並べるだけで、いかに彼が卓越したキュレイターであるかが見てとれよう。他方で〈Room40〉はツジコノリコやテニスコーツ、畠山地平といったアーティストの作品も数多くリリースしており、ローレンスとここ日本とのつながりはことのほか深い(ちなみに畠山地平は『ele-king vol.14』でローレンスにインタヴューをおこなっている)。
そんな彼のバックグラウンドをより深く掘り下げるべく、われわれはいくつかの質問をブリスベンへ向けて送信した。彼はそれらの問いに快く、丁寧に、真摯に答えてくれた。彼の鳴らす重厚なドローンはどのようにして生み出されたのか。なぜ彼は音楽が政治的であると考えているのか――。ローレンス・イングリッシュは、ひとりの人間が抱えるにはあまりにも大きすぎる希望を抱いている。その希望の片鱗を、あなた自身の目で確認してほしい。
私は、音と音楽の可能性はすべての人に届くと非常に強く信じています。要は、人びとがいかに良き文脈と機会を通じて、有意義に音楽とのつながりを持てるか、ということです。
■日本ではまだローレンス・イングリッシュという音楽家/キュレイターの存在を知らない方も多いと思いますので、まずは基本的なことから伺わせてください。あなたが〈Room40〉をスタートさせたのは2000年です。また、あなた自身の最初の作品『map51f9』が世に出たのは2001年です。1976年生まれとのことですが、それまではどのように過ごされていたのですか?
ローレンス・イングリッシュ(Lawrence English、以下LE):私はクイーンズランドのブリスベンで育ちました。さまざまな意味で、私の成長過程の話はブリスベンという都市の成長の話と重なります。70年代後期から80年代初期、クイーンズランドは政府からの退行的な圧力に苦しんでいました。その後、その傷跡から回復の兆しを見せるまで、およそ10年の月日がかかりました。1990年に私は初のファンジンと、のちに最初のレーベル、そして〈Room40〉へと至る、小さなカセット・レーベルを始めます。同時期にインダストリアル・バンドでも演奏をしていましたが、1997年には収束し、1998年からソロ・ワークとして本格的に実験的な試みを始めました。この時期はとてもおもしろい時期で、ステージのセッティング時期とも言えるでしょう。
■音楽をやっていこうと思うきっかけのようなものはあったのでしょうか?
LE:初めは音そのものに興味があり、その後音楽へと移行しました。子ども時代のあらゆる体験から音に興味を持ちましたが、やはり特にバードウォッチングからのものが大きいでしょう。ヨシキリという素晴らしい声を持つ、見つけにくい小さな鳥がいます。ある日、沼地に隠れるヨシキリを双眼鏡で探していたのですが、そのとき父が私に、目を閉じて鳥の声に耳を澄ますようにと言いました。耳で鳥の居場所を感知してから、その姿を探すようにと。結果、鳥を見つけることができました。私たちの耳が、この世界を知覚するツールとしてとても可能性に溢れている、ということに気づく体験でした。この頃から、音と音楽の世界が拓かれていくのを感じました。
■あなたの音楽的なルーツはどこにあるのでしょう? 音楽家として、もっとも影響を受けたアーティストを教えてください。
LE:音楽でないものから影響を受けることが多いです。いつも読書をして、自分の思考を可能な限り押し広げるようにしています。たとえば最近は、「緩やかに消失する未来(slow cancellation of the future)」という挑発的な主張を持つ、フランコ・ベラルディ(ビフォ)(註:アウトノミアの運動で知られるイタリアの思想家)の作品を読んでいます。彼は、進歩と資本主義の成長に根ざした20世紀の政治的な願望として想像する未来は、もはや有効ではないと主張しています。こういった挑発的な思考が、私の作品制作にとって最も重要だと考えています。もちろん私は音楽を愛していますが、音楽がいつも作品制作に直接的に影響するとは考えていません。
■〈Room40〉は、ツジコノリコやテニスコーツ、畠山地平やminamoなど、日本のアーティストの作品も多くリリースしています。あなたがプロデューサーを務めているアルバムもありますよね。ほかにもあなたは鈴木昭男とコラボしたり、最近では福岡のレーベル〈duenn〉のコンピレイションにも参加したりしていますが、日本の音楽に興味を持つきっかけとなるようなことがあったのでしょうか?
LE:オーストラリア人として、日本は最も近い近隣諸国のうちのひとつである、ということを強く感じます。東京までは9時間なので、比較的近いと言えます。私個人としては、日本には、鈴木昭男や灰野敬二、メルツバウ(Merzbow)に代表されるような、とても特殊で極端に個性的な音へのアプローチがあると感じます。それは人生を通じての実践への深い考察に根ざしていて、私の「人生において実践と芸術はどのように発展を遂げるのか」という、深い興味の対象に通じます。また、水琴窟や、鶯張り(城への敵の侵入者を知らせる仕組み)に代表されるような、日本に存在する歴史的な音へのアプローチに非常に惹かれます。武満(徹)の作品もしかり。特に彼の音に関する著述は、注目せずにはいられません。日本には素晴らしい多様性があり、吸収すべきものがあります。
■あなたの日本とのつながりや、実験的なものからポップなものまで手がけるそのスタンスは、どこかジム・オルーク(Jim O'Rourke)の活動を想起させる部分があります。彼がBandcampで展開している『Steamroom』シリーズの第29作では、〈Room40〉の15周年記念フェスティヴァルのために作られたセクションが含まれているようですが、彼と交流はあるのでしょうか? 彼の音楽や活動についてはどう思っていますか?
LE:私はジムを最高にリスペクトしています。彼の同時代のミュージシャンのなかでも、最も重要な人物のひとりだと思います。驚くべきほど豊かな電子音楽を創り出し、ウィットに富んだ詩を書き、インスピレイションを与える、いわゆる本物のアーティストです。彼から仕事を委託されたことはとても光栄でしたし、彼の作品をストックホルムやシドニー、ブリスベンへ普及できたことはとても嬉しいことでした。素晴らしい機会でした。
■あなた自身や〈Room40〉の作品、あるいはオーレン・アンバーチ(Oren Ambarchi)のような実験的な音楽は、オーストラリアではどういう位置づけなのでしょう? 日本では、ミュージック・ラヴァーを除く大多数の一般の人びとは、チャートに入っている音楽だけで満足してしまい、そこから幅を広げようとはしないのですが、それはオーストラリアでも同じなのでしょうか?
LE:おそらくそれはどこでも同じでしょう。私は、音と音楽の可能性はすべての人に届くと非常に強く信じています。要は、人びとがいかに良き文脈と機会を通じて、有意義に音楽とのつながりを持てるか、ということです。
■『Airport Symphony』(2007年)はブライアン・イーノ(Brian Eno)の『Music For Airports』へのオマージュだそうですが、イーノについて、また彼が創始した「アンビエント」というコンセプトについてはどうお考えですか?
LE:私はブライアンに多くの敬意を抱いています。私は彼を、思想家でありミュージシャンであると考えています。他のアーティストと制作をする際に、皆を見事に親和させる彼の能力には畏敬の念を感じます。彼は、人びとの作品の多様な側面を解き明かし、サポートする方法を知っていて、私たちそれぞれにとってとても有益なことです。数年前に彼と一緒にランチをしましたが、彼はとてもオープンな姿勢を持っていて、そのことが人びとに、普段のアプローチとは違う方法で新たなものを発見するスペースを与えるのだろうと感じました。ボウイのレコードを聴くだけでも、その音から素晴らしいパートナーシップを感じることができます。「アンビエント」についてですが、音と音楽へのアプローチの仕方として、素晴らしい表現手法だったと思います。ハリー・ベルトイア(Harry Bertoia)の音響彫刻作品にも明らかにルーツを持つでしょう。ベルトイア、イーノのふたりとも、私たち自身を巻き込む、特殊な共鳴空間を創り出すことに関心を示しています。
■他方であなたは『For / Not For John Cage』(2012年)という作品も発表しています。ケージについてはどうお考えなのでしょうか?
LE:ケージを忘れることはできません。彼は20世紀最初の偉大な音への挑戦者でした。彼の暖かい笑顔と、問い続ける姿勢、このふたつの印象は私の心に刻みつけられています。彼は疑いなく伝説的な存在であり、彼の精神は時を超えて残り続けるでしょう。
■あなたは〈A Guide To Saints〉というカセットテープに特化したレーベルも運営されていますよね。カセットテープというフォーマットに対する何か特別な思い入れのようなものがあるのでしょうか?
LE:音楽との出会い方という意味で、メディアは非常に影響力のあるものだと感じます。物体としてのメディアは、音響だけではなく表意的な一連の意味合いを包み、音楽の物理的なインターフェイスは、私たちと音楽とのつながりを形作ります。私にとってカセットは、唯一の線状の音楽メディアでした。レコードやCDでは、実際に早送り機能を使うことはほとんどなく、スキップを使用しますが、テープではこれは不可能です。私はある種の音楽はテープで聴いた方がより良いと感じます。
■ヴェイパーウェイヴというムーヴメントについてはどうお考えですか? ヴェイパーウェイヴの作品はカセットテープで発表されることが多く、形態の上では〈A Guide To Saints〉と同時代性があるように思えるのですが。
LE:いくつかのリリースは大好きです。とても興味深いムーヴメントです。
質問・文:小林拓音(2017年3月16日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE