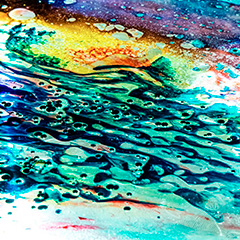MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Lawrence English- Wilderness of Mirrors

英国のオンライン・ミュージック・マガジン『FACT』の2014年ベスト50において、数あるポップ・ミュージック勢に混じって、ローレンス・イングリッシュの2014年作品『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』が選出されていたのには驚いた。順位は21位だが、この種のエクスペリメンタル・ミュージックなアンビエント/ドローン作品がポップ・ミュージック勢に混じって選出されたことは注目に値する。これは昨年リリースされ、多くのメディアの年間ベスト内に選出されたティム・ヘッカー『ヴァージンズ』以降の変化だろう。あの作品への評価は、ドローン/アンビエントなアルバムが、ポップ・ミュージックとして受容=需要されつつあることの象徴といえる。
近年のローレンス・イングリッシュの活動を振り返ると、〈ウィンズ・メイジャー・レコーディングス〉からのリリースや、自身が主宰する〈ルーム・40〉の旺盛なレーベル活動に加え、ベン・フロストの『オーロラ』(2014)への参加も重要に思える。ベン・フロストと〈ベッドルーム・コミュニティ〉の面々はティム・ヘッカーの『ヴァージンズ』にもエンジニア、パフォーマーとして全面参加しているのだから、西欧のドローン/アンエント・シーンは、コミュニティのように連帯しているのだろうか。
そして、〈ベッドルーム・コミュニティ〉といえば、ニコ・ミューリーなど、ポスト・クラシカルの話題作もリリースしており、日本人が思う以上にポストクラシカル(=モダン・クラシカル)とドローン/アンビエントの境界も、また曖昧ともいえる。(ポスト/モダン)クラシカルな音楽(ハーモニー/メロディ)が(西欧)人の心にもたらす安堵と沈静は、日本人がときに「癒し」などと軽い言葉で消費するのとは違い、音楽的な源泉のようなものである。だからこそアルヴォ・ペルトは偉大な作曲家なのだ。しかしペルトのような作曲家ですら、かつてのニッポンの知識人層からは、通俗的な癒しの音楽などと断じられてしまったわけで、となると、そもそもわれわれはドミソの三和音のハーモニーの美しさですらわかっていなかったのではないかと自虐的に思ったりもするが、これは余談。
アンビエント/ドローン/ノイズ、ポスト(モダン)・クラシカルの交錯。ローレンス・イングリッシュの新作『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』(イングリッシュ自身が主宰する〈ルーム・40〉からのリリース)は、そのような状況下にリリースされたわけだが、その音は、一聴し即座にわかるように、これまでの穏やかなドローン/アンビエント・サウンドのイメージを覆すように一種の轟音化/ノイズ化の様相を示している。リリース時は、ティム・ヘッカーの『ヴァージンズ』の類似なども指摘されたが、先に書いたように彼を取り囲む現在のコミュニティを体現しているといえるから当然の変化だろう。またローレンス・イングリッシュは、本作の制作中にスワンズやマイ・ブラッディ・ヴァレンタインのライヴを体験し、轟音空間に打ちのめされ、影響を受けたとも語っているのだから、近年のノイズ・ムーヴメントの空気を存分に吸収して生まれたアルバムともいえる。さらに、その不穏な音は、インダストリアル・テクノ以降の「世界の不穏さ/不安さ」を体現したような音楽にもリンクしており、インダストリアル・テクノ以降のダーク・アンビエント作品として聴くことも可能である。その意味で、二―ル『フォボス』などとともに聴くべきアルバムかもしれない。
しかし、そうはいっても本作は、「静寂と空間の作家ローレンス・イングリッシュ」の作品である。その音響空間の設計/構築には、かつてと同様に複雑な静寂性がある。ドローンといえば単一の音が持続するものだが、イングリッシュの音は、いくつものドローン的な持続が、平行的/多層的に続き、絡み合い、まるで一瞬の響きを引き伸ばされた、いわば弦楽のようなドローン=電子音響に仕上がっているのである。2012年にリチャード・シャルティエの〈ライン〉からリリースされた『フォー/ノット・フォー・ジョン・ケージ』と本作を続けて聴いてみると、サウンドの構造的には非常に似通っているのがわかってくると思う。
これはステファン・マシューの『ザ・サッド・マック』(2004)あたりをオリジンとする、00年代後半のドローン/アンビエント・シーンのベーシックなフォームともいえるが、その中にあって、イングリッシュの音は、かなり洗練されたものだ。低音部から高音部の音が、ハーモニーともレイヤーともちがう調和/非調和で持続する感覚。私見だが、10年代のノイズ/ミュージックは、80年代のそれが反社会的なイデオロギーを内包し表出していたのとは対照的に、サウンドの多層性によって、時間/音響をコントロールし、静寂(のイメージ)を生成しようとしていたように聴こえる。その意味で、エレクトロニカ以降のドローン/ノイズ・ミュージックは、新しいハーモニーの生成ですらあったのではないか。
それはローレンス・イングリッシュの場合も同様で、音響と音響のレイヤー、つまり音と音の重なりあいの構造によって新しい沈静(=ハーモニー)が生成している。つまり、サウンド/音響の構造によって、静寂が生まれているのだ。たとえ轟音化した『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』であっても、それは同様であり、〈ウィンズ・メイジャー・レコーディングス〉からリリースされた彼のフィールド・レコーディング作品『Suikinkutsu No Katawara Ni』や、鈴木昭男との共作『Boombana Echoe』などと、それほどかけ離れた作品ではない。つまり、『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』は、現在のアンビエント/ドローン・シーンの変化を十二分に体現しつつも、彼のサウンド・デザイナー/音楽家としての資質を浮きぼりにした作品なのだ。
同時に、『FACT』の2014年ベスト50内に選出されたということは、先に述べたような西欧音楽の源泉のようなエレメント、つまり調和による鎮静というものが、『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』にも埋め込まれているからではないかとも思う。ドローン/アンビエントは、鎮静に特化した音楽形式でもあり、決して、難解な音楽ではない(それは新しいハーモニーの生成でもあった)。それゆえむしろポップ・ミュージックになりえる。『ウィルダネス・オブ・ミラーズ』は、ポップ・ミュージック化するドローン/アンビエントいう2013年の『ヴァージンズ』以降の環境を象徴する一作ともいえる。まさしく2014年の必聴作だ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE