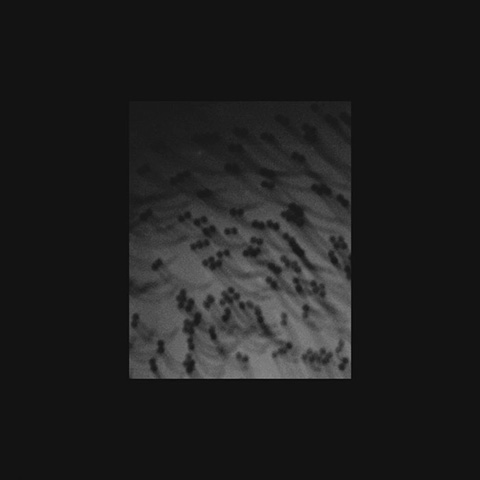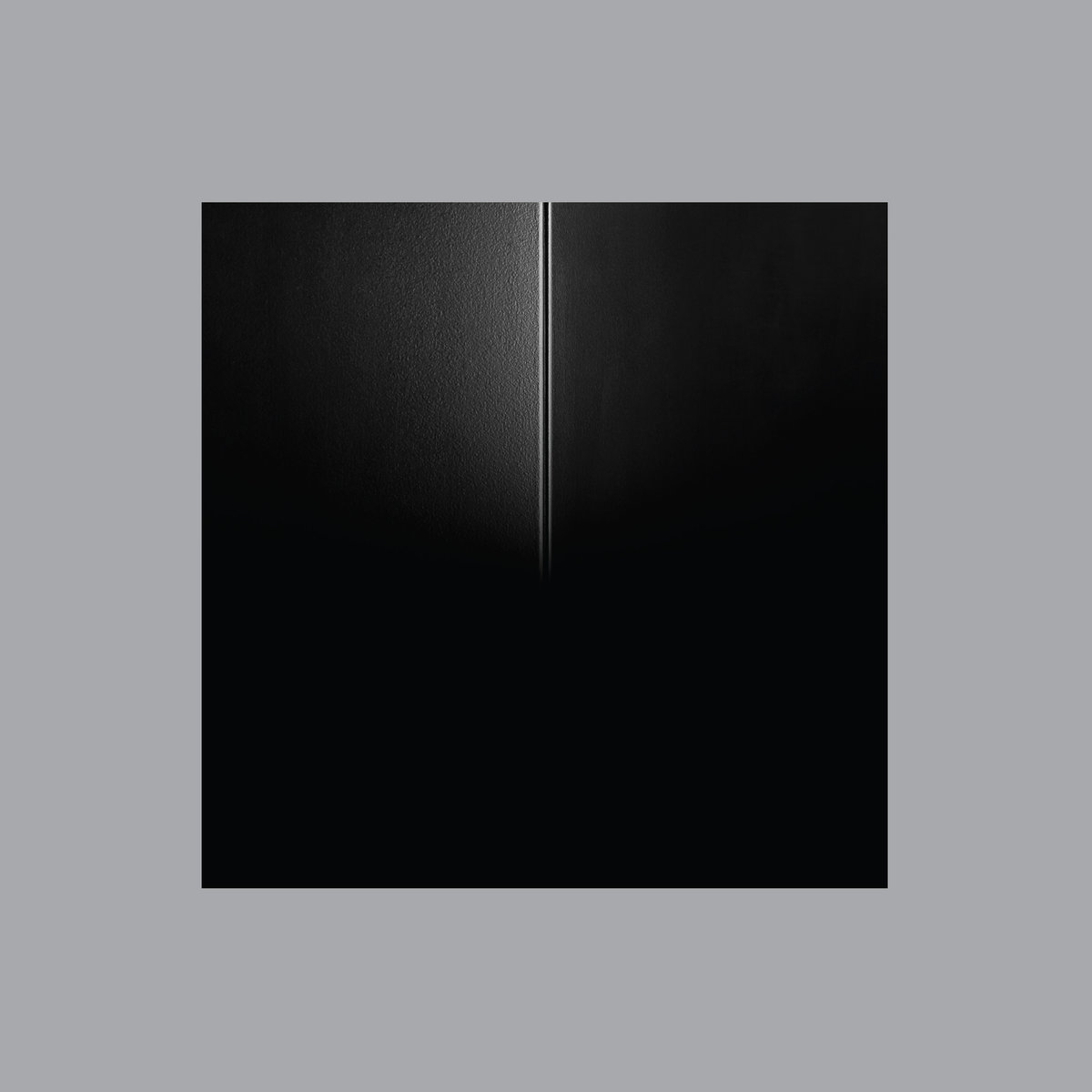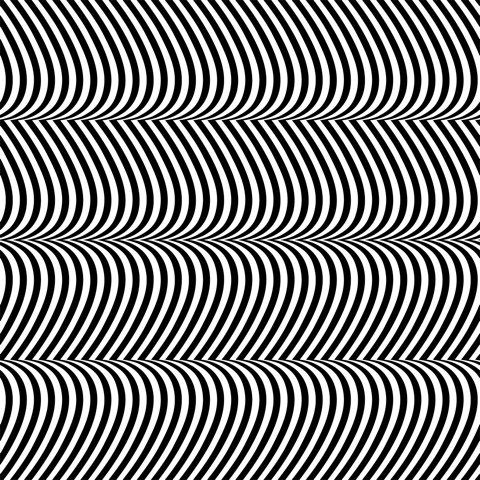MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Merzbow- Monoakuma
ノイズ/ミュージックとは物体の持つ「声」の残滓だ。いまは/いまも存在しない「声」でもある。発したモノがなにものかわからない「声」。しかし、その「声」は、かつて確かに世界に響いていた。音、音として。どんなに小さく、どんなに儚くとも、その「声」は世界に対して轟音のような己の意志を発する。そのようないまは消え去ってしまった「声」のすべてを蘇生すること。「声」とは存在や物体すべてが有している音でもある。「声」とは音だ。となれば刹那に消え去ってしまった「声」は「最後の音楽」といえないか。音。その音は小さく、しかし大きい。存在と幽霊。蘇生と爆音。となればノイズ/ミュージックとは「声」=音の存在を拡張する方法論だ。いまここでは幽霊になってしまった最後の「声」=音たちの蘇生の儀式なのである。
メルツバウの新作『Monoakuma』を聴きながら、改めてそのようなことを思ってしまった。なんと想像力を刺激するアルバム・タイトルだろうか。「モノアクマ」。具体と抽象が同時並走するようなこの言葉は、先のノイズ/ミュージックというマテリアルな「音楽」の本質を見事に掴んでいるようにも思える。まず、このティザー映像を観て頂きたい。
まるで黒い幽霊の「声」と「影」のごとき映像は、まさに「モノアクマ」ではないか。「モノアクマ」の発する「最後の音楽」としてのノイズ(の断片)。この感覚は、本作だけに留まらない。私は、メルツバウのノイズを聴いていると、いつも「最後の音楽」という言葉が頭を過ってしまうのだ。音楽から轟音/ノイズが生まれ、やがて音楽はノイズに浸食され、融解し、そのノイズの中にすべて消失し、やがて終わる。消失直前の咆哮のごとき「最後の音楽」。
だが重要なことは、「最後の音楽」である以上、「最初の音楽」もあったという点である。その「最初の音楽」とはキング・クリムゾンの『アースバウンド』かもしれないし、ピンク・フロイドの70年代の演奏かもしれないし、ジミ・ヘンドリックスかもしれない。もしくはサン・ラーかもしれないし、ブラック・サバスかもしれない。あるいはデレク・ベイリーなどのフリー・インプロヴィゼーションかもしれないし、ヤニス・クセナキスなどの現代音楽/電子音楽かもしれない。
しかしここで重要なことは、それぞれの固有名詞「だけ」ではない。メルツバウにとって「最初の音楽」が「複数の存在」であったことが重要なのだ。複数性からの始まりとでもいうべきか。ノイズという原初の音の中に複数の音楽聴取の記憶が融解し、生成変化を遂げている。いわばノイズ/ミュージックとは、千と一の交錯であり、音の記憶の結晶であり残滓なのだ。
そこにマイクロフォンによる極小の音から最大への拡張があったことも重要である。マイクロフォンで音を拾い、拡張し、どんな小さな音も轟音へと変化させること。メルツバウがその活動最初期に掲げていた「マテリアル・アクション」は、そういったノイズの原初の音響を示していた。
つまり、メルツバウというノイズ・プロジェクトは、その活動最初期から三段階の進化を一気に得ることでスタートしたといえる。まず、ロックやフリージャズ、現代音楽などの音楽の記憶、ついでマイクロフォンによる音の拡張、そしてそれらの意識/手法の融合としてのノイズ/ミュージックの生成。となると2010年代のメルツバウは、その進化の最先端/最前衛に位置しているともいえる。
じじつ10年代のメルツバウは、まるで巨大なノイズの奔流と微細な神経組織が交錯するようなノイズ・サイバネティクスとでもいうべきノイズの生態系へと至っているのだ。それは実体と抽象が交錯するノイズ/ミュージックの必然的な進化=深化だろう。現在のメルツバウのサウンドを聴取すると、私などはローラント・カインの音楽を思い出してしまうほどである。40年近い活動の中で、メルツバウのノイズを生み、ノイズを越境してきたのだ。
その意味で、00年代以降のドローン音響作家を代表するローレンス・イングリッシュが主宰するエクスペリメンタル・ミュージック・レーベル〈Room40〉からリリースされた『Monoakuma』は重要な作品に思える。まずここで重尾なのは「40」という数字だ。1979年から活動を開始したメルツバウ(初期は水谷聖とのユニット)は、2019年に活動40周年を迎える。
その「40周年」を直前とした2018年12月に「40」という数字を持った名のレーベルからアルバムをリリースしたのだ。これは非常に意味深いことに思える。むろん、ローレンス・イングリッシュはヘキサとしてメルツバウとのコラボレーション・アルバムをリリースしているし、イングリッシュ自らが署名付きで執筆した本作のリリース・インフォメーションで、2000年代半ばにおけるメルツバウ/秋田昌美との出会いを書き記してもいた。つまり〈Room40〉との邂逅は10年以上前から準備されてはいたのだが、それゆえに「40」という数字を巡る必然には改めて唸ってしまう。アンビエントを基調とするレーベルからメルツバウのアルバムがリリースされたことは、やはり必然/運命だったのだろう。
録音されている音自体は、2012年にブリスベンの Institute of Modern Art でおこなわれたライヴ録音だという。しかし一聴しただけでも10年代のメルツバウのノイズ音響そのもののような音だと確信できる。まさにメルツ・ノイズの現在形そのもののような素晴らしい演奏と音響なのである。
マテリアルとアトモスフィア、モノと幽霊の交錯のような硬質なノイズが、激流のように変化を遂げている。加えて不思議な静謐さすら感じさせてくれた。爆音のノイズが生成するスタティックな感覚。具体音、ノイズ、エラー、モノ、アトモスフィア、生成、終了……。そう、この『Monoakuma』から、過去40年に及ぶメルツ・ノイズの時間の結晶を感じてしまったわけである。
80年代のマテリアル・アクションからノイズ・コラージュ時代、90年代のグラインドコアの潮流と融合するような激烈なアナログ・ノイズ時代、00年代の〈メゴ〉などによって牽引されたグリッチを取り入れたデジタル・ノイズ時代のサウンドの手法と記憶と音響が、さらなるアナログ・ノイズの再導入と拡張によって結晶化し、聴いたこともないエクセレントな衝撃性を内包したノイズ音響空間が生成されている。まさしくノイズによる無数の神経組織の生成だ。そのような「神経組織の拡張」は、当然、コラボレーションに及び、アンビエントやフリージャズや電子音楽などの音響空間にも浸食し続けている。
浸食するノイズ/ミュージックの巨大/繊細な神経組織としてのメルツバウ。むろん、マウリツィオ・ビアンキもホワイトハウスもラムレーもスロッビング・グリッスルも SPK もニュー・ブロッケーダースもピタもフランシスコ・メイリノも、すべてのノイズ音楽は「音楽」に浸食する存在だった。そもそも20世紀という時代は、ノイズと楽音の区別が消失した時代である。しかし、そのなかでもメルツバウは、ひとつの原初/オリジンとして20世紀音楽から21世紀の音響音楽に巨大なメルクマールを刻んでいるのだ。メルツバウは、まさに「ノイズ/ミュージック」のひとつの最終形態とは言えないか。
メルツバウにおいて、「音楽」はノイズの波動と化した(「最後の音楽」だ)。そのノイズ=波の中には無数のノイズが蠢き、ひとつの/無数の音の神経組織を形成する。その聴取は驚異的な快楽を生む。そう、メルツバウを聴くことの刺激と快楽は、そのマクロとミクロが高速で生成されることに耳と肉体が拘束される快楽なのだ。ノイズはモノであり、そのノイズ=モノはアクマのようにヒトを拘束し、しかし魅惑する。
本作もまた50分が一瞬で過ぎ去ってしまうような刺激と、永遠を感じさせるノイズ・コンポジションが発生している。その音はまさに「40」という時間を超える「22世紀のノイズ」の胎動そのものに思えてならない。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE