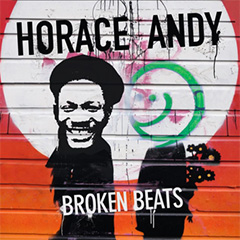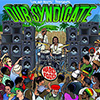MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > Horace Andy- Broken Beats
レゲエを聴かないリスナーが、マッシヴ・アタックの衝撃的デビュー作『Blue Lines』(1991)でホレス・アンディの存在を知ってから、もう20年以上経った。その後も彼の声はマッシヴ・アタックのブリストル・サウンドにとって透徹したフェティシズムの対象であり続け、今日まで彼らの作品に欠かせない要素になっている。そして、レゲエ歌手がモダンなダブ/エレクトロ・サウンドの"ヴォーカル・パート"に用いられるトレンドの嚆矢ともなった。
もちろん、当初"トリップ・ホップ"と形容されたマッシヴ・アタックのサウンドはレゲエ、ヒップホップ、ダブ、ダウンビート、アンビエント等々のファクターを縫うものだったわけで、レゲエ自体とは薄からぬ血縁があった。しかし彼らの音のなかにレゲエから引かれていたものは、レゲエの軽快で陽性の側面よりもむしろ、鋭利な重量感に雄弁な精神性が宿るダブの前衛と、同時にそこからにじみ広がるアンビエントなサウンドスケイプであり、そこにメタリックな光沢さえ感じさせるアンディのハイ・トーン&ヴィブラート唱法が強烈なマッチングを見せたのだった。
そうしたアンディの特質と合致した彼の代表作として、とくにマッシヴ・アタック以降のファンが愛聴するのが、NYの〈ワッキーズ〉レーベルに残された名盤『Dance Hall Style』だ。ここで聴かれる80年代初頭のワッキーズ・サウンドの、音が地面に重くめり込んで歪んでしまったかのようなドラム&ベイスの暴力的なブースト、それから硬く無機質なダブの質感は、それまでのジャマイカ産の音とは明らかに異なっている。そしてルーツ・レゲエの陰影から冷たい闇のエッセンスだけを抽出、培養したようなそのサウンドが、90年代以降のブリストル・サウンドや欧州のダブ・クリエイションの新潮流にとって、ひとつのプロトタイプとなったことは間違いない。マッシヴ・アタックが『Blue Lines』収録の"Five Man Army"でアンディに『Dance Hall Style』の収録曲"Cuss Cuss"や"Money Money"のリフレインを歌わせたり、続く2作目『Protection』では同じく『Dance Hall Style』収録の"Spying Glass"を丸々アンディ本人を迎えてカヴァーしたのは、自分たちのサウンドの指向性(ルーツ)のひとつを示した、リスナーに対する種明かし的啓蒙だと言えるだろう。
2000年代に入って、その〈ワッキーズ〉レーベルのカタログがベルリンのテクノ・プロダクション/レーベル:ベイシック・チャンネルによってリイシュー配給されたことも象徴的な出来事だったが、その後もレゲエとディジタル・ダブとエレクトロニカの分野の相互干渉と拡張はヨーロッパ全体で実に自然な成り行きのなかで進行し、折りに触れてジャマイカの源流を仰ぎ見ながらも、独特の、低温度でダークでヘヴィーなサウンドを醸成してきた。
本作はその"支流"の最先端から、またも欧州型ダブ・エレクトロ・クリエイションとホレス・アンディとの相性のよさを再発見しよう、という企画である。とはいえアンディは近年も(彼らもブリストル・サウンドの代表的ユニット)アルファとのコラボでアルバムを発表したり(『Two Phazed People』)、UKハウス界のレゲエ通アシュリー・ビードルとも、〈ストラット〉レーベルの人気の異種ジャンル交配シリーズ〈Inspiration Information〉の一環でアルバムを作ったり、クラブ・ミュージック・クリエイターからの引きが切れなかったゆえに、いまとなってはこの種の作品に新鮮味を感じない人も多いだろう。
ただ、本作の出口はハンブルクのダブ・レーベルの名門〈エコー・ビーチ〉だけに、その支持者がヌルい音で満足しないことはプロダクション側が一番よくわかっている。参加したクリエイターはレーベルに縁の深い名だたる面々で、ブリストルの顔役ロブ・スミス(RSD)、ベルリン・レゲエ・シーンの重鎮フロスト&ヴァグナーのオリヴァー・フロスト、ベルリンのダブ・テクノ・クリエイターのラーズ・フェニン、オーストリア/ウィーンから世界的名声を獲得したダブ・バンド:ダブルスタンダート、スイスのダブ・ユニット:デア・トランスフォーマーetc.......。
肝心の収録曲は、前掲"Cuss Cuss"や"Money Money"、さらには"Skylarking"など、アンディのクラシック・チューンの焼き直し。〈エコー・ビーチ〉は、UKの名レゲエ再発レーベル〈ブラッド&ファイアー〉の古典ダブ音源を新世代のテクノ・クリエイターにリミックスさせた刺激的な〈Select Cuts〉シリーズの発売元でもあるから、昔の曲を聴かせるならこれもリミックス企画でよかった、という声も上がりそうだ。あるいは、この面々の作る音で新たに吹き込むなら、新曲のオリジナル・アルバムが聴きたかった、という意見も出るに違いない。しかしながら、ミニマル・ダブもダブステップもブレイクビーツもクラシカルなダブのセオリーもすべてが手段として前提化している上に、楽曲自体にも目新しさがない、というところまで自らハードルを上げておいて、この面々でアンディ・クラシックスの2013年版を提示しようとするわけで、つまりはそのレーベルの野心とクリエイターそれぞれの手腕とイマジネイションこそがまさに聴きどころだと捉える人なら、多くの曲でかなりスリリングな体験ができるはずだ。
7楽曲で15トラック。つまりダブ・ミックスへの展開まで収録した曲があれば、同一曲を複数のクリエイターがそれぞれのヴァージョンにいちから作り変えた曲もあって、豊かなヴァージョニング・アートの妙が展開される。といっても、奇矯なトラックやミックスで驚かせるわけではない。還暦越えにしてなおもみずみずしいアンディの声は、その美点を削がぬようにとても丁重に扱われている。そしてカネに狂わされる人間の性(Money Money)、仕事、階級社会、若者の退廃(Skylarking)、善悪観念(Bad Man)、争いごと(Cuss Cuss)といった普遍的な曲のテーマ、直截的でシンプルな歌詞のリフレインも入念に強調されながら、サウンドとヴォーカルの調和はどれも見事に保たれている。これエイドリアン・シャーウッドがアレで使った技じゃん、というようなツッコミが免れないパーツもあったり、全トラック同じように感心できるわけでもないが、1曲1曲が濃密な仕事の集積であることはたしか。12インチ・シングル4枚とかにバラして出してもらうとよろこぶ人も多いんじゃないか。
微妙にムッシュ・アンドレやバンクシーもどきなグラフィティ仕立てのジャケットはぞっとしないが、中身はきちんとヨーロッパのストリートの音がする。さすがに20年前のインパクトは望むべくもないにせよ、この我らがレゲエ・レジェンドは、変わらず新しい音に興味と理解を示し、そしていまもその上で自分の特性をきちんとアピールできている。
鈴木孝弥
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE