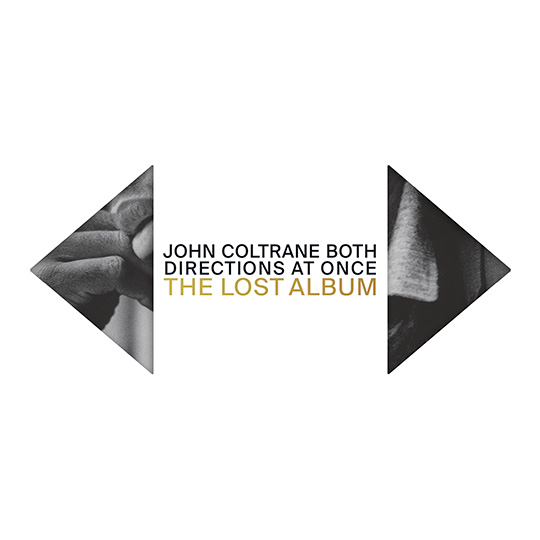2014年、デビュー直後のjan and naomiのライヴに偶然接することが出来たのだが、美しく儚げな男性ふたりが、極めて繊細にコントロールされた弱音の響きを紡ぎ出す様に、非常なインパクトを受けたのだった。ファッション・モデルをもこなすというその出で立ちのシャープさ、そして奏でられる音楽の圧倒的幽玄。アートの匂いを強烈に振りまきながらも、まるでこの街でないどこかからふと現れた超俗的な佇まい。
その後もEPリリースやフジロックへの出演などを経て着実のその特異な存在感を浸透させていくなかで、彼らの表現は「狂気的に静かな音楽」とも称されるようになっていったという。なるほどこのファースト・アルバム『Fracture』は、その言葉に強く頷くことの出来る出色の内容だ。
広がりあるサウンドケープや抑制のきいたエレクトロニクスの用法からは、所謂チル・ウェイブ以降のサイケデリック感覚が強くにじみながらも、ジェイムス・ブレイクやキング・クルールといったサウンドメイカー達とも共通するような透徹した音響意識を感じさせる。しかしながら、メロディーとそれを届ける歌はあくまでインディー・フォーク的であり、その意味で、かつてのサッド・コア~スロウ・コアのアクト達に通じるような、静謐な「うたもの」としての快楽性も備えている。
また、ほぼ全曲が英語詞で構成されているその歌詞世界も、彼らの「狂気的に静かな音楽」を創り出す重要な要素となっている。全編において、神(逆説的に、ときに悪魔的なものへの憧憬も隠さない)や愛といった形而上学的存在への問いかけが染み出す。しかし、ゴスペル音楽のような、熱狂的な覚醒や躍動は締め出され、その変わりに、甘く物憂げな静謐がメロウネスとなって全体を浸す。
邦訳:あなたがいないと、大空を羽ばたく羽をなくしたようだ/何度あなたがこの世界に存在したかと思っただろうか/何度あなたが実存すると思っただろうか、/何度もそう思った ‘Forest’
こういったペシミスティックなヴィジョンは、近代以来の放蕩への回心・贖罪を経て救済へと向うべきだったはずの現代の文明が、むしろ日々自らの手で神を葬り、救済を遠ざけてしまったことで代わりに引き寄せることとなったニヒリズムに強く培養されているようにも見える。一方で、そういった諦念の淀みの中でも、
邦訳:ここはあなた夢の入り口、今までのことには別れを告げて/この折れた骨で、エスの街から抜け出すのだ/私たちの夢のためにその約束は守って、今まで見てきた罪に別れを告げて ‘Fracture’
とタイトル曲に歌われるように、これまで重ねてしまった罪を見つめつつも、新たなフェイズを切り開こうとする心性を垣間見せもする。
 jan and naomi Fracture cutting edge |
耽美的音楽と審美性から、ある種「浮世離れした」存在と見做されそうなjanとnaomiによる音楽は、その実、「諦念」と「希求」、「破壊」と「再生」の間に揺れる生活者の告白として、極めて実直で真摯なものだとも言える。
この、蠱惑的なほどに極めて静謐な音楽は、静寂に取り囲まれるとときに静寂そのものが我々を圧するような不安を喚起するように、静謐であるがゆえ我々を内省へと誘い、内省の果には実存世界の外延へと連れ出しもする。熟れ、爛れ、饐えを抱えながら、それでも今、救いを希求する。破壊を受け入れながら、そこから新たな物語を紡いでいく。
卓越した現代のレクイエム集であるとともに、賛美歌集とも言える本作『Fracture』をリリースしたjanとnaomiのふたりに話をきいた。
naomiさんと一緒に音楽を作りはじめた時期、反骨精神のある音楽がすごく好きで。そのなかで何がいちばんパンクなのかって考えたときに、もちろん大きい音を出して真正面からぶつかっていくのもすごくカッコいいんだけど、東京の渋谷で、絶えず様々な音が無秩序に鳴っているところで、それを「フッ」と止めるというようなことがもっともパンクかな、と思ったんです。
■2016年の前作EP『Leeloo and Alexandra』のリリース以降、フジロックやロシアのフェス(V-ROX FESTIVAL)への出演や、映画『Amy Said』の音楽担当など、いろいろなフィールドで活動してきたかと思うのですが、そういった経験は今作に制作に影響を与えていますか?
jan(以下j):いちばん大きかったのは映画音楽制作の経験ですね。
naomi(以下n):劇伴すべてとエンディング・テーマを、という依頼で。限られた予算内で多くの楽曲を作らなくてはいけなかったので、レコーディング・スタジオに入る予算も無くて、自宅で完パケまでもっていけるようなやり方をしっかりしなくてはいけなかった。だから自然と俺もjanもDTM的に制作する環境が整ってきて。それは今作の制作を進める上で影響がありましたね。今までは、生ドラムと、アンプから出しているギターの音を主軸にしていたものが多かったんですけど、そういうプロセスではない楽曲が増えたというのがあります。
■いままでは普通にプリプロを制作して、それをスタジオへ持っていって、というようなスタイル?
n:そうですね。
■今回はふたりがお互い事前にデモを投げあって、みたいな感じ?
j:お互いに交換するっていうよりは、基本スタジオに入るまでは別々に形を作って、スタジオに入ったらふたりでいろいろ遊ぶっていうやり方だったかな。
■そういうプロセスがアルバムの音にも反映されている気がしますね。これまでに比べてギターよりもピアノが目立ってきている感じとか、エレクトロニクス音の比重も増えている気がしました。
j:naomiさんが打ち込みで作るものもあれば、俺がシンセサイザーを使うということもあったり。あと家でヴォーカルも取れる環境になったことも大きかった。
■新作についての話に本格的に入る前に、映画『Amy said』の音楽制作について訊いておきたいんですけど、おふたりの音楽は所謂映像喚起力が強いなという気がしていて。基本英語詞であるにも関わらず、特定の風景を喚起させるというか。監督の村本さんとしても、そのあたりを汲んでのオファーだったと思いますか?
j:たぶん最初は監督もそういう気持ちだったと思うんだけど、徐々に監督にも明確なヴィジョンがあるっていうことがわかってきて。
n:打ち合わせのときにラフの映像を見ながら「具体的に思っていることがあったら教えてください」って言ったら、めちゃ具体的で(笑)。
■「こういう音をここに入れてください」的な?
n:そうです。「何年代の誰々みたいな音楽が欲しい」とか、「ここはテクノで言うとあの時代の感じ」とか、「バーで鳴っているBGMも欲しい、このマスターはこの年代の音楽に影響を受けているから、たぶんかかっているのはこういう音楽だ」といったような。
■そういう意味では、アーティストっていうよりプロの映画音楽作家さん的な感じですね。それが経験としては大きかったと。
n:そうなんです。いままでトライしなかったこともできたし。「トミー・ゲレロみたいな曲で」というようなオーダーとかもあったな。
■映画音楽って、監督によって全然やり方違うみたいですよね。厳密に音符レベルで指定してくる人もいれば、「ふわっとした感じでお願いします」みたいな人もいる、と。いろんなミュージシャンに映画音楽制作の話を聴くと、みなさん「大変だけどいろいろ鍛えられる」というようなことを言いますね。
n:それはかなりありますね。
j:結局、僕らも映画音楽のプロじゃないから、作ったものにはjan and naomiらしさはやっぱり残ってはいるんですけどね。
■今回のアルバムはとくに映像喚起力が強いなと思いました。各曲、何か具体的な映像世界を想定した上で曲作りしていくんでしょうか?
j:前作までは割と、イメージや言葉の輪郭を帯びていないものを曲のなかに投げ込んで聴き手にそのエッセンスを自由に解釈して欲しい、というのがあったんですが、今回、自分が歌詞を書いたものに関しては具体的にして、抽象表現は抑えてストーリーテリングする感じでやりたいなあ、と思いました。聞き手によってはもしかしたら以前より映像性がなくなったと思うこともあるかも知れないけれど、割と自分的には具体的なヴィジョンが見えたものを投げ込んでいるというイメージです。
■場面設定的がしっかりある感じを受けました。
j:劇っぽくつくれたらな、と思っていました。
■各曲、曲ごとにテーマを先に設定して、そこから作っていく、という形ですかね?
j:俺が作った曲は最初に歌詞書いてという感じだったんですけど、naomiさんは?
n:はじめはテーマはとくに決めないですね。何か映像にあてはめるような作り方もしていない。
■曲を作っていく段階で徐々にテーマのようなものがあぶり出されていく、と。
n:そうですね。
[[SplitPage]]janの声は独特で、音程がなくても成立するような感覚があって。ひとりで活動していた頃やjan and naomiの初期にはそういう曲がけっこうあるんですが、音程が合っていないないというかズレているのかな、というのも含めて味にするような歌声と歌い方もできる。
 jan and naomi Fracture cutting edge |
■先ほどデモは各人で作っていくと言っていましたが、その後のふたりのキャッチボールってどうやっているんでしょう?
n:普通のバンドと違うところだと思うんですが、僕たちはデモをつくったら基本的にはそれで完成というイメージ。今回は、その後レコーディング・スタジオで録っていくなかで、もう一方がその上でいろいろと遊ぶ、みたいな感じでした。家で8割9割仕上げて、スタジオでしか録れないものを録り直したというようなやり方が多かったですね。
j:その遊び方もまったく定形があるわけじゃなくて。例えばお互いが作った曲について、演奏的にはほぼ何もしてなくても、意見をひとつの楽器として織り交ぜていく、というか。例えば俺が演奏して歌ったものに、naomiさんが「ああしたほうが良いと思う、こうした方が良いと思う」と言うことが、jan and naomiの音楽の色というか、ひとつのフィルターとなっていると思います。
■細かなアレンジとかもほぼ作曲者の主導で?
n:俺の曲はそうでした。janのものは、弾き語りのデモが用意してあって、セッションしながらレコーディングしていく、みたいな感じでしたね。
j:割合コラージュっぽく部分的に、っていうのが今回はとくに多かったかな。
■一般的な、Aメロ固めて、Bメロ固めて、構成作り込んでいって、プリプロ作って、スタジオにもっていって、録って、ラフミックスして、みたいな感じで作っていないのだろうな、というのは感じました。音の差し引きなども当意即妙にその場でやっているのもけっこうあるんだろうだとうな、という。非常に作り込まれているのに一方でセッション感もあるという、不思議なバランスだなと思いました。
j:ミックスがはじまってから音を足すこともありましたね。
■ミックスはエンジニアさんと?
j:メールベースで意見を言い合ってという感じですね。
■音像の部分でも、一聴して全体にすごく深さと広がりがありつつ、曲ごとの緩急もあって、構成的なこだわりも感じました。
j:最近になって思い出したのは、互いの曲が徐々にビルドアップされていく上で、この曲はEQ的にビルドアップしたから、あの曲のこの部分をちょっとマイナスしてみようとか、そういうことがあったな、ということ。例えばnaomiさんがある曲のなかでシンセサイザーにリバーブを深くかける判断をしたときに、俺のこの曲のリバーブは逆にもう少しカットして、マットな曲の響かせ方にしようかな、とか。それがレコーディング~ミックスのプロセスのなかで多くあった気がしますね。
■それぞれすごく空間的な処理なんだけど、1曲1曲の粒立ちというか個性みたいなものがちゃんとありますよね。曲ごとでBPMに幅があるとかじゃないのに、そういう各曲の個性がある。
j:たしかに自然とbpmだけはそんなに離れていない形になりましたね。
野田:音響はすごく独特ですよね。俺も聴いて思いますね。
■「ダーク」といえばいいのか……重いけど広がりのある空気感というか。おふたりの音楽的趣向が音響デザインに反映されてるんでしょうか?
j:あまり何かに影響されてこうなったというのはないかな。それより、日々naomiさんとライヴをして一緒にお酒飲んだりとか、そういう普段の生活のなかから得たことが大きいかもしれない。大概そういうことって歌詞にしか影響しないと思うんだけど、お酒を飲んでいるところでかかっていた音楽とかが無意識に影響しているのかも。
■もともとおふたりは、渋谷の百軒店で別々で活動している中で知り合ったらしいですね。例えば学生時代に出会って、とかいうような場合、お互いどんな音楽が好きとか話をする中でバンドに発展するというのが一般的かなと思うのですが、おふたりの場合は、どういう形で音楽的ルーツの共有といったことが行われたのでしょうか。
j:「これが好き、あれが好き」っていう音楽の話をする前に、曲を一緒につくる機会があって。それで出来た曲がいい感じだったんです。
n:もともとjanの音楽が好きだったし、janももしかしたら俺の音楽を好きでいてくれたのかしれない。だから最初に曲を一緒に作ってみても上手く行ったということなんじゃないかな。
野田:性格的に気があったとか?
n:俺のほうが年上で、ちょうど良い年の離れ方だったっていうのもあるかもしれないですね。物事を決める時にもケンカしないし、素直に譲れるし、janも譲ってくれることもあるし。
野田:性格を陰と陽に分けるとすると、どちらがどちらですか?
n:場面によるんですけど、基本的には通常時はjanの方が陽で俺が陰。でもお酒を飲むと俺のほうが陽になる。janは逆にお酒を飲むとどんどん陰に向かっていく(笑)。
野田:そういう観点からもバランスが良いんですね。お互い陽になっちゃうとね(笑)。
j:取り留めのないことに(笑) 3年に1回くらい稀にふたりとも陽になるときもありますけどね(笑)
■ふたりとも歌声の面でもまったく違った個性を持っていますよね。naomiさんはハイトーンヴォイス。janさんは、レナード・コーエンなども思わせるような低い声。お互いの歌声の魅力を挙げるとしたら?
j:naomiさんの声は怖いくらい透き通っていて、そのホーリーな感じに感動します。
n:janの声は独特で、音程がなくても成立するような感覚があって。ひとりで活動していた頃やjan and naomiの初期にはそういう曲がけっこうあるんですが、音程が合っていないないというかズレているのかな、というのも含めて味にするような歌声と歌い方もできる。今回は歌い方を試行錯誤してヴォーカルのテイク数も重なっていきましたが、以前は1回録っても5回録っても全部OKという感じだった。厳密に言うと外れているけど、それがむしろ良い、っていう。
j:今回のように抽象性が薄い曲の場合、いままでの歌い方だとどうしても説得力がなくて、歌い方を変えた曲もありました。
■ちなみに、技術的な影響を受けているかどうかは別として好きなシンガーっていますか?
j:エルヴィス(プレスリー)かな。
■おお、意外な気がしつつ……でもわかる気もする……。
野田:ほんとに? 冗談とかではなくて(笑)?
j:本当ですよ(笑)。子供の頃から好きで、いまも変わらず好きかな。
■どんなところが好きですか?
j:なんといえばいいか……聴いた瞬間に自然とゾワッとするというか。神聖なときもあれば、すごく悪魔的なときもある。そういったものに魅了されるんです。そういった振れ幅があるものは、エルヴィスに限らず好きですね。でも、エルヴィスはその究極形といえる歌声だなあと個人的に思います。
■どこかでjanさんの歌声が「スコット・ウォーカーを思わせる」と評されいてるのを見ましたけれど、彼の歌にもそういう振れ幅がある気がしますね。
J:そうですね。でもスコット・ウォーカーの歌声も美しくて好きなんですが、甘さがないかな、と。エルヴィスにはそれもあるな、と感じます。
■naomiさんは?
n:玉置浩二。
■また意外な。
n:あとASKA。
■おお……。
n:歌がいいって思う人って誰かなあ、っていまずっと考えてて。一番最初に出てきたのが玉置浩二。
■それは親の影響で聴いていたとか?
n:2年くらい前に、僕らがよくいく渋谷の「カラス」でケヴィンさんっていう常連さんが、玉置浩二をずっとかけて歌の魅力を店中の人に語っていた夜があって。安全地帯含め玉置浩二の存在は知っていたけど、「歌が良い」っていう耳で聴いたことはなくて。で、「ああ、良いな」と。
■ASKAは?
n:ASKAの歌もやっぱり本当に独特で、歌い出して2秒で「あ、これASKAだ」って思わせる声の独特さ。歌上手い人っていうのはたくさんいるけど、玉置浩二も含めその人だけの「節」があるな、っていう人に憧れる。
■自分の声の帯域に近いとかは関係なく……その人だけの個性がある歌声が好きということですね。
n:正直ジェイムス・ブレイクとボン・イヴェールのヴォーカルの差とかわからないですよ。好きな人はわかるんでしょうけど。自分の歌に関しても、「あれだったら誰が歌っても一緒じゃん」ってなったら嫌だな、っていうのはあります。
野田:jan and naomiを聴いて日本的だとは全然思わなかったし、言われなければ日本のアーティストだって気づかずに聴いてしまえると思うんですよね。だからいまの「玉置浩二の歌が好き」っていうのは無理して言ったんじゃないかなと疑っていますけどね(笑)。本当はジェイムス・ブレイクやボン・イヴェールが好きでしょ! ライバル心があって言えないんじゃないんですか(笑)?
n:いや、そんなことないですよ(笑)。
j:でも今回のアルバム、外国人の友達に聞かせると、「アニメっぽい」って言うんですよ。
■へえ~。
j:微妙な細かいところに、アニメ的にニュアンスがある、と。
■無意識で出てしまう日本固有の土着性みたいなことなんでしょうか……?
j:おそらく。歌謡曲感ということの延長線上なのかもしれないですけど、アニメっぽいメロディだったりピアノのフレーズが入っていると言われて、確かにそういう耳で聞き直したら、そうなんですよね。ジブリっぽさというか…久石譲的なものを連想させる要素が意外と入ったりしているのかもなあ、と思いました。
[[SplitPage]]勇気づけられたのはSTRUGGLE FOR PRIDE。音源ももちろん聴いてますが、やっぱりライヴですかね。
■おふたりとも育ちは日本ですか?
n:俺はニュージーランドに90年代の5年間くらい住んでいたことがあります。
■J-POPが日本から耳に入ってきて意識したりとかは?
n:当時はJ-POPを聴きたかったですけどインターネットもなかったから簡単に聴けなかった。憧れはありましたけど。
■janさんは?
j:俺は幼少期から日本です。
■では日本の音楽には10代のときから普通に触れていて。
j:それがあんまり……母が好きな洋楽が家ではよくかかっていましたね。ニルヴァーナとかPJハーヴェイとかその当時のリアルタイムなもの。
■それでも滲み出てしまう日本の土着感というのがある意味魅力ということですかね。何かミーム的に受け継がれているものが無意識に入っているのかも知れないと……。ちょっと話を変えて、アルバムのタイトルについてですが、「Fracture」という単語には「骨折」とか「硬いものが玉砕する」とか、ちょっと物騒な意味であったり、または「複雑性」という意味もあるみたいですが。
j:辞書をひいて大体初めに出てくる意味は「骨折」ですね。
n:これは実際の経験談から来ているタイトルです。
■骨折の経験ってこと?
n:そうなんです。このアルバムのジャケットの打ち合わせも兼ねてアートワークをやってくれたChim↑Pomたちと飲んだ日の帰りに、泥酔していて高円寺の住宅街で足を折ったんです。
野田:もう治ったの?
n:大体。まだボルトとか鉄板入ってるんですけど。
■え、けっこうな骨折だ。
n:で、アルバム・タイトルをどうしようって考えていたときに、「骨折」って英語で何ていうんだろう、って調べて。単純に「broken bone」だと思っていたけど、「fracture」っていう言葉があると知って。しかも、janが過去に映画に出ていることがあって、そのタイトルもまた「fracture」で。あ、これタイトルに良いかもなって思ってすぐjanに相談しました。骨が折れる、硬いものが壊れる……破壊、と連想をしていくなかで、僕らがいま生きている2017年~2018年の渋谷を見ると、ビルがどんどん壊されて再開発されている。そこから、時代とも「fracture」というワードが共鳴しているかも知れないと思って、俺の肉体とこの街との繋がりもある、と。初めはそんなに意味を持たせるつもりもなかったんですけど、自然とそうなっていった。
■仮にこの曲たちからひとつ言葉を抽出せよとなったとき、「fracture」ってすごくピッタリなワードだと思いました。
n:そうですよね。その気もなく歌詞書いていたら、破壊と再生というイメージが立ち上がってきたというか。終わりからまた物語がはじまるといったイメージ。
■いきなり1曲目のタイトルが“THE END”という。ドアーズの同名曲はアルバムの最終曲でしたが、今作では幕開けの曲として置かれている。これにはなにかこうした意図があると思うのですが。
n:そう。曲順上これだけはこうした理由があって。アルバムを作るとなると、いままで作ってきたEPよりちゃんと曲順を考えなくてはならない。けれど、各曲歌詞も「これが最初で、これが次で、これがその次で」といったように時系列的に並べる感じではないし、どうやって決めようかなって思っていたんです。けどこのM1を“THE END”というタイトルにしたとき、ふと、映画も最後に“THE END”となって終わるけど、その映画の世界では明日もあるはずだ、と思って。終わりからはじまるなにかもあるはずだ、と思ったんです。
■ネガティヴなモチーフ、終焉、破壊、そして罪の意識、喪失、諦念が散りばめられながら、そして一方で再生への希望も求めている……。実際に「神」という言葉も出てくるし、キリスト教的世界観を強く感じたんですが、それはやはり意識して?
j:とくに意識的というわけではないかもしれません。宗教ついても興味を持っていろいろ勉強もしたんですけど、教義そのものというよりキリスト教美術のあり方が好きで、そういう文献を読んでいたりするから、自然とそれが反映されているかもしれない。そういったなかで、人が何かにすがったり祈ったりするプロセスが凄く美しいなと思うことがあって。地獄から天国へ這い上がる願望だったり、人間の根本的な祈りの心性に魅了されることが多いです。
■そういった祈りの賛美という感情がある一方で、諦めというか、すごく膿み疲れている感じというか……ある種の厭世的世界観とのバランスが興味深かったです。日本語訳詞を読んで「こんなダークなことを歌っていたのか」と驚きました。いま自身がそういうモードなのか、前々から本質的ににそういう傾向があるのか。
j:うーん。諦めがあって、しかし祈る気持ちが生まれて、けれどまた諦めて、みたいなエンドレスなループが常にあるかもしれないですね。
■衝撃的だったのが「悪魔」というモチーフが頻出でした。しかもその誘惑に惹かれている自己というのが描かれている気がして。歌詞のなかにそういった表現を入れるというのは勇気あることだなと思いました。これは、自らの弱さを表明しているのか、それとも純粋に「悪」というものへ憧れがあるのか。
j:いや、憧れと言うより、悪魔も神もどちらも美しい、という視点で物事をみたいということの現れだと思います。「神も悪魔だし、同時に悪魔も神である」という思いでいます。
■naomiさんもそういう世界の見方に対しては共感できる?
n:俺は直接的にはそこまで共感することはなくて……。俺の曲の場合は、あくまで物語というか、そこに作者たる俺の本心や主観的な感情が表れているっていうわけではないですけね。
■そのときに物語を駆動させるものは?
n:例えばさっきも話に出た渋谷の再開発で見えてくる破壊と再生というもの……。僕らが制作に至るまで、そして歌詞が完成するまでの日々の歩みですね。それこそ、こうやってみなさんと知り合って話すなかで感じたこととか、友だちと飲んで骨折ったこととか、飲みすぎちゃったこととか、そういったことがベースにあるんでしょうね。
■いまの時代これくらいダークな力がある歌詞って珍しいなという気がしました。アメリカン・ゴシックのような世界、例えばある時期のジョニー・キャッシュとか、デヴィッド・リンチとか……それを渋谷っていう風景にオーヴァーラップさせると、ここで描かれているような世界になるのかな、とも思いました。
j:どこにでも潜んでいる伝統的な悪のエネルギーみたいなもの、絶対に変わらない悪のようなものが少しでも輪郭化されて、認識することができれば、逆に恐れがなくなるんじゃないかな、って思うことがあって。無視することでは恐れは解消できないけど、認識することで怯えがなくなるのではないか、というような。
■見ないことによって却って知らぬうちにその悪に取り込まれてしまうかも知れない、というね。怖いものをあえて見ることで強くなる、という感覚は分かる気がします。いまの「恐れ」ということで思い出しましたが、やはりこの音楽の、特異ともいうべき静かさについても伺いたいです。静かさって、リラックスもさせるけど時にすごく不安を喚起させもしますよね。子供の頃、周りが静か過ぎることで逆に泣き出してしまったりとか。
J:わかります。
■「静か」というのは心地いいということだけではない、という意識があるのかなと思ったのですが。
j:naomiさんと一緒に音楽を作りはじめた時期、反骨精神のある音楽がすごく好きで。そのなかで何がいちばんパンクなのかって考えるときに、もちろん大きい音を出して真正面からぶつかっていくのもすごくカッコいいんだけど、東京の渋谷で、絶えず様々な音が無秩序に鳴っているところで、それを「フッ」と止めるというようなことがもっとも、パンクかな、と思ったんです。
■なるほど。コデインとかロウとか、かつてスロウコアと呼ばれたバンドたちも、ポスト・ハードコア的文脈から出てきたということを思い起こさせる話ですね。わちゃわちゃしたものがレベル・ミュージックの主流だと思われがちなところに、カウンター加えてやろう、というような?
j:そうですね。
野田:では自分たちが勇気づけられた音楽ってなんですか?
n:STRUGGLE FOR PRIDE。音源ももちろん聴いてますが、やっぱりライヴですかね。
野田:いつ観たんですか?
n:「RAW LIFE」の頃に初めて観て。
■それはどういう意味で勇気づけられたんでしょう?
n:「音楽をやろう!」って思ったんです。「俺もやりたい!」って。みんなが楽しそうにしていて。「RAW LIFE」とか「CHAOS PARK」とかで、大きな規模じゃなくても、自分たちで手作りの楽しい空間が作れるんだ、っていう気持ちを持った。僕らもいつも飲食店とかでライヴをするけど、店の人と俺たちとお客さんだけで勝手にやっている感じ。そういうのはあの時の経験に勇気づけられているかもしれないです。
■janさんは?
j:具体的に「この出来事」というのはないんですけど、聖歌かな。いろんな音楽を聴いて、ああだこうだいろいろ考えはじめちゃうときに、ふとグレゴリオ聖歌のレコードをかけたりする。自分の心臓の鼓動だけ聞いて、それに正直にいれば良いんだという気持ちに戻れる。
■僕は聖歌を聴いていると美しいなと思うと同時にちょっと空恐ろしくなってくることもあって……。
j:そういう風に感じるプロセス自体も一気にフッとなくなって、子宮のなかにいる胎児のような気持ちになる。完全に無意識に状態になれる。瞑想とは違うんですけど。普段の生活で人と話したことなどは、記憶としては蓄積されていくんだけど、その記憶のなかにだけに埋もれないようにする。その、埋もれないでいられるというこが喜び。
■お話しているとふたりで本当にタイプが違いますね。
野田:そうだよねえ。SFP v.s.聖歌だもんね(笑)。
■違いもあるけど、でも一緒に演っていると。
野田:むしろ違いがあるからこそ合うんじゃないですかね。
■具体的な方向性は違えど、ふたりともエクストリームなものが好きってことは共通しているということですかね?
n:ハッとさせられるものが好き。
■変にバランスを取ろうとしているものより振り切れたものが好き?
n:うん。
j:エクストリームなもの、例えばノイズとか聴いていても、俺は聖歌と同じ様に聞こえることもあったりしますね。
■音楽以外にもいろいろファッションやアートにも興味があって実際にも繋がりがあると思うのですが、それらについてもやはりエクストリームなものが好きですか?
j:うん。
n:好きですね。
例えばさっきも話に出た渋谷の再開発で見えてくる破壊と再生というもの……。僕らが制作に至るまで、そして歌詞が完成するまでの日々の歩みですね。
 jan and naomi Fracture cutting edge |
野田:アートワークをChim↑Pomにお願いしようと思った理由は?
n:Chim↑Pomとは去年の夏に出会って、彼らのイベントに呼んでもらってライヴをやって。ジャケットは自分たちがやるよりも誰か外部の人に頼みたいなってずっと思っていて、誰か面白い人いないかなって考えていた時、年末に新宿で演ったライヴにまたChim↑Pomが観に来てくれて。ちょうどレコーディングも中盤に差し掛かっていて、そろそろアートワーク周りの話を本格的にしなきゃなってときに彼らに再会したから、その場のインスピレーションで「ジャケの制作とかやるんですか?」って訊いてみたら「いいよ」って言ってくれたので、お願いすることしたんです。
■内容はChim↑Pomに一任って感じ?
n:そうですね。いくつか提案してもらって、その中から一つだけ選ばせてもらいました。
■(ジャケットを見ながら)これって、琥珀ですかね……? 琥珀のなかに何かが入っている…?
j:いや、ドラム缶なんですよ、それ。
n:ドラム缶の中にエリイちゃんが入っているのを実際に上から撮ったらしいです。
■え! そんなんだ。全然気づかなかったけど、そう言われてみるとたしかに人間が入っている。
j:ドラム缶に閉じ込められている女性っていうのが、寂れゆく都市、再生していく都市というこのアルバムの世界観に合っていると思います。
■なにかの動物の受精卵のようなものかな、とも思いました。
n:そういう解釈もいいですよね。蓄光印刷にしてもらったので、これが暗闇で光るんですよ。それも受精卵とか、かぐや姫のような感じがあっていいなと思う。
野田:俺は繭のなかに人間がいる、と思ったんだよね。jan and naomiの音楽はどこかシェルターっぽいから、そのなかにいる女の子というふうな見方だった。まさかドラム缶だったとは。Chim↑PomとかSFPとか、渋谷の話とか、基本的にjan and naomiはアティチュードがパンクなんだね。
n:そうだと思います。だから、ジェイムス・ブレイクとボン・イヴェールに対して興味ないのも理解してくれました(笑)?
◎ツアー情報
【Fracture tour 2018】
2018年6月23日(土) 北海道・札幌PROVO
前売り:¥2,500 (税込・1Drink別)
PROVO電話予約:011-211-4821
メール予約:osso@provo.jp ※お名前・人数・連絡先をメールにてお送りください。
【問】PROVO 011-211-4821
2018年7月14日(土) 福岡・UNION SODA
前売り:¥2,500 (1Drink別)
チケットぴあ P-コード: 118-465
Live Pocket : https://t.livepocket.jp/e/4dw_4
メール予約 : info@herbay.co.jp ※お名前・人数・連絡先をメールにてお送りください。
【問】HERBAY 092-406-8466 / info@herbay.co.jp
2018年7月16日(月祝) 京都・UrBANGUILD
前売り:¥2,500 (1Drink別)
Urbanguild HP予約:https://www.urbanguild.net/ur_schedule/event/180716_fracturetour2018
ePlus:https://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002262177P0030001
【問】Urbanguild 075-212-1125
2018年7月21日(土) 東京 ドイツ文化会館 OAGホール(6/9チケット発売)
前売り: 立ち見¥2,500・座席指定¥3,500 (1Drink別)
ePlus:https://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002262177P0030003
【問】Slowhand Relation inc. 03-3496-2400
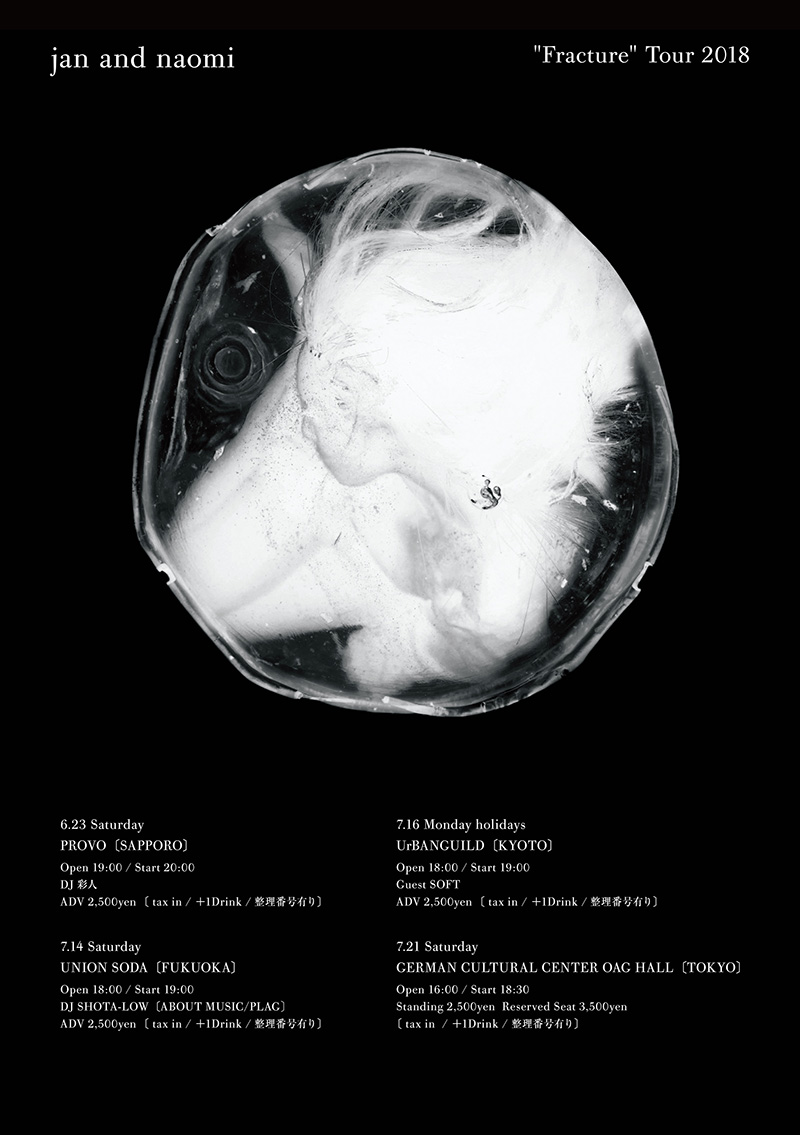
◎イベント出演
7/6 TOKYO CUTTING EDGE vol.02
@ liquidroom open/start 24:00
ticket now on sale
Line Up:長岡亮介 / jan and naomi / WONK DJ:SHINICHI OSAWA(MONDO GROSSO) / EYヨ(BOREDOMS) / DJ AYASHIGE(wrench)
https://cuttingedge-tokyo.jp/