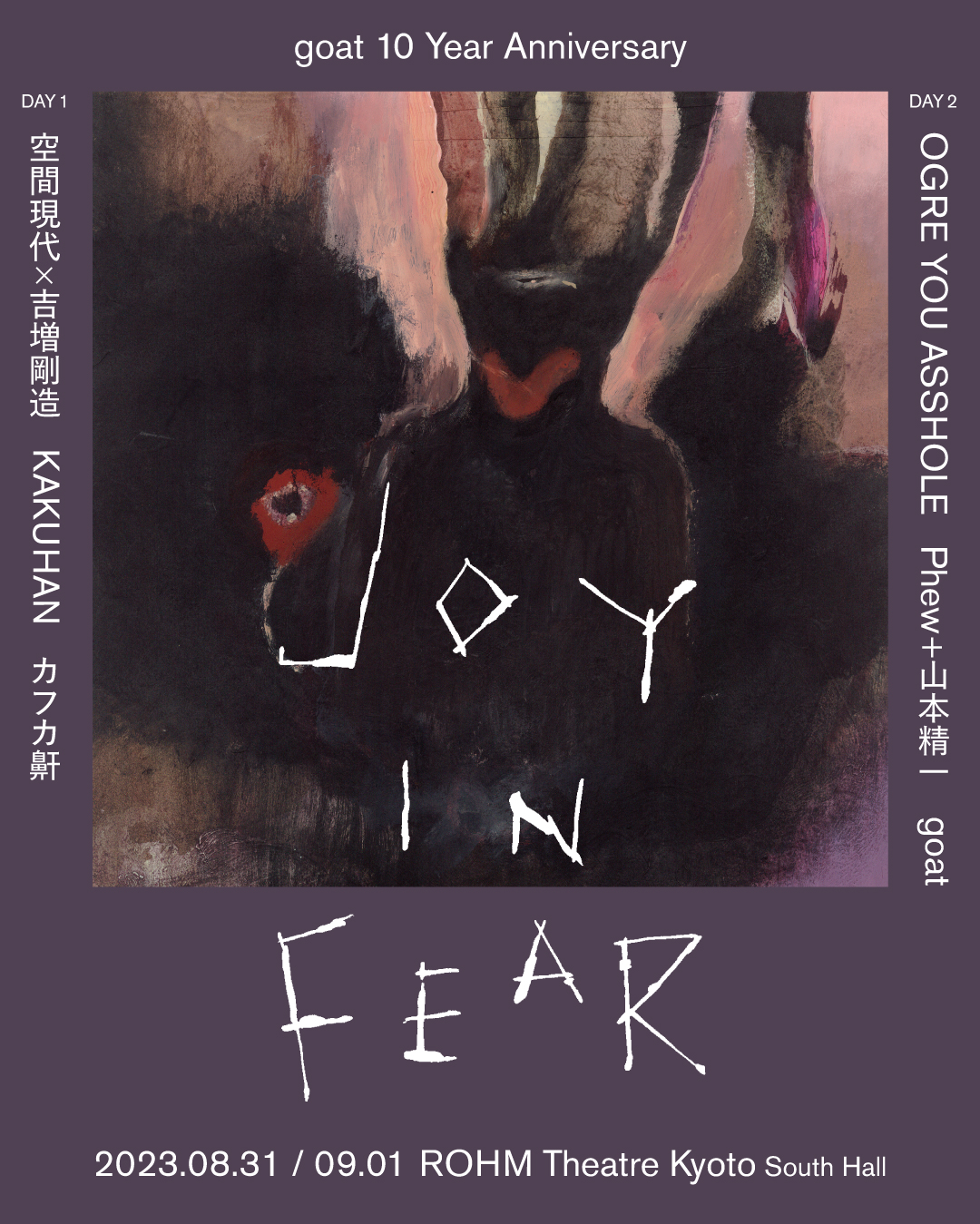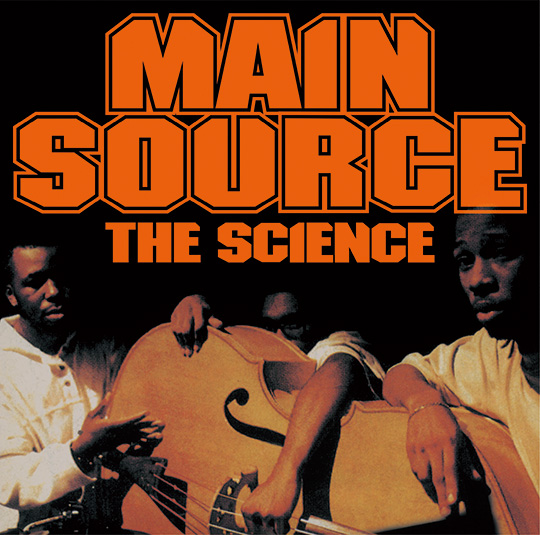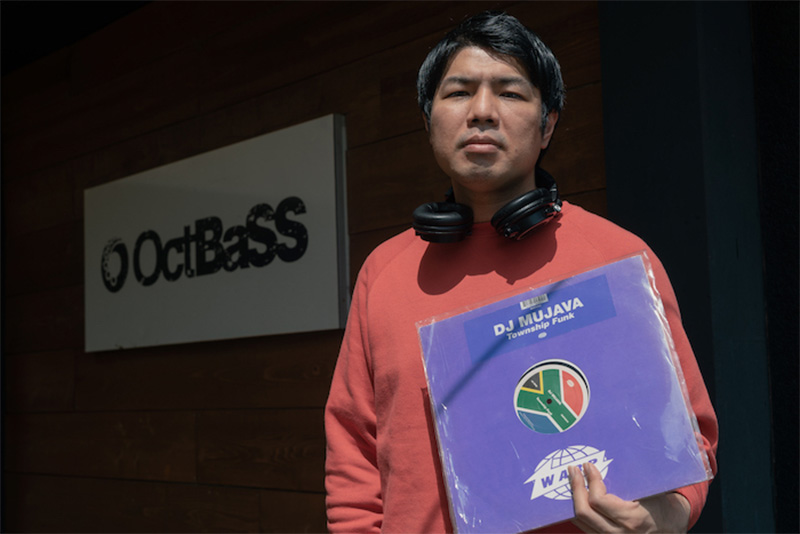韓国のハードコア・シーンを先導するソウルのバンド、SCUMRAID。そのドラマーである JUYOUNG が楽器をギターに持ち替えヴォーカルも担当、東京のガレージ・シーンで活躍するドラマー YAKUMO(MAGNATONES/TOKOBLACK)とともに結成したバンドが THE VERTIGOS だ。新ベーシスト Sako を迎えて完成させたファースト・アルバム『LIVE TODAY ONLY』が今週発売されている。疾走感あふれるパンク・サウンドに注目しよう。
THE VERTIGOS 待望の1st アルバムが本日遂にリリース!!
韓国HARDCOREバンドSCUMRAIDのドラマー JUYOUNG(Vo/G)、東京GARAGEシーンでMAGNATONES・TOKOBLACKでも活動しているYAKUMO(Dr)が中心となり結成されたTHE VERTIGOSが新ベーシストSakoを迎え入れ、1st Album『LIVE TODAY ONLY』を本日リリース!

コロナ禍に曲を創作し2019年に発売し評判となった1st シングル盤を完売させて以来のリリースとなる今作は、ドライブ感が増しよりパワーアップした作品となっております!
[THE VERTIGOS - LIVE TODAY ONLY Official Teaser]
https://youtu.be/lwa-283kUIA
[Streaming/Download/Order]
https://p-vine.lnk.to/581pMM

[リリース情報]
アーティスト: THE VERTIGOS
タイトル:LIVE TODAY ONLY
フォーマット:CD/LP/DIGITAL
CD:
発売日:8月16日
品番:PCD-25370
価格:¥2,500+税
LP:
発売日:2024年1月24日
品番PLP-7678
価格:¥3,980+税
[収録曲]
Live today only
I don’t mind
Stuck
Tiger fur
Picky
Focus on yourself
Out of my head
꿈이야 생각하며 잊어줘 (Forget me as if it was a dream)
Unseen world
Something to me