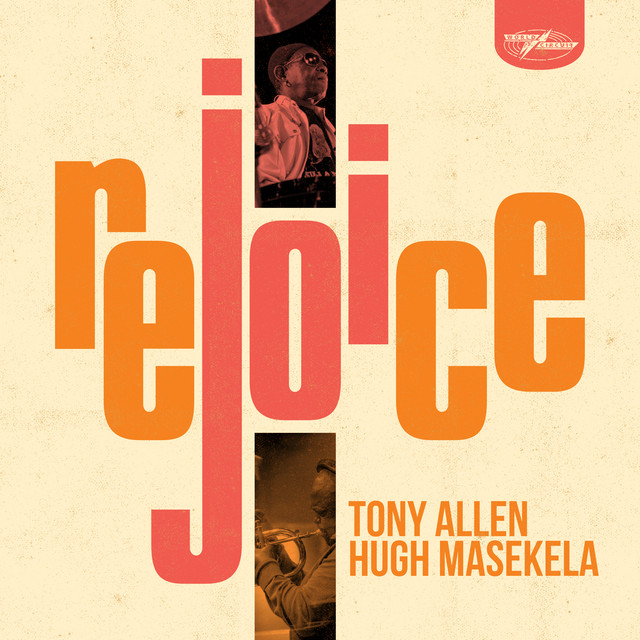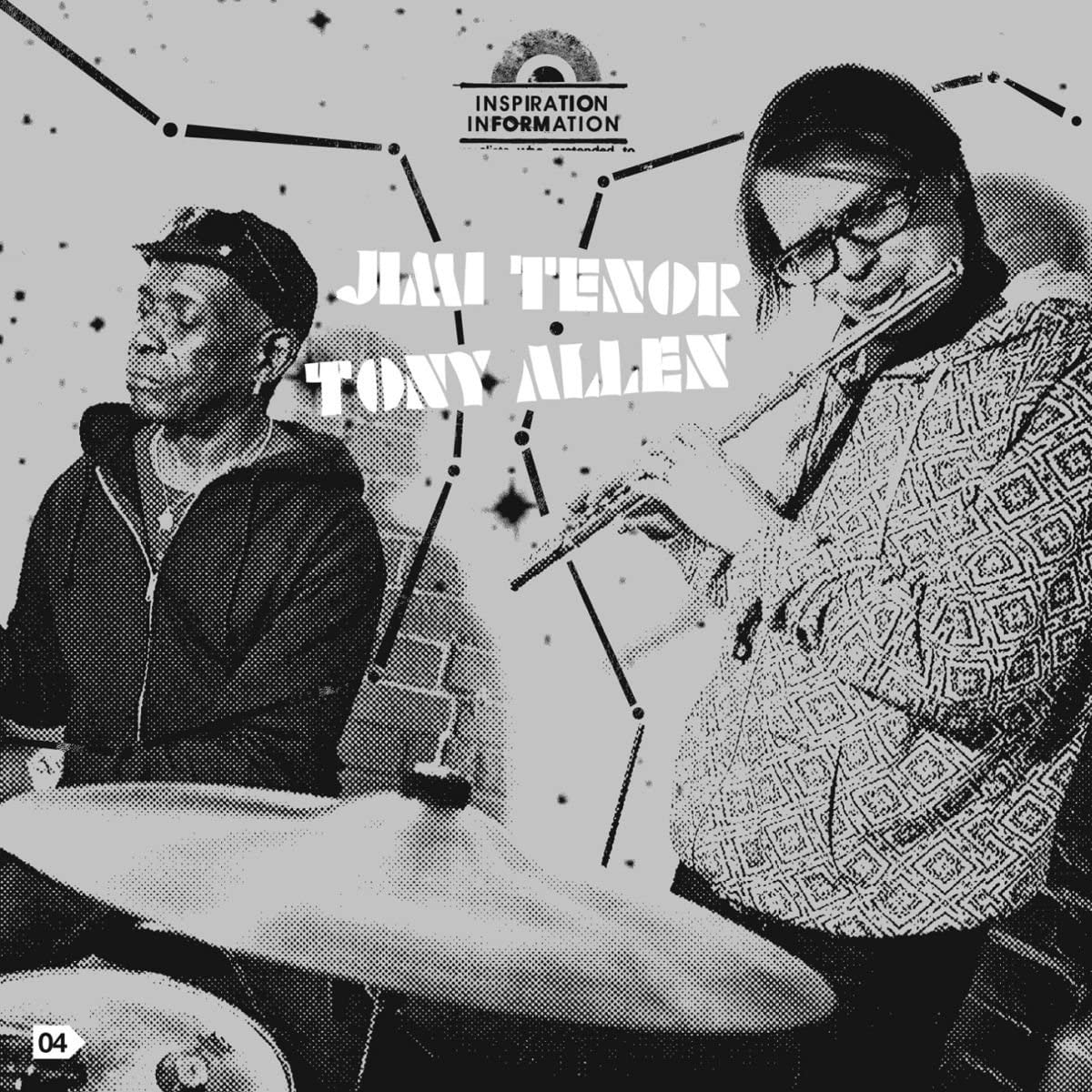MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > News > RIP > R.I.P. Tony Allen

文:増村和彦
誰よりもオリジナリティを湛えたドラミングで僕たちを踊らせて、何よりも僕たちを解放に導いてくれたトニー・アレンがいなくなってしまった。
「一部のドラマーは、ソフトに演奏するという意味を知らない、彼らの辞書にないんだ」彼は2016年にそう言った。「私のドラムは派手に盛り上げることだってできる。が、しかしもっと繊細に叩くことだってできる。その音は、まるで川がながれるように聞こえるだろう」
あらためてソフトに演奏するということに思いを馳せる。
“アフロビート”の向こう側に見える“アフロなビート“の醍醐味のひとつは、ひとりひとりが叩き出すリズムはシンプルながら、それらが絡み合ったとき形成される大きなうねり。ダイナミック且つロジカルで、究極の共同分担作業。もうひとつは、うねり続けることによって得られる高揚感。いつの間にか思考が薄れ、渦のなかにただいるかのような感覚。繰り返しに気持ちよさを感じる経験は演奏しなくても誰しもきっとあると思う。そして、そのビートは多くの場合ダンスと密接な関係を持つ。
トニーは、ドラムという楽器でこれをひとりでやってしまった。右手、左手、右足、左足にそれぞれドラマーを湛え、それらは絡み合ってタイトにうねる。そして、そのビートは踊らすこと以外のためにはないと語る。トニーが抜けたあとのアフリカ70に、複数のドラマーが必要だったという伝説も頷ける。
“アフロビート”には大いに“アフロなビート“の影響があると思いたい。その上で“アフロビート”たらしめたのは、もう散々伝えられている通りジャズの影響だった。トニーは、バップ・ドラミングとりわけアート・ブレイキーのドラミングを聴いて、ひとりではなく、まるで複数人で叩いているように聞こえたそうだ。あなたのドラムを初めて聴いた時、全く同じことを思ったよ!
たしかに、フレーズがバップまんまなところがあるというのはわからないでもないが、そんなことではなくて、キック・スネアもフレージングの一部にしていくバップのアイデアと、“アフロなビート“感覚の融合が、“アフロビート”を生み出す原動力になったのではないか。トニーのドラムは、いつも同じ匂いがしながらも、よく聴くとフレーズの多様さに溢れている。トニーが叩いていると一聴しただけでわかるのに、全く同じフレーズというものがない。覚えたフレーズを使うのではなくて、自在に四肢でフレージングさせていく。しかも、踊らせることを忘れることなく、複雑なことをやっているようで、その実はシンプルだ。これは本当にすごいことだ。あなたのドラムを初めて聴いた時、頭にスネアがバシッとくるだけで面食らったよ!
もっともジャズに近いけど絶妙に所謂スイングはしないニクいハット、変幻自在で流れるようなスネアワーク、タイトなベードラ、嵐のようなフィルとそのあとのスネア頭一発、どれもしびれ上がるけど、どうやらそれらを操っている部分があることに段々気づいてきた。おでことおへそが、みぞおちの辺りで繋がっている感じ、第三のチャクラとかスポットとかいろいろな呼び方があるのだろうが、そういえば、ブレイキーも、ケニー・クラークも、バップドラムをさらに進化させたエルヴィン・ジョーンズもそこで叩いているような気がしませんか。常にリラックスしながら、たとえ音が小さくても太鼓がとても気持ちよく響き、フィルの瞬間風速は凄まじく、いつまでも止まらないかのようなビートで踊らせてくれる。
ソフトに演奏するって、こんなことらなんじゃないかなって思いながら書いていたけど、きっとそれだけじゃないですよね。「川のように流れていく(flowing like a river)」ドラム、わかる気もするけど、まだわかっていないことのほうが多い。でも、これからも多くの気づきを与えてくれそうな感じがするのも楽しみで、ずっと聴き続けたくなります。
60年代フェラ・クティと出会った頃すでに“アフロビート”ドラミングのスタイルを確立していたみたいだけど、フェラ・アンド・アフリカ70の映像を見ると結構ガシガシやっているのも見受けました。“アフロビート”は集団戦。強烈なクティの個性だけを聴く音楽ではなくて、数え切れないほどステージにいるもの全員が合わさって“アフロビート”だ。そしてそれをひとつにまとめあげたのが、トニー・アレンの発信と説得力の塊のようなドラミング。フェラ・クティとトニー・アレンが“アフロビート”を創り出した。
トニーズベストに挙げる人も多いだろう、トニー・アレン・ウィズ・アフリカ70は、勢いとリラックスが同居して、まさに油の乗った様がかっこいい。"Jealousy"の鍵盤は何度聴いても気持ちよいです。その直後のトニー・アレン・アンド・ザ・アフロ・メッセンジャーズは、めちゃくちゃ渋い。『No Discrimination』というタイトルからしてもっとも勇気を与えてくれる作品のひとつだ。
円熟味は増し続け、ジャンルを越えた様々なコラボレーションは、僕たちを解放へ向かわせてくれる。オネスト・ジョンズが熱心に再評価し続けたこともあり、南ロンドン勢の生きた影響を感じられる作品たちも興味深い。「でもさ、実はみんな同じものじゃない? ハウスにジャズ云々、いろいろとジャンルはあるものの、要は同じ。誰もがあらゆるものを分け隔てなく聴いている、と。ほんと、ソウルフルな音楽か、リズミックな音楽かどうかってことがすべてなんだしさ」カマール・ウィリアムスのこの言葉は、そのままトニーの軌跡にも当てはまるだろう。
最近のジャズに還ってきたかのような作品群では信じられないほど四肢の動きが小さいまま、踊らせるのも見受けました。文字通り「to play soft」の極意が最高まで達したかのようなドラミング。
「ベストであること。それは他の誰かと同じことすることではない。ベストであることとはつまり、他の誰かがそこから学べる、それまでなかった何かを創造し、残すことである」
たしかに、あなたはいままでもこれからもあまりに大切なものを生み出して、変遷を辿れば辿るほどに、ボクたちに多くの気づきを与えてくれている。
“I wanted to be one of the best — that was my wish,“
たしかに、あなたは間違いなく最高中の最高だ!
文:小川充
文:増村和彦、小川充
| 12 |
NEWS
- Seerkesinternational——カナダのいまもっとも面白いダブ・アーティストが来日、真夏のダブの祭典がはじまる
- VINYL GOES AROUND PRESSING──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Brian Eno──観るたびに変わるドキュメンタリー映画『ENO』のサウンドトラック収録曲のMVが公開、発掘された90年代イーノの姿
- Overmono──10月に来日するオーヴァーモノ、新曲が公開
- Kim Gordon and YoshimiO Duo──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Mighty Ryeders──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Lusine──エレクトロニカのヴェテラン、ルシーンが11年ぶりに来日
- Meitei──延期となっていた冥丁のツアー日程が再決定、11都市を巡回
- Mica Levi──ミカ・リーヴィが〈ハイパーダブ〉から新曲をリリース
- Tribute to Augustus Pablo──JULY TREEにて、オーガスタス・パブロ関連の写真やゆかりの品々などを展示、およびグッズ販売
- Kinnara : Desi La——ele-kingでお馴染みのデジ・ラ、1日だけのポップアップ
- John Carroll Kirby──ジョン・キャロル・カービー、バンド・セットでの単独来日公演が決定
- VINYL GOES AROUND──「静かな夜」がテーマのコンピレーション、アンビエントやジャズからメロウで美しい曲を厳選
- Li Yilei Japan Tour 2024——中国人サウンドアーティスト/作曲家リー・イーレイの初来日ツアー決定
- Terry Riley——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Koshiro Hino + Shotaro Ikeda──日野浩志郎と詩人・池田昇太郎、3年にわたるプロジェクトの初回は小野十三郎から触発された音楽公演
- Theo Parrish──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場
- Aphex Twin──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場
- Jeff Mills──早くも送り出されたジェフ・ミルズのニュー・アルバムはメンタル・ヘルスを守ることがテーマ
- Burial / Kode9──ベリアルとコード9によるスプリット・シングルがサプライズ・リリース
R.I.P.
- R.I.P. Steve Albini- 追悼:スティーヴ・アルビニ
- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木
- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー
- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー
- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン
- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル
- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート
- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター
- R.I.P. 鮎川誠
- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン


 DOMMUNE
DOMMUNE