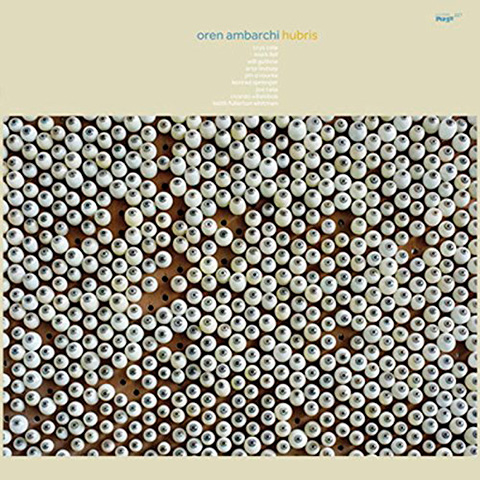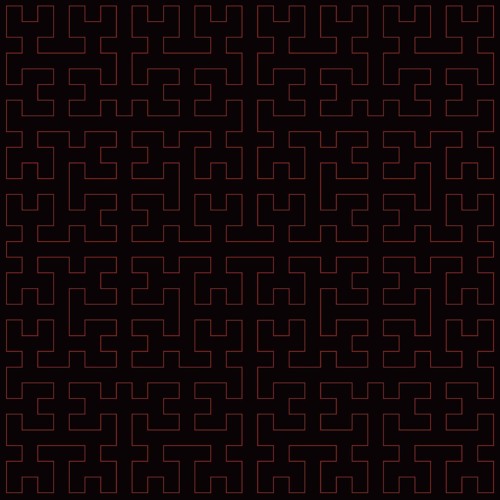MOST READ
- Columns 大友良英「MUSICS あるいは複数の音楽たち」を振り返って
- 別冊ele-king 音楽が世界を変える──プロテスト・ミュージック・スペシャル
- Milledenials - Youth, Romance, Shame | ミレディナイアルズ
- Loraine James ──ロレイン・ジェイムズがニュー・アルバムをリリース
- Dolphin Hyperspace ──凄腕エレクトリック・ジャズの新星、ドルフィン・ハイパースペース
- KMRU - Kin | カマル
- Squarepusher ──スクエアプッシャーのニュー・アルバムがリリース
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Deadletter - Existence is Bliss | デッドレター
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- ele-king Powerd by DOMMUNE | エレキング
- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Jill Scott - To Whom This May Concern | ジル・スコット
- Free Soul × P-VINE ──コンピレーション・シリーズ「Free Soul」とPヴァイン創立50周年を記念したコラボレーション企画、全50種の新作Tシャツ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- Cardinals - Masquerade | カーディナルズ
- Laraaji × Oneohtrix Point Never ──ララージがワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日公演に出演
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
Home > Reviews > Album Reviews > Oren Ambarchi & Thomas Brinkmann- The Mortimer Trap

さすがに「ドローン」も......というところで新機軸か。この数年、待ち続けた「テクノ」とのコラボレイションがようやくお目見えである。
オーレン・アンバーチはオーストレイリアのギタリストかつパーカッショニストで、いわゆる実験音楽や即興演奏では中堅的存在。ゼロ年代に入ってからはディジタル・プロセッシングを軸にドローンを多様化させ、フェン・オ・バーグの3人などコラボレイションの相手には事欠かない位置にいる。エレクトロニカとも袖摺り合う距離にいて、いわゆるアブストラクト表現を大量にアウトプットしてきた。ブラック・トラッフルは彼が主催するレーベル。
一方のトーマス・ブリンクマンはマイク・インクを追ってケルンから頭角を現したクリック・テクノのヴェテラン。リッチー・ホゥティンとのインターフェイスなどアカデミックなヴァリエイションで名を挙げ、数々のアノニマス的なプロジェクトに加えてブラック・ミュージックのカット・アップを多用した「ソウル・センター」のシリーズなども人気。4年前にタキシードムーンのウインストン・トンをヴォーカルに迎えた『ウェン・ホース・ダイ......』以降、久々のリリースとなる。
この2人が取り組んだのは、現代音楽家のモートン・フェルドマンが残した『フォー・ブニータ・マーカス』というピアノ曲にヴァリエイションを与えること。フェルドマンの作品には表面的には静かなものが多く、アンビエント・ミュージックとして機能するものが多い(裏アンビエントP34)。しかし、創作の動機を先に推測してしまうと、この2人の念頭にあったのはスティーヴン・オモーリーとピタによるKTLではないだろうか。ドゥー ム・メタルをエレクトロニカの次元へ持ち去ったKTLからメタルの要素を取り除き、ドローンに違う道筋を与えようとしたのではないかと。実際、ブラック・トラッフルのスリーヴ・デザインはすべてオモーリーが手掛けていて、お互いの作品を意識しやすい距離にいることはたしか(今回に限ってはブ リンクマンがデザインも担当している)。
とはいえ、まず念頭にあるのは『フォー・ブニータ・マーカス』で、オリジナルで試みられているものとはすべてが異なって感じられる。フェルドマンのそれと聞き比べてみるとよくわかるのだけど、音階とリズムで「間」を聞かせようとするオリジナルが必然的に不条理を演出してしまうのに対して、隙間なく音を詰め込んでしまうともいえるドローンは常にリスナーを音で包み込んでいるようなもので、どこかに投げ出されるような感覚を与えることはない。この2作を同時に再生してみると、まった くぶつからずにひとつの曲に聞こえてしまうことからもその相反性は証明されたも同じだろう。
また、前者のリズム感覚には緊張感を持続させようという意図があるのに対して、アンバーチ&ブリンクマンによるそれは引き伸ばされたダブに聞こえるほど瞑想性が高く、むしろリラックス効果に重点が置かれているとさえいえる(こういうものを聴き付けない人には同じかもしれないけれど)。緊張感をもたらす要素としては単純に音量を上げたり、トーンをうねらせるなど、それもマッサージの強弱のような範囲で推移し、正直、どこにヴァリエイションを生み出そうとする動機があったのか、正確には掴みかねてくる。この差は、しかし、現代音楽のフェルドマンと実験音楽として分類されるアンバーチの距離(=時代性)のなかにも存在はしたものだろうけれど、そのポテンシャルを最大に引き出したのが、やはり、ブリンクマンであり、テクノだということは間違いない。あるいは、従来のドローンとは違うものに聞こえるのはテクノが原因だとしか言いようがないのではないだろうか。
まったく代わり映えのしないダンス・ミュージックとしてのテクノも健在だし、モーリツ・フォン・オズワルド・トリオのようにファンク・ミュージックとしての成熟を志すもの、あるいはハーバートのようにジャズとのハイブリッドを作り出すものなど、テクノにも明確な分岐が散見できるなか、ここで試みられていることは(アルヴァ・ノトの軌跡と同様)90年代にテクノが普遍化させた快楽性を抽出し、他のジャンルへ移植し、その機能性を全うさせることだろう。さらにいえば、テクノとドローンが結びつくということは、90年代とゼロ年代のアンダーグラウンドにひとつの横断線が敷か れたということでもある。冒頭の「ようやく」というのは、そういう感慨でもある。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Milledenials - Youth, Romance, Shame
- KMRU - Kin
- Deadletter - Existence is Bliss
- Cardinals - Masquerade
- Jill Scott - To Whom This May Concern
- Amanda Whiting - Can You See Me Now? + The Liminality Of Her
- xiexie - zzz
- Cindytalk - Sunset and Forever
- CoH & Wladimir Schall - COVERS
- KEIHIN - Chaos and Order
- DIIV - Boiled Alive (Live)
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations


 DOMMUNE
DOMMUNE