MOST READ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- aus - Eau | アウス
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Reviews > Album Reviews > Alva Noto- UNIEQAV
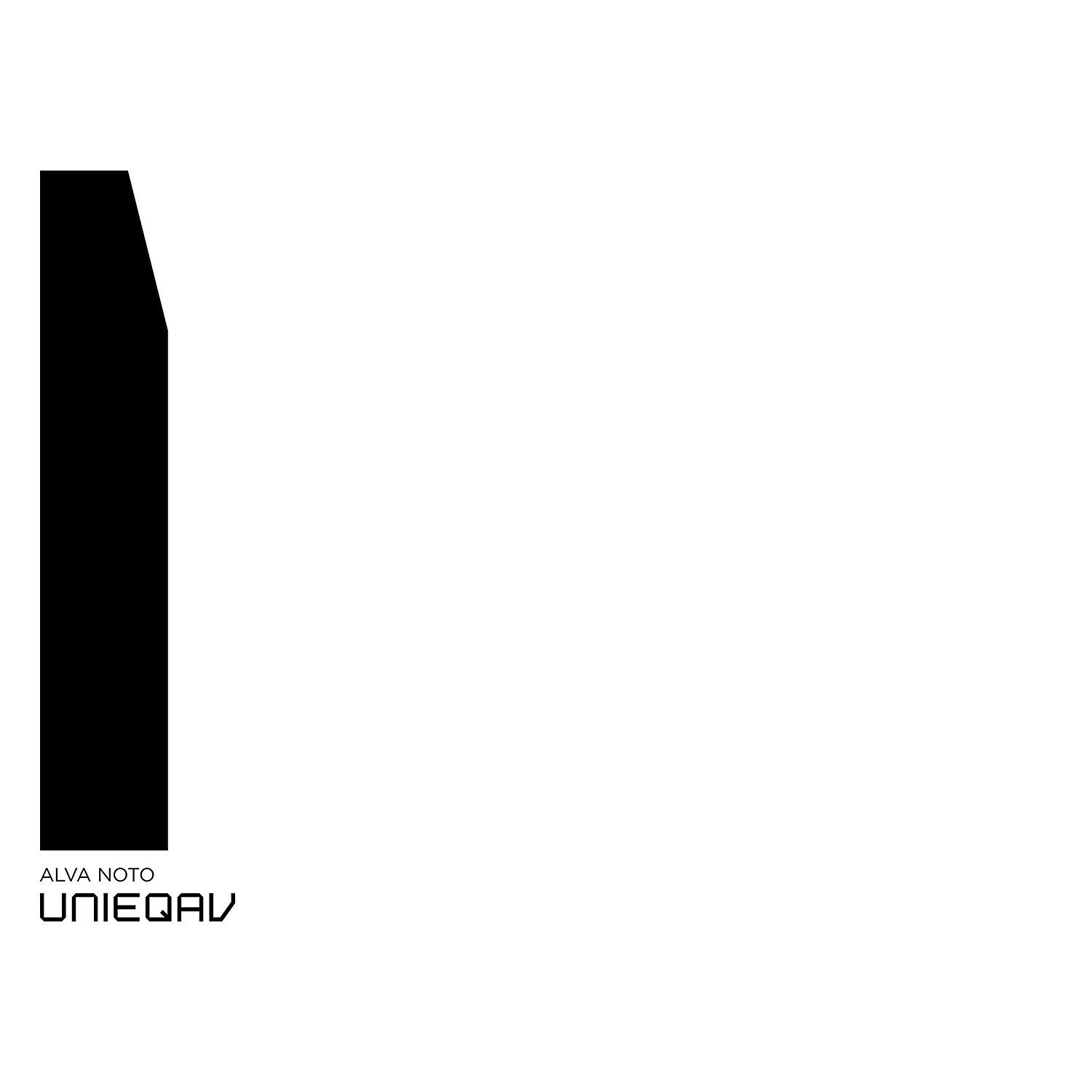
本作『UNIEQAV』は、カールステン・ニコライの新レーベル〈ノートン〉におけるカールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトによる初のソロ・アルバムであり、同時に08年の『UNITXT』、11年の『UNIVRS』から続いてきた「UNI」シリーズの完結編でもある。
ここで「UNI」シリーズについて簡単に説明しておこう。まず、00年代中盤以降のアルヴァ・ノトが〈ラスター・ノートン〉で展開した連作シリーズはふたつあった。ひとつは「UNI」シリーズ。もうひとつは「ゼロックス」シリーズである。「ゼロックス」シリーズは07年に「Vol.1」、09年に「Vol.2」、15年に「Vol.3」が発表され、このシリーズも三作目で一区切りをつけたようだ。ゼロックスの名前のとおり「コピー」をテーマとしたアンビエント・ドローン連作である。
対して「UNI」シリーズはリズミックなトラックを中心に収録するシリーズだ。発端は「アルヴァ・ノトが数十年前に東京のクラブ“UNIT”にブッキングされた際、その環境に応じたサウンドを作り出そうとしたのがきっかけ」という。つまり最初から「クラブユース」のトラックであることを目指していたようである。
同時に『UNITXT』の後半部分で聴かれるように、音素からノイズ領域に還元された音響もサウンドの特徴を形成していたことも大きな特徴であった。いわばリズム/ノイズという音楽・音響の構成要素を素材の状態から再蘇生するように突き詰め、サウンド/トラックの生成・構成・構築を行っているのだ。
その意味で「UNI」シリーズは00年代初期までの初期のサイン派のリズミックなコンポジションによるウルトラ・ミニマルな電子音響の流れにあるシリーズともいえる。コピー/生成という「ゼロックス」シリーズに近いテーマ性を読み込むことも可能だろう。
新作『UNIEQAV』においては、そんなカールステン・ニコライのリズム/ノイズの生成・構築が洗練の極を迎えていた。かつての過激なまでのウルトラ・ミニマリズムは影を潜め、実にエレガントで端正なテクノ・トラックである。細やかなリズム、高密度な低音、ミニマムな電子ノイズなどが、ときにダイナミックに、ときにしなやかにコンポジションされ、聴き手を音響の渦の中に巻き込んでいく。グリッチ・サウンドを経由した10年代後半的な「モダン・テクノ」といっても過言ではない見事なトラックだ。
この『UNIEQAV』では、そんなモダン・テクノ的なマシン・グルーヴに加えて、「ゼロックス」シリーズ(特に「Vol.3」)や、坂本龍一との共作である映画『レヴェナント』のサウンドトラックなどにあった音楽的な和声感覚もそこかしこに埋め込められてもいる。たとえば「ゼロックス」『レヴェナント』的な持続音で幕を開ける“Uni Mia”、その途中から鳴り始める「二つ目のコード」のように。
加えて「声」の導入も「UNI」シリーズの重要な要素である。カールステン・ニコライが「声」をトラック内に本格的に用いたのは、おそらくは「UNI」シリーズからのはず。そして「UNI」シリーズの「声」といえば、フランスの音響詩人アン=ジェイムス・シャトンである。
彼は〈ラスター・ノートン〉から11年に『Événements 09』、2012年にアルヴァ・ノトと、長年のコラボレーターであるアンディ・ムーアらとの共作で『Décade』をリリースしている。二作とも途轍もなくクールなヴォイス+電子音響だ。
そのふたりの最初の共作トラックが収録されたアルバムが、08年にリリースされた『UNITXT』であった。カールステンの電子音響トラックに、アン=ジェイムス・シャトンの無機的な質感の声がこれほどの見事なマッチングを聴かせるとは思いもよらなかった。それは電子音響ヒップホップとでも形容したいほどの「クールさ」だが、何より世界の満ちている資本主義社会的な記号=言葉を反復するヴォイスは、「UNI」シリーズが内包していた世界認識論を体現していた。じじつ、11年の『UNIVRS』にもアン=ジェイムス・シャトンは参加し、三文字の企業・団体名/ロゴの英字を繰り返し発声し、アルバムのメッセージを強く体現していた。
それは『UNIEQAV』の“Uni Dna”でも同様だが、前作までとは反対に、まずはトラックが先行制作され、そこにアン=ジェイムス・シャトンのヴォイスが重ねられたらしい(曲名どおりDNA情報に関するワードだ)。結果、アン=ジェイムス・シャトンによる「声」のリズムとアルヴァ・ノトのトラックのリズムの関係性が、ふたりのこれまでのコラボレーションから反転しているのだ。
ではカールステン・ニコライは、この『UNIEQAV』ではトラック優先で、ビートの可能性を追及したかったのだろうか。しかしそれはビートというより、ある法則で区切られた音の線=リズムというべきかもしれない。「声」もまた法則で区切られた音の分割=リズムである。じじつ『UNIEQAV』におけるリズムは、“Uni Clip”などで聴かれるようにキーボードをタイプする音にも聴こえるし、“Uni Sub”のベースの3連などは、アン=ジェイムス・シャトンの声のようにも聴こえる。横溢する分断されるリズム=音の線。
リズム。ノイズ。分断される音。これらが交錯する本作を聴いていると、不意にカールステン・ニコライが育った「東ドイツ」のことを考えてしまった。たとえば、彼が少年期などに耳にしていた東ドイツにおけるラジオ放送などを。
私見だが、この最先端の電子音響の本質には、どこかカールステン・ニコライの記憶の層が織り込まれているように聴こえてならない。もしかすると「東」に住むカールステン少年・青年は、(おそらくは検閲によって)消えかけて(分断された)ラジオ放送を耳にしていたのではないか、と。思えば「ゼロックス・シリーズ」の「Vol.3」もまたどこか記憶の旅のようなアルバムあったが、本作『UNIEQAV』も音楽のフォームは違えども、やはり、同様のものを感じてしまった。
サイン・ウェイヴ、グリッチ。ノイズ。マシン・リズム。90年代以降、ヒトから離れたマシン/エラーな音響作品を作り続けてきたカールステン・ニコライだが、00年代後期から10年代以降のシリーズ/アルバムには、彼の幼年期の記憶/人生も結晶しているようにも思えるのだ。20世紀後半、東ドイツの記憶。モダニズム建築。放送。ノイズ。音響。リズム。
そう、知覚を圧倒するテクノロジーの交錯による最先端電子音響/モダン・テクノ『UNIEQAV』が放つマシニック・リズムのむこうには、ヒトの記憶が、まるで光のように交錯し、反射しているのだ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations
- Ikonika - SAD
- Eris Drew - DJ-Kicks
- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet
- DJ Narciso - Dentro De Mim
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion
- Debit - Desaceleradas
- Sorry - COSPLAY
- K-LONE - sorry i thought you were someone else
- claire rousay - a little death
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer
- Roméo Poirier - Off The Record
- TESTSET - ALL HAZE


 DOMMUNE
DOMMUNE








