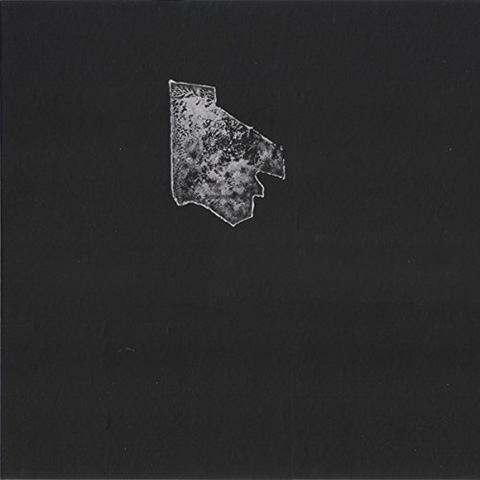MOST READ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50
- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催
- aus - Eau | アウス
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース
- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー
- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス
Home > Reviews > Album Reviews > Grischa Lichtenberger- Ostranenie

「Ostranenie(異化)」とは、1920~1930年代のロシア・フォルマリズムを代表するソビエト連邦の言語学者・文芸評論家ヴィクトル・シクロフスキーが提唱した概念・理論である(演劇の文脈ではブレヒトによる異化効果が広く知られる)。
芸術の役割は、「慣れ」によって鈍化した知覚を揺さぶり、対象をあらためて認識させることにある。それがシクロフスキーの主張だった。「見慣れたもの」を「見慣れぬもの」として再提示し、感覚の自動化に抗うこと。その装置としての方法論が「異化」なのである。
ドイツのサウンド・アーティスト/音楽家グリシャ・リヒテンベルガーの新作『Ostranenie』は、この「異化」の音楽的実践にほかならない。電子音響における緻密な実験で知られるグリシャ・リヒテンベルガーは本作『Ostranenie』において、もっとも親密で情緒的な楽器といえるピアノを軸に、その音を分解・再構築し、聴覚そのものの認知構造を問い直す。リリースはドイツの電子音響レーベル〈Raster〉から。
2012年に〈Raster-Noton〉からリリースされたファースト・アルバム『and IV [inertia]』以降、オウテカやカールステン・ニコライから影響を受けた作家として知られるグリシャ・リヒテンベルガーだが、このピアノ音響作品はキャリアにおける明確な転機といえよう。2019年に〈Raster〉からリリースされた電子音響とジャズの融合を試みた『Re: Phgrp (Reworking »Consequences« By Philipp G)』を経由して以降、自らの音楽をメタ的に再検証する試みともいえるアルバムに仕上がっていた。
本作『Ostranenie』に収録された全13曲は、いずれも1~3分ほどの即興的なピアノ小品で構成されている。冒頭の1曲目 “what lies beneath 3 arp” を聴いた瞬間、アーティストを間違えたのではないかと錯覚するほどだった。かつての彼の音楽からは想像もできない、ドビュッシーやラヴェルといったフランス印象派、あるいはサティを思わせるような響きがそこにはあった。モーダルな和声、あいまいな拍節、断片的な旋律が交錯する美しいピアノ曲だ。
だが、この『Ostranenie』に甘味料のような抒情はない。どの楽曲もフランス印象派のような響きを放ちつつも、どこか機械の音楽のような冷徹さを持っている。加えて4曲目 “spiderman” や5曲目 “chilling adventures of sabrina” あたりから現代的な音響編集とグリッチによる「断絶」が意識的に挿入されることで、音のエンヴェロープや残響も人工的に操作される。
グリシャ・リヒテンベルガー特有の精緻なデジタル処理によって構造はズラされ、音の質感は変容する。聴き込むほどに、ピアノの響きが原音のままではないことに気づかされる。曇り、濁り、にじみ、そして時に破綻していく音。深く崩れるリヴァーブ、歪んだエフェクト、断続的に挿入されるグリッチ。楽曲の「中心」はぼやけ、記憶の断片が浮かんでは消える……。そんな印象を残すアルバムなのだ。聴き手は、何かを思い出しかけているのに、最後まで辿り着けない。全体を通じて、そのような感覚が貫かれている、とでもいうべきか。情緒は徹底して削ぎ落とされている。
クラシカルとデジタルの境界線で、グリシャ・リヒテンベルガーが目指しているのは単なる20世紀印象派の再演ではない。いわゆるノスタルジーを拒絶しつつ、音楽とは情緒の装置という事実そのものを批評/解体し、なおかつその先にある「感覚の再起動」=「異化」を見出す。
グリシャ・リヒテンベルガーの関心は音楽による情動の喚起ではないのだ。むしろその情動の解体にある。ピアノという情緒的な媒介を使いながら、感情がいかに条件反射的に作動するかを露呈させ、「聴くこと」そのものを宙づりにしてみせる。「美しい」と感じた瞬間に、その感受性の自動性に切り込みを入れる。それが『Ostranenie』の核心といえよう。
加えてグリシャ・リヒテンベルガーの問題意識は、「没入文化」に対する批評的なスタンスにあるように思える。各楽曲のタイトルには、“spiderman”、“stranger things”、“mad men”、“irma vep” といった映画やドラマのシリーズ名が並ぶ(シーズン数やエピソード番号まで明記されている)。これらはポップ・カルチャーへのオマージュのようでいて、そのじつ、メディア環境へのアイロニーだ。アルゴリズムによる選別とレコメンドが支配する現代社会において、「感情の即時反応」ばかりが促進され、「意味」や「文脈」は平板化されつつある。音楽もまた、「癒やし」「集中」「感動」といったラベルとともに、機能的に消費されている。
『Ostranenie』は、そうした現状に対する明確な異議申し立てといえる。ここでは感情は決して「わかりやすく」提供されない。リスナーは、受動的な快楽ではなく、能動的な聴覚の再構築へと促される。楽曲は意味を拒みながらも、静かに、しかし確実に、感覚の深層へと楔を打ち込んでいくだろう。グリシャ・リヒテンベルガーは、日常に埋もれた音や記憶、感情の断片を、異化というフィルターを通じて再提示するわけだ。即興性と構築性、詩情と冷徹さ、アナログとデジタルの往復運動。そのなかで彼は、「慣れ親しみ」という知覚そのものを揺さぶりをかける。つまり「異化」だ。
再構成されるピアノ。異化される情緒。『Ostranenie』という「ピアノ楽曲集」は決して「耳に優しい音楽」ではない。グリシャ・リヒテンベルガーは、一音一音を通じて、世界を見慣れぬものとして差し出す。『Ostranenie』は、その意味で、現代におけるもっとも静かで、もっとも過激なプロテストのひとつといえないか。
グリシャ・リヒテンベルガーは本作『Ostranenie』で、自らの到達点をまたひとつ更新した。もしも坂本龍一が『Ostranenie』を耳にしたなら、彼はいったい何を、どのように語っただろうか。そんな想像をめぐらせながら、私は今日も『Ostranenie』を聴き返している。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- aus - Eau
- 見汐麻衣 - Turn Around
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations
- Ikonika - SAD
- Eris Drew - DJ-Kicks
- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet
- DJ Narciso - Dentro De Mim
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion
- Debit - Desaceleradas
- Sorry - COSPLAY
- K-LONE - sorry i thought you were someone else
- claire rousay - a little death
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer
- Roméo Poirier - Off The Record
- TESTSET - ALL HAZE


 DOMMUNE
DOMMUNE