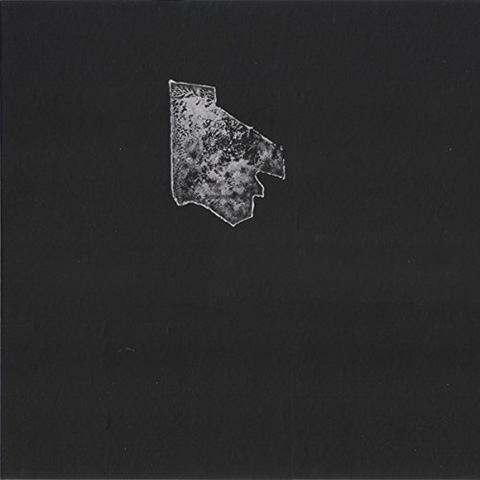MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Grischa Lichtenberger- Re: Phgrp (Reworking »Consequenc…
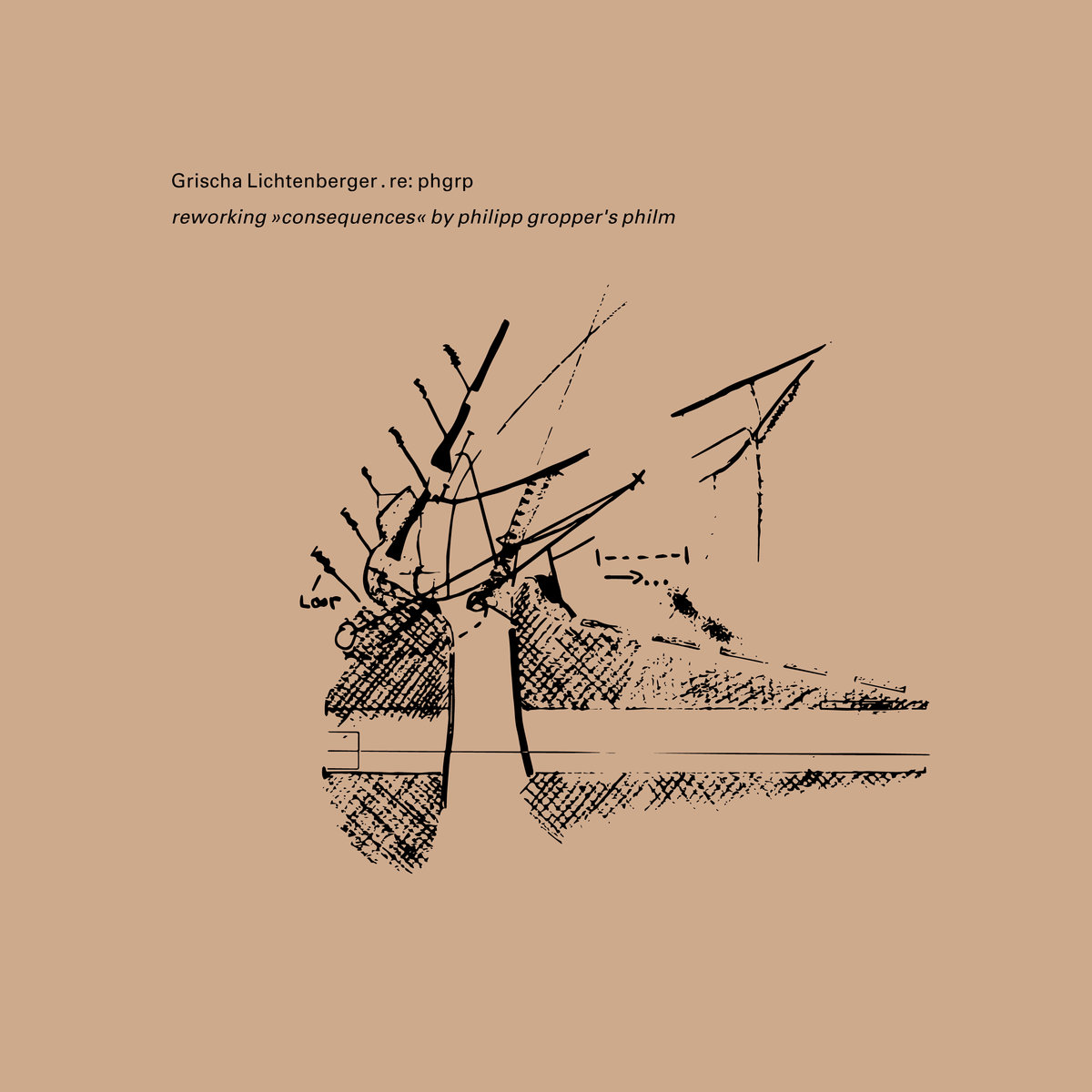
グリシャ・リヒテンベルガーは2009年に名門〈Raster-Noton〉からシングル「~Treibgut」をリリースした。2年後の2011年にスヴレカ(Svreca)が主宰する〈Semantica Records〉からEP「Graviton - Cx (Rigid Transmission)」を発表。翌2012年には〈Raster-Noton〉よりアルバム『and IV [inertia]』をリリースする。3年を置いた2015年にセカンド・アルバム『La Demeure; Il Y A Péril En La Demeure』を発表し、翌2016年にはジェシー・オズボーン・ランティエとの競作による『 C S L M | Conversations Sur Lettres Mortes』をリリースした。同2016年には20世紀後半の歴史と思想をバックボーンにしたEP三部作をひとつのパッケージにしたトータル・アート作品的な傑作『Spielraum | Allgegenwart | Strahlung』を発表するに至る。
本作『Re: Phgrp』は、ベルリンの電子音響作家グリシャ・リヒテンベルガー、待望の新作である。『La Demeure; Il Y A Péril En La Demeure』(2016)以来、実に4年ぶりのアルバムだ(EP三部作をまとめた『Spielraum | Allgegenwart | Strahlung』もカウントすれば3年ぶり)。
グリシャ・リヒテンベルガーの音響音楽の特質はポスト・オウテカ的なグリッチ美学の応用にある。ノイズと音響の生成と構築によって律動を組み上げていくのだ。彼は思想から建築、科学まで援用・貫通しつつ聴覚の遠近法を拡張させる。私が彼の音楽に最初の衝撃を受けたのはご多分にもれず『and IV [inertia]』だったが、そのグリッチ・サウンドの中に、「音楽」以降の「音から思考」する意志を強く感じたものだ。リズムですらも解体されていくような感覚があった。いわばポスト・ポスト・テクノ/ポスト・ポスト・クラブ・ミュージック。リズムという無意識を冷静に解析する分析学者のようにすら思えたものである。
新作『Re: Phgrp』も同様に感じた。いや、これまで以上に斬新ですらあった。本作では電子音響とジャズの融合を試みている。『Re: Phgrp』はアルバム名どおりドイツのサックス・プレイヤーにしてコンポーザーであるフィリップ・グロッパーによるフィリップ・グロッパーズ・フィルム(Philipp Gropper's Philm)『Consequences』(2019)のリワーク・アルバムなのである。しかしながら本作はいわゆるリミックス作品ではない。コラボレーションでもない。グリシャ・リヒテンベルガーのソロ・アルバムである。「リヒテンベルガーによる電子音響とジャズを交錯させるという実験報告のような作品」とでもすべきかもしれない。
ジャズと電子音響をミックスした成功例はあまりないと思うのだが、それはジャズの音楽的構造が強固であり、ミニマルな構造と非楽音的なノイズとリズムを組み上げていく電子音響とでは食い合わせが良くないからだろう。だからこそジャズを音楽ではなく音響として「聴く」必要があった。本作の第一段階で、聴くことのジャズ聴取のパースペクティヴを変えていくモードがあったのではないかと想像する。そう、ジャズの演奏シークエンスを、大きな「音響体」として認識すること。それによってサウンドを解体すること。ジャズは豊かな和声を持った音楽だが、音響体としてジャズ音楽全体を認識したとき、細部からズームアウトするかのようにサウンドの総体は糸が解れるように解体してしまう。そして音楽が音響体へと変化する。「全体」への認識によって聴覚の遠近法が変わるのだ。ズタズタに切断されたジャズの音響体は、聴覚の遠近法の変化によってサウンドとして新たに息を吹き返すだろう。まるで新たな生命体に蘇生するかのように。
フィリップ・グロッパーズ・フィルムの音楽性は2010年代的に高密度なインプロヴィゼーションとサウンドが交錯したポスト・フリージャズといってもいい端正かつ大胆なものだ。ジャズ・マナーに乗った上で音楽の内部からジャズを更新しようとする意志を感じた。
グリシャ・リヒテンベルガーはいささかオーセンティックな彼らのサウンドから「律動」を抽出した。グリシャ・リヒテンベルガーが必要とするのは「ジャズの律動」エレメントだ。たしかにアルバム冒頭のトラックは、フレーズも旋律も和声も残存しているのだがアルバムが進むにつれ次第にジャズの残骸は電子ノイズの中に融解し、グリッチと律動へと変化させられていく(サウンド的にはこれまでの楽曲以上にビートの音色が強調されているのも律動への意志のためか)。
だから本当のところ事態は反対なのだ。ジャズを解体し律動を抽出したのではない。ジャズの律動を抽出するためにジャズを解体したとすべきなのである。「律動」にジャズの本質を「聴く」こと。その律動のエレメントを抽出し音響化すること。そのときはじめてジャズが、オウテカ、カールステン・ニコライ、池田亮司、マーク・フェル以降ともえいえる先端的な電子音響/電子グリッチ・ノイズと融合可能になったとすべきではないか。本作はジャズ的律動とグリッチ的音響を交錯させる実験と実践なのである。
その結果、『Re: Phgrp』からポストパンク的な切り裂くようなソリッドかつ重厚なリズムを感じ取ることができた。なぜか。もともとブルースを電気楽器と録音機器によって拡張に拡張を重ねたロックは、サイデリック・ムーヴメントを経て、プログレッシヴ・ロックやポストパンクへと極限的な変化を遂げたものである。ロックはブルースの解体の果てにある音楽(音響体)であり、それゆえ根無し草の音楽であった。同じように電子音響とジャズの解体/交錯が、新しい「ロック」(のようなものを)生成=蘇生させてしまった。和声も旋律も剥奪されたジャズのソリッドな律動は「ロック」のカミソリのようなリズム/ビートに共通する。私がこのアルバムにポストパンク的なものを感じた理由はここにある。
確かに70年代以降、先端音楽としてのロックは終わった(ロック・エンド)。だが、その意志は、電子音響と尖端音楽に継承されていたのだ。『Re: Phgrp』はその証明ともいえる重要なアルバムである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE