MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Grischa Lichtenberger- Spielraum | Allgegenwart | Strah…
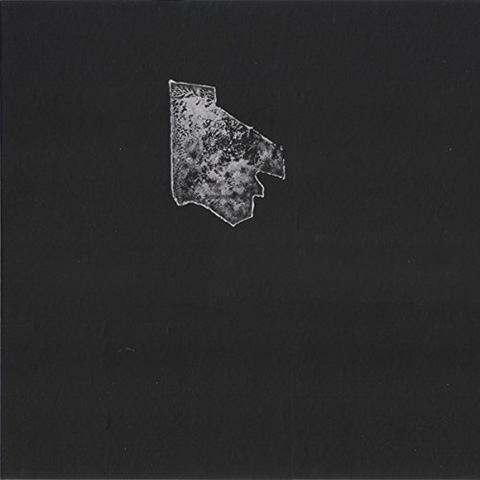
2010年代的「グリッチ以降・電子音響/テクノロジカルな先端的音楽」は、さまざまな「ノイズ」を誤用することで生まれるスタイリッシュ・エクスペリメンタル・ミュージックであった。この場合の「ノイズ」とは、いわゆる楽音以外のさまざまな音のマテリアルを意味し、俗にいう「轟音」とか「雑音」としてのノイズのみを意味するわけではない。社会から溢れ落ちた諸々の音の残滓を掬い上げるかのように、「ノイズ」をエクスペリメンタル・サウンドとしてコンポジションしていったのだ。
そのような先端的音楽の系譜にあって、90年代中期からグリッチやサイン派を用いたモダン・テクノ(ロジカル)な音響作品のプレゼンテーション/リリースを繰り返してきた〈ラスター・ノートン〉の存在は、とても大きい。現在はカールステン・ニコライ(アルヴァ・ノト)とオラフ・ベンダー(バイトーン)を中心に運営されているこのレーベルは、20年にわたり最先端の電子音楽を見出し、われわれリスナーの知覚にむかって新しい電子音楽を提示している。
彼らのキュレーション能力は常に研ぎ澄まされており、近年は日本人アーティストのキョーカのアルバムも〈ラスター・ノートン〉から発表された(本年11月にレーベル20周年を記念するジャパン・ツアー「ラスター・ノートン 20th Anniv.」が開催される。東京公演は日本初開催「MUTEK」にて!)。
そして2012年、(事実上の)ファースト・アルバム『アンド IV [イナーシャ]』をリリースしたグリーシャ・リヒテンバーガーもまた〈ラスター・ノートン〉によって、その才覚を見出された電子音楽アーティストである。
ベルリンのビーレフェルトの農村で生まれ育ったグリーシャ・リヒテンバーガーは、インターネット上の「マイスペース」でトラック/楽曲を発表していた。その「マイスペース」を通じて、カールステン・ニコライからコンタクトを受けたというのだ。その結果、2009年にEP『~トレイブギュット』、2012年にアルバム『アンド IV [イナーシャ]』をリリースするに至った。
リリース当時、『アンド IV [イナーシャ]』は、いわゆるオウテカ以降のサウンドとして高く評価されたが(じじつ彼は90年代においてオウテカやトータスなどから影響を受けたという)、しかし、4年が経過した現在の耳で聴き直してみると、先に書いたような極めてスタイリッシュな10年代的ノイズ・モダン・コンポジション・サウンドであったことに気が付く。
『アンド IV [イナーシャ]』には「ノイズ」を通して社会・科学・歴史を考察するような知的な営み、つまりは「コンセプト」を強く感じた。じっさい『アンド IV [イナーシャ]』は、「ニュートリノ観測装置の後継器のことをテーマ」にした作品でもあった。グリーシャは当初、「小説」として、同テーマの作品にとりかかろうとしたようで、彼は音楽を含めて「芸術」を総合的な思考/認識する媒体として認識しているのだろう。
裏を返して考えれば、彼は創作にあたって常にコンセプト=言葉を必要としているともいえる。1983年生まれのグリーシャは、スタイルの新奇さや実験的手法の目新しさを追及すれば、「新しい」音楽が自動的に生まれるとは考えてはいないはず。あらゆるものは出尽くした。だからこそそれらをいかにリ・サイクルし、そこに新しいコンセプト=思考を見出していくのかが重要なのだ。
そして、昨年2015年に発表されたアルバム『ラ・ドゥムール;イリヤ・ペリル・アン・ラ・ドゥムール(La Demeure; Il Y A Péril En La Demeure)』では、「ドゥムール=「住居」は、親密性や、隔離とその可能性ともいえるが、隔離されて、経済、時間、社会の制約から自由になって作業や探求、実験をする喜びが本作の着目点の中心となっている」アルバムであった。これは20世紀的な技術/居住空間=公共圏の問題に連なる問題ともいえ、いわばテクノロジカルな音楽を通じて、20世紀のモダンの問題(とその限界)を「イメージさせること」が目的なのだろう。
また、この『ラ・ドゥムール;イリヤ・ペリル・アン・ラ・ドゥムール』は、全5部作のシリーズの最初の作品としてもアナウンスされていた。アルバム『ラ・ドゥムール;イリヤ・ペリル・アン・ラ・ドゥムール』を発表し、その後に3部作のEPをリリース、最後にアルバムで締めるという壮大な計画である。いわばグリーシャ・リヒテンバーガーによる20世紀技術史/思想史の音による論文/著作といった趣のシリーズとでもいうべきか。
ちなみにこの隔離された居住空間から社会へのこだわりは、彼がビーレフェルトの農村出身であり、都市の喧騒から距離を置きつつ、創作を始めたことと無縁ではないかもしれない。
そして本年2016年。シリーズの中核「EP3部作」がセットとしてリリースされた。それが本作である。EPといってもアルバム2枚から3枚分の曲が収録されており、もはやアルバムといってもいいボリュームだ(フィジカルはヴァイナル3枚組の限定500セットで発売され、グリーシャ自身による美しいシルクスクリーンも封入されている)。
このEP3部作は、『シュピールラウム』、『オールゲーゲンヴァルト』、『シュトラルンク』と名づけられ、それぞれ6曲、5曲、8曲のトラックを収録している。グリーシャのサイトでは、『シュピールラウム』には「目に見えない自由」、『オールゲーゲンヴァルト』には「目に見えない存在」、『シュトラルンク』に「目に見えない力」という副題が付けられている。私見だが『シュピールラウム』では、20世紀的な直線的なクロノス時間の問題、『オールゲーゲンヴァルト』ではファシズムに至る群集心理の問題、『シュトラルンク』では原子力などの科学技術の問題が内包されているように思えた。それぞれのEPは、著作でいえば、ちょうど本文の核となる各論といった趣であろうか。くわしくはグリーシャのサイトをご覧頂きたい。彼の手によるシルクスクリーンによるアートも閲覧することができる。
じっさい、『シュピールラウム』に収められた電子音響的なグリッチなテクノ・トラックは、いやがおうにも進展的な時間を実感させるし、『シュトラルンク』のさまざまな音素材を用いてコンポジションしたミュージック・コンクレート的テクノ・トラックは、人の「声」まで引用しつつ、大衆の無意識にアジャストするように、社会の残滓・残骸を感じるトラックを収録している。『シュトラルンク』は、シンセ音や、細やかな音のレイヤーなどがアンビエンス感覚を助長し、目に見えない原子力のアトモスフィアを表象しているようにすら感じられた。
「映像的でサウンドトラックのような音楽」とはよくいわれる比喩だが、本作のように「思考/思想をトレースするような音」は、あまりない。本作(本シリーズ)でグリーシャは、「思想のサウンドトラック」を実現しようとしているのではないか。先のサイトでは、ヴァルター・ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」、エリアス・カネッティ『群集と権力』、モーリス・ブランショの『文学空間』なども援用しており、20世紀的な(人文学的な?)問題を、ドイツ人として追求していることは明白だ。以前のインタヴューなどでレヴィナスからハイデガーの問題まで語っていたほどである。
あえて私なりに本作を語るならば、1909年に「未来派宣言」を発したルイジ・ルッソロによる「イントナルモーリ」を用いた元祖(ノイズ)音響作品の系譜につらなる2010年代的な先進的電子音響作品に思えた。「未来派」は、ファシズムの魅惑=危険性と同時に神経的芸術の幕開けを予言した芸術運動でもあったわけだが、この『シュピールラウム | オールゲーゲンヴァルト | シュトラルンク』は、21世紀的な世界的不穏の只中におけるアフター・モダン・ミュージックとして、戦争と技術の時代たる「20世紀」を総括し、不穏と崩壊の世紀である21世紀中葉にメッセージを発している……。そんなふうに思えてならないのである。時代の節目と境目に鳴る音響?
そう、本作こそ「マテリアルな素材=ノイズをスタイリッシュにコンポジションする2010年代のエクスペリメンタル・グリッチ・テクノ」の「ひとまずの完成形」ではないか。ビート/リズム・トラック面での進化=深化がみられ、ジャズ的なビートの断片をサンプリングし導入している点も聴き逃せない。ジェシー・オズボーン・ランティエとの共作『C S L M』(こちらも傑作)とともに、電子音楽/音響の「現在」を体感することができるアルバムといえよう。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE