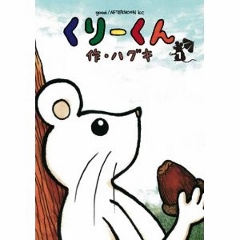MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
- 『成功したオタク』 -
- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー
Home > Reviews > Comic Reviews > くりーくん- ハグキ
2013年にひとつ足りないものがあったとすれば、それは『ハトのおよめさん』におけるハトよめの暴言だ。1999年に始まり、2012年末になかば強引に結末を迎えた長寿連載を終えて、作者のハグキはいま何をしているのだろう。下ネタ・暴言もしくは暴力ネタ、シュール・ネタが乱発する、そのくっだらない動物ものギャグ・マンガを友人とゲラゲラ笑いながら長い間読んでいたものだが、『ハトよめ』が終わってしまった世界がこんなにも寂しいものだとは想像していなかった。いや、僕がハグキのマンガに思い入れるようになったのは、わりとひっそりと発表されていた、同じく動物ギャグ・マンガ『くりーくん』を読んでからだろう。
『くりーくん』は同じ2012年に第2巻が出て完結しているが、僕はいまでも読み返すたびに「現代の日本からこんな表現が出てくるとは……」と嘆息せずにはいられない。そこには、僕が海の外の国で生まれた表現に――たとえばアキ・カウリスマキの映画に――見出してきたものがあるように思えるからだ。端的に言ってしまえば、貧しい者たちの尊厳と、彼らのコミュニティで生まれる誇りのようなものが描かれている。長年の経済的な行き詰まりを受けて、たしかに困窮を「リアルに」描くマンガは増えた。けれど、金がない男がいかにモテなくて(童貞で)みじめかとか、ほんとどうでもいいし、さらにはその非モテの主人公が現実にいるはずもない美少女に恋をされるようなものにうんざりしていた僕にとって、『くりーくん』は大いなる発見だった。いや、『くりーくん』だって、基本的には小学生が描いたような絵の、くっだらないギャグ・マンガとして、である。ニートで頭の悪いケンちゃん(クマ)が「ス☆ゴーイ!」とか「クリティカル・ショック!!」とかいう一発ギャグを繰り出す第1話を読んで、この物語が向かう先を想像できるひとは少なかっただろう。
そう、物語だ。『ハトよめ』にはそれほどなかった明確なストーリー・ラインが本作にはある。冒頭ではくりーくんはリストラされた妻子に逃げられた無一文の中年のネズミで、人生に絶望している。が、そんなことに気を遣わずに遊びに来る能天気なケンちゃんと日々を過ごしながら、次第に仕事を始めていく。まずは自分の食材を森で拾い、次は山菜を採ってそれを売る。金持ちのホームヘルパーは(金持ちの尊大さに気づいて)失敗するが、フォークリフトの免許を手に入れて運搬の仕事を始める。つまりここでは労働が内容も含めて非常に具体的に描かれており、また、完全にDIYで……たとえば自宅のドアを木材を拾って作るなどして、くりーくんが自分の生活を着実に立て直していく様子もページをさいて、じつに細かく見せていく。逃げられた妻のところで暮らす娘に会いに行って、あとでその元妻にバレて怒られたりもしながら……。
そうこうしているうちに、くりーくんの周りにはたくさんの動物たち――それはつまり、「多様な人びと」の比喩だ――が集まってくる。ケンちゃんとのちにお笑いコンビを組むフリーター(トビネズミ)、事故でケガをしたが金も保険を持っていないために病院に行けないボヘミアン(渡り鳥)、長年やっていたボーリング屋をたたんでカラオケチェーンに土地を売ってソバ屋を始めるおじさん(リス)、独居老人(モグラ?)、アル中の父親からの暴力に苦しむ母子(プレーリードッグ)、恋人を亡くして失意に暮れる刑務所帰りの元漁師(アナグマ)……。彼らはそれぞれの事情を抱えながら、だが、めげずに労働に勤しみ、できる範囲で助け合いながら、ただただ逞しく毎日を生き抜いていく。履歴書の「趣味」の欄に「ビヨンセ パックマン エビフライ」と書いて雇い主に「君は計り知れないバカじゃな!」と言われてしまうケンちゃんだって、お笑い芸人を目指して何とかやっていくし、出世した同級生に会ってちょっと落ち込みもするが、焚き火を囲んで友人たちと夕飯を食べていればそんなみじめさは忘れてしまう。『くりーくん』では出世して金を稼ぐことよりも、仲間たちと手作りしたパンをいっしょに食べる時間のほうが尊いと信じている人間が描いたマンガ、タフな楽観主義に貫かれた物語である。
時間はどんどん過ぎていく。くりーくんの娘は成長して親元を離れて彼氏と同居し、ケンちゃんの相方のトビネズミは実家の工場を継ぐために地元に帰っていく。そんななか、くりーくんはチーズ生産の仕事を始めてヒットするし、ケンちゃんだってピン芸人としての道を見出していくが、面倒な問題は相変わらず毎日目の前にある。しかし、くりーくんは言う……「大丈夫! なんとかなるだろ」。そして、作者からのかなり率直なメッセージがこめられた最終回では、くりーくんは遠くない未来に死ぬだろう予感が漂っているが、その日もみんなで淡々と夕飯をいっしょに食べ、ケンちゃんは第1話と同じように「ス☆ゴーイ!」のギャグを繰り出している。
これは現代日本におけるプロレタリア文学なのだろうか? ……いや、それ以上に能天気なギャグ・マンガであり、だから僕は愛さずにはいられない。はじめ読んだときは『ハトよめ』にはない豊かな叙情性と仄かな無常観に驚いたが、しかし思い返せば、『ハトよめ』にだって労働を知っている人間が描いたものだと思わせる箇所がそこここにあった。ハグキはいまどうしているのだろう? 僕には知る由もないし、またマンガを描いてほしいとも思うけれども、同時に、地道に労働をしながらタフに生きているのだろうと勝手に想像して安心している。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE