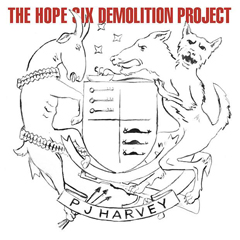MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Reviews > 合評 > PJ Harvey- Let England Shake
これは「好きになるべきレコード」か?文:野田 努
 PJ Harvey Let England Shake ユニバーサル インターナショナル |
家のレコード棚には2種類のレコード(CD)がある。ひとつは「好きなレコード」。そしてもうひとつは、「好きになるべきレコード」だ、そう、レスター・バングスやカート・コバーンが薦めるような、たとえばサン・ラ、ファウスト、キャプテン・ビーフハートのような連中のレコードである。PJハーヴェイのレコードは、その2種類に重なっている――昔、『ガーディアン』の記者は彼女のことをこのように表現していた。PJハーヴェイがUKでいまだ特別なリスペクトと愛情を集めているのは、彼女が2000年に発表した『ストーリーズ・フロム・ザ・シティ、ストーリーズ・フロム・ザ・シー』への評価からもうかがい知ることができる。UKのどのメディアからもゼロ年代を代表するアルバムに選ばれたこの作品の評価は、「彼女の作品のなかでもっとも前向き」という点に集約される。端的に言えば、PJハーヴェイが高揚すればみんなも嬉しいのだ。そして『レット・イングランド・シェイク』は、『ストーリーズ・フロム・ザ・シティ、ストーリーズ・フロム・ザ・シー』以来のずばぬけた評価を得ている「好きになるべきレコード」というわけだ。
『レット・イングランド・シェイク』は、音楽的にも魅力的な作品だ。これは寒々しいブルース・ロックやダーティなノイズ・ロックではない。英国風のフォーク・サウンドを取り入れつつ、エディ・コクランとザ・バッド・シーズに会釈しながら20世紀初頭のミュージック・ホールに戻ってくるような......ニック・ケイヴ的なアコースティックなサウンドで、実際アルバムではミック・ヘーヴェイ(ザ・バースデイ・パーティ~ザ・クライム&ザ・シティ・ソリュージョン~ザ・バッド・シーズなど)がピアノやオルガンを担当して、ベースを弾いて、ハーモニカを吹いている。そして、彼女らしいコード・ストロークがあるいっぽうで、鼓笛隊のリズムがあり、ラッパが鳴っている。苦痛に満ちた声の代わりに誰もがアプローチしやすい親しみのあるメロディがあり、美しいハーモニーがある。アルバムの主題を知らなくても充分に繰り返し聴かれるであろう、つまり「好きなレコード」になりうる作品である。
が、やはり興味深いのは今回の主題だ。『レット・イングランド・シェイク(英国を揺さぶれ)』は、主に第一次大戦のイギリスを題材にしている。そして、それまで内面ばかりを歌ってきた女性シンガーが、8枚目にして初めて外の世界を歌ったときの題材が第一次大戦というのは気になる話である(いま思えば前作『ホワイト・チョーク』はその題名通り、本作への予兆とも言える)。
ちなみにUKにおける第一次大戦とは......ヴィクトリアニズムからモダニズムへの架け橋となったイングランドにおけるターニング・ポイント、イングランドの近代国家のはじまり......で、考えてみればフランツ・フェルディナンド暗殺が第一次大戦開戦のきっかけなっているので、僕は不勉強でまだよく知らないけれど、UKにおいてその意味は大きい。帝国主義という観点において。
日本盤のライナーノーツによれば「政治をちゃんと理解していない以上、あまり話してはいけないと思う」という旨の本人の発言があるけれど、『ガーディアン』によれば彼女は、2年半かけて戦争の研究している。報告書を読み、ドキュメンタリーを見て、生存者と話したという。その努力を聞いただけでも僕は胸が打たれる。そして彼女は「歴史は繰り返すということを示したくなった」と打ち明けている。アルバムの最後から2番目の曲のみが、唯一、イラク戦争に関する曲である。
もうひとつ僕が興味を抱くのは、彼女の母国への愛についてである。セックス・ピストルズの"ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン"の背後からは愛国心がうかがえるという議論がUKではあったように、好きだからこそ否定するというニュアンスはUKの音楽からはたまに滲み出る。王室や政府は嫌いだけれどUKは好き、というわけだ。マニックスはウェールズを実直に愛し、USのロックでは星条旗がたびたび登場するが、それはもちろん国粋主義ではなく民主主義への忠誠心である。ブラジル音楽ではそれがさらに顕著だ。カエターノ・ヴェローゾのような反抗者もみんなみんなブラジル万歳だから。が、しかし、さすがにクラウトロックはドイツ最高とは言えないぞ(それを考えると『クラウトロックサンプラー』と『ジャップロックサンプラー』に対する新たな興味も湧いてくる)。
とにかく彼女はイングランド思いである。が、PJハーヴェイがアルバムで描写しているイングランドは、残酷で、絶望的で、悲しみに満ちた、気が滅入るイングランドである。「私は生き、そして死ぬ、このイングランドで」と彼女は歌う。そしてこう続ける。「残るのは悲しみ/口に残るのは苦い味」
さて、『レット・イングランド・シェイク』は「好きなレコード」であり、「好きになるべきレコード」だろうか。むしろサン・ラ、ファウスト、キャプテン・ビーフハートのほうが「好きなレコード」となっている今日において、彼女の真摯な態度は「好きになるべきレコード」というジャン分けを粉々にしているようじゃないか。
文:野田 努
 | PJ Harvey / White Chalk |
|---|---|
 | PJ Harvey / Dry |
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE