MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Youth Lagoon - 夢の世界で辻褄を合わせよう
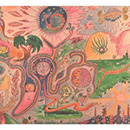 Youth Lagoon - Wondrous Bughouse Fat Possum / ホステス |
なるほど、彼はベッドルームで録音などしたことがないのだそうだ。てっきりテレコで部屋録りした素材を大事に作り直しているのだとばかり思っていたが、それはベッドルーム・ポップと呼ばれるものへのひとつの偏見だったかもしれない。「音がアイデアのはじまり」と語るユース・ラグーンことトレヴァー・パワーズは、制作環境ではなく、めぐらせた音によって彼自身のパーソナルなスペースを築いている。けっして陰険な音楽でも人嫌いなタイプでもないが、〈ウッジスト〉や〈キャプチャード・トラックス〉にも連なるようなリヴァーブ感は、心地よい遮蔽感覚を与えてくれるだろう。いい具合の隙間にすっぽりと入り込んで、外に陽のあたたかさを感じながら、膝を抱えて眠り込んでしまうような感覚。そこにはうっすらと狂気のにじんだドリーミー・ヴァイブが満たされている。ジャケットの絵が薬物中毒患者の手になるものだというのは、本作のサウンド・スケープをぴたりと象徴するものだ。
2011年、ドリーム・ポップに活気づくインディ・シーンの追い風も受けながら、彼のデビュー作『ザ・イヤー・オブ・ハイバーネイション』は高評価をもって迎えられた。その時点では、流行や数多の才能のなかにやや埋もれがちな印象もあったが、ときをおいて、いま、彼本来のシンガー・ソングライター的な佇まいがようやくくっきり見えてきたように感じられる。遠景にパンダ・ベアをかすませて、イディオット・グルーやザ・ウォー・オン・ドラッグスやMGMTの間を縫いながら、まるでポスト・チルウェイヴ世代のダニエル・ジョンストンといったような楽曲が並ぶ。プロデューサーは、アニマル・コレクティヴやディアハンターでもお馴染みのベン・アレンだ。ドリーミー・サイケはお手のもの。もちろん時代性やモードに比較するよりも、彼個人の本当にパーソナルな表現だととらえるほうが、本作は輝くだろう。そのような遠近法がとれるようになった、よいタイミングでの快作である。ダニエル・ジョンストンもジャド・フェアも知らないというのは驚きだったけれども......。
自分の心が妙なはたらき方をするっていう事実を受け止めるのに少し時間がかかったんだ。その間に、不安だらけで心配性みたいな、間違った僕の人物像ができてしまったけど、実際の僕はそうじゃないよ。
■あなたが活動をはじめた2010年前後から、音楽シーンも少しずつ変化しました。アニマル・コレクティヴが2000年代半ばに示したような新しいサイケデリック・ミュージックも、あなたのような才能を産みながらいろいろな方向へと拡散しています。いまあなたがこのアルバムを “スルー・マインド・アンド・バック”というメディテーショナルなノイズ・アンビエントからはじめたのはなぜでしょう?
パワーズ:アルバムへのイントロダクションになるものが欲しくて、あの曲がそれにぴったりだったんだ。あの曲自体が完成したのはアルバムに入っている曲のなかでも最後の方だったんだけど、出来上がったとき「この曲は冒頭に入れたら上手くいくんじゃないか」って思ったのさ。
■“スルー・マインド・アンド・バック”の「バック」とは何ですか?
パワーズ:これはある意味で転換点みたいなトラックなんだ。僕がこの曲を書いていたとき、まるでどこか別の、何もかもつじつまの合っている世界へと連れて行かれたような感じがした。そして書き終わった途端に、また元の世界に「戻って」来たような感じがしたんだよ。
■今作はプロダクションも整理されて、しかしあなたの音楽のシンセの丸みや太さ、ノイズ感やえぐみといったものはきちんと残されていますね。プロデューサーのベン・アレンとは相性も合うのではないかと思いますが、録音はいかがでしたか?
パワーズ:ありがとう。このアルバムの録音のプロセスはかなり綿密なものだったよ。ベンと僕は2ヶ月近くもの間、毎日レコーディングし続けた。インターンやエンジニアから成るベンのチームもみなすばらしい人たちだったよ。とても健全な感じのするプロセスだったね。僕が目指していたようなものを引き出しやすい雰囲気だった。
■あなたの方からプロダクションについて要望したことはありますか?
パワーズ:レコーディングのためにアトランタに行く前から、ベンとはしばらく電話で話をしていたんだ。彼とは最終的なゴールについてしっかり話し合って意見を一致させておきたかったからさ。そしてそれってどんどん変わっていくものなんだ、ある曲やアルバムについて特定のヴィジョンを持っていたとしても、実際の制作が始まると、そこからまったく違ったものへと変化してしまったりする。それぞれの曲が意志を持って動きはじめるんだよ。今回のプロダクションでは、それぞれの曲が発したがっている音をそのまま出せるようなものにしたかったから、ベンと僕との間には良い意味での緊張感があった。彼の見方が僕の見方と違っていることはあっても、目指しているゴールは同じだったのさ。
■ファースト・アルバムは大きく注目され、高い評価をもって迎えられました。このことがその後の音楽制作上の足枷になっているようなことはありませんか?
パワーズ:唯一気にかかるのは、前のアルバムと同じものを期待している人たちがいるってことだね。僕自身が音楽でエキサイティングだと思うことは、予測の出来なさなんだ。同じことを2度はやらないよ。だからそういうのを期待している人たちには、何もあげられるものがないね。
■ファースト・アルバムには「不安の克服」というモチーフがあったという記事を読みました。今作にはより穏やかであたたかいムード(“ミュート” などは力強くすらあります)があると思うのですが、「不安の克服」はその後今作にいたるまでの間に形を変えたと思いますか?
パワーズ:とくに不安の克服っていうテーマを意識していたわけじゃないよ。自分の心が妙なはたらき方をするっていう事実を受け止めるのに少し時間がかかったんだ。その間に、不安だらけで心配性みたいな、間違った僕の人物像ができてしまったけど、実際の僕はそうじゃないよ。
取材:橋元優歩(2013年5月02日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE
