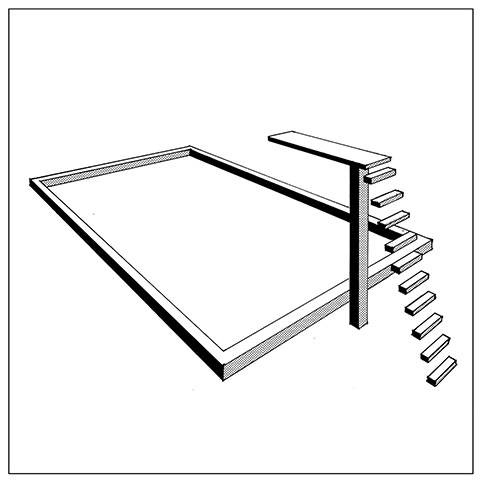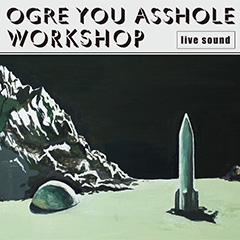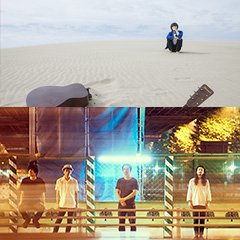MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Ogre You Asshole - ディフェンスよりも“黒歴史”を

出戸くんの声とか、馬渕くんのメロディ・センスがもともと資質としてメロウだと思うんですよね。叙情的というか。ミニマルとメロウ、その両方の要素がバンドのなかにもともと存在していた。(清水)
勝浦:それを聞いて思い出したんですけど、最初バンドに入ったときに、当時のUSのインディ・ロックをぜんぜん聴いてなくて、いまのロックがどうなっているのかってことをまったく知らなかったんですよね。僕は淡々とリズムを刻みたいのに、AメロとBメロでドラムのパターンを変えろって言われたりとか。「なんだそれは」と。「ドラムは一定のものだ」と(笑)。それはわりと昔から思ってたんですけど、それが『homely』以降になって、めちゃくちゃやりやすくなりましたね。
■それは勝浦さんのどういう思想とつながっているんですか?
勝浦:何なんですかね。もともとメロディがない人間なので、機械っぽいとはよく言われるんですけど。
出戸:資質なんでしょうね。
勝浦:そうかもしれない。生まれ持った体質ということにしておいてください。わりと繰り返したりするのが好きなんですよね、昔から。ただ、最近のライヴを録音して聴いてみたら自分で思っている以上に揺れてたんですよ。それがすごいショックで。
一同:ははは(笑)
勝浦:まだまだ正確ではないです。
■では、「メロウ」の方はどうですか?
清水:それはもう、出戸くんの声とか、馬渕くんのメロディ・センスがもともと資質としてメロウだと思うんですよね。叙情的というか。ミニマルとメロウ、その両方の要素がバンドのなかにもともと存在していたし、そういう意味ではもともとミニマルメロウなバンドだったのかもしれないけど、それを意識的に混ぜ合わせたことがなかったってことだと思います。
■なるほど。ただ、たとえば正確なリズムだったら機械で打ち込めるだろうし、いまなんてそのちょっとした揺れさえもプログラムできるんじゃないかと思うんですよ。だとすれば、オウガ・ユー・アスホールがそれでもロック・バンドという形態にこだわるのはなぜですか?
勝浦:「ロック・バンドとしてはじめたから」という答えになるんだと思います。さっきの出戸くんの責任感の話といっしょで、自分たちを少しずつ変えていくことに面白味を見出しているから。
清水:もう、職人と同じだよね。モノを作るときに機械をどんどん導入する人もいるかもしれないけど、手で作ること自体によさがあるというか。彫刻やっている人に「なんで手でやるんですか?」って訊くようなもので、端的に「やりたいから」っていう。
出戸:もともとロックを聴いて育ってるっていうところも大きいですけどね。テクノとかも多少は聴きますけど、リスナーとしての主軸がロックにあるというのが僕の場合は大きいかな。
彫刻やっている人に「なんで手でやるんですか?」って訊くようなもので、端的に「やりたいから」っていう。(清水)
■わかりました。話は一気に変わるんですけど、『homely』の1曲め、“明るい部屋”というタイトルは、ロラン・バルトの引用ですか?
出戸:そうですね。
■その引用の意味みたいなものって、説明できますか?
出戸:うーん、意味かあ。あれは石原さんとふたりで考えていて、ロラン・バルトの引用はどうかという話をしていたことは覚えているけど、意味って訊かれるとなあ。どうなんだろう、難しいですね。
■なるほど。出戸さんはそもそも、「自分の作品を自分で語る」というのはあまり好きではない方ですか?
出戸:なかなか難しいですよね。どちらかというと苦手な方だと思います。
■音楽で表現する以上の言葉が見つからないという感じですか?
出戸:そうですね。「言葉の人」って感じではないですね、僕は。
■ロラン・バルトっていうと、いわゆるポスト・モダンの批評理論みたいなものを意識して引用したのかな、とも思ったのですが。(注:「明るい部屋」は、ロラン・バルトの最後の写真論である。)
勝浦:そんなに理屈っぽく言葉を選んでいる感じじゃないんですよね、僕から見ていると。
■出戸さんの曲名とかって、短いセンテンスで印象的な曲名をつけるじゃないですか。その威力がすごいなと、いつも思うんですけど。
勝浦:あれってフィーリングでつけてるんじゃないの?
出戸:フィーリングなのかな。順番としては歌詞のあとに曲名をつけることが多いし、何かを考えてつけてることは間違いないんですけど、何を考えているかを言葉にするのは難しいですね。
■では、歌詞を書くのは好きな方ですか?
出戸:いいときはいいんですけど、嫌なときは嫌ですね。
一同:ははは(笑)
■自分の歌詞が評価されているとは思いますか?
出戸:『homely』以降はまだ考えて書いているので、わかってもらえてればいいなとは思いますけど。
「表面だけ立派で、綺麗にみえるけど、じつはペラペラ」みたいなものについて考えたりしていました。「居心地がいいけど悲惨な場所」というイメージを意識的にも無意識的にもずっと考えていたように思います。(出戸)
■今回のアルバムの歌詞を書いていく上で、アルバム・コンセプトのようなものはありましたか?
出戸:「表面だけ立派で、綺麗にみえるけど、じつはペラペラ」みたいなものについて考えたりしていました。また『homely』から『100年後』、そして今回の『ペーパークラフト』を通して、「居心地がいいけど悲惨な場所」というイメージを意識的にも無意識的にもずっと考えていたように思います。
■『ペーパークラフト』で綴られた歌詞が、怒っているか、諦めているかのどちらかに分類されるなら、どちらだと思います?
出戸:どちらでもないですね。
■でも、怒りや憂いみたいなものがないと出てこない歌詞だと思ったんですよ。
出戸:何かに白黒つけてるわけじゃないんですよ。日常的にも、楽しいけれど心のどこかでそれを嫌だなと思っていることとか、あるじゃないですか。そこはすごく微妙なもので。個人的にもすごく怒ったりとか、すごく悲しんだりとかしない人間ですから。だから、ひとつの強烈な感情を描いているわけではないですね。
■わかりました。メンバーのみなさんは出戸さんの歌詞は気にしますか?
馬渕:気にしなくていいところがいいんですよね。たゆたっているというか。
勝浦:前はたゆたっていて、意味を感じにくかったんです。いまは、歌詞のなかにちゃんと芯がありつつ、なおかつたゆたってる感じかな。そこが最近の進化だと思う。
出戸:たゆたう感じが好きっていうのは根底にあって、聴いている人の耳に何も意味が残らないような歌詞をわざと書いていたような時期もあったんですよ。文法とかもわざと間違ってみたり。音に溶けこむのがいちばんだと思っていたから。でも、意味のない歌詞を書いたつもりでも、そこから嫌でも浮き出てしまうものがあって。言葉ってそういうものじゃないですか。どんなに消そうと思っても消せないものがあるという。だからいまは、言葉の意味と音の関係性の中から出てくるものっていうのは、昔よりは意識して絞っていますね。
■評論によっては「ポリティカル」、つまり政治的という言葉が出てきますし、僕もいまの日本の状況を反映したような歌詞だなと思ったのですが。
勝浦:うーん、政治的なわけではないよね。
出戸:僕らが、というよりは、いまは世の中が政治的なのであって、そういう世の中にも順応できるアルバムだと思ってもらえればいいんじゃないですか。でも、政治的な事柄が薄まった世の中になれば、そこでもぜんぜんちがった聴かれ方をされたい。具体的に何について歌っていると感じるかが、聴く人や聴く時代によって少しずつ変わっていくような、鏡のような作品になればと思ってますね。
■「オウガ・ユー・アスホールは(おもに詩作の面で)震災以降に大きく変化したバンドのひとつだ」という評論があるとしたら、出戸さんは反論しますか?
出戸:たまたま震災がバンドの変化と重なっているので、そう見えても仕方ないと思います。でも『homely』に収録されているほとんどの曲は、震災前に作られているんですよね。
取材・文:竹内正太郎(2014年12月26日)
Profile
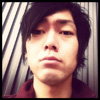 竹内正太郎/Masataro Takeuchi
竹内正太郎/Masataro Takeuchi1986年新潟県生まれ。大学在籍時より、ブログで音楽について執筆。現在、第二の故郷である群馬県に在住。荒廃していく郊外を見つめている。 http://atlas2011.wordpress.com/
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE