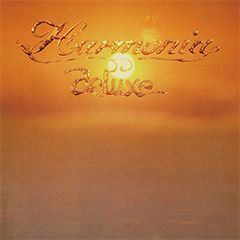MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Michael Rother - いまを生きるクラウトロック
 Harmonia - Musik Von Harmonia Brain/Grönland/Pヴァイン |
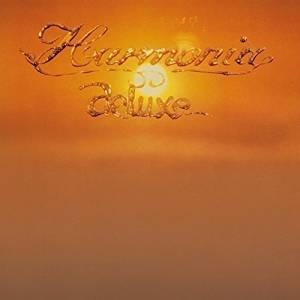 Harmonia - Deluxe Brain/Grönland/Pヴァイン |
クラウトロック、あるいはジャーマン・エレクトロニク・ミュージックの最重要人物の一人であるミヒャエル・ローターが、去る7月末に来日公演をおこなった。
ローターは70年代初頭、結成されて間もないクラフトワークにギタリストとして短期間参加した後、同じくクラフトワークでドラムを叩いていたクラウス・ディンガーと共にノイ!を結成。“ハンマー・ビート”と呼ばれる剛直な8ビートを軸にしたパンキーなサウンドはクラウトロックの一つの象徴的モードとして、後のパンク~ニュー・ウェイヴに絶大な影響を与え、更に90年代以降のクラウトロック再発見/再評価のきっかけにもなった。
ローターはまた、ノイ!での活動と並行してクラスター(ディーター・メビウス&ハンス・ヨアヒム・レデリウス)と共に結成したハルモニアでも活動。ポップでパンクでストレンジでアンビエントなそのエレクトロニク・サウンドは、80年代から今日に至る様々なスタイルのエレクトロニク・ミュージックに影響を与え続けている。ローターの業績に対するリスペクトを公言するミュージシャンも、古くはブライアン・イーノから近年はステレオラブやエイフェックス・ツイン、オウテカに至るまで、枚挙にいとまがない。
ローターは、ハルモニア解散後はソロ活動に専念し、たくさんのアルバムを発表してきたが、特にここ数年、ノイ!やハルモニア時代のレパートリーを中心にしたライヴ活動が増えているのは、クラウトロックに対する若いリスナーたちの関心と評価がますます高まっている証でもある。今回の日本公演を企画したのがクラウトロックのテイストを受け継ぐ前衛ロック集団オウガ・ユー・アスホールだったことも、実に納得がゆく。ドラムのハンス・ランペ(ex.ノイ!~ラ・デュッセルドルフ)、ギターのフランツ・ベルクマン(ex.カメラ)とのトリオ編成によるそのライヴでは、ノイ!やハルモニアの名曲がふんだんに演奏され、会場につめかけた新旧クラウトロック/エレクトロニク・ミュージック・ファンたちを熱狂させた。
おりしも『フューチャー・デイズ~クラウトロックとモダン・ドイツの構築』日本版も出たばかりというジャスト・ミートなタイミングでの本インタヴューがおこなわれたのは、東京でのライヴ直前の楽屋。時間が短かったため、ハルモニア結成あたりで話が終わってしまったのは残念だが、ほぼノーカットで、“クラウトロック大使”ミヒャエル・ローターの貴重な肉声をお届けしよう。
当時は音楽だけではなく、芸術や映画、さらに政治や社会制度でも大きな変化が起こっていた。私の成長をそのような変化と切り離すことは不可能だ。私は“変化の暴力”とでも言うべきものに強く影響されたんだよ。
■近年、ライヴでノイ!やハルモニアの曲を積極的にやっているようですが、どういう理由からですか?
ミヒャエル・ローター(Michael Rother、以下MR):まずは、それらの曲を演奏することが楽しいというのが第一の理由だ。あと、音楽に対する私の考え方が昔から変わっていないというのもあるね。いや、少しずつ変わってはいるんだげど、それが円を描くように元の場所に戻っていく様子を、違った場所から眺めているとでも言うか……。私の場合、時にはより抽象的な音楽を好むし、メロディやリズムにより強い関心が向かうこともある。近年は、実験を更に重ねる必要性を感じているんだけど、オーディエンスたちは、速くリズミカルなビートを求めているように思える。まあ私も最近はそういったものも好きなんだけどね。
■昔の曲を演奏してほしいというリクエストが、プロモーターやファンから直接あるんですか?
MR:ない。それはあくまでも私が決めたことだ。だけど、ノイ!やハルモニアの曲をやると告知すれば、どんな感じのショウになるのかオーディエンスたちにとってイメージしやすいよね。だから昔の曲をやるとあらかじめ発表している部分もある。
■ノイ!やハルモニアは90年代以降に再評価のムーヴメントが興ったわけですが、その背景にはソニック・ユースやステレオラブのリスペクト宣言の効果もあったと思いますか?
MR:うーん、それはわからないけど(笑)……確かに、私たちは80年代には一旦忘れ去られた存在であり、90年代にはノイ!について話しているドイツのミュージシャンなんて誰もいなかった。でも、我々の音楽がCDや海賊盤によって世界中を移動した結果、ソニック・ユースやステレオラブといったバンド、あるいは『クラウトロックサンプラー』(95年)を書いたジュリアン・コープなどのミュージシャンがその音楽を聴いてくれた。特にジュリアン・コープの本は、大きな衝撃をもたらしたと思う。理由はわからないんたけど、ずっと、ドイツのジャーナリストは私たちのようなミュージシャンに対する理解がなかったし、誇りにも思ってなかった(笑)。そういう状況の中、「あなたの音楽は素晴らしい」と外部からやってきた人間に言われたわけだ。ノイ!のアルバムが2001年に〈Gronland Records〉から再発されたのは、大きな一歩になった。それら再発アルバムはそれまで以上にたくさん売れたわけで。
当時は、Eメールやウェブ・サイトなど、コミュニケイションにおいても大きな変化が見られた時期で、世界中の人々と直接連絡をとれるようになった。今や私はフェイスブックだってやっているからね。もっとも、更新にはさほど時間をかけているわけじゃないけど。たとえば東京でライヴをすることになったら、その報告をする程度で。自分の朝食にコンプレックスがあるので、それをフェイスブックに載せるなんて、とてもじゃないができない(笑)。
■90年代にはステレオラブが盛んにノイ!的なサウンドをやって人気を集めたわけですが、当時、クラウス・ディンガーはそれに対して怒っていましたよね。つまり、「おれたちのサウンドが盗まれた」と思っていた。あなた自身はどう思っていましたか?
MR:友人がステレオラブのライヴに連れて行ってくれたことがあった。私はそれまで彼らを聴いたことがなかったので、演奏が始まると「あれ? これは自分の曲かな?」と思ってしまったんだ(笑)。それはそれで面白いけどね。どんなミュージシャンも情報に晒されているので、そこから影響を受けることもあるし、むしろ影響に身を任せてしまった方がいろいろと楽なこともあるとは思う。
でも、私はそうじゃないんだ。ずっと、周囲とは違うことをやりたかったし、誰かのコピーではなくオリジナルになりたかった。だから私が満足することなんて、これからも決してないと思う。他人から「君のアイディアは20年前に別のミュージシャンがやっていたよ」なんて言われた日には動揺してしまうよね(笑)。もし音楽を作るのが好きなら、その創作活動のアイディアは、「なぜ音楽を作るのか?」というところからくるべきだ。そして心や空間に漂っているメロディやリズムを拾い上げる。そういうことをしないで、誰かのモノマネをするなんてけっしてやってはいけないことだと思っている。
私が音楽を始めたのは激動の時代だったので、新しいものを作ることによって自分自身の音楽的アイデンティティを獲得するのは自然なことだったんだ。当時は音楽だけではなく、芸術や映画、さらに政治や社会制度でも大きな変化が起こっていた。私の成長をそのような変化と切り離すことは不可能だ。私は“変化の暴力”とでも言うべきものに強く影響されたんだよ。
とはいっても、私が作った音楽に誰かが反応してくれるのは率直に嬉しいものだよ。オアシスやレッド・ホット・チリ・ペッパーズのような人気バンドまで関心を持ってくれているわけだしね(笑)。その結果、ある日、ジョン・フルシアンテに会ってセッションをして、ステージにも一緒に立つことになったわけで。共演がどんな感じになるのか最初は見当もつかなかったけどね。私だって、他のミュージシャンからインスパイアされることは大歓迎だ。いつも、新しいものを作るべきだと思っているからね。

photo: 松山晋也
ジミ・ヘンドリクスやビートルズを繰り返すことはまっぴらごめんだったんだ。とにかく違うことがしたいと、いつも意識していた。
■最近の若者たちが、ノイ!やハルモニアのようなプリミティヴなロック・サウンドに魅せられるのはなぜだと思いますか?
MR:それは、どうして音楽が好きなのかを尋ねるようなもので、とても難しい質問だな(笑)……でも、ちゃんと答えるなら……その楽曲がある特定の状況に結びついているものだからだと思う。私たちはゼロから物事を始めなければならなかった。音楽に対するラディカルなアプロウチをもってして、アメリカやイギリス的な構造を持つ音楽的過去から脱却する必要があった。つまり……「OK、いったん全部をぶっ壊そう。そして小さなかけらを拾い集めて、新しい方向に向かい、新しい音楽を始めよう」という具合に。ジミ・ヘンドリクスやビートルズを繰り返すことはまっぴらごめんだったんだ。とにかく違うことがしたいと、いつも意識していた。私は昔も今も、他の音楽に対しては敬意を抱いている。でもそれは私の音楽じゃない。私のラディカルさが若い人々に魅力的に映るかもしれないのは、こういった姿勢がいつの時代でも生じうるものではないからじゃないかな。
たまに「これはノイ!やハルモニアにそっくりじゃないか !?」と思う曲に出会うけど、それが先週録音されたものなのか、はたまた15年前の作品なのか知る由はない。なぜならそれは、音楽の発展の時間軸とは切り離されているものであり、私のしてきたこととは違うまったく新しい一歩だからだ。特定の時代の音楽のテイスト、さらにはファッションなどから切り離された独自性があり、新鮮に感じる……そういった曲を作る若者たちが、私の作品を聴いてくれているのは嬉しい限りだね。だいたい、自分と同世代の人間にしか音楽が届かないのは悲しいことだし。
■70年代初頭にクラフトワークに加わる前、あなたはいくつかアマチュアのバンドをやっていましたよね。スピリッツ・オブ・サウンドその他。当時は主にどのような音楽をやっていたんですか?
MR:私は65年にバンド活動を始めたんだが、その頃はまだギターを始めて1年くらいしか経ってなかったし、みんながみんなイギリスの音楽に夢中になっていた。ヒーローは言うまでもなくビートルズやストーンズだったから、私たちも進んでコピーをしていた。それを2~3年続けていくうちに、自分たちが何をやっているかがわかるようになり、即興演奏をするようになったんだ。そこから自分たちのアイディアを自由に持ち込むようになり、70年代に入る頃にはかなりの変化を遂げていた。あと、サイケデリック文化の影響などもあったよね。ひとつはっきりしているのは、そこにはいつも壁があったということだ。他人の音楽やポップ・カルチャーから引用してきたアイディアをいくら使っても、その壁の向こう側へは到達できなかった。つまり、そのドアを開けるために、いったん自分たちのやっていることをやめなければならなかったというわけだ。
取材・文:松山晋也(2016年9月13日)
| 12 |
Profile
 松山晋也/Shinya Matsuyama
松山晋也/Shinya Matsuyama1958年鹿児島市生まれ。音楽評論家。著書『ピエール・バルーとサラヴァの時代』、『めかくしプレイ:Blind Jukebox』、編・共著『カン大全~永遠の未来派』、『プログレのパースペクティヴ』。その他、音楽関係のガイドブックやムック類多数。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE