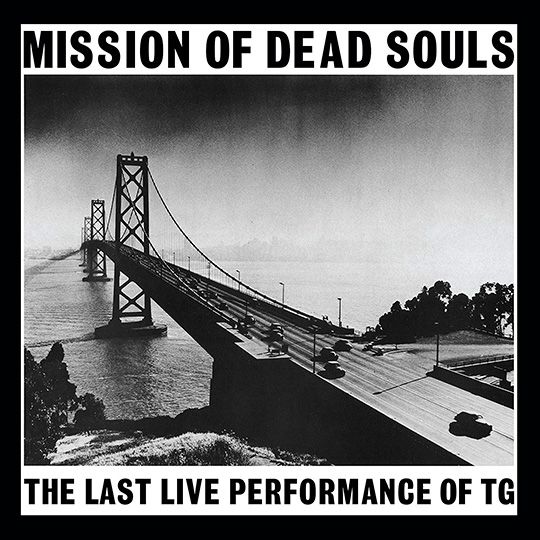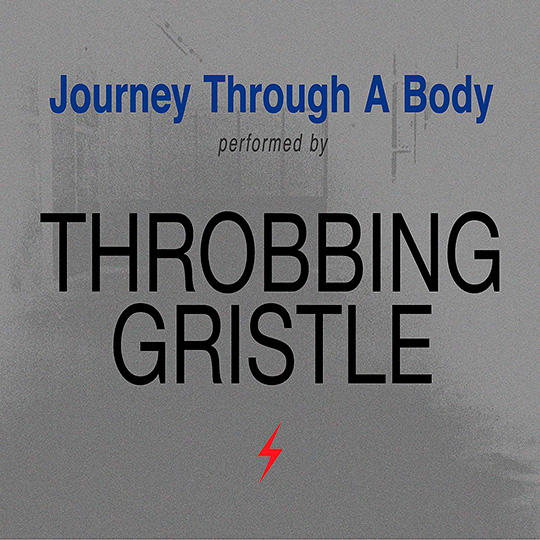MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - コージー、『アート セックス ミュージック』を語る
だから女性たちも、「セックスをしたらうっかり妊娠するかもしれない」という恐れを抱かずに済むようになった。そこである種の多幸感みたいなものが生じたし、突然、女性たちは「解放された!」と感じたわけ。ところがわたしたち女性が気づいていなかったのは、その解放感に伴う現実はどんなものか、ということで。
■ハルという暴力的な地方都市のなかで、労働者階級の娘として生まれ育ったあなたから見た1960年代の英ヒッピーのコミューン文化の描写も、興味深かったもののひとつです。この意見は間違っているかもしれませんが──少なくともわたしが思い出す限り、イギリスの「60年代カウンター・カルチャー追想記」や「シックスティーズの物語」みたいなものの多くは、いわゆる「スウィンギング・ロンドン」が中心に描かれてきたな、と。
コージー:ああ、そうよね。
■なので、当時ロンドンから遠く離れた地方都市で生きていて、基本的にはロンドンのヒッピーたちと同じようなことをやっていた人の目線から書かれた文章を読むのはとても新鮮でした。というか、「コージーはどうしてこういうことをやれたんだろう?」とすら。「なにもロンドン(首都)にいなくたって、アンダーグラウンドのカルチャーや精神に触発されるのは可能だ」と確認できて、その意味でも励まされました。
コージー:なるほどね。たしかに(地方都市で)ああいうことをやるのは、とても難しかった。そう言っても、自分の周りには仲間がいたし──かなり少人数のグループだったけれども。ただ、その小規模な集団だって、やがてどんどん大きなグループへと花開いていったんだけれどね……とはいえ、ハル全体の人口からすれば、わたしたちはごくちっぽけな集団だった。それでも、自分たちのやりたいことはこれだという、その決意はとても固い集団だったわね。
■平たく言えば、あなたたちは「ハルの変人集団」だった、と。
コージー:そう。わたしたちは変人だった。
■でも、あの時期のコミューン描写を読んでいて驚かされた──というか、いまでは驚きではないかもしれませんが、60年代文化というのはずっと「ラヴ&ピース」的に描かれてきたわけですよね。ところがあなたの本を読むと、実際は非常に男性優越主義なカルチャーだったことがわかる、という。
コージー:ああ、ほんと、そうだったわ。
■女性であるあなたは掃除・洗濯・食事作りの役目を負わされて、一方で男性連中は居間でなごみながら政治だの革命的なアイディアを話し合っている、という図式。あれを読んで、やはりちょっと驚いたんですよね。
コージー:うん、だから、あなただってヒッピー・ムーヴメントが起きていた時期というのは、「フリー・ラヴ」の時代だった、と思うでしょうし……
■ええ。男女問わずフリー、なので平等だったのかと思っていたら、そんなことはなかったわけです。
コージー:ええ、それはなかった。あの時点ではまだ男女平等は見えていなかったし……そうは言っても、ここで思い出さないといけないのは──あの当時、女性は避妊剤、ピルを手に入れられるようになったわけよね。女性たちも、「セックスをしたらうっかり妊娠するかもしれない」という恐れを抱かずに済むようになった。そこである種の多幸感みたいなものが生じたし、突然、女性たちは「解放された!」と感じたわけ。ところがわたしたち女性が気づいていなかったのは、その解放感に伴う現実はどんなものか、ということで。
だから、ええ、わたしたち女性も自由にセックスできるようになった。けれども、それは男性たちにとっても、誰かを妊娠させることなく、好きに誰とでもセックスできるようになった、ということであって。それは男性から見れば都合の良い、二重の勝利だったわけだけど、当時の女性にとっては決してそうではなかった、とわたしは思っていて。突如としてこの自由が手に入ってわたしたちはとても喜んだわけだけど、それが男性優越主義にどう影響するか、そこまで考えてはいなかった。わたしたちはただ「自由だ、最高」とばかり思っていたし、これで家庭から出られる、婚約し結婚して子供を作り、そして職に就くという、当時若い女性が進むべきとされていたルートから出られる、そうやって自由になれる、そう考えていた。ところがその自由は、制約や条件付きのそれだった、わたしはそう思っていて。というのも、当時わたしたちの周囲にいた若い男性たち、彼らにしてもまだ「家庭の主たる男」という考え方を持ち、そうなるべく育てられた、そういう世代の人間だったわけで。で、男は家庭において女性から奉仕されるもの、という。
■そういう男性たちにとって、ある意味60年代はハーレムのような状況になったわけですね。
コージー:そう! うん、実はそういうものだったんだと思う。そうは言っても、当の男性たちだって「自分たちはフリーだ、女性も解放された」、そう考えていたわけだけれども。そうやって分析してみると興味深いものよね。
■もちろん、男性がハーレム状況を作ろうとした、とは言いませんが──
コージー:それはないわよ。
■ただ、ピルにしても100%安全な避妊法ではないし、望んでいない妊娠をしてしまう女性もいるわけですしね。
コージー:わたしもそうだったしね(苦笑)。
■ええ……。で、妊娠は難しいなと感じるんですよね。わたしは子供を持たない身ですが、子供ができるのは素晴らしい経験だろうな、とは思うんです。母親になるのも女性にとっての新たな開花でしょうし。ただ、同時にそれが女性にとって足枷になる場合もあるわけです。男性は妊娠しないので、そういうジレンマは起こらないんだろうな、と。
コージー:そうね、男性の人生は妊娠にまったく左右されることなくそれまで通りに続いていく、と。妊娠による妥協というのは存在するし、そこで妥協させられるのはまず女性なのよね。だから、「子供を持とう」という覚悟を決めないといけない。子供を持つと自分自身の人生に影響が及ぶ、それを理解した上で決心しないと。それは自分に依存する誰か、自分自身よりも優先するべき誰かが自分の人生に現れるということだし、子供がまず第一になる。そういう責任を負うことになるわけよね。わたしとクリスが息子のニックを授かったときは、わたしもその点は理解していた。ただ、17歳で初めて妊娠したときの自分には、子供を持つことが自分になにを意味するか、まったくわかっていなかったのね。だから……とてもつらかったわ。というのも、いざ子供を持ってみると、若い頃の自分がやったこと、そのリアリティが再びぶり返してきてショックを受けるわけで。本当に、悲しいことだから。
■中絶や流産、そして妊娠といったことは、男性と女性とで影響の出方が違うでしょうしね。男性でも、大きくショックを受ける人ももちろんいますし。
コージー:ええ、それはもちろんそう。これは、女性も男性も共に、両方で進んでいかなくてはいけない問題だし。というのも、とてもエモーショナルな経験だから。子供を持つこと、その実際面も親の人生にもとても大きく影響するわけだけだけれど、「子供を持とう」と決心すること、それは男女双方にとって本当にエモーショナルな面で大きな決断なのよね。軽い気持ちでやれることではないから。ほんと、とても大変だしね。
■あなたとあなたの父親との関係から、当時のサブカルチャーやアート界であなたが味わったひどい経験、そしてジェネシス・P・オリッジの存在もふくめて、『アート セックス ミュージック』では父権社会というものが浮き彫りにされていきます。これは、意図して描いたものなのでしょうか、それとも包み隠さず書いていったらそうなったということなのでしょうか?
コージー:ええ、隠さずに自分の人生を書いていったらこうなった、ということね。というのも、実際に起きてしまったことは変えようがないんだし。あなたは父権社会というカテゴリーに入れるかもしれないけれど、それは実際にわたしが体験したのがそういうものだったから、なのよね。それ以外にも、男性優越主義、女性嫌悪といったものもそこにぴったりと収まるわけ。ただ、それらはわたしが自分で自分に対してやったことではなかった。
■ええ、どれもあなたの外部から発したものですよね。
コージー:そう! だからなにも、人びとの集まったところにわたしが入っていって、「どうぞ、女性嫌悪者として、できるだけひどい振る舞いをわたしに対してやってください。その体験について本を書くつもりなので」なんてお願いしたわけではなかったんだし。でしょう?
■(笑)ええ、もちろん。
コージー:だから……あれらが事実だった、ということ。で、事実というのは一部の人間の口に合わないこともあるわけよね。そういう人たちは、わたしはお立ち台に立って父権社会や女性嫌悪、抑圧云々について叫んでいるだけだ、そう考えたがっているわけだけど、そんなことはない。そうではなく、わたしはあれらを実際に「生きた」わけ。だからといって、それによって……わたしは犠牲者ではないのよね。自分が犠牲者だとはちっとも感じない。だからユーモアの存在も、そうした抑圧を乗り越えるための戦略だったんでしょうね。そしてまた、わたしを実際よりちっぽけな存在だと思わせようとする連中や、わたしの潜在的な可能性やなりたいものを目指す思いを引き留めようと足を引っ張る人間たち、彼らに対して挑んで反抗していく、という。自分の人生のはじまりの段階にしたって、父親とは──そうね、彼がいろんなやり方でわたしをコントロールしようとしたにも関わらず、わたしはいつだってそれを無視して外出し、やりたいことをやって支配に反抗してきた。そうやって外に出て、やりたいことをやったおかげで、わたしは最高に楽しい思いとものすごい充足感とを味わうことができた。で、そうやって楽しい思いをすること自体、支配に対するカウンター攻撃の一部でもあったのよね。そのせいでお仕置きを受けたわけだけれども、それにしたってまあ……罰を受けたりいろいろあったけれども、自分はこの家を出て行くんだ、それはわかっていたし、実際10代で家を出たわけだし。だから、家を離れる日が来るまで、自分はできるだけ楽しんでやる、そう思っていた。そうは言っても、門限を破っては父にぶたれていたわけだけど(苦笑)。
■にしても、せっかく父親から「逃れた」ところで、続いてあなたはジェネシスに出くわしたわけですよね。彼も最初のうちは一見フリーな精神の持ち主、ルネッサンス・マンっぽかったものの、やがてあなたを支配し意のままに操ろうとする面が出てきた。せっかく父親のコントロールから逃げ出せたのに、またもや人生に同じようなタイプの男性が存在することになったのは、あなたとしてもさぞやがっかりさせられた体験だっただろうな、と思いましたが。
コージー:ええ。でも、そこを見極めるのに半年しかかからなかったわ。
■(苦笑)なるほど。
コージー:彼との恋愛関係のはじまりの段階から、わたしはかなり懐疑的だったのよね。まあ、あなたからすれば「なんだってまた、彼女は彼を愛していると思ったんだろう?」と、さぞや不思議でしょうけれども。ただ、もうひとつあったのは、あの関係がはじまったときというのは、両親の家の外に広がっている自由な世界がわたしに見えたときと重なっていたのよね。で、その自由に至る道というのは、ヒッピーのコミューンに参加することだった、と。さっきも言ったように、付き合いの最初の頃から懐疑的だったし、だからあのコミューン内でも初めのうちは自分だけの一人部屋を借りていて、ジェネシスと一緒に暮らすことはしなかった。というわけで、そうね、家を出てわたしは外の世界に出て行ったし、ありのままの自分になれて、いろんな機会にも出会い、世界の中心に自分はいる、そんな思いを味わっていた。で、そこでもこの……イライラのタネに対処しなくてはならなくなったわけだけれども、あの手の苛立ちは、実家にいた頃から父親相手に体験してきたわけで。わたしにはもう経験済みのものだった、と。きっと、だからなんでしょうね、たまに「あんな目に遭わされたのにどうして我慢したんですか?」と、わたしの行動の理解に苦しむ、と言ってくる人がいるのは。でも思うに、そうね、17年ものあいだ父を我慢してきた経験を通じて、自分自身を失わずにいるには、自分のやりたいことをやるにはどうすればいいか、なんとかそれをやっていく方法を見つけ出していたわけで。それに、ある意味では……彼のやったこと、そして彼がどういう人間だったか、それらはわたしにとっても有用だったんだし。彼はわたしの役に立ってもいた、という。その面も考えに入れるべきよね。あの場にいたことは、実際わたしの役にも立ったんだし。
■なるほど。でも、そうやって自分に有利なものへと状況を引っくり返せたのは、あなたがそれだけ強い人だった、ということでもあるんでしょうね。仮にあなたと同じようなつらい立場に立たされた女性がいたとしたら、彼女たちの何人かは屈服させられ、黙らされていたでしょうし。
コージー:それはもちろん! だからなのよね、人びとが女性の側を責めて批判することに対して、わたしが賛成できないのは。人びとは「(そんなに苦しいのなら)どうして君は家を出なかったんだ?」、「なんで相手を捨てられなかったんだ?」等々……だけど、そうやって批判する側は、ひどい目に遭ったり虐待された人間とは違う類いの人びとなわけよね。そういう人たちに、「自分はこの状況から逃れることができない」と感じている人を批判する権利はないから。というのも、「逃れることができない」とその人間が感じる理由は本当にいくらでもあるんだし、それは感情面が理由なこともあるし、実際面や金銭面、ときに政治的な理由ということもあるし、あるいはまた、アートをやっていくために、その状況から脱出できないことだってあるわけで。
わたしがジェネシスと別れたのは、COUM〜スロッビング・グリッスルが本当に好調に進んでいたときだったわけよね。だから、あれは本当に大きな決断だった。というのも、わたしが彼から去ってしまったらCOUMもTGも終わるだろう、それは承知していたから。だけど、(笑)実はそれはどうでもいいことだったのよね。というのも、その先にはもっと素晴らしい、もっとずっと素敵なものが待ち構えていたんだし、それがクリスだった。でまあ、この本に関するインタヴューを受けるたび、話題はジェネシスに集中しがちなんだけれども、わたしの人生でもっとも大きかった存在、それはクリス・カーターなのよね。
■それは、わたしも本を読んで強く感じました。彼はどれだけあなたにとって意味のある存在なのか、と。
コージー:そう。だからそれ以前に起きてきたことはすべて、わたしがクリスに出会う瞬間、その場面にわたしを連れていってくれるのに役立ってきたものだった、という。で、彼と出会ったところで、それまで自分の経てきたなにもかもの意味がわかるようになった。だから、彼と出会う以前に自分に起きてきたこと、そのなにもかもが、彼とわたしのあいだにある「これ」、この関係こそ自分がこれから保っていくものなんだ、と気づかせてくれた、というか。そしてまた、愛とは本当はどういうものなのか、自分のアートや自分自身に対して満ち足りた思いを抱くのはどういうことなのか、そこにも気づかされた。
というのも、クリスのおかげでわたしはわたしを完全に信頼し、応援してくれる人を得たんだし、しかも彼にはわたしをコントロールしようという面が一切なかったわけで。それだけ、彼はわたしを愛してくれているのよね。でも、それが愛というものなのよ。愛している人間を変えようとは思わないでしょう? というのも、あなたはその人間をまるごと愛しているんだから。
■この本は、COUM〜TG〜クリス&コージーそしてX-TGへの物語であり、同時にひとりの女性の人生譚/サヴァイヴァル譚でもあります。女性からの共感が多かったと聞きますが、男性からのリアクションで、なにか面白い感想があったら教えて下さい。
コージー:どうなのかしらね、わたしは「女性/男性」と分けて考えることはないから……「人びとのリアクション」としか考えない。もちろんそういう見方をとることもできるけれども、それでもやっぱり、わたしはあらゆるジェンダー、セクシャルな性向に向かっていきたいし、それが本の基盤にもなっているわけで。だから、「ある人間」についての本なのよね。もちろん、「男性VS女性」の図式とか、トランスジェンダーだとか、みんなそれぞれに違う。ただ、これはある人間についての、かつあなたがいま言ったように、サヴァイヴァルについての物語であって。そうは言っても、わたしは自分に生まれついて与えられたもの、渡されたカードに対して闘ったことはなかったんだけれども。とにかくただ、自分には自分の人生のなかでやりたいことをやる権利がある、そう信じてきただけのことで。だからなのよね、この本に「男性/女性」という見方でアプローチしないことが重要なのは。
というのも、性別がなんであれ、やりたいことをやる権利は誰にとっても大切なことだから。そうは言っても男性のほうが、「自分にはこれをやる権利があって当然」という感覚が女性よりも強いものだけれども。ただ、自分自身を信じて、これはやらなくてはいけないと強く感じることをやっていくこと、それは誰にとっても大切。で、そうやって「自分はいったい何者なのか」を理解していくこと。それは大きな課題だわ。自分が誰かを理解するためには、様々な人生経験を経ていかなくてはならない。シェルターのなかに身を隠しているわけにはいかないのよね。というのも、人びとや経験、世界はそこに存在しているんだから。けれども……本当にたくさんの人たちから、本に対してとても素晴らしい反応をもらってきたわ。とは言っても、わたしはフェイスブック等々はやっていないから、あの手の場でなにを言われているかは知らないけれども。そもそも興味もないし、ゴシップだらけだしね。
■でも、この本を読み終えて真っ先に個人的に感じたのは、「若い女性に広く読んで欲しいな」ということだったんですよね。あなたの本なのでスロッビング・グリッスルやクリス&コージーのファンがいちばん読むでしょうが、いま「女性に読んで欲しい」と言いましたが、実際もっと広く、性差etcに関わらず様々な形での抑圧や支配に苦しんでいる人に読んでもらえたらいいな、と。そうしたコントロールに対する対処の仕方も書かれている、ドキュメントになっている本なので。
コージー:そういえば、面白けれども、友人から「世界最初の小説は日本人の女性が書いた」と教わったのよね(※紫式部の『源氏物語』と思われます)。
■ああ、はい。
コージー:だから、日本人女性のあなたから、わたしの本に対してそういう感想をもらうのはとても興味深いわね……うん、本当にそう思う。というのも、大昔の日本の宮廷で宮仕えしていた、そういう女性が小説を書いたわけでしょ? だからそれを考えてみれば、何百年も前の世界ですら、女性たちは「自分の思いを、言葉を聞いてもらいたい」という必要を感じていたわけで。で、彼女たちには耳を傾けてもらう権利がある。わたしたち女性はなにも、「沈黙したままの多数派」ではない、という。でも、そうね、とにかくこの本が、色んな層の多くの読者に届いてくれることを願っている。で、本を読んだ人たちにとっても、彼らの持つポテンシャルを活かして自分のありのままの姿を追求する、そのインスピレーションになってくれたら本当にいいな、そう思っているわ。彼らは彼ら自身であればいいんだし、流行りのファッションだとかを真似する必要はない。というか、わたしのやったことをコピーする必要すらないのよ。それくらい、誰の人生だってみんなそれぞれに違うんだし。
人びとが女性の側を責めて批判することに対して、わたしが賛成できないのは。人びとは「(そんなに苦しいのなら)どうして君は家を出なかったんだ?」、「なんで相手を捨てられなかったんだ?」等々……だけど、そうやって批判する側は、ひどい目に遭ったり虐待された人間とは違う類いの人びとなわけよね。そういう人たちに、「自分はこの状況から逃れることができない」と感じている人を批判する権利はないから。
■スロッビング・グリッスルという言葉は男根の暗喩ですよね。男根はパワーの象徴で、歴史的にも崇拝されてきましたが、それを敢えてグループ名にしたのはどうしてですか? ひとつのアイロニーというか、TG内においても暗黙のなかで反父権社会的/反マチズモ的なものがあったからでしょうか?
コージー:まあ、あのタームを使うことにしたのは、わたしの友人のレズ、彼がペニスを意味するタームとしてあれを使っていたからなのよね。その意味合いは彼がすっかり説明してくれたし、あれはそれまで、わたしたちの誰ひとり行き当たったことがなかった言葉で。それに、もうひとつあったのは……あれはバンドが普通だったら絶対にバンド名にしない、そういうものだったところ。
■(笑)なるほど。
コージー:というのも、あれはパンク以前の時代だったわけで。あの頃、「包皮」とか、そういう名前のバンドは存在していなかったでしょ。というわけで、スロッビング・グリッスルという名前は……だから、さっきも話した「笑える」点、ユーモアも関わっていた、ということ。誰かがレコード店に行って、「スロッビング・グリッスル(陰茎)のレコード、ありますか?」と尋ねる場面を想像する、という。
■(笑)。
コージー:だから、「バンドの名前だ」とわかっているつもりでも、そこにはダブル・ミーニングもある、という。そうはいっても、あの名前は「TG」に縮められてしまったんだけどね。クリスはあの名前が嫌いだから。
■らしいですよね。彼はいつも「グリッスル」か「TG」としか呼ばなかったそうで。
コージー:ええ。それから、前身だったCOUMトランスミッションズとの繫がりもあった。COUMのシンボルには「COUMペニス」があったし、あのペニスは性交後の萎えたそれだったけれども、そこからTGになったところで、勃って準備万端、世界を相手に固く立ち向かっていく存在になった、と。それが、わたしの見方ね。
■1970年代、セックス産業に与しているという理由によってフェミニストから批判されたあなたが、いまとなってはフェミニズム的な文脈のなかで評価されていることをあなたはどう感じていますか?
コージー:まったく問題なし。だから、どういう文脈にわたしの作品を当てはめるかそれ次第だ、という。わたしやわたしの代理人のギャラリー側に「こういう展覧会があるので作品を貸してほしい」という提案が届くと、わたしたちは話し合い、その展示の文脈にわたしの作品の本来持っていた意味がフィットするかどうか考えるし……だからとにかく、わたしの作品に対する評価の変化というのは、時代の変化、そして物事への姿勢が変化した結果だと思っていて。だからある意味、何年も前に自分のやっていたことに時代が追いついたんだな、と。いまの人びとはあの作品をありのままに眺めるけれども、発表した当時の人びとにはそういう風に観ることができなかった。ということは、早過ぎたのかもね? どうしてそうだったのかは、わたしにもわからないけれども。ただ、あれらの作品は現在の時代に居場所を見つけてみせた。とは言っても、そこまで何年かかったのかしら……それこそ、40年近く?
■(笑)ですね。長かったですね。
コージー:(苦笑)ええ。
■ただ、やっぱりあなたにも新鮮な気分だったんじゃないでしょうか。「受容」や「評価」があなたの目的だったことはなかったし、自分の作りたいアートを作るのみだったとはいえ、ああして時代が追いついたことは嬉しかったのでは?
コージー:まあ、クリス&コージーの作品にしたって、人びとがあれに追いつくのに10年近くかかったわけだしね。
■ああ、たしかに。
コージー:で、人びとが追いついた頃には、わたしたちはもうカーター・トゥッティに変わっていた、という。でも、それはいまでも続いているのよね。人びとはカーター・トゥッティ・ヴォイドを求めているけれども、わたしたちは既に他のなにかに取り組んでいる。たとえわたしのやる仕事の一部に対する人びとからの受けが良いからといって、それに足止めを食らわされるわけにはいかないから。わたしのやっているのはそういうことではないんだし……いま現在にしたって、わたしは他のことに取り組んでいるけれども、それでも人びとからはわたしたちが10、20、30年くらい前にやっていたようなことをやって欲しい、と求められる。だけど、自分の持ち時間のなかで、自分にやりたいことは他にもっとあるから(苦笑)。
■常に先を行っているんですね。
コージー:いいえ、そんな風に考えたことはない。とにかく、常に自分のやりたいことをやっているだけ(笑)。
取材:坂本麻里子+野田努(2018年9月12日)
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE