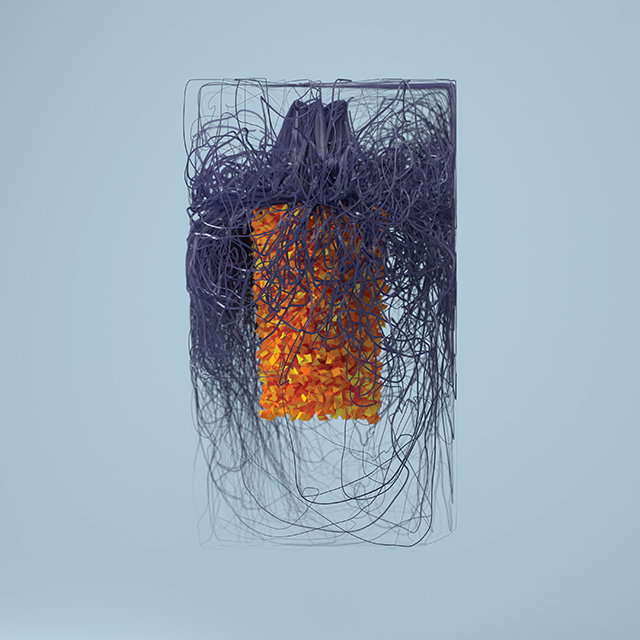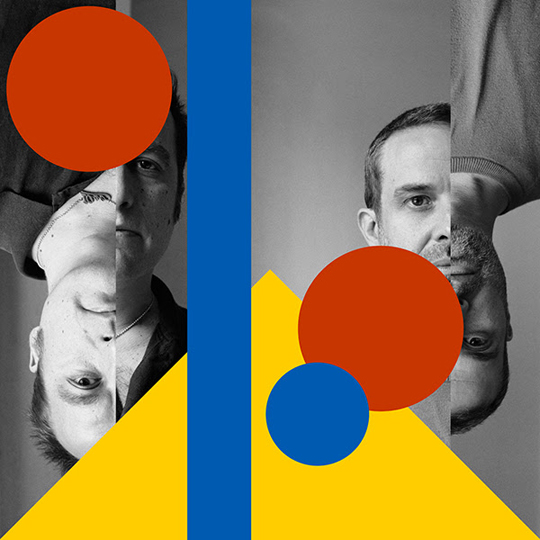MOST READ
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す
- Cindytalk - Sunset and Forever | シンディトーク
- Fumitake Tamura ──「微塵な音」を集めたアルバム『Mijin』を〈Leaving Records〉より発表
- Stones Taro ──京都のプロデューサーが新作EP『Foglore#1』をリリース
- Geese - Getting Killed | ギース
- Reggae Bloodlines ——ルーツ時代のジャマイカ/レゲエを捉えた歴史的な写真展、入場無料で開催
- Columns 内田裕也さんへ──その功績と悲劇と
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Visible Cloaks ──ヴィジブル・クロークスがニュー・アルバムをリリース
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- interview with Toru Hashimoto 30周年を迎えたFree Soulシリーズの「ベスト・オブ・ベスト」 | 橋本徹、インタヴュー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Quadeca - Vanisher, Horizon Scraper | クアデカ
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- キングギドラ ──『空からの力:30周年記念エディション』のインスト・ヴァージョンと96年作EP『影』がアナログ盤で同時リリース
- Street Kingdom 日本のパンク・シーンの胎動期を描いた、原作・地引雄一/監督・田口トモロヲ/脚本・宮藤官九郎の『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』が来年3月公開決定
- R.I.P. Tadashi Yabe 追悼:矢部直
- Father John Misty - I Love You, Honeybear | ファーザー・ジョン・ミスティ、J・ティルマン、フリート・フォクシーズ
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
Home > Interviews > interview with Plaid - ヴェテランが紡ぐ、調和と衝突の美しき重合体

なんでこれを新鮮でおもしろいと思う人たちがいるんだろうと思うんだけど、その人たちは元ネタを聴いたことがないんだって気づくわけだよ(笑)。それに飽きちゃってるのはちょっと歳をとった僕らのような人たちだけなんだよね。(エド)
いろんな分野がロボットに乗っとられて、音楽もそうなるっていうジョークをよく聞くけど、でも僕はそれをとくに脅威だとは思っていない。それも含めてさまざまなものが混ざったときにそこから何か新しいものが出てくればいいと思うんだ。(アンディ)
■美しい旋律もプラッドの大きな特徴です。それは今回も“Maru”や“Dancers”、“Nurula”や“All To Get Her”などに表れていますが、メロディを書くときに意識していることはなんですか?
AT:重点を置いているのはそれぞれがそのメロディにたいして感情の部分でどう反応するかっていうことだと思う。それが作る上でのガイドになっているというか。そのメロディが自分のなかのどんな感情を呼び覚ますのかっていうことだったりね。音符が正しく並んでるときっていうのは聴けばわかるんだよ。
Maru (Official Audio)
■他方でプラッドはリズムも多彩です。リズムを組むときにもっとも意識していることはなんですか?
EH:僕らの場合はメロディ・ラインからはじめることが多くて、しかもリズムはメロディに本来備わっているもので、だからメロディがリズムを方向づけることが多い。でもその逆の場合もたまにあって、とくにごくありがちな表現に抗いたいとか、少し外したもの、尖ったもの、散乱したものが作りたい場合はね。ただ通常リズムは定まってることが多いと言えるかな。それはおそらくリズムが僕らにとって二次的なものだからだと思う。メロディ・ラインが主導するというのが僕らのアプローチだからさ。もちろんときにはキック、スネア、ハイハット以外のサウンドも使いたいとは思ってるけどね。まあまだ勉強中かな(笑)。
■“Meds Fade”や“Ops”、“Dust”など、今作は声へのアプローチも印象的ですが、あなたたちにとって声とはどのようなものなのでしょう?
AT:まあ僕らはふたりとも、残念ながらとくにいいシンガーとは言えないんだ。というわけでシンセティックな声を使うことが多いんだけど、結局は他の楽器と同じように使っているんだと思う。声が曲の構成の中心点にならないようにしているというか。なぜなら言葉をとおしてメッセージを伝えようとしているわけじゃないからね。というわけで声はテクスチャーやレイヤーとして使ってるかな。
■この2月に、あなたたちの参加するリピートのアルバム『Repeats』が〈Delsin〉からリイシューされましたけれど、これはどういう経緯で?
EH:これは、あのアルバムを一緒に作ったマーク・ブルームが〈Delsin〉との繋がりがあって、それで実現したものだよ。マークは僕らの友だちでありミュージシャンでありDJで、〈Delsin〉は古いテクノ・レコードだったりエレクトロニックのレコードをリイシューする傾向があるところで。マークとはいまも繋がってるし、彼はいまもDJしたりプロデュースしたりしてるよ。
■そもそもあのコラボは1995年当時、どのようにはじまったものだったのですか? 『Spanners』と『Not For Threes』のあいだの時期ですよね。
AT:友だちと一緒にやろうっていう感じのものだったんだ。マークのことはあれを作る数年前から知ってて、彼は当時、リピートの4人目のメンバーであるデイヴ・ヒルと一緒にやってたからね。あれはいま思うと僕らにとってもっともジャム・セッション的に作った音楽のひとつだったね。何回か集まって、それぞれがシンセサイザーを持ってて、みんなで車座になって音を鳴らして、それをシークエンサーで録ってさ。すごく楽しいプロジェクトだったよ。
■近年はバイセップやダニエル・エイヴリー、シェフィールドの〈CPU〉など、90年代のテクノから影響を受けたサウンドが話題にのぼることが多々ありますが、オリジネイターであるあなたたちの目に、そのようなリヴァイヴァルはどのように映っているのでしょう?
EH:何かが繰り返したりループしたりするのは、なかなか理解するのが難しい。自分が好きだった、あるいは自分も参画したものがふたたびポピュラーになると、ちょっと退屈だなって思うことがたまにある(笑)。自分はすでにやったわけだし、進歩を見たいわけだからさ。でもじつは同じままで繰り返すことってほとんどなくて、どこかが新しく改良されているし、リヴァイヴァルされるまでのあいだには他の影響もいろいろ挟んでるからね。だからいま言ったような人たちも90年代テクノのサウンドを使ってるけど、超プロデュースされた、超改良されたヴァージョンになってたりするんだよ。だから、なんでこれを新鮮でおもしろいと思う人たちがいるんだろうと思うんだけど、その人たちは元ネタを聴いたことがないんだって気づくわけだよ(笑)。それに飽きちゃってるのはちょっと歳をとった僕らのような人たちだけなんだよね。それにたいして文句はないし、そうやってサイクルが続いていくんだろうし、音楽はずっとそうやって続いてきたんだと思う。しかも遡って古いレコードを聴いてみようって人もいるから、そういう意味で言うと素晴らしいことだと思うよ。
Recall (Official Audio)
■今年で〈Warp〉は30周年を迎えます。レーベルの方針や雰囲気やスタッフ、置かれた状況などにかんして、『Bytes』(1993年)を出したころともっとも変わったところはどこだと思いますか?
EH:それほど変わってないと思う。悲しいことにだいぶ前にロブ・ミッチェルが亡くなって創設者のひとりを失ってしまったというのはあるけどね(※2001年)。それがレーベルにとってはいちばん大きな変化かな。もうひとりの創設者であるスティーヴ・ベケットも昔ほどは積極的な役割を担ってないしね。でもそれ以外は、何人かほぼ最初からいる人がいまもいて、James Burthton(※表記不明)なんかはもうずっと長年いて、ほとんど僕らと同じくらい長いんじゃないかな(笑)。だからずっと変わらない部分もあって、A&Rも相変わらず革新的で興味深いものを見つけてくるし、選ぶ基準も比較的変わってないと思うし、まあいまのほうがもう少し洗練されたものになってるかな。それから、いまは「〈Warp〉とはこういうレーベルだ」っていう定義ができあがってるけど、はじまったばかりのころは未定義でレーベルがみずからを形成していくようなところがあったね。でもその他は、アーティストにかなりの自由が与えられているインディ・レーベルであり、多くの音楽好きが知っているほどのブランド力があるという部分は、ずっと一貫していると思うし、その一部でいられることにたいしてありがたいと思ってるんだ。
■最近はA.I.の話題をさまざまなところで見かけ、じっさいそれを用いて作曲している音楽家もいます。A.I.が音楽にもたらすものとはなんだと思いますか? A.I.が作る音楽と人が作る音楽に違いはあると思いますか?
AT:僕らもたまにアルゴリズムを使ってメロディやリズムを作ることはあって、それはたとえば、ほとんどセッション・ミュージシャンと仕事をするような感覚というか、つまりはアルゴリズムに演奏してもらって、それを聴いてその一部分を使ってさらに自分たちの好みに改良するとか。だからひとつの情報源として使っているような感じかな。いろんな分野がロボットに乗っとられて、音楽もそうなるっていうジョークをよく聞くけどね。優れたプログラムであれば、人間よりもすごい音楽を作れるようになるんだっていう。でも僕はそれをとくに脅威だとは思ってなくて、それも含めてさまざまなものが混ざったときにそこから何か新しいものが出てくればいいと思うんだ。
■日本では6月2日に映画『鉄コン筋クリート』が地上波で放送されるのですが、当時の裏話があれば教えてください。
AT:最初に監督(※マイケル・アリアス)から〈Warp〉に連絡があったんだ。彼はその何年か前に僕らのライヴを観たとき、いつか自分が映画を監督するときは僕らに頼みたいと思ったそうだよ。僕らにとっては『鉄コン』が初めてのサウンドトラックだったから、監督が僕らを起用することはかなりの賭けだったはずだけど、僕らにとってはまたとない機会に恵まれて嬉しかった。でも何しろ大部分が手描きというあの映画の性質上かなり時間がかかって……おそらく4、5年かかったのかな。そのおかげでサウンドトラック入門編としてはかなり緩やかなものになった。何しろアニマティックを参照しながら1年以上かけて作ることができたからね。
■いま音楽以外でもっともやりたいことは?
EH:ライヴのための映像をちょっとやってて、音とシンクロするイメージを作ったりしてるんだ。それはふたりとも興味を持っているかな。もちろん音楽以外にも興味を持ってることはあるけど、キャリアとして考えると音楽以外の仕事は難しいだろうな。創作にかんして言えば、いろんな人とコラボレイトすることでほんとうにいろんな音楽ができるから、自分たちにとって音楽がおもしろいものであり続けているんだよ。音楽にはまだまだ発見がたくさんあると感じてるし、学ぶべきこともまだまだたくさんある。調べることや探求することもたくさんあると思うし、自分はまだひよっこだと感じるよ(笑)。まだ100年分くらいやることがあると思う。
質問・文:小林拓音(2019年6月07日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE