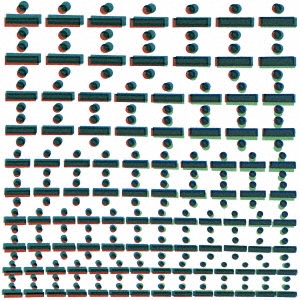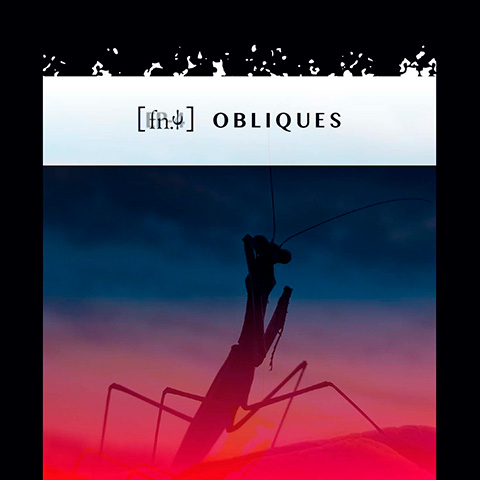MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Kaoru Sato - 甦る、伝説のエレクトロ・ノイズ・インダストリアル
■佐藤さんの場合はシステムに対するテロリズムじゃないですけど、音楽のメタなところから揺さぶりをかけるみたいなことをしてきたと思います。R.N.A.にもその感覚があるのかなと思いましたが、先ほども言いましたが、DJだったことが大きかったように思います。
佐藤:非常に大きいと思います。いろんな箱でまわしましたから。六本木でもやっていたし、関西に移ってからはパートタイムで何件か回るみたいなことをやってたんです。だから、ほかのDJがやっていないようなこと、違うことを意識して、工夫してやるようになった。いまでは当たり前ですけど、当時はあまりそういう考え方はなかったと思います。選曲もそうですけど、どういうミックスをするか、そういうことには人一倍気を使ってたところはありますね。
■当時の佐藤さんの選曲リストとかみたいですね。
佐藤:75年くらいまでは基本的にブラック・ミュージックばかりだったんですけどね(笑)。
■しかしなぜ佐藤さんは、ディスコから離れてパンクやポスト・パンク、あるいはクラウトロックみたいなとこにいったのでしょうか?
佐藤:ひとつ大きかったのはアフリカ音楽とブラジル音楽でした。それに当時のディスコには制約があって、70年代前半からかけたいけれどかけられないというフラストレーションがずっとあったんです。同時にアメリカのリズム&ブルースがどんどん判で押したようなディスコ・ミュージックになっていってしまった。そういうことが重なったんでしょうね。
■佐藤さんにとって、クラフトワークやポスト・パンク的なものの魅力とは何でしたか?
佐藤:黒くないのに踊れることと、汗をかかないこと(笑)。単純にダンス・ミュージックとして新しいという直感。そこがいちばん惹かれたところじゃないかな。
■失礼な言い方になってしまいますが、ぼくのなかで佐藤さんはリチャード・カークとすごく重なっているんです。
佐藤:ははは。
■だって、あの人たちはもともとブラック・ミュージックが大好きですよ。それがああいうインダストリルなサウンドになった。インダストルになってからも、キャブスには強いビートがあるじゃないですか。同じように、ブラック・ミュージック的なものは佐藤さんにもずっとあるんだと思います。だからEP-4にはファンクがあるわけだし、じっさい数年前にユニットでやったライヴでもパーカッションを取り入れてリズムには注力されていた。決してホワイティ―な音楽とも思えないんですけど、ブラックネスがないところに共感したとはどういう意味でしょうか?
佐藤:おそらく黒さって言い方がちょっと違うのかもしれませんが、どういったらいいかな……、ビートがこう埋没していくような音楽が、まぁいわゆるブラック・ミュージックのなかから生まれてきたら面白いなと、いまそう思ってるんですけどね。波形としては明らかなリズムを持たない音楽がブラック・ミュージックのなかから出て来たら面白いんじゃないかと、ぼくはずっとそう感じているんです。わかりやすい音の例だと、サン・ラや電子マイルスの弾くシンセサイザーかな。クラフトワークにはそれがあった。ノイにもそれを感じたんです。これで踊ったら気持ちいいなと。まあどちらも現代音楽的遺伝子の濃い音ですから、特殊なウイルスが情報交換に関与したのかも──というのがR.N.A.オーガニズムのスタートアップコンセプトの中核です(笑)。
■やっぱり、佐藤さんにはダンス・ミュージックというコンセプトはひとつありますよね?
佐藤:それはありますね。だから、ダンスにはけっきょくビートがなくてもいいんじゃないかとなってきたんですよね。70年代の終わりから80年代くらいにクラブ・モダーンでDJをしていたとき、その前後にはいろいろ違う曲もかけましたけど、完全なノイズ・ミュージックでも人が踊りはじめたんですね。そのときの状況をみて、やっぱりそういうことだったんだと確信しましたね。まあ、外から見ると異様な光景でしたけどね。
■でもひょっとしたらそれが20年早いことをやってたかもしれない。
佐藤:ははは、まぁそうですね(笑)
■メビウスとコニー・プランクの『Zero Set』が1983年だから、アフリカ音楽とヨーロッパ的なるもののミクスチャーは70年代末から80年代初頭にかけてあったひとつの共通感覚なんでしょうね。京都では佐藤さんがそれを実践されていて、ほかの都市でもそうしたことが起きていた。
佐藤:そう思いますね。ただぼくの場合は、踊りを突き詰めて電子パルスに行ってしまった。リズムを切り刻んだり圧縮/伸長してるうちに、人間の技では認識不可能なハイパーポリリズムや、数年に一拍刻まれるような日々の生活に埋没したリズムというか、リズムではなくパルスに行きついたというね。『Zero Set』の名が出たので補足しておきますが、オーネット・コールマンの『Dancing In Your Head』なんかも複雑なバイアスのかかったミクスチャーとしての共通感覚を感じますね。『Zero Set』のひと時代前の作品ですが、オーネットは母国よりヨーロッパで圧倒的人気があったし、特にドイツでは現代音楽を学んだりしていてクラウトロック周辺には影響力があったと思います。

でも当時これを出していたらやっぱり厳しかったなっていう感じはします。アナーキックなパンクのように受け取られて、そのままでは理解されなかったんじゃないかな。やはり適切な時間というのは必要かと。長いか(笑)。
■佐藤さん個人としては今回R.N.A.オーガニズム出すにあたって、どのような感想を持ってますか?
佐藤:けっきょく記憶との戦いになっていて、俺ほんとにこんなんやっていたのかなっていう(笑)。まったく記憶にないものもあったり面白い。でも当時これを出していたらやっぱり厳しかったなっていう感じはします。アナーキックなパンクのように受け取られて、そのままでは理解されなかったんじゃないかな。やはり適切な時間というのは必要かと。長いか(笑)。
■でも〈Vanity〉って、当時3〜400枚とか、そのぐらいの枚数しかプレスしていないじゃないですか。しかも海外には熱を入れてプロモーションしたようですが、おそらく国内ではほとんどされていませんよね。こういう音楽がもっとしっかりした流通のもとプロモートされてリリースされていたら、日本の音楽シーンも少しは違ったものになっていたんじゃないかなと思いますけどね。ぼくなんか全然知らなかったし。佐藤さんにとっては、いまこうやって評価されることは複雑だったりしますか?
佐藤:阿木譲は意図してなかったと思いますが、はなから〈Vanity〉は日本の音楽シーンに向けて音を発信していたレーベルではなかったように思います。R.N.A.の場合も明らかに海外からのオファーが多くて、R.N.A.は〈Vanity〉のなかでも特殊なのかなという感じはしますけどね。だいたい〈Vanity〉はいろんなものを出していて、それこそプログレからパンクまで。ヴァイナル・コレクター向けのショーケースみたいな。そこでもR.N.A.はちょっと特殊だったと思います。
■この時代の佐藤さんにとってなにか大きな影響ってありましたか?
佐藤:このころは本当に目まぐるしい時代だったので、とにかく場所のことや音のこと、そういうものを支えるための組織を作ったりだとか、そっちのことをより考えていましたね。自分たちでオーガナイズして演奏できる場所をもっと広げていくということですね。音楽に関しては、ぼくは自分でやる音楽と聴く音楽があまりに違うので人は驚くんですけど、聴いていたすべての音楽から影響されているんじゃないでしょうか。
■それでは別の質問にいきます。佐藤さんにとって阿木譲さんとはどういう存在でしたか?
佐藤:ぼくと阿木さんの関係は、あんまり触れちゃいけないと思われているみたいです。でもじっさいは、ぼくと阿木さんと特別なにかあったわけでもなんでもないんです。むしろいい関係にあったんじゃないかな、とぼくは思っているんだけど。ただ、周りからはね、阿木さんからこうされた、ああされたという話ばかりでね(笑)。
■佐藤さんがそこであいだに入ったりしたんですか?
佐藤:それでぼくが煙たがられる存在になってしまった。だから『ロック・マガジン』にはEP-4のことはまったく書かれていないんです。
■ポスト・パンク時代に日本からは良い作品がたくさん生まれているんですけど、いくつかのレーベルに関しては問題があったという話は聞きますね。UKの〈ラフ・トレード〉みたいなレーベルはアーティストとの契約の仕方まで公平にするよう変えましたけどね。
佐藤:阿木さんはもともと歌手だったから、歌手時代に自分がやられたことと同じことをやってしまったんでしょうね。ただね、亡くなるちょっと前にも同じようなことがあったんですよ。〈Vanity Records〉の音源に関しては全部自分だけのものだって言い張るわけです。歌謡界と同じ発想で日本初を謳うインディー・レーベル運営しちゃうのはまずい。いくらなんでもそれはない、少なくともアーティストとレーベル半分半分だと思います。
■少なくとも著作権は曲を作った人のものです。
佐藤:基本はアーティストのものですが、阿木さんはスタジオ代を払っているから、そういう意味では一緒に作ったようなものじゃないですかと言ったんだけど、死ぬまで譲らなかったですね。だから曲が切り売りされていたこともあったりして。しかも無断でやるんです。ほかのアーティストも同じことをさんざんされている(笑)。いくら音楽を聴く耳が先端でも、そんな態度では音楽もDIYもへったくれもないですからね。まあ晩年はずいぶん落ちついたようですが。
■今回、R.N.A.についての当時の阿木さんの文章(https://studiowarp.jp/kyourecords/r-n-a-organism-%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88-1980/)を読ませていただいたんですけど、何を言いたいのかぼくには理解できない文章でした。ただ、熱量は感じますけどね。
佐藤:音楽の紹介誌としては先端をいっていたとは思います。
■それはたしかにそうですね。それでは、松岡正剛さんは佐藤さんにとってどんな存在ですか?
佐藤:松岡さんはもう、お兄さんみたいな存在ですね。
■松岡さんは佐藤さんのことが大好きなんですよね。いまでも佐藤さんのことを話しますから。
佐藤:77〜78年ぐらいですかね、松岡さんが京都に遊びに来てらしたときに初めて会いましたね。別人だと思っていたDJをやっている人間と音楽を作っている人間が同一人物だったことが松岡さんには面白かったそうです。松岡さんが京都に来るといっしょに遊んでもらって、ぼくが東京にいたときには泊めてもらったりしていました。
■佐藤さんは一時期音楽活動から遠ざかってましたが、この十年間は精力的に動いています。レーベルも始められていたり、活動を再開されていますけど、現在のようにはじめた理由はなにかあったんですか?
佐藤:いちばんの理由は居所を探し出されてしまって、音源を形にしてくれる〈ディスク・ユニオン〉がアーカイヴとしてちゃんと取り上げてくれたことがきっかけです。以前にもそういう話はぽつぽつあったんだけど、一切応じなかったんです。自分で作ってきた音は自分たちでやりたい形で表に出したかった。EP-4以外の仕事を形にしてくれるんだったら活動を再開しましょうという話で始まったんです。
■2018年から〈φonon〉もスタートされていますが、レーベルをはじめたのはどんなきっかけがあったんですか?
佐藤:2013年くらいからレーベルのやり方をいくつか考えていました。アナログがやりやすくなってきたということで、当初はアナログ盤のレーベルを考えていたんです。同時にEP-4の新作を作りたいと思っていましたから、アーカイヴがひと段落したところで、そういう作業に入りつつあったんですけど……、一身上の都合というか、家族の介護にシフトしなければいけないことになって、いま信州に住んでいます。だから、移動しないでレーベルをやる方法を考えはじめたんです。ネットと知り合い関係をうまく繋いで、制作費基本ゼロの現物支給でという最低限のシステムを考えて、これだったら電子系の人たちとか、すでに音源を持っている人に声を掛けたらなんらかのかたちでやっていけるんじゃないかなと。それで始めたのが〈φonon〉です。
だから、一般的なバンド形態の音はちょっと無理なんです。制作費もないから、録音スタジオを使うのも難しい。フィジカルで出したいと思うものがあれば聴かせてもらって、ぼくの方でも面白いと思ったら出すという。レーベル側でのネット配信による販売は基本ありませんし、すべての権利はアーティストが持つので配信したい場合は自由にしてもらっています。お金をかけないで、最低限の流通は確保して、なおかつアーティストは現物支給で手売りすれば、最低限の収入にはなる。だいたいそういうシステム・モデルができたので、なんとかここまで続いてます。
■もうそろそろEP-4の新作が出てもいいんじゃないかなと(笑)。
佐藤:いまのところどうしようもないです。EP-4の命運は家族の案配にかかっているとよく言われます(笑)。
■そうですか、でもシングルぐらいはそろそろ聴きたいですね。今日はどうもありがとうございました。
(2月26日、ZOOMにて)
試聴リンク(シェア可):https://audiomack.com/sp4non
φononレーベル・サイト:www.skatingpears.com
取材・序文:野田努(2021年7月12日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE