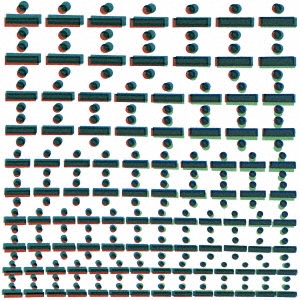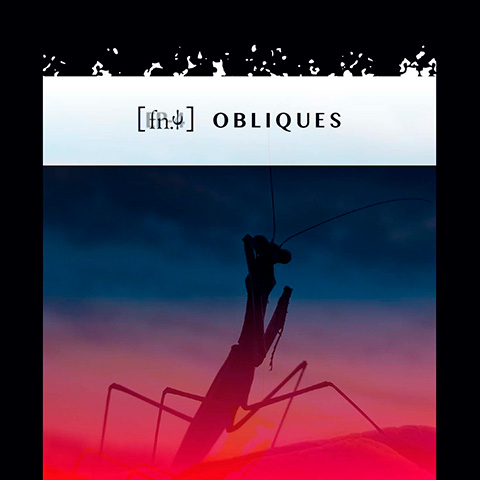MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Kaoru Sato - 甦る、伝説のエレクトロ・ノイズ・インダストリアル
「過去をコントロールするのは誰だ」と言ったのはジョージ・オーウェルだが、音楽作品における未発表曲集というのは、ときに過去の意味を変えることができる。じっさいはもっと違った音楽がプロデューサーやレーベルの意向によってひとつの局面にのみ焦点が当てられた場合は、とくにそうだ。1980年に大阪の〈Vanity〉から『R.N.A.O Meets P.O.P.O』なるアルバムをリリースしたR.N.A.オーガニズムという佐藤薫がプロデュースしたプロジェクトの未発表音源集を聴いていると、思い通りに発表できなかった過去が現在において新鮮に聴こえることもありうるのだと、あらためて思う。高価に取引されている1980年の〈Vanity〉盤をユーチューブで聴いてみると、なるほどたしかに時代を感じさせて面白いのだが、棚からキャバレー・ヴォルテールの“Nag Nag Nag”を引っぱり出していることは明白で、しかし佐藤薫のレーベル〈φonon〉からリリースされる未発表音源集『Unaffected Mixes ±』においては、より抽象的で、このプロジェクトの遊び心と実験性がより際立っている。ときには(それこそその後のEP-4に通じるところの)露骨なまでの政治性もあり、R.N.A.オーガニズムのラディカルで、アイロニカルな表情は際立っている。暗い時代に虚飾の明るさを描くのではなく、むしろ悪夢を描いて逆説的に夢を見るというメソッドは、それこそ70年代末のUKポスト・パンクの多くがやったことだった。
以下のインタヴューは、今年の2月にZOOMにて収録したもので、R.N.A.オーガニズムや今回リリースされる『Unaffected Mixes ±』についての話以外にも、ぼくにとって佐藤薫は近くて遠い人だったこともあって、作品のこと以外にも、個人的に知りたかったことも脈絡なく訊いている。散漫になってしまったことをお詫び申し上げるとともに、その全貌がいまだ不明瞭なままの日本のポスト・パンク期における重要な記録(ドキュメント)に注目していただけたら幸いである。(敬称略)

ティアックのカセットマルチトラックレコーダーが79年に出るんですよね。それによってかなり状況が変わりました。まず、スタジオではなく家でも自由な時間に音を作れるようになった。それで、どんどん断片を作っていった。
■R.N.A.オーガニズムのことはまったく知らなかったんですけど、今回聴かせていただいてまず思ったのは、いまの音だなと。たとえば〈Edition Mego〉や〈Diagonal〉みたいなレーベルから出ても全然不自然ではない音ですよね。佐藤さんもそう思ってリリースするのでしょうけれど、まず、この作品をお出しになることの経緯みたいなところから教えてください。
佐藤:ちょっと複雑でしてね。基本的にこれらは〈Vanity〉での音源なんですよ。〈Vanity〉で録った1枚目のアルバム(『R.N.A.O Meets P.O.P.O 』)の音源をもとに、ぼくたちが自分たちで勝手に作っていたやつなんですよね。要するに、阿木譲が諸々の事情によってリジェクトし、出さなかった音源です。
■もともとは〈Vanity〉で出すつもりで録音したものだったということでしょうか?
佐藤:いや、〈Vanity〉で出した作品を録ってるときに、仮落としとかの音源をカセットコピーしていろいろ自分たちでカットアップ/ダビング/編集などアレンジしていたんです。でも一応〈Vanity〉でスタジオも用意してもらって録ったものですから、好き勝手にするつもりはなかった。阿木譲との関係がもっとうまくいってれば早いこと出せてた気もするんですけどね。まあ、当時出たアルバムのほうは、阿木譲の好みによってストレートな感じのミックスのアルバムになってるんですね。その意味ではボツテイク集ということになります(笑)。
■今回この未発表音源を出すにあたって、佐藤さんのほうである程度リマスタリングはされたと思うんですけど、若干の、音の加工みたいなことはされたんですか?
佐藤:曲の頭出しで削ったりしたほかには加工はほとんどしてないです。あと断片を多少つなげたりしたトラックも入ってますね。で、カセットで残っていたので、すべて一度しっかりアップコンバートしてからリマスタリング的作業をしただけです。
■R.N.A.における佐藤さんの役割は、全体のプロデュース、サウンドのプロデュースですか?
佐藤:そうです。録りはじめたのが78年くらいで、初期の音源も入ってるんですけど、みんなでリハーサルスタジオで遊びで録ってた音源も含まれています。〈Vanity〉で出すという話になった段階で録音したものもありますし、大阪でのレコーディング中に録音したものもあります。
■佐藤さんはもともとは京都でずっとDJをされてたんですよね。R.N.A.の人たちは佐藤さんのDJに来るような人たちだったんですか?
佐藤:ではないです。美大の学生であったり、ひとりはディスコの従業員というかそんな感じで(笑)。みんな音楽家ではない。好きに集まって遊んでいた一部がユニット名を名乗ってやりはじめた感じですね。
■いまだとこのサウンドはグリッチとかミニマルとかインダストリアルとか呼ぶと思うんですけど、冒頭にも言ったように、いま聴いて充分に魅力があるサウンドだと思いました。だからこの先駆的作品が、佐藤さんとバンドのメンバー3人のあいだでどうやって作られていったのかを知りたく思います。
佐藤:アルバムのリリースが決まったころ、ティアックのカセットマルチトラックレコーダー(CMTR)〈タスカム244〉が79年に出るんですよね。初代ウォークマン発売と同じ年です。それによってかなり状況が変わりました。まず、スタジオではなく家でも自由な時間に音を作れるようになった。それで、どんどん断片を作っていった。あらかじめ曲があって作っていたわけじゃないんですよ。それまでは、オープンテープやカセットテープを再生しながら音を重ねてダビングしたりと、面倒で涙ぐましい作業を練習スタジオで繰り返していたわけです。宅録黎明期の到来です。大音量のアンプ出力や繊細な生音はスタジオにCMTRを持ち込んで録音。それを自宅であれこれいじりまくるという。それにCMTRだと、ちょっとした過大入力でサチッたり特定の音源で隣の別トラックに音漏れしたりと、ピグマリオン効果というか実験者効果がおもしろくて。CMTRはプロやプロの卵の音楽家に貢献したのはもちろんですが、アマチュアや非音楽家にとっては革命的ツールでした。
■ちょっとエキゾティックな感覚のコラージュも試みていますよね。1981年にはイーノとデヴィッド・バーンの『マイ・ライフ・イン・ブッシュ・オブ・ゴースツ』が出て来ていますが、ああいうの出たとき俺らのが早かった、とか思いませんでした(笑)?
佐藤:そこまでは思いませんでしたけど(笑)。ただ、ぼくはDJでそういうことをやっていましたね。
■クラフトワークやカンと同時にフェラ・クティやブラジル音楽なんかもかけたりしていたそうですね。
佐藤:そう。それ以外にも、かけ方であったりとか、BPMを合わせるとかそういう単純なことではなく、エフェクトを入れたり、LチャンとRチャンで違う曲を流したり、そういう遊びをぼくは70年代から相当やっていたんです。だからサウンドをコラージュするということに関しては、ぼくのなかでは自然だったんですよね。
■DJだったということが大きかったんですね。
佐藤:いまから考えるとそういう気はしますね。
■率直にいってキャバレー・ヴォルテールからの影響を強く感じたんですけど、実際はどうでしたか?
佐藤:みんな好きでしたからね。アイドルと言ってもいいくらい(笑)。
■〈Vanity〉から出ているアルバムはキャブ色が強いですよね?
佐藤:そうですね、それは阿木さんの好みも大きい(笑)。〈Vanity〉のアルバムでは、曲の体を成さないような感じのミックスやDJ仕様のビートトラックを使ったものは、全部リジェクトされてしまったんです。今度出す未発表トラック集にはたくさん入ってるんですけどね。
■今度〈φonon〉から出るアルバムの音源は、かなりアブストラクトですもんね。
佐藤:そうですね。
■阿木さんがボツにしたという今回の未発表のほうが圧倒的に尖ってます。
佐藤:阿木さんはライヴもしてほしかったんで、最初のアルバムではわかりやすい曲をピックアップしたということだと思いますよ。
■でも、当時じっさいのライヴはやらずにカセットテープだけ流したんですよね?
佐藤:そう、そうなんですよ(笑)。なにも説明せずに流れるもんだから、インターミッションのBGMのように通り過ぎて、メンバーが客席にいても誰も気づかないし気にも留めないという事態となりました(笑)。
■それはもう、佐藤さんらしい発想じゃないですか? いかにもEP-4的な。
佐藤:そうですね(笑)。まあ、本人たちもまったく音楽家でも何でもなかったんでね。だったらそういう形でやってみようかと。
取材・序文:野田努(2021年7月12日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE