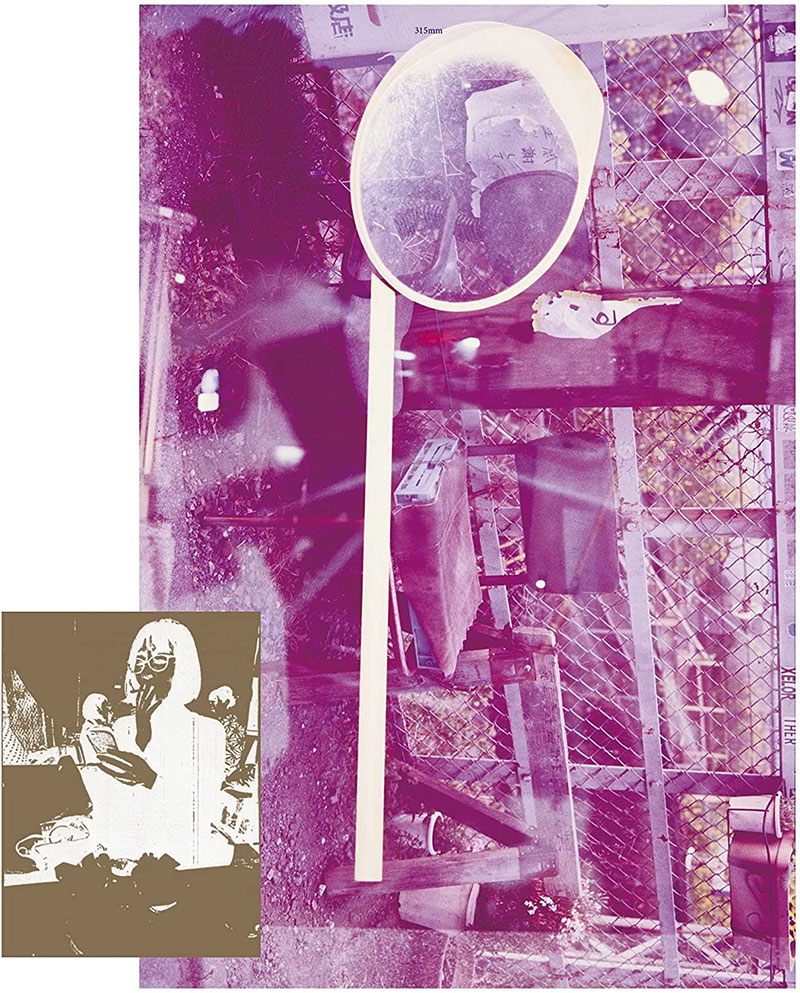MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > Interview with Phew - 音が導く、まだ誰もみたことのない世界
Interview with Phew
音が導く、まだ誰もみたことのない世界
——Phew、新作『New Decade』における他者と過去とのつながり
ツアー先の英国で手渡された一枚のメモをきっかけに生まれた『Vertigo KO』は既発の電子音楽作品を編んだ、いわば単独者=Phewの集成ともいえるものだった。そこにはアンビエントな風情のエレクトロニック・ミュージックの傍らに本家を漂白したかのようなレインコーツのカヴァーがあるかと思えば、幽玄の境地にあそぶ電子音とヴォイスによる山水画のごとき作品もあった。この多彩さは2014年の『A New World』を皮切りに、2017年の『Voice Hardcore』、翌年のレインコーツのアナとの共演による『Islands』とつづくPhewのソロ時代が、いかにひろがりをもつかの証でもある。あるはいその起点を、小林エリカ、ディーター・メビウスとのProject Undark名義の『Radium Girls 2011』にみるなら、東日本大震災の翌年にリリースのしたこのアルバムからそろそろ10年の月日がたとうとしている。
十年紀をひとつのサイクルとして、そこに意味をみいだすことに私たちはなれきっている。とはいえ体感をもって俯瞰可能な時間の厚みは事後的な気づきをうながしもする。『Vertigo KO』から間を置かずとどいたPhewの新作のタイトルが『New Decade』と知ったとき、私は来たるべき十年紀への無根拠な楽観より、いままさに終わろうとする時代への透徹したまなざしを感じたのだった。むろんこのことは『New Decade』が後ろ向きだということではない。電子音楽という、いささかクラシカルな用語が、テクノロジーをさすばかりか、私たちの身体のかかわりを問い直すことで新たな展開をみせてきたように、Phewはこの新作で最初のいち音が導く過程をたどってエレクトロ-アコースティックの新領域に達している。電子音だけでなく、そこには声があり、ギターとノイズがあり、リズムがあり、言語と意味の切断線が走っている。聴覚的な快楽とも観念的自足ともちがう、Phewの新十年紀を問うた。

まず構想とかコンセプトから離れるということがおおきかったです。ひとつの音を出してその音に導かれて次の音が出てくるみたいなつくり方でみんな録音しています。最初に構想を立てるのではなく、なにもないところでまず音を出し最初の音が次の音を呼んでく。
■『New Decade』の制作は去年の秋口にははじまっていましたよね。
Phew:自主制作でね。松村さんに、音源ができてもいないのにライナーをお願いしましたよね。
■それもあってトラフィックの中村さんにご連絡いただいてちょっとおどろきました。
Phew:今年に入ってから、1月あたりに中村さんからご連絡をいただき、私もびっくりしたというか、それはすごくうれしいおどろきだったんですけど。
■偶然ですか。
Phew:偶然です。私は自主で出すつもりでいろいろすすめていたので。
■そもそも自主で出そうと思ったのはいつで、きっかけはなんだったんですか。私が拝聴したのは『Vertigo KO』が出てまもない時期だったと記憶しています。
Phew:このアルバムはそもそも『Voice Hardcore』を録音し終えたあと、次のステップのつもりで、ずっと温めていました。家で録音はしていたんですが、一昨年録りためたものはこれはダメだということ全部捨てたんです。
■どこがダメだったんですか。
Phew:聴いてこれはダメだと(笑)。アルバムにつながるものではないということですよね。(『Voice Hardcore』と)同じところで足踏みしている作品だと思ったといいますか、これはいっぺんゼロにしてイチからはじめたのが2019年です。その年は海外のツアーが多かったです。
■『Vertigo KO』は海外ツアーの結果生まれたアルバムともいえますよね。
Phew:レーベル(Disciples)に未発表音源をおくって、曲を選んだのが2019年の暮れでした。そこから選曲が終わった時点で次のアルバムということで、制作、録音を再開したときは2020年になっていました。
■『Voice Hardcore』の続編の位置づけとなると、その要素は――
Phew:電子音とヴォイスということですね。
■じっさい『New Decade』はその感触ですよね。途中で制作を断念したものの『Voice Hardcore』のながれは生きていたんですね。
Phew:ながれは継続しているんですけど、いっぺん録りためたものを2019年で全部チャラにして、新たにつくろうと思ったのは2019年のツアーから帰ってきた12月、もしくは2020年あけた直後ですね。
■2020年の秋口に私は1曲だけ、いま“Into the Stream”になっている楽曲の音源を拝聴しましたが、最初に手がけられた楽曲でしょうか?
Phew:そうです。『Vertigo KO』の最後の曲、ヴォイスだけの短い曲(“Hearts And Flowers”)のつづきからできた感じです。キーも同じだと思います。
■“Hearts And Flowers”から“Into The Strom”ができた、と?
Phew:そうです。
■ということは『Voice Hardcore』だけでなく『Vertigo KO』からのながれをふまえていた?
Phew:はい。

ギターは弾いたというよりは鳴らした――がちかいかな(笑)。ギターの音は好きでね、ここにギターの音があれば、と思って、やむをえず自分で弾いたんですが、こうしたい、でもできないというギャップは楽しかったですよ(笑)。
■よくある質問ですが、『New Decade』を制作するにあたっての構想はなんだったんですか?
Phew:そうね、まず構想とかコンセプトから離れるということがおおきかったです。ひとつの音を出してその音に導かれて次の音が出てくるみたいなつくり方でみんな録音しています。最初に構想を立てるのではなく、なにもないところでまず音を出し最初の音が次の音を呼んでく。そのうえで“Into The Stream”などは途中にハイチのヴードゥっぽいリズムがほしい、と頭のなかでそれが鳴りはじめるようなことがあった、でも最初から決めていたわけじゃない。
■電子音と声という枠組みはあっても内実は出たこと勝負だったということですか?
Phew:自分が出した音がどこに連れて行ってくれるかなということですよね。だけど、それを1枚のアルバムにするときに、ちょっと行き詰まったといいますか。とくに2020年にパンデミックになったじゃないですか。ずっと家にいて、出てくる音が閉所恐怖症的なものになると、自分で聴いていてもしんどいんですよ(笑)。中村さんにご連絡をいただいたのが2020年の1月で、その時点でアルバムにするだけの長さはあったんですけど、それで1枚にするのは私はいいとしても、聴くほうはヌケ感がなくてしんどいかもしれない。そんなことを考えていた今年1月、アルバムの制作も終盤にさしかかっていたころ、rokapenisこと斉藤洋平さんがANTIBODIES Collectiveの東野祥子さんの映像を撮るということで音楽の依頼があったんです。映像作品の場合、音楽をつけてはみたものの、うまくいかなくてボツテイクになるトラックがあるじゃないですか。それをアルバムにあてはめてみるとすごく解放感をおぼえた。その結果できたのが2曲目の“Days Nights”です。第三者の視点といいますか、あれはおおきかったですよ。第三者の依頼がなければ、ああいうリズムボックスの曲はできなかったですよ。
■リズムのニュアンスから次の“Into The Stream”の露払い的なイメージでしたが、関連はなかったんですね。
Phew:後から並べてみた結果でした。
■東野祥子さんは京都ですよね。
Phew:そう聞いています。
■お会いして相談されたわけではなさそうですね。
Phew:全部メールとZoomです。斉藤さんはライヴのVJをやってもらったり、これまでご一緒させてもらったこともあるんですけど、東野さんはANTIBODIESの公演はみたことはありますけど、お話したことはなくて、いまはみんなそういう感じですすんでいくから実感がないですよね。
■たしかに私も『Vertigo KO』のときもオンラインで、今回もそうですから、Phewさんとお話はしてもお会いしてないですもんね。
Phew:誰とも会ってないですよ。2日ぐらい前にひさしぶりに録音があって、そこに生きている人間がいるだけでベタベタさわりたくなっちゃいました(笑)。
■わからなくもないですけど、では生活はたんたんと変わらず、といった感じでしょうか?
Phew:もともと積極的に外に出て行くほうではないので、ずっとうちにいるのは苦にはならないんですけど、それって選択じゃないですか。どこにでも行けるけど私は家にいるというのと、家に居ざるをえないというのはぜんぜんちがいますよ。
■作品を音楽的な要素に分解して分類するのが正しいかはわかりませんが、『New Decade』を聴くと、電子音と声のほかに打楽器音が耳につきます。それとギターがあります。今回Phewはギターを弾かれたとうかがいました。
Phew:弾いたというよりは鳴らした――がちかいかな(笑)。ギターの音は好きでね、ここにギターの音があれば、と思って、やむをえず自分で弾いたんですが、こうしたい、でもできないというギャップは楽しかったですよ(笑)。
■2000年代以降のアナログシンセのリヴァイヴァルはギター・サウンドの退潮とパラレルだったと思うんですね。アンチギター・ミュージックとして電子音といいますか。
Phew:だってギターは弾けなきゃはじまらないですか。電子音楽は(鍵盤楽器が)弾けなくてもできてしまう。パンクのとき、みんな楽器をもったことなくてバンドをはじめたということになっていますよね。でもやっぱり弾いているんですよ。スリーコードであってもコードを押さえているしドラムも稚拙とはいえエイトビートを叩いている、その点でパンクのなかでいちばんパンクだったのはモリ・イクエさんですよね。
■私もDNAを思い出していました。
Phew:なにがもっともパンクかといえばDNAのモリさんのドラムですよ。だってね、パンクといってもみんなリズムを刻んで、どんなにズレていてもフィルインを入れたりしますよね。だけど、モリさん、DNAは曲の途中でドラムが止まったんですよ。これはすごいと強烈に思いました。ドラムはリズムを刻む楽器だという役割からこのひとは自由なのだと。『No New York』では、私は圧倒的にモリ・イクエさんのドラムとマーズですね。DNAはギターで語られることが多いじゃないですか。
■アートさんのギターの革新性はよく話題になりますよね。
Phew:ちがいます(笑)。新しかったのはモリ・イクエさんのドラムです。ギターも好きですけど、新しいとか新鮮というのはちょっとちがう。ご本人はとくに意識していなくて、やりたいようにやった結果だと思いますが。逆説的にいうと、ほとんどのパンク・バンドは制度から自由じゃなかった。最低限のことはできるように練習はしましたから。
■Phewさんも当時練習されました?
Phew:私はヴォーカルだから(笑)。ギターがヘタだとかいわれつつも、ちゃんと練習はしていたし巧い。今回ギターを演奏してみてギターをやっているひとはみんなすごいなと思った。Fがね。
■何年音楽をやっているひとと話しているかわからなくなりますが、家にギターがあってもPhewさんはふだんギターを手にとることはなかったわけですね。
Phew:定期的にさわってはいたんですけど、コードという時点で止めちゃうんですね。かといってデタラメに弾いておもしろいことってそんなにないというか、すぐあきてしまう。弾けないと自由にあつかえないというかおもしろいことができるようになかなかならない。
■そこまでわかっていてもギターの音がほしかったからつかってみたということですね。
Phew:頭のなかでピーンっという音、単音なんですが弦を弾いて出る音が鳴ったんですね。その弦の感じがほしかったんです。
■“Into the Stream”にもその音がありますね。
Phew:ギターのノイズっぽい音がはいっていますね。
■最初にとりかかった“Into the Stream”にギターがはいっているということは、ギターも音色のパレットの上に最初からあったということですね。
Phew:極一部ですけどね。それとB面の1曲目。CDだと4曲目の“Feedback Tuning”です。
■最初につくったのが“Into the Stream”で最後“Days And Nights”だと、のこりの順番はボーナストラックの“In The Waiting Room”をのぞくとどうなりますか?
Phew:2作目が“Snow and Pollen”。3月で雪が降っていて花粉症と雪が一緒に来たということを歌っていたんですけど――
■私はライナーで東日本大震災をひきあいに出しましたが、ひとつの考えということでおゆるしいただくとして、では3作目に手がけた楽曲は?
Phew:“Feedback Tuning”ですね。それから“Doing Nothing”~“Flash Forward”とつづきます。
■そして最後が“Days And Nights”がくるわけですね。曲が出そろって最後に曲順を考えたということですか?
Phew:録りためた曲を並べつつ確認していたので、“Flash Forward”も最後のほうで撮ったんですよ。今年にはいってすぐくらいかな。全体的にあまりにも声がうるさいというかね(笑)。情報量のない曲が必要だと判断したんですね。
■『Voice Hardcore』や『Vertigo KO』でも声はそれなりの比重を占めていたと思いますが、それらとはちがうんですか?
Phew:活字の情報をいっぱい調べていて、情報つかれが去年、今年とあると思うんですね。
■「意味」ということですよね。
Phew:「ひとのことば」ですね。「意味」のないことをいっていても、人間の声はそこにあるだけで耳をそばだたせてしまう。私たちは意味があろうとなかろうと、声から情報をとろうとするが習慣になっている。それは自分の声だけじゃなくてひとの声もそうです。それがしんどい。どうしてもしゃべっているひと、声を出したひとのなにかが伝わってしまう。
■私などは習性的にそこに意味を読もうとする傾向がつよいのかもしれません。Phewさんのおっしゃるとおり、2曲目や5曲目に疎らな空間があることでくりかえし聴けるポイントになったと思います。
Phew:この感覚っていまが最初ではなくて、震災後は歌を聴くのがしんどかったですよね。どうしようもないことが起こっていて、現にひとが進行形で死んでいて、それはどうすることもできない状況で、そんなときに音楽、歌って……というのと似ている気がしますよね。
■それもあって震災から10年目にあたる今年世に問わなきゃいけないと考えたのではないか、とライナーで述べた気がします。
Phew:世に問うつもりはなかったですが、つながった気がしてすごく助かりました。でも自主制作じゃなくて中村さんから声をかけてもらって、外の世界とつながりができたのが、生き延びさせられてもらった感じがします。
序文・取材:松村正人(2021年10月21日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE