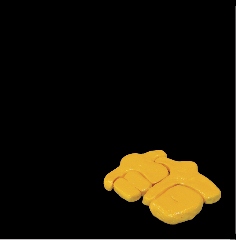MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > 左右- 左右
凡庸な生き方とは、凡庸を2ミリほど超える人間にとってはかなりしんどいものだ......いまなお絶滅することのない『地下室の手記』(ドストエフスキー)型自意識をかかえる人間が、ペンではなくギターを手にしたとき、たとえば左右が誕生するのだろう。ギターとドラム(ベース兼任)のシンプルな編成、まだ25を出ないくらいのかぼそい男女デュオである。彼らは2010年に出会い、楽器を手にした。きっかけは「ふたりともあぶらだこのファンだった」ことだそうだ。凡庸を2ミリ超える自意識である!
そうしたことは、この絶妙に踊れない変拍子(野田努)と棒立ちの演奏スタイルによくあらわれている。踊れれば、あるいは関節がやわらかければ、そもそも彼らは音楽をやっていないかもしれない。それはまさに"神経摩耗節"なるリズムであり、落ち着くところのない精神の依り代である。若さゆえの混乱とみまがわれるかもしれないが、けっしてそのためばかりではない。ある種の人間が生真面目に生きていこうとするときに、このような硬直性を帯びてあまりうまくいかなかったりすることを、われわれはよく知っている。
しかし社会生活においてはそうでも、音楽としておもしろいかたちを結ばせることができれば救われるというものだ。アヴァンギャルドな雰囲気を極力控えめにただよわせ、ポスト・パンクを大枠として、歌とギターがユニゾンする、言葉の立った個性的なフォームを生み出している。神経症的な変拍子に、ガリガリと痩せてとがったファズ・ギターがひっかくような軌跡を描く。それが傷などの表象に癒着しないのは、このふたりの隠れた牧歌性のためだ。フューを意識したような桑原のヴォーカルは、声質自体が甲高くてハリがあるためだろうか、じゃりん子のようにはつらつとした不屈さを感じさせる。花池はメグ・ホワイトに吹っ飛ばされそうなキックを打ちながら「今日も俺は/真に受けるぜ/いちいち俺は/気にするぜ」と自身のしょぼさ正直さをユーモアにする。こうした性質の端々から、彼らのいっけん突飛な音楽性が、奇態やエキセントリックを偽装するものではなく、むしろそうしたものへの嫌悪からひねり出されてきたものだということが想像される。
彼らはなかなかむずかしいテーマを扱っているのだ。「生きにくさ」「退屈さ」「不合理性」等々を、負け組的な視点から糾弾していくスタイルでは、往々にしてまったくありふれてしまう。当事者性や言っていることの正しさはほとんど関係ない。つまらない日本語ロックやパンクの多くはこうした罠にはまってしまうように見える。だがリアリティを歌うためにはもっとべつの力や工夫がいる。
彼らは健闘しているのではないだろうか。先に述べたようなユーモアもそうだが、詞を立てた曲作りも、詞を目的として終わらせないようによく工夫が凝らされている。"箱のうた"では桑原が声で伴奏をとり、一種の閉塞感をテーマとするこの曲を、間違ったシリアスさへと導かないようにとぼけさせている。皮肉にもジョークにもならず、花池の詞が届いてくる。クレジットでは作曲はすべて花池のようだが、詞は分担していて、作詞者がヴォーカルをとるというダイレクトさもいい。それぞれの曲はおもに作詞者の曲と考えてさしつかえないのかもしれない。"河童"や"悩みのマーチ"など桑原作詞の華のある楽曲は、やはり桑原の表現力によって支えられている。作品全体がそのようにわりと明確に2色にわかれておのおのを対象化する。さしずめ左右、というところである。録音も、スカスカでごくミニマルな形態ではあるが、スタジオで録りっぱなしという感じでもなさそうだ。とくにヴォーカルは意識されていて、構築性が感じられる。
本作リリースは2012年で、初EPといったたたずまいであるが、昨年ライヴ会場限定で販売されていたというデモが、本作収録音源と同一のものかどうかはわからない。この形態にしばられず、もっといろんなものをやってほしいと思った。やって"全然駄目"でも「気まずい空気を吸う為」("全然駄目")と思って、彼らの地下室から音と言葉を飛び立たせてほしい。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE