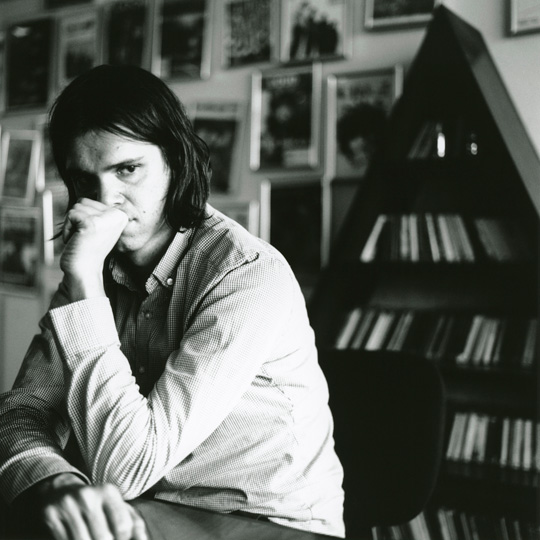MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Dirty Projecters - コンテンポラリー・ポップの知性
『スウィング・ロー・マゼラン』がすばらしい。ダーティ・プロジェクターズがキャリアの峠を越えたと勝手に合点している人は2度振り向くことになる。とはいえ筆者自身も漫然と期待していたひとりだった。はや6枚にもなるフル・アルバムのリリース、前前作はシーンに驚きをもたらし、前作は各メディアから絶賛を受けた2000年代の名盤として不動の地位を得ているうえ、昨年はビョークとのコラボEPという破格の課外活動もパッケージ化。このうえ度胆をぬくような作品など、そうそうできるものだろうか?

 Dirty Projectors Swing Lo Magellan Domino/ホステス |
この10年ほどのインディ・ミュージック・シーンにおいて、ブルックリンという土地名にわれわれが連想するのは、アーティで奔放な実験主義者たちの姿である。多文化混淆的なムードもそこにつけ加えられるだろうか。イェーセイヤーやTVオン・ザ・レディオらの名にならんで、ダーティ・プロジェクターズもまたその列をかざる存在である。だが今作にはそうした高い方法意識から解放されたようなところがある。どことなくこのバンドのキャラクターを形成していた学生気質な青さやかたさがすっと抜け、とても素直にエモーションが流れだしていて、それがため息がでるほどすばらしいのだ。さまざまな文化を参照したフォークロアは、今作ではただ彼ら自身のフォークへと姿をかえ、ダイレクトに心を打ってくる。ラフな作風になったのではない。彼と彼らの構築的な音楽性は、より緻密に、より洗練されることで目につきにくくなったという感じだ。"スウィング・ロー・マゼラン"など、ほんとにささやかな曲なのである。だが、そこにはあふれるようにエモーションがたくしこまれているし、"ダンス・フォー・ユー"のストレートな歌心や情愛にみちたストリングスにはふるえがくる。なんということだろうか。筆者はデイヴ・ロングストレスという人の、創作に対する深い深いモチヴェーションに完全にうたれてしまった。『ビッテ・オルカ』(2009年)までで、やることをやったという自信があったからこそ、彼は力強くつぎへと踏み出すことができたのだろう。箸やすめの1枚ではない。音楽をやるというのは本来このようなことだということを思い知らされずにはいられない、気にみちた作品である。
インタヴューは音源を聴いた翌日であったから、筆者の興奮が勝りすぎていることがよくわかるだろう。プロモーションのためにひとり来日したソング・ライター、デイヴ・ロングストレスは、なかなかクセのある人物ではあった。夕闇がせまるなかでわざわざサングラスを取り出す彼を奇人と呼ぶのは狭量だろうか? だが死生観からチルウェイヴ論議まで、その理知的な語り口はじゅうぶんに彼の人となりをつたえている。時間切れでオキュパイについて聞けなかったことが心残りだ。
いろいろなものを愛してしまうということと、いつだって死んでしまいたくなるということとの間には、ほんとにせまい、細くてうすい境界線があるだけで、僕はいつもその間を行ったり来たりしている。
■あなたのなかにある民俗的なモチーフ、たとえばエストニアや東欧のフォークロアを思わせるハーモニーや、アフリカの民族音楽からインスパイアされたようなヴォーカリゼーション、また中東的な雰囲気など、いろんなエスニシティが圧縮されたようなモチーフはどこからくるものなのでしょう? あなた自身、それらに関係した強烈な音楽体験があったのですか?
DL:多くの人がコーラス・ワークとか強烈なヴォーカル・ラインとかにブルガリアの音楽を感じたり、テレキャスターとかで弾いてるギターの音が西アフリカを彷彿させたりするって言うし、言ってることはわかるんだけど、いまこの時代、それらはグローバルなこの世界においてじゅうぶんアクセス可能な音楽であって、もはや未知の音楽ではけっしてない。ガレージ・ロックをやっていたりする人にはこういうものは必要じゃないかもしれないけど、僕のやってる音楽はただそういうヴォキャブラリーを持っているってだけだよ。
■今作も非常にエキサイティングでした。きっとよく指摘されていると思うのですが、"スウィング・ロー・マゼラン""インプレグナブル・クエスチョン"などとてもシンプルでフォーキーな曲にも驚かされました。あなたのなかのフォークというテーマが一周して自国のフォークと向かい合うようになったのではないかと思ったのですが、どうですか?
DL:まあ、そのとおりかな。これまでの作品が80年代のハードコア・ミュージックだったりブルガリアの声楽だったりっていう世界中の音楽からの影響を受けたものであるのに対して、今回はすごくシンプルでダイレクトでパーソナルなものにしたかった。ほかの国の音楽のある特定の要素を集めることにこだわった作品ではないんだ。だからほかのジャンルとは関係ないっていう部分で、必然的にドメスティックな、アメリカのフォーク・ミュージックに近くなっていくのかなって思うよ。
■いい意味でとても力が抜けていて、しかしとてもタイトなつくりの曲が多かったと思いました。かつ保守的になったわけでもない。聴くのがとても気持ちいいという感じと、音楽としてとても立体的でエキサイティングだという感じが両方満たされていて、本当にすばらしいと思いました。
DL:今回いちばん気にしたことは、けっして完成されたものをつくりたいわけではない、ということなんだ。未完の部分が残ったものをつくりたかった。この時間、この瞬間を切り取って記録することにフォーカスしたかったんだ。もちろん演奏を適当にする、とかそういう意味ではない。
■"インプレグナブル・クエスチョン"などはあなたのなかの「コンポーザー」というよりは、「シンガー・ソングライター」というキャラクターが表にあらわれてきたもののように感じました。あなたはとてもエッジのたった音楽を追求するとともにキャロル・キングとかトッド・ラングレン、あるいはジョン・レノンなど、すぐれたシンガー・ソングライターたちが立っているような地平に立ったのではないでしょうか。
DL:ああ、なるほどね! はははっ。僕自身のパーソナルな表現だからね。
■その意味では『ザ・グラッド・ファクト』を10年越しに完成させたものだっていう感じもしますね。
DL:そうそう、それはたしかにあるね! 原点回帰って意味じゃないけど、ファーストのころに戻った感じ。シンプルにしていった方向性っていうのはたしかに似ているかもしれない。
文:橋元優歩(2012年7月13日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE