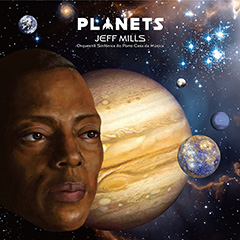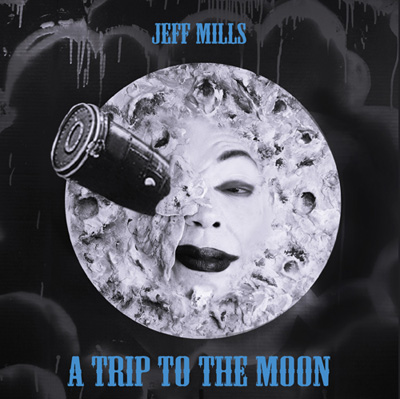MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Jeff Mills - 未来を考える理由
ハード・ミニマルとは、ジェフ・ミルズがひとりで切り拓いたダンスのサブジャンルだ。最近ではそれが、大雑把に言って、インダストリアル・ミニマルとして呼び名の元でリヴァイヴァルしている。20年後にして、『ウェイヴフォーム・トランスミッション』のようなサウンドをふたたび聴くことになるとは思ってもいなかった。そして、ジェフ・ミルズがそうしたリヴァイヴァル現象を良く思っているはずもなかった......。
昨年の、彼自身のレーベル〈アクシス〉20周年を記念してのベスト盤『シーケンス』を経てリリースされるジェフ・ミルズの新作は、驚くべきことに、宇宙飛行士である毛利衛との共作となった。毛利衛がストーリーを書いて、ジェフ・ミルズが音を加えた。『ウェア・ライト・エンズ』=明かりが消えるところ=闇=宇宙ないしは宇宙体験がテーマだ。
精力的な活動を続けながら、とにかく迎合することを忌避し、誰もやっていないことにエネルギーを注ぐデトロイト・テクノの重要人物のひとりに話を聞いた。
僕のインダストリアルな感覚は、もともとファイナル・カットのスタイルから来ている。当時、デトロイトでウィザードとしてDJをやっていたときも、インダストリアルとハウスとテクノをミックスしていた。
 Jeff Mills Where Light Ends U/M/A/A Inc. |
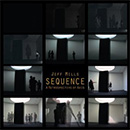 Jeff Mills SEQUENCE-A Retrospective of Axis Records(2CD Japan Edition) U/M/A/A Inc. |
■この取材では、新作の『ウェア・ライト・エンズ』について、そして、昨年の〈アクシス〉レーベル20周年にも焦点を当ててやりたいと思います。
ジェフ:これから何をしたいのか、何を考えているのか話すことのほうが興味深いかもしれないけどね。
■ぜひ、過去と未来のふたつで。
ジェフ:何かについての作品を作るというプロジェクトをやり続けてきている。その基盤がいまできていて、それは10年、15年前にはなかったことだから、ぜひ先のことについても話したいんだ。
■若い読者も多いので、昔のことも訊かせて下さい。
ジェフ:オッケー。
■昨年、〈アクシス〉レーベル20周年企画のBOXセット『シーケンス』を出しましたが、ジェフが自分で書いたそれぞれの曲に関するコメントが面白かったです。そのなかで、〈アクシス〉レーベルのマニフェストとして、最初に「AXISは失敗を犯さない。失敗とは目的と計画が明確ではない場合にあり得ることであるからだ」とありますよね。ジェフらしい言葉だなと思いましたが、これはあなたの人生にも当てはまることですか?
ジェフ:ノー(笑)。人生には当てはまらない。
■はははは。
ジェフ:アイデアにチャレンジして、そしてうまくいかなかったとしても、それが他の場面で役に立つこともある。失敗を失敗として片付けてしまうことはない。アクションを起こしてからアイデアをキャンセルしたこともない。別の機会をうかがうということもつねに考えているから。
それは、自分以外の、ほかのインディペンデント・レーベルをやっている人たちの視点を変えることでもある。つねに、正解はない。状況が変われば結果に結びつく。だからすべてはポジティヴであって、ネガティヴに捉えることはないと思っている。
■なるほど。失敗と言えば、"コンドル・トゥ・マヨルカ"という曲のエピソードも面白かったですね。プロモーターが迎えに来なくて、マヨルカ島行きの飛行機に乗り遅れて、せっかくの休暇が台無しになった話です。あの曲に、まさかそんな背景があったとは(笑)......その旅費は、その曲を作ることで取り戻せたのですね?
ジェフ:あのときは、まったくがっかりした。とてもタフな体験だった。いまのようにビジネスクラスに乗れるわけではなかったし、まだ空の旅にはいろいろな制約があった。あのときの自分にできることは、このバカげた体験に関するトラックを作ることだけだった。お金のためというか、ちょうどのその頃、『ウェイヴフォーム・トランスミッションvol.3』(1994年)を作っていたので、旅ということで、そのアルバムにもうまくハマるんじゃないかと考えた。当時はDJとしてツアーするのも乗り継ぎなど大変だったな。若かったからできたんだと思う。
■『ウェイヴフォーム・トランスミッションvol.1』の1曲目は、"デア・クラング・デア・ファミリエ"というラブパレードのテーマ曲でもあったトラックを使っていますが、初期のあなたにとってベルリンとはとても重要な都市だったと思います。当時のベルリンに関する思い出を教えてください。
ジェフ:初めてベルリンに行ったのは、1989年だった。インダストリアル・バンドのファイナル・カットのメンバーとして行った。そのときにトーマス・フェルマンやモーリッツ・オズワルドたちと知り合った。
デトロイト・テクノの初期の頃、デリック・メイ、ホアン・アトキンス、ケヴィン・サンダーソンたちはイギリスを中心にツアーしていた。そこで、僕とマイク・バンクスはドイツを選んだ。最初、僕たちにとってのドイツの窓口は、〈トレゾア〉だけだった。〈トレゾア〉が自分たちの音楽に興味を持ってくれたからね。そして、リリースできるかもしれないという話から、デトロイトとベルリンとの関係がはじまった。ちょうどデトロイトでも、デリックやホアンたちとは別の、テクノの進化型が生まれつつあった時期だった。ベルリンではラヴパレードやメイデイがはじまって、メディアも創刊されて、すべてが新しかった。
■当時のあなたの作品は、とてもハードでした。あのハードさはどこから来たものなんでしょうか?
ジェフ:ああいうインダストリアルな感覚は、もともとファイナル・カットのスタイルから来ている。当時、デトロイトでウィザードとしてDJをやっていたときも、インダストリアルとハウスとテクノをミックスしていた。ミート・ビート・マニフェストとスクーリー・DとDJピエールをミックスするようなスタイルだね(笑)。だから音楽を制作するうえでもいろいろな要素が加えられた。それにマイク・バンクスは、フォースフルな(力を持った)音楽の必要性を考えていた。また、ヨーロッパのクラウドの規模がだんだん大きくなって、1万人規模の人たちを動かすことを考えると、密度であったり、強さを持ったものではないと効果はでなかった。
最初にヨーロッパに行ったときは、僕にはそんな考えはなかったよ。ヴォーカル・ハウスだったり、ハードではない音楽をプレイしていた。しかし、ハードでなければダンスしてもらえない。相手のドイツ人はそんなにうまくダンスできる人たちでもない。それで考えたのが、もっとカオティックで、踊れなくてもうわーっと熱狂できるような、そしてよりハードでより速い音楽を目指した。必ずしもそれがもっともやりたいことではなかったけれど、効果はあった。自分では、ソウルフルな音楽を作りたいと思っていたんだけどね。
■初期の頃のあなたはヘッドフォンだけを使って、低い音量で作っていたとありますが、そのことも意外に思いました。その理由を教えてください。
ジェフ:音量を下げたほうがすべてのフリーケンシーが聴こえるんだ。スタジオでは、たいていニア・フィールド・スピーカーで音像が目の前に来るようにセッティングしているんだけれど、大きくしてしまうと、音のエンヴェロープが前ではなく頭の後ろで鳴ってしまい、どうなっているのかわかなくなる。もちろん大きな、ちゃんと設備の整ったスタジオなら大きな音を出してもすべての音がしっかり聴こえる。しかし、インディペンデントでやっている小さなスピーカーでは難しい。フルステレオの音の領域を聴くには、小さな音量のほうがいいこともある。さらにヘッドフォンで聴けば、サウンドのロスが少ない。これがレコーディングの話だ。
ところが現場では、スピーカーがぜんぜん違う。ロウが強くて、中域がなくて、高音が強いという、いわゆるクラブの音になるので、スタジオで作業していたときの音との違いに気がつく。だから現場でどう鳴るのかを補正しながら作っていくようになるんだ。90年代なかばのトレンドは、各チャンネルの音量を目一杯上げて作ることだった。それがエレクトロニック・ミュージックがミニマルになっていく大きな要因でもあったし、ある意味、音が画一化されていく要因でもあった。
音楽はどういう風に聴くかでも変化するものだろうね。現代のPCDJたちは、ヘッドフォンすら使わなくなっている。つまり、出音で、オーディエンスに聴こえる音と同じ音でDJしているわけだ。それによってサウンドのクオリティは良くなってくべきだ。
■あなたのベースに対する考え方を教えてもらえますか? あなたのベースのアプローチの仕方はユニークだと思います。
ジェフ:ベースラインは、デトロイトの音楽にとって重要な要素だ。僕は、メロディとベースを同時に弾いている。右手でメロディを弾いて、左手でベースラインを弾いている。右手と左手が同時に鍵盤を押すことはない。ベースとメロディが同時に鳴っていることはないんだ。タイミングがあって、順序がある。普通のやり方とは違っているから、独特なベースになっているんだと思う。
■パーカッシヴな感覚ですか?
ジェフ:そうだね。パーカッションに近いと思う。
■あるジャズ・ミュージシャンによれば、あなたの音楽は譜面に書くとブルースだそうですね。自分では意識していますか?
ジェフ:それは僕が生まれてから生きてきた長い人生の経験、環境から来ていることだ。子供の頃に何を聴いて、そして、どれが良い音楽なのか、そうした判断力などすべてと関係している。モータウン、ジャズやブルース、ゴスペルからの影響を無視して語るわけにはいかない。音楽は、自分がどういう風に感じているのかを反映するものだから、デトロイト・テクノにはある種のブルース・フィーリングが滲み出ているんだろう。
取材:野田 努(2013年4月01日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE