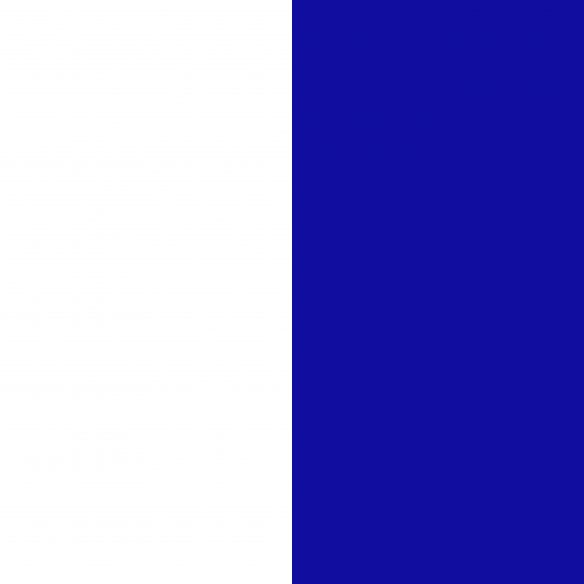MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Ben Frost - ダイアン、僕らはコントロール過剰な世界に生きている
 Ben Frost - Aurora |
ベン・フロストは、激情の人であり理知の人である。彼の腕には黄金律のタトゥーがある。ムダのない完璧なものを愛するということだろうけれども、その愛し方にはどこか理屈におさまらない過剰さが感じられる。ベン・フロストは矛盾の人でもある。
しかしその矛盾はいつしか円になって膨大なエネルギーを生む。
オーストラリアの実験的音響レーベル〈ルーム・40〉より2003年にデビュー・アルバムをリリースし、その後アイスランドに移住、エレクトロニカあるいはポスト・クラシカルの文脈においてアルバムを重ねてきたプロデューサー、ベン・フロスト。近年では映画のサントラやバレエなどの舞踏のための音楽などを手掛けることが増える一方で、大きく注目を浴びたティム・ヘッカーの『レイヴデス1972』(2011)、『ヴァージンズ』(2013)にエンジニアとして参加するなど、その力量の幅を示してきた。
アルバム・リリースについても、2009年の『バイ・ザ・スロート』の後はサントラがつづくため、このたびの『オーロラ』のような個人的な作品は久しぶりの制作となる。『セオリー・オブ・マシーンズ』収録の“ウィ・ラヴ・ユー・マイケル・ジラ”というタイトルに顕著だけれども、インダストリアル的なアプローチへと接近してきたかにも見える彼が、その久方ぶりのフル・アルバムを今年〈ミュート〉からリリースするというのは、時流と彼自身の個人的な創作モチヴェーションとの幸福で鋭い交差を意味していると言えるだろう。
とはいえ、硬質で理性的なイメージの裏側に熱くたぎるエモーションを爆発させる、フロストのロマンティシズムは健在だ。今作のモチーフのひとつとして「コライダー(加速器)」が挙げられているが、円形軌道を描いて加速する荷電粒子、そこから生まれる爆発的なエネルギーのイメージは、そのまま音の喩となり説明ともなろう。彼の音楽はハイ・カルチャーからのアプローチを受けつつも、その芯にあっては敷居の高くないものだ。もっとポップでもっとドリーミーな轟音──エクスプロ―ションズ・イン・ザ・スカイや65デイズ・オブ・スタティックといった激情系マスロック・バンドから、シガー・ロスのファーストの若い衝動にまで通じるみずみずしさがその奥に押しこめられている。
理詰めを加速して感情の爆煙となった音響。音楽は円を描くと彼は言ったが、彼の論理とエモーションもまた円を描いて発熱する。90年代の先に2000年代の黎明の再評価の機運が見えつつある昨今、ベン・フロストが鮮やかにシーンへ帰還した。
オーストラリア出身、現在はアイスランド・レイキャビクを拠点に活動するプロデューサー。ティム・ヘッカーやブライアン・イーノ、ヴァルゲイル・シグルソン(〈ベッドルーム・コミュニティ〉)、コリン・ステットソン、スワンズらとの共作で知られ、最近ではVampilliaの新作『my beautiful twisted nightmares in aurora rainbow darkness』のプロデュースも手がけている。5年ぶりのフル・アルバムとなる2014年作『オーロラ』には、スワンズのソー・ハリス、ブルックリンのブラックメタル・バンド、Liturgyの元メンバーであるグレッグ・フォックスなどが参加する。

今回のアルバムはおもに「光」を題材にしているんだ。そしてそれはエナジー──内省的なものではなくて外に向かってどんどん拡大していくべきものだと思っている。
■あなたにとっては少し古い話になるかもしれませんが、『スティール・ウーンド(Steel Wound)』(2003年)をリリースされた頃は、あなたの音楽にはもう少しゆるやかな、ギター・アンビエントといった雰囲気がありました。そこから時間が経って、何作も経て、今回はすごく音の詰まったものになっていますね。
人は年をとるほど余白を生んでいくものかとも思いますが、今回あなたの音の余白を埋めているものは何なんでしょう?
BF:10年以上前になるけれども、もともと私はオーストラリアのメルボルンに住んでいたんだ。そこは、たとえばこの渋谷にも似ていて、すごく人口密度の高いところだった。建物もたくさんあるし、街自体が、凝縮された濃密な空間だったんだ。何もかもが濃厚というか。街の景色を思い出してみても、どこにも隙間がない。そういうところに住んでいたぶん、自分のなかでもバランスを取ろうと思っていた部分が大きかったんじゃないかな。私は若かったし、いろいろと混乱する部分もあった。安定してなくて、自分の心が平らな状態ではなかった。だからこそ、自分のなかのでこぼこした部分を研磨するような、そんな気持もあったんじゃないかと思うよ。外の環境に対して補正をしていきたいというか。その頃の自分には、外的なものから圧迫されるような感覚があったんだ。そして、それをなんとかして押し返したいという欲求もあった。
それに比べると、いまは住んでいる環境もちがうし、歳をとることによって自分の感情をコントロールすることもうまくなった。そうしたことが、いまのアルバムに反映されているんじゃないかなと思うよ。
■なるほど。この作品はアトラス・プロジェクトという、「ラージ・ハドロン・コライダー(大型ハドロン衝突型加速器)」(※)という装置を用いた実験にインスパイアされたものだともおうかがいしたのですが、今作の音の激しさには、個人的な背景とともにそうしたモチーフも関係しているということでしょうか。
※2008年に完成。史上最高のエネルギーを生み出す装置と言われている
BF:たしかに、ラージ・ハドロン・コライダーからはインスパイアされた部分がある。今回のアルバムはおもに「光」を題材にしているんだ。そしてそれはエナジー──内省的なものではなくて外に向かってどんどん拡大していくべきものだと思っている。具体的にコライダーのどの部分からインスピレーションを得たというようなピンポイントでの影響はないけれども、すべてがつながっているんだよね。リズムというのはつながってできているものであり、サウンドも同様だ。そのなかのひとつだけをとってきても意味はない。つながっているからこそ意味があるのであってね。
リズムでもサウンドでも、基本的には円を描いているものだと思う。
リズムでもサウンドでも、基本的には円を描いているものだと思う。それらが円を描きながら音楽を構成している。たとえば、完全なる円があると仮定するならば、そこにあるのはテクノのような均一なビートだろうね。しかし、その円をすごくゆがめてみることで生まれる複雑性もあるだろう。しかし音楽自体は円。そしてコライダーも形状的にくっきりとした円のイメージがある。そして、あれは何か新しいものを探したいという実験でもあった。ふたつのものが衝突するからこそ生まれてくる新しいものをね。……というところで今回の作品につながってくるんだ。ふたつのものが衝突して生まれてくる新しいエネルギーという。
■なるほど、あの過密な情報量とエネルギーを持ったアルバムとコライダーの比喩はすごくよくわかるんですが、一方に「光」というテーマもあるわけですね。ラージ・ハドロン・コライダーという装置は、ブラックホールを生み出しかねないものだということなんですが、そうすると、光と闇、この世のすべてのエネルギーを持つかのようにイメージがふくらみます。
BF:宇宙は、じつはブラックホールの中に存在しているという説があるんだ。ギャラクシー自体も、トイレの渦なんかと同じで、すべていっしょの方向に回っていっているってね。だから、あらゆる磁場が同じ方向に回っていることによって、宇宙の均衡が保たれているのかもしれない。その意味では、ブラックホールの中にあらゆる情報量が詰まっているというような考え方はアリかもしれないね。
自分が好きなアーティストなんかを思い浮かべてみると、抽象的で不確かな部分を抱えながら、それを具現化する手段として音楽を用いている人が多い。それはたぶん自分自身にもあてはまる。まだ私自身にとっては、その不確かなものを形にすることを完璧にはできていないんだけど、年齢を重ねるにつれてどんどんと手段を得ているような気はするよ。
■想像の追いつかない世界ですね……。年齢とともにバランスがとれてきたということでしたが、まるで青春期の心象風景であるかのような激しさも感じました。
BF:うーん……、そうかもね。
■あ、ちょっと違いますか(笑)。
取材:橋元優歩(2014年10月30日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE