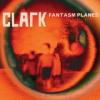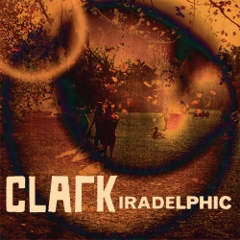MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Clark - 冬のための電子音楽
 Clark Clark Warp/ビート |
今年はエレクトロニカ/IDMの年だったというひとも少なくないだろう。EDMが席巻し、バカ騒ぎのイメージばかりが目立ってしまったフロアに対するカウンターとしてエレクトロニック・ミュージックの実験主義はいまこそ存在感を増しているし、何と言ってもエイフェックス・ツインさえも復活してしまったのだから。クラークによる7枚めのアルバム、その名も『クラーク』は、そんな年の締めくくりにふさわしい1枚だ。
クリス・クラークは2001年の『クラレンス・パーク』のデビュー以来、エイフェックス・ツインと度々比較され、その多作ぶりで結果的にエイフェックスの不在を埋めることとなったが、時代はけっしてずっとIDMに味方していたわけではなかった。彼自身はマイペースに、そしてワーカホリックに気の向くままひたすら作曲を続けてきたとの発言を繰り返しているが、しかしながら大胆にハードなテクノ、あるいはエレクトロに転身した『ターニング・ドラゴン』(08)、オーガニックな生演奏をふんだんに取り込んだ『イラデルフィック』(12)など、かなり思い切った変化を見せてきた。いま思うと、その変身と多面性が彼のこの10数年のサヴァイヴのあり方だったのかもしれない。
本作『クラーク』の特徴をいくつか挙げるとすれば、まずはビートが比較的リニアなものが多くダンサブルであること。序盤はBPMが同じトラックが続く場面もある。次に、これまで彼が辿って来た音楽的変遷がたしかに溶け込んでいること。シンセやピアノ、あるいはストリングスによる多彩な音色使いによって曲ごとのカラーはさまざまで、“アンファーラ”のような勇壮なテクノ・トラックもあれば、“ストレンス・スルー・フラジリティ”のようなピアノ・ハウス、“バンジョー”のような音の隙間で聴かせるユーモラスな電子ファンクもある。ラストの“エヴァーレイン”はほとんどドリーミーなアンビエントだ。そして、ほとんどのトラックで印象的で美しいメロディが奏でられている。
本作のポイントは、雪を踏みしめる音や雷雨を録音したフィールド・レコーディングであるという。しかし、それらは一聴してわからないほどサウンドに溶け込んでおり、あくまで隠し味としてアルバムのそこここに息を潜めている。この事実が示しているように、ずいぶん複雑で洗練されたやり口で彼のエレクトロニック・ミュージックの実験と冒険はここで編み込まれているのだ。考えてみればキャリアも10年を悠に超えるこのベテランは、その間ずっと作曲ばかりをしてきたのだ。
この多様な表情が隠されたアルバムのアートワークが彼のセルフ・ポートレイトの黒塗りになっているのは、クラークならではのジョークだと思えばいいだろうか。どこか飄々とした彼のこれまでの歩みが、このセルフ・タイトルの静かな自信へと辿りついたことが何とも感慨深い。
イギリスの田舎にある古い農家のなかで作った。誰もいなくて、村みたいな場所だった。だからその4ヶ月間、曲を書く以外ほとんど何もしなかった。すごく特別な4ヶ月だったよ。本当に孤立していたんだ。
■やはり、まずはここから訊かせてください。7作めにして、タイトルを『クラーク』としたのはなぜですか?
クラーク:この質問、みんなから訊かれるんだよ(笑)。たしかかに変だからね。普通だと最初の作品をセルフ・タイトルにするひとのほうが多いからね。今回のアルバムは最初、自分をテストするような作品だったんだ。エレクトロニック・ミュージックにおいて自分がやってきたことをただまとめるだけじゃなくて、もう少し自分のサウンドを表現してみたいと思った。だから自分をテストしてみることにして、4ヶ月かけてこのアルバムを書いたんだ。いままでにそんなことはなくて、いつも何年かかけて書いてきたトラックを集めてアルバムを作ってた。でも、この作品に関しては、4ヶ月かけて最初に何もない状態から書きはじめて完成させたアルバムなんだ。すごく集中していたし、そのエナジーが反映された作品だと思うよ。
■(通訳)その新しい試みは、実際やってみていかがでしたか?
クラーク:どうだろうね。前まではやっぱりコレクションだった分、コラージュって感じであまりトラックが直線上に並んだ感じはしなかったと思う。でもこれは4ヶ月集中して……って、さっきからなぜ「クラーク」ってタイトルにしたかの答えにあまりなってないよね(笑)、ごめん。でもとにかく、そういう理由があって、アルバムを「クラーク」と呼ぶのがすごく自然に感じたんだ。制作の最初の時点からこのアイディアはあって、セルフ・タイトルってすごく大胆だから、正直不安はあった。果たしてじゅうぶん良い作品になるんだろうか、とか、失敗するかもしれない、とか、愚かなアイディアかもしれない、とか。でも最終的にアートワークも含め見てみると、すごく自然に感じたんだ。このアルバムにタイトルは必要ないと思った。すごくいい気分で、いろいろ経験してついてきた自信がこのレコードに反映されていると思っているんだ。作品の内容自体がよければ、タイトルってあまり気にならないだろ? 自分がそう感じることができたってことは、自分がこのアルバムに心地よさを感じることができてるってことなんだと思う。
■(通訳)制作はどこで?
クラーク:イギリスの田舎にある古い農家のなかで作った。誰もいなくて、村みたいな場所だった。だからその4ヶ月間、曲を書く以外ほとんど何もしなかったね(笑)。すごく特別な4ヶ月だったよ。本当に孤立してたんだ。ヒゲも伸びまくって(笑)。実際やってみて、集中できたからすごくよかったよ。
■リミックス・アルバムであなたは自分の音楽性を「フィースト」と「ビースト」という、ふたつに大別していました。それをこのアルバムでひとつにしたかったのではないかとわたしは感じたのですが、そういった意図はありましたか?
クラーク:うーん……でもそう感じるのはありだと思う。今回の作品は、ライヴ楽器を一切使っていない生粋のエレクトロニック・アルバムなんだ。シンセと古い機材しか使ってない。『フィースト/ビースト』もそういうアルバムだったし、『クラレンス・パーク』や『エンプティ・ザ・ボーンズ・オブ・ユー』に戻る部分もあると思う。すべてのトラックが俺の昔の作品が持つ何らかの要素を思い起こさせる。でも今回は、それを表現するだけじゃなくて、新しいフォームに作り替えることにフォーカスを置いたんだ。
■実際、『フィースト/ビースト』はあなたの全キャリアを振り返る作業となったわけですが、そこで何か発見したことはありますか?
クラーク:何かを発見すると言うより、リミックスはただ好きでやってるんだよね。リミックスはひとの作品だから、その作品は自分にとってそこまで重要じゃないから、良い意味で遊べるんだよ。周りから与えられるプレッシャーも好きだし。だいたい一週間くらい与えられるんだけど、その時間のプレッシャーがあると最高の作品が出来る。「仕上げないと殺すぞ!」みたいなプレッシャーに駆り立てられるんだ(笑)。で、完成したら報酬をもらって、次の作品制作に進む。そのシンプルさが好きなんだよね。
■以前から疑問に思っていたのですが、あなたは音楽性をガラッと変化させるときも、ほかの多くのエレクトロニック・ミュージシャンのように、名義を使い分けるようなことはしませんでしたよね。そういったことはまったく考えてこなかったのですか?
クラーク:名義の使い分けはあまり意味がないと思っていて……どんな作品であれ、みんな結局それが同一人物の作品ってわかるわけだし、俺はジャンル・ミュージックは書かないし。ひとによっては、これはテクノのプロジェクト、これはヒップホップのプロジェクト、これはダブステップでこれはトラップ、みたいにプロジェクトをわけて名前を使いわける。でも俺は、なんでそういう風にジャンルにリミットを定めて音楽を作るのかわからないんだ。
■とくに前半ですが、本作はビートが一定のものが多く、非常にダンサブルなアルバムとなっています。『イラデルフィック』のときあなたは、「テクノ・ミュージックから少し距離を置きたかった」とおっしゃっていましたが、今回ストレートにテクノ・サウンドを打ち出してきたのはどうしてですか?
クラーク:前に探索していたものに戻って、そこからまた何かを広げていこうと思ったんだ。
質問作成:木津 毅(2014年11月06日)
Profile
 木津 毅/Tsuyoshi Kizu
木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE